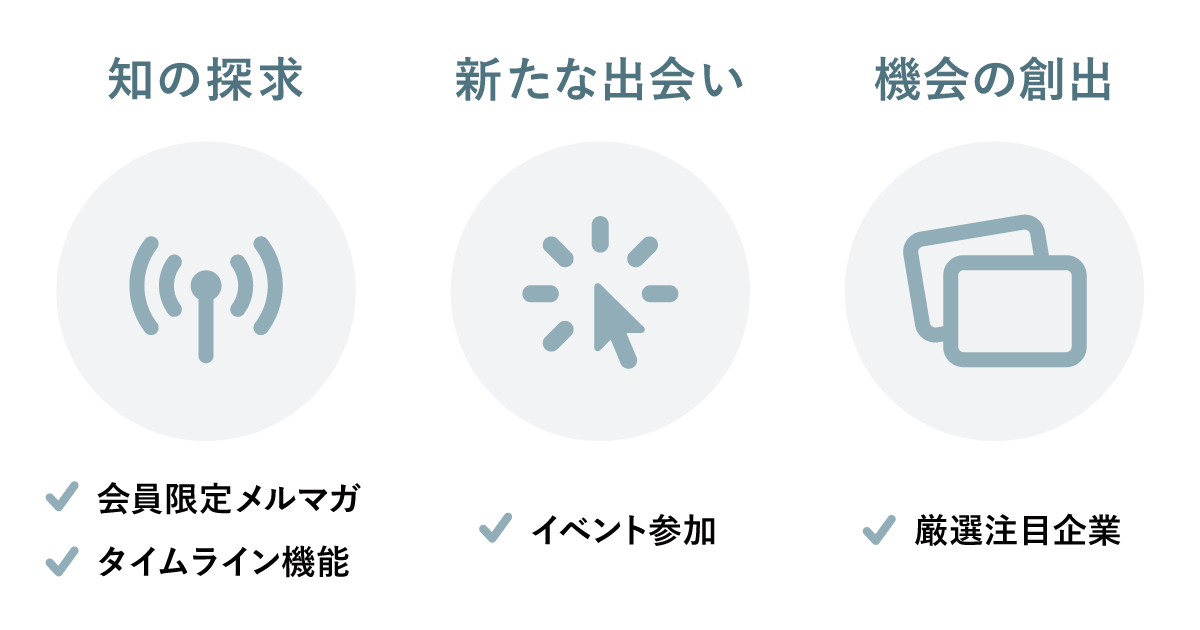テスラが日本車を圧倒したブランド戦略を、“イチゴ”に応用して米で55億調達──Oishii Farmに学ぶ、世界を席巻するプロダクト開発術
1パック50ドル(約5,000円)という高価格にもかかわらず、ひとたび売りに出れば購入希望者が殺到し、瞬時に完売──2018年に突如としてその姿を現し、今やニューヨークの星付きレストランシェフの中にその名を知らない者はいないという、幻の“イチゴ”がある。
その名も、Oishii Berry……「おいしいベリー」。そう、このイチゴを世に送り出したのは、他でもない日本人だ。これは“植物工場で生産されたイチゴ”であり、MBAを経てアメリカで起業した34歳・古賀大貴氏が、ほぼ前例なき中で一般流通させたものである。
Oishii Berryを手がけるスタートアップ・Oishii Farmは、2021年3月、アグリテック(AgriTech)業界に激震をもたらした。シリーズAで60億円という、大型の資金調達を発表したためだ。注目すべきは調達額ではない。まだ他のどの企業も成功していない“植物工場でのイチゴの量産”が、ついに拡大フェーズに入ったことを意味している。
「世界最大の植物工場を作り、未来の"食"を救う」。一見途方もないミッションの実現に向けて誰よりも速く歩みを進めるOishii Farmは、資金も人脈もほとんどゼロの状態から、いかにして急速な事業成長を実現したのか? 世界で戦う起業家に求められる、緻密な戦略と情熱の内実に迫る。
- TEXT BY MARIKO FUJITA
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
- EDIT BY MASAKI KOIKE
最初からイチゴしか眼中になかった
──圧倒的なプロダクト追い求めて起業
Oishii Farmが勝負する「植物工場」というマーケットについて、馴染みが深い読者はそう多くないかもしれない。日本ではあまり話題にあがらないが、全世界で市場規模が2018年時点で約174億円、2025年には400億円を超えると見られているこの急成長市場について、まずは、簡単に説明しておこう。
植物工場とは、LEDライトなどを光源として室内で農作物を育てる、新しい農業の仕組みだ。温度や湿度、空調が管理されているため、従来の農業と違って気候や土壌、季節などの影響を受けない。生産技術が確立し、コスト面の問題さえクリアになれば、どんな場所でも季節を問わず、世界中の美味しい農作物を食べられるようになると期待されている。
とはいえ、そこに至る道のりはまだまだ長い。現在世界の植物工場で生産されている農作物のほとんどは、レタスを主とする葉物野菜だ。裏を返せば、レタス以外の農作物を植物工場で生産する技術が、未だほとんど確立されていないということでもある。
競合企業が軒並み葉物野菜の生産拡大に注力する一方、古賀氏は「最初からイチゴしか眼中になかった」と語る。

Oishii Farm 古賀大貴氏
古賀僕たちが目指しているのは、農業界に圧倒的なパラダイムシフトを起こすこと。そのゴールから逆算して考えたときに、まず圧倒的なプロダクトをつくり、ブランドとして確立する必要がありました。日産もテスラも電気自動車を作った点では同じですが、テスラがあそこまでのブランド力を持てたのは、「ポルシェよりも速い電気自動車」という圧倒的な製品を作ったからです。
農業の世界において、圧倒的なプロダクトとは何か。レタスのように、比較的味に差が出にくく、付加価値の出し辛いものでは難しいです。もっと、誰もがあっと驚くような美味しい食べ物を……そう考えたときに出てきたのがイチゴです。日本だとイチゴは「美味しいフルーツ」というイメージですが、アメリカのイチゴは、びっくりするほど甘さがないんですよ。
アメリカのイチゴは、日本のイチゴとは全く別物だという。アメリカで生産されている四季なりイチゴは、硬さがあって傷みづらいが、甘さは弱い。生産地域がカリフォルニアなどの西海岸に集中しているアメリカでは、長距離輸送が必要になるため、日本で食べられているような甘くて傷みやすいイチゴは作られていないのだと古賀氏は見ている。
新鮮な食品が手に入りにくいニューヨークで、日本クオリティの美味しいイチゴを作る──「これこそが、僕たちが最初に採るべき戦略だ」。マンハッタン中のミシュラン星付きレストランを“アポなし訪問”する中で、その自信は確信へと変わった。
古賀MBA2年目に差し掛かった頃、「イチゴで植物工場をやる」と決めてビジネスプランを立てたのですが、「アメリカで日本のイチゴって、本当にニーズあるの?」と聞かれたときに、答えられる材料が欲しかった。
そこで実際の生産に入る前に、日本のイチゴをバッグいっぱいに詰めて空輸し、マンハッタンの高級レストランへ持ち込みました。普通の方法では取り合ってもらえないので、“アポなし”の飛び込み営業です。
怪訝な顔をされながらも持ってきたイチゴをシェフに見せ、一粒食べてもらったとき、彼らの顔つきが変わりました。そのリアクションを見た瞬間、「このイチゴを作れれば絶対にヒットする」と確信しました。

画像提供:Oishii Farm
こうして「世界最大の植物工場」という野望に向けた、大いなる一歩が踏み出された。それから2年後、試行錯誤を経て生み出されたOishii Berryは、瞬く間にニューヨークの食通を虜にし、アメリカの植物工場業界にはざわめきをもたらした──「どうやらイチゴの生産に成功したスタートアップがあるらしい」と。
原点は「無力感」。
“平凡な大学生”が、世界レベルでの戦いを志してUCバークレーへ
一躍業界の注目を集めた古賀氏ではあるが、かつては周囲の意見に流されてしまいがちな、平凡な大学生だったという。はたしてそこからどのようにして、世界で活躍する起業家へと変貌を遂げたのか。
幼少期を欧米で過ごすも、中高大と日本の学校に進学した古賀氏。“普通”の学生生活を送っていた彼に転機が訪れたのは、大学2年生でスタンフォード大学の留学プログラムに参加したときだったという。
古賀夏休みの1ヶ月間を使ってそのプログラムに参加したのですが、一緒に参加していた海外の学生のハングリー精神や目線の高さに、ものすごく衝撃を受けて。当時の僕は何もやっていない、どうしようもなく平凡な大学生だったので(笑)、「自分は日本にいる間に、全く世界に通用しない人間になってしまったな」と危機感を覚えました。
「どこかのタイミングで海外に出ないとダメだ」と痛感したものの、いきなり海外の会社に就職するのは、ビザの関係上ハードルが高い。もう一度海外に挑戦するためのきっかけとして思い当たったのが、MBAだった。
とはいえMBAに行くには職歴が必要なうえ、それなりにお金もかかる。どのようなキャリアならMBAに留学できるかを考えた結果、さまざまな業界を見ることができそれなりの給料も期待できるコンサル業界に魅力を感じ、新卒でデロイトトーマツコンサルティングに入社した。

入社から5年後、無事に留学資金の1,500万円を貯めMBAを受験した古賀氏。起業の決意を固めたのは、大学を選んでからだったという。
古賀MBAを受験して受かった学校が2つありました。1つはケロッグ経営大学院という、コンサルや投資銀行で活躍したいエリートの育成に強い学校。もう1つが、僕の行ったカリフォルニア大学バークレー校 (以下、UCバークレー)。シリコンバレーにある、多くの起業家を輩出している学校です。
コンサルとして働く中で、自分はお金やピカピカのキャリアには興味がないことはわかっていたので、UCバークレーを選びました。そして、「どうせUCバークレーに行くなら、本気で起業をしてみよう」と、そういう制約を自分にかけたんです。
すべてのピースが揃った感覚
──「アメリカでイチゴの植物工場」という“必然”にたどり着く
起業のアイデアを練りはじめた当初から、「植物工場をやりたい」という気持ちはあった。コンサル時代に国内の植物工場の案件を担当する中で、この業界の課題と可能性について知見を蓄えていたからだ。
国内で植物工場に取り組む企業が軒並み苦戦している理由について、「日本には優れた技術がある一方、既存の農作物に対する商品としての優位性がなかった」と古賀氏は指摘する。
古賀日本の植物工場の歴史は、パナソニックや東芝、シャープといったメーカーが、「LEDやIoTに関する自分たちの技術を使って、何か新しいことができないか」と、新規事業として取り組んだところからはじまります。
IoTと並んで植物工場の技術のベースとなっている施設園芸の技術に関しても、もともと日本はオランダと並んで世界一の技術力を持っていたため、大手メーカーの技術力と掛け合わされて、日本には世界トップレベルの植物工場の技術が生まれました。これが2000年代のことで、当時は大変もてはやされた。
ところが、いざ植物工場で作った農作物を市場に流通させてみようとすると、商品としてほとんど成り立たないことがわかりました。既存の農作物のクオリティが高く、物流の仕組みも整っている日本では、新鮮で美味しい野菜が一年を通して安く手に入るからです。コストの高い植物工場の農作物は、これらの競合品に全然歯が立たなかったのです。
こうしてテクノロジードリブンで開発が進んだものの、生まれたプロダクトはまったく市場にフィットせず、日本において植物工場は“儲からないビジネス”の烙印を押された。
しかしながら、所変われば事情も変わる。日本では勝ち目の薄かった植物工場も、海外では全く違った捉え方をされていた。

古賀アメリカでは、僕が留学したちょうど2015年にカリフォルニアで大干ばつが起き、「車を洗うのに水を使っちゃいけない」と言われるまでの事態になりました。日本でも、山火事のニュースが何度か放送されましたよね。地球上の水の7割が農業に使われていると言いますから、これはアメリカの農業に非常に大きなダメージを与えました。
加えてトランプ政権になったことにより、それまで農業に従事していた不法滞在のメキシコ人が国外へ追放され、人件費も跳ね上がりました。水、土地、人……食物生産にかかるコストが、鰻登りに上がっていったのです。
「今後も異常気象は起こる可能性があるし、このままでは農業がヤバい……」。人々がそう気づき始めたアメリカでは、この問題を解決すべく、植物工場のスタートアップが立ち上がりはじめました。
日本の技術をアメリカに持ち込めば、大きなインパクトが起こせる。そう思いはしたものの、ソフトウェア事業と違い、植物工場には多くの物理的なアセットが必要になる。2年以内の起業は難しいと考え、まずはMBAの同級生2人と、全く別のコンシューマー系ビジネスで起業した。
ところが事業を始めて1年ほど経った1年生の夏休み、一緒にやっていたメンバーが、就職活動のため大企業のインターンへ行くと言い出す。起業家輩出校として有名なUCバークレーとはいえ、250人いた同級生のうち、実際に起業したのは古賀氏を含めて3人だけ。ほとんどの学生にとって夏休みは、今後の人生の命運を握る大事な時期なのだ。
1人になってしまった古賀氏は、やむなく事業の継続を断念。ベンチャーキャピタルのインターンに参加した。
古賀「起業するなら投資家側のことも学んでおいた方が良い」と思いVCのインターンに行ったんですが、そこで起業や資金調達に関するさまざまなことを学びました。
その後大学院2年目に入り、戦略がかなりクリアになっていきました。「まだ他のどの企業もやっていないイチゴを生産する」というものです。日本で関連する研究に取り組んでいる人にも心当たりがあり、すべてのピースが揃った感覚がありました。「思っていたより、早く立ち上げられるんじゃないか」と。
予想通りの大ヒット。
コロナ禍に直面も、事業戦略を柔軟に変更
夏休みが明けた、2016年9月。古賀氏は1年生のときに知り合った日本人のシリアルアントレプレナーから、500万円の投資を受けることが決まった。その資金を元手に市場調査を開始し、星付きレストランへの飛び込み訪問を始める。そして同年12月、Oishii Farmを創業した。
創業後はすぐにシードで数億円を調達。コンテナを購入し、ほとんど自力で工場を建てて、日本の技術者や研究機関と連携しながら生産に着手しはじめる。わずか1年で、まだ他のどの競合も実現していないイチゴの生産に成功した。
古賀植物工場でイチゴを作るうえで最も大きなハードルとなるのは、「ハチがきちんと受粉してくれるか」という部分。ハチが「自然」だと錯覚してくれるような環境をコンテナ内に再現するのが難しいのです。コンテナ内に放ったハチがピッとイチゴの花に止まり、お尻をこすりつけて受粉する様子を見た瞬間は、「ついに生産技術が確立できた」と胸が躍りましたね。
創業から1年余りで生産に成功したOishii Berryは、星付きレストランを始めとするニューヨークの高級レストラン向けに売り出され、瞬く間に評判になった。特にニューヨークの三つ星レストランの中でも「最もこだわりが強い」ことで有名なChef’s Table at Brooklyn Fareのシェフ、セザール・ラミレス氏がOishii Berryを導入すると、業界内で一気に噂が広がり、ニューヨークの食通の間にこのイチゴの名を知らない者はいなくなった。

画像提供:Oishii Farm
2020年に入ってからは、満を辞して一般消費者向けの小売販売を開始。コロナ禍によってスケジュール等に多少の変更はあったものの、基本は当初の計画通りだ。
古賀高級レストランへの卸しは、ブランディング戦略の一環として始めたことであって、最初から目指していたのは一般消費者向けの小売りのビジネスモデルです。そのため、ブランディングが十分に出来たどこかのタイミングで、小売りに切り替えようとは考えていました。
2020年に入った時点でミシュランレストラン全体の2〜3割にOishii Berryを入れていただき、認知度もある程度取れていたので、そろそろ小売りに向けたマーケティング戦略を展開しようと考えていたところでしたが、ちょうどそこにコロナ禍が来た。
街のスーパーもほとんど閉まっていましたし、これだけ世界が大変な状況にある中で「1パック50ドルの高級イチゴを大々的にローンチする」のはちょっと違うなと思い、直販サイトを立ち上げてD2Cモデルで小売り販売を始めました。
もともと描いていたようなアクセル全開でのスタートとはならなかったが、それでもOishii Berryは、毎日飛ぶように売れていった。家にいる時間が増えたことで自炊の機会が増え、以前より食品に対する関心が高まったことも、背景にはあった。
そして2020年12月のクリスマス頃には、ついにニューヨークの高級スーパー「ゼイバーズ」での小売り販売を実現した。
農業こそ次なる“cool things”
──Oishii Farmにアメリカのビジネスエリートが集う理由
Oishii Farmの躍進ぶりは、MITやハーバード出身者のようなアメリカのビジネスエリートも惹きつけ、社員数は2020年の1年間で約20人から50人へと倍増した。Oishii Farmが優秀な人材に訴求できる理由について、古賀氏は次のように推察する。
古賀Oishii Farmを「ただのイチゴを作っているスタートアップ」と捉えれば、「なぜそんなところに優秀な人材が?」と思われるかもしれません。でも僕らが目指しているのは「世界最大の植物工場」であって、イチゴはそのためのファーストステップに過ぎないんです。
農業は一見”uncool”な産業に見えますが、実は自動車業界よりはるかに大きい産業です。「次のcool thingsは何か?」を常に探している彼らにとって、この巨大な産業において革命を起こすこと、それに取り組むスタートアップに早い段階からジョインすることが、“cool”に映るんだと思います。
ここまでかなり順風満帆に見える古賀氏の起業の軌跡。大変だったことや大きな苦労した経験はなかったのだろうか?

古賀大変かどうかで言えば、毎日死ぬほど大変です。今までやったことがないことの連続なので、事業も組織もどんどん成長するし、やることはどんどん増える。何百枚もあるような英語の契約書をレビューしたり、建設会社に数億円を払って工場を建設するときに、「お金を持ってどっか行っちゃわないか」と不安にかられたり(笑)。
ただ、“苦労”という観点では、正直何もありません。毎日事業に取り組むのが楽しくて仕方なくて。これをやって給料がもらえて、成功したらスゴいことになるかもしれないと考えると、これ以外に何をやったらいいかわからないですね。学園祭の前日準備が、ずーっと続いているような感覚です。
成功を掴むには、「とにかくチャンスに飛びつくこと」
2021年は、コロナ禍で延期となっていたブランディングやマーケティングの領域にも力を入れ、さらなる飛躍の年にしたいと意気込む古賀氏。今後は主に3つのことに取り組んでいく。
1つ目は、10年以内にイチゴで世界トップの生産者になることだ。世界的に見れば、イチゴには数兆円の市場規模がある。アメリカではドリスコルというメーカーが40%のシェアを持っているが、ブランドさえ確立できれば、イチゴは結構なシェアを獲得できる作物だと古賀氏は見ている。
古賀大半の消費者はきゅうりやレタスのブランドを知らないのに対して、日本だと「とちおとめ」や「あまおう」のように、いちごに関しては誰もが数種類のブランドを知っている。いちごは数多くある作物の中で、唯一と言っていい、「品質の良い製品を作ればブランドが定着する」作物なんです。
そのため、まずはニューヨーク以外のアメリカの地域や海外の国にもOishii Berryを展開し、生産数を増やして確実にシェアを獲っていくという。
2つ目は、イチゴの生産拡大に並行して、他の農作物の研究開発を進めることであり、今回調達した60億円も、主にこの研究開発費に充てていく予定だ。そして3つ目は、「Oishii」ブランドの確立だ。具体的には、PRもブランドもこれまでの生鮮食品や消費財と一線を画す、「Oishiiの食品を消費している自分が好き」と自分のアイデンティティの一部として消費されるライフスタイルブランドを目指していきたいと考えているという。
「世界最大の植物工場を作る」というゴールへの道のりはまだまだ長い。ただ、アイデアの着想からたったの4年で、しかも国内よりはるかに競争の激しいグローバルの舞台でここまでの成功を収めた古賀氏を、“海外で活躍する日本人起業家”と呼んでも誰も異論はないだろう。
最後に、自身がこの成功を掴めた要因について聞くと、世界という舞台を恐れるどころか全力で楽しんでいる古賀氏らしい、明るい答えが返ってきた。

古賀まだ何も成し遂げてはいないですが、ここまでこれたのは、本当に運なんですよね。日本で偶然、植物工場というものに出会い、アメリカに行ったタイミングで、たまたま植物工場ブームが来た。さらに、そのときたまたまUCバークレーという場所にいて、VCでも経験を積むことができて。たまたまあのとき、あの場所にいて、すごい偶然が重なっただけなので、偉そうなことは何も言えないんですよね。
ただ唯一あるとすれば、「チャンスを掴む」ということだと思います。僕は今まで、「チャンスと感じたものにとにかく反射的に飛びつく」ということをやり続けてきました。デロイト時代に社内で農業のチームが立ち上がる際、誰も行きたがらない中で真っ先に手を挙げたときも、UCバークレーの始業式をサボって農業カンファレンスに行ってそこで最初の投資家に出会ったときもそうです。
そうやってチャンスに飛びつき続けているうちに、だんだんと運がついてきた。チャンスはそうそう訪れるものではないし、みんなが「これはチャンスかな?」と思いはじめた頃には、もうそれはチャンスではなくなっている。
“自分にしか気づけないチャンス”って、絶対に誰にでもあると思うので、それをいかにはやく掴むかということだと思います。
撮影協力
東京エディション虎ノ門
| 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー内 |
| 電話 :03-5422-1600 |
こちらの記事は2021年03月26日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
藤田マリ子
写真
藤田 慎一郎
編集
小池 真幸
編集者・ライター(モメンタム・ホース所属)。『CAIXA』副編集長、『FastGrow』編集パートナー、グロービス・キャピタル・パートナーズ編集パートナーなど。 関心領域:イノベーション論、メディア論、情報社会論、アカデミズム論、政治思想、社会思想などを行き来。
おすすめの関連記事
「国策」と「スタートアップ」は密な関係──ユナイテッド・PoliPoliが示す、ソーシャルビジネス成功に必須の“知られざるグロース術”
- ユナイテッド株式会社 代表取締役社長 兼 執行役員
エンプラ攻略したくば、9割の「見えない現場の動き」を許容すべし──Asobica×ナレッジワーク対談に見る、スタートアップがエンタープライズセールス立ち上げ時に陥りやすい8つの罠
- 株式会社Asobica VP of Enterprise Sales
「令和の西郷 隆盛」、宇宙を拓く──Space BD代表・永崎氏が語る、“一生青春”の経営哲学
- Space BD 株式会社 代表取締役社長
真のユーザーファーストが、日本にはまだなかったのでは?──「BtoBプロダクトの限界」に向き合い悩んだHERP庄田氏の、“人生の時間”を解き放つコンパウンドHR戦略
- 株式会社HERP 代表取締役
【独占取材】メルカリの0→1事業家・石川佑樹氏が、汎用型AIロボットで起業した理由とは──新会社Jizai立ち上げの想いを聞く
- 株式会社Jizai 代表取締役CEO
【トレンド研究】スタートアップならではのDEI──30社超のポリシー・取り組みの事例から考察
SmartHR、実は想像以上の“実力主義カルチャー”だった──「あの会社の“実は”ここがすごい」Vol.1
「もはやシニア“も”含めた戦略が必須の時代に」──シニアDXで大手との協業多数。オースタンス主催の国内最大級カンファレンス“AEC2024”とは
- 株式会社オースタンス 代表取締役社長