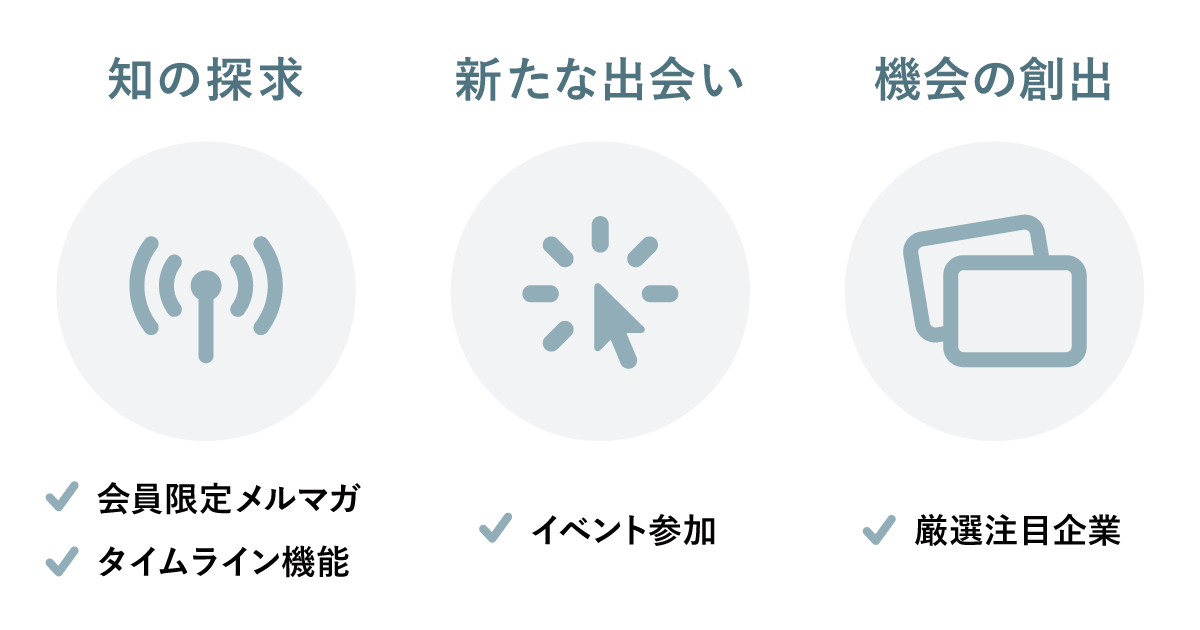今、このPdMがすごい!<Vol.1>次代をつくるプロダクトに携わる、エースPdM5名に学ぶ事業論──estie、リブセンス、STORES、パラレル、ファインディ
プロダクトマネージャー(PdM)は、ITスタートアップの心臓部とも言える存在だ。ユーザーニーズとエンジニアリングを結びつけ、ミッション・ビジョンとプロダクトの方向性を一致させる重要な役割を担う。市場の変化を敏感に捉え、迅速な意思決定と実行を導くPdMの存在が、多くのスタートアップで成長と革新のエンジンとなっていることに、そう異論は出ないだろう。
FastGrowでもこれまで、さまざまなかたちでPdMの存在を追ってきた。ようやく最近、「PdMキャリア」が一般化してきたように感じる。そこで改めて、「これから注目すべきPdMたち」を特集し、各プロダクトカンパニーの進化に貢献するような情報を届けていきたい。
今回はVol.1として、IT×不動産のestie、HR関連領域のリブセンス、店舗DXを推進するSTORES、新世代SNSのパラレル、エンジニア転職のファインディという5社のプロダクトに携わるPdMたちを取り上げる。その経歴や役割、直面する課題とその解決方法を詳しく紹介する。
ユーザーインタビューを重視した機能開発、既存サービスの連携による新たな価値創造、組織横断的な開発体制の構築など、それぞれ独自のアプローチがある。一人ひとりのバックグラウンドや、キャリアチェンジでPdMになった例も紹介していく。
- TEXT BY ENARI KANNA
estie・中村優文氏──ITと不動産を掛け合わせ、新たな価値の創造を目指す
市場規模10兆円にもおよぶオフィスをはじめとする商業用不動産に特化したスタートアップとして、ITを利用した不動産業界の価値向上を目指して複数の事業を展開するのがestieだ。
いわゆる“コンパウンドスタートアップ”である同社は、プレシリーズA、シリーズA、そしてデットでの調達を公表済み(直近のリリースはこちら)。デロイトトーマツグループが発表したテクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2023」では11位にランクイン。前年比売上高398.1%という急速な成長を見せている。
まだ創業から5年半に満たないにもかかわらず、すでにプロダクトは8つ。マーケット調査から実際の売買、案件管理までをサポートしている。一方でもちろん、すべてのプロダクトが順調に軌道に乗っているわけではない。時には苦戦を強いられたり失敗をしたりと悪戦苦闘しながらつくられてきたのが、現在のプロダクトたちだという。
こうしたプロダクト開発をPdMとして牽引するのが、中村優文氏だ。代表の平井瑛氏と同じく三菱地所での勤務を経て、創業初期に第一号社員兼一人目PdMとして同社に参画した。主に新規プロダクト開発に取り組む中村氏は、これまでにもestieで複数のプロダクト立ち上げを経験してきた。
同社の第一号かつ主力のプロダクトである『estie マーケット調査』の開発にも、もちろん関わっている。同プロダクトは、物件情報、空室情報をはじめとするオフィス賃貸に必要なすべての情報が揃う日本最大級のデータ基盤だ。たとえば賃貸価格を決める際の相場リサーチが容易になったり、競合物件に入居する営業候補先を瞬時にリストアップできたりと、商業用不動産取引をデータの面からより便利にするプロダクトといえる。
一方で、『estie マーケット調査』だけでは入居希望者との出会いや、そもそもの新規不動産の購入、購入後の案件管理などを行うことはできない。既存プロダクトでは解決できない領域における課題にアプローチするべく生まれたのが、後続の『estie 物流リサーチ』『estie 案件管理』だ。
中村氏は一人目のPdMとして新規プロダクト立ち上げの旗振り役となり、数々の意思決定をしてきた。コンパウンドスタートアップである同社では、0→1を同時並行で進めていくことになる。そうなると、UIやデータ利用について常に共通性を検討する必要があり、スピーディーな意思決定をしにくい場面も多くなるだろう。こうした意思決定において、中村氏は3つの基準が大事だと、自身のブログでも述べている。その内容からは、同氏が「スタートアップのCEO並みの事業創造」ができるよう、視座やマインドセットを高め続けようとしていることが伺えた。
estieでも、他のスタートアップと同様に、PdMに求められる一番の役割は「誰の何を解決するためにどのようなプロダクトをつくるのか」である。そこで一人目のPdMとしての役割を担い、創業者に近い視点を持ちながらプロダクトロードマップの策定やスクラム開発のリードなどをしてきた中村氏。こうしたPdMの役割の面白さについて、「型がなく、どこまでも追及できてしまう理想像とプロダクトユーザーから届く足元の要望のバランスを取るポイントで力量を試される点」と「仮説検証による絶え間ない思考実験ができる点」だと述べている。
PdMとしてだけでなく、もはや事業開発の役割も担う中村氏。学生時代からITと何かを組み合わせることが好きだったという彼は、今まさにITと不動産を掛け合わせて、大きな価値を創り出そうとしている。これから彼は一体どんな価値をつくり出すのだろう。そしてそれは10兆円市場をどのように変えていくのだろうか。
リブセンス・ 加藤めぐみ氏──マーケ×PdMとして、新たな挑戦へ乗り出す
『マッハバイト』や『転職ドラフト』などHR業界を代表するサービスを次々とリリースするリブセンス。2006年、代表の村上太一氏が19歳で創業し、そのわずか5年後の2011年に東証マザーズ市場(当時)へ上場した。史上最年少上場の社長が誕生した衝撃を覚えている人も多いのではないだろうか。
近年はHR領域だけでなく、不動産情報サービス『IESHIL』や紹介型マッチングサービス『knew』などの開発も行い、多角的な事業展開を行う。
同社の主力事業のひとつである、転職口コミサイト『転職会議』の事業部長を務めるのが、加藤めぐみ氏だ。大学1年生だった2008年に参画。その後カスタマーサポートを中心とした何でも屋のような役割を担ったのち、同社独自の役職でありPdMとマーケターを合わせた職種である「P&M(Product & Marketing)」職に就いた。そして2023年1月より、『転職会議』の事業部長へ就任。彼女は、同社初のP&M出身の事業部長でもある。

加藤氏
同社では数年前から「P&M」とのポジションを設けている。創出の背景には、事業テーマの複雑性があった。「DXによるモデル刷新」「高い透明性」「人間性の尊重」をテーマとして、リブセンスらしいプロダクトを作りグロースさせていくためには、PdMとマーケターが融合しなければならない。いや、むしろ、PdMとマーケターが分離していては最適な対応ができない。こうした考えのもと、P&M職の設置を決定したそうだ。
現在、社内にP&Mは約20名。PdM要素が強い人もいれば反対にマーケター寄りの人もおり、そのスタンスにはグラデーションがある。こうした特徴から、組織としては互いに専門性を補強し合って、ひとつの職種だけでは出せない大きなパワーの出力が期待できる。その一方で、「どっちつかずとなって市場価値が高まらないのでは」とキャリアに不安を抱える人もいるという。
そこで、改めてP&Mを再定義する「モンタージュプロジェクト」がスタートした。このプロジェクトはP&Mの強化を目的としており、対話や議論を通じて、「リブセンスのP&Mとしてありたい姿」を言語化し、最終的には評価制度を含めたそれを実現できる環境を整えようとするものだ。加藤氏は新しいP&Mの形が生まれることを期待し、本プロジェクトを率いている。
また、同社のプロダクトにも変化の時が来ている。これまでは、バイト、転職、不動産など領域こそ違えど、変わらぬ共通した強みを追求してきた。それは、「圧倒的なSEO力によって無料で個人ユーザーを集客する一方で、企業には広告を低価格で提供し、両者をマッチングする」というものだ。
ところが、事業環境の変化によりこのモデルでの成長に限界も見えてきた。そこで『マッハバイト』では料金体系の変更を試行錯誤したり、新価格に見合った価値を生み出す新たなプロダクト開発に乗り出したりと、事業を変容させてきているのが現在だ。またこれまでは、検索需要が旺盛な市場を攻めるライフイベント型のサービスが多くを占めていたが、BtoB オンライン面接ツール『batonn』など、ユーザーとの長期的な関係性を築き、愛され続けるプロダクトを生み出そうとする動きも出てきている。
顧客との長期的な関係性といえば、マーケターとPdMを融合させたP&Mの経験を持つ加藤氏の強みでもある領域だ。マーケティングにも造詣が深く、顧客の声の変化に鋭敏な加藤氏は、『転職会議』をどのように成長・変革していくのだろうか。同社の提唱するP&Mというポジションの行方も含めて、今後も追っていきたい。
STORES・宮里 裕樹氏と西岡 大揮氏──プロダクトの連携で目指すより質の高い顧客体験
以前、FastGrowの「マルチバーティカルSaaS特集」でも取り上げたSTORES。ECサイト、キャッシュレス決済、予約システムをはじめとする5つのサービスを提供し、小売店や美容院、飲食店などさまざまな“店舗”のデジタル化を総合的にサポートしている。
もともとは予約システムという非常に汎用性の高いツールを提供していたホリゾンタルSaaSだった同社。しかし一口に店舗の予約システムといっても、業態によって課題はまったく異なる。そこで顧客の抱える多様な課題をより深く理解し、より抜本的に解決することを目指すべく、マルチバーティカル戦略へと舵を切ったのだ。
同社による店舗ビジネス改革への期待は大きく、2023年2月にはGoogle社から約30億円の資金調達を実施した。またこれと同時に、『STORESネットショップ』に掲載した商品情報が自動的にGoogleマーチャントセンターに連携され、Googleの各種サービスに無料で商品を掲載できる仕組みも実装された。
Googleからの支援があった2023年は、同社にとって創業5周年となる節目の年である。その節目に取締役の佐藤氏と佐俣氏は対談インタビューにて、佐俣氏は「単なる便利ツールを超えて、プロダクトの利用者であるオーナーの商いそのものを支えるプロダクトを目指す」と語っている。
このようにGoogleも注目するSTORESのプロダクト開発を率いるツートップが宮里裕樹氏と西岡大揮氏だ。宮里氏は『STORES 予約』のプロダクトマネジメントとともに、個々のプロダクトを横断的に開発するための組織づくりに携わる。西岡氏は、シニアマネージャーとして、『STORES 予約』と 『STORES レジ』のプロダクトマネジメントを担っている。
新しいプロダクトの開発も重要ではあるが、同社が今注力しているのは、既存のプロダクト間の連携だという。そのなかで西岡氏は、『STORES 予約』と 『STORES レジ』を連携した新プロダクト『予約システムと、ひとつになったPOSレジ』を担当。2024年1月にリリースしたこのプロダクトは、ヘアサロンやフィットネスジムの事業者へのヒアリングによって明確になった課題を解消するために生まれた。
事業者の多くは、レジ、決済、予約で別々のサービスを利用していることが多く、そのため、データが分散し、顧客情報を正しく把握できなかった。その結果、手動で対応するしかなく、オペレーションミスの温床になっていたが、『STORES 予約』と 『STORES レジ』の連携によって解決した。
そんな同プロダクトの開発において西岡氏が苦労したのは、開発業務以上に30名以上関わるメンバーで意思決定を行い、細かい仕様に落とし込む合意形成だったという。対策として、隔週でメンバー全員がオフラインで集まる機会をつくった。東京以外の勤務地のメンバーも含め、開発メンバー全員が顔を合わせることにこだわった。その結果、抽象度の高い概念の共有レベルが上がっただけでなく、オンライン上のコミュニケーションまで効果が表れ、開発は加速していったという。
宮里氏はというと、STORESのプロダクト間で顧客データを連携できる仕組みの開発を進めている。STORESは企業統合を経て誕生した会社であり、現在のプロダクトも元を辿ればそれぞれ別の会社でつくられたものだ。つまり思想もつくり方も異なるプロダクトのデータを統合することとなるため、非常に難易度の高い挑戦でもある。
一方でプロダクト間の連携を強固にすることは、STORESの強みの強化にもつながる。そして連携を強化するためには、実際に開発を担うPdMやエンジニアたちが、プロダクトの枠を超えて連携・連帯することが欠かせない。連帯感醸成のために、事業部を超えてオフラインで交流するプロダクト会議を定期的に実施するなどの取り組みを行いながら、連携を進めているのだという。
以前の同社noteでのインタビューで、西岡氏は「お店を作ることが『ストアーズする』と言われるようになることを目指したい」と話していた。そうなるのは果たして何年後か。これからも彼らの挑戦を追っていきたい。
パラレル・石田 達也氏と稲田 隼人氏──それぞれの強みを活かして取り組むプロダクトマネジメント
今や日常に完全に溶け込んだSNS。読者も友人との交流、情報収集、ビジネス機会の創出など、さまざまな用途で『X(旧:Twitter)』や『Instagram』、『TikTok』などを使っていることだろう。だがこれらのサービスはすべて海外で誕生したものである。2010年頃に大流行した『mixi』やバーチャルワールド『Yay!』など国産SNSも複数存在しているが、世界的なメインストリームにはなれていないのが現状だ。
そんななか、海外比率25%を達成した注目のSNSが“友達と遊べるたまり場アプリ”の『パラレル』だ。2024年3月にはシリーズCラウンドにて、KDDI Open Innovation Fund 3号などから総額約12億円の資金調達を実施した。累計調達額は約29億円となり、国産SNSスタートアップでは最大規模の調達実績となった。
同社のプロダクトの特徴は、ゲームや動画、音楽などのコンテンツを楽しみながら友人と交流できることだ。これらのコンテンツはすべて無料。通話やチャットのみならず、ボイスチェンジャーなどのコミュニケーションをより楽しくする機能も搭載。気軽に友人とオンラインゲームを楽しめることからZ世代を中心に人気となり、口コミでユーザーを増やした。2024年4月現在のユーザー数は400万人を超えている。
こうした遊び心満載のプロダクトのPdMとして紹介するのは、新卒でゲーム会社に入社し、チーフプランナーやプロデューサーを経て、ゲームタイトルの売上回復に貢献するディレクターとしても活躍した経験のある石田達也氏と、新卒でグリーに入社し、ソーシャルゲームチームのマネージャーを経験した後、ビズリーチでプロダクトマネージャー、プレイドでCSになるなど幅広い領域を経験してきた稲田隼人氏だ。
コンテンツを友人と楽しむという、アプリの使いやすさや利便性はもちろんだが、ユーザー満足度の向上にはコンテンツの質が求められる。また、ただ質が高いだけでなく、友達と遊んで楽しいことや、友人同士の絆を深められることも重要だ。石田氏は、ゲーム会社での経験やゲーマーとしての自身の感覚を活かし、ユーザーが「この人と遊んでいると楽しい!」と思えるコンテンツづくりに取り組んでいる。
「プロダクトマネージャーがをしている人間がコンテンツまでつくるのか?」と思われただろう。しかし、パラレルというプロダクトを開発の肝はユーザーの「楽しい」という声に他ならない。PdMとはユーザーの声を拾い、さまざまな仮説検証を経てプロダクトを進化させる存在である。そう考えれば、コンテンツづくり=プロダクト開発といっても過言ではないのではないだろうか。また、石田氏は過去のインタビューにて、そこにやりがいを感じるとも語っている。
一方の稲田氏は、多彩な経験を活かすかのように、「周囲が拾いきれないボールを拾いまくることを心がけている」と過去のインタビューで語っている。ビジネスサイドと開発サイドがそれぞれ得意なことに邁進できるよう、そこから溢れた部分をPdMとして担っているのだ。同氏は「良いプロダクトはいいチームから出来る」ということを信じており、自分にしかできないPdMの役割をパラレルで果たしている。このようにそれぞれアプローチの異なる形で、よりよいプロダクトづくりに向けて日々開発を進めている。
『パラレル』は友人たちとのクローズドなコミュニケーションに主眼を置いており、『X(旧:Twitter)』や『Instagram』のように多くの人に何かを伝えることを念頭においたSNSとは、プロダクトの思想も方向性も大きく異なる。だからこそ、世界を取れる可能性は十分に秘められているのではないだろうか。『パラレル』が世界中に広まり、世界中で「あとで『パラレル』に集合ね!」という会話が地球のそこかしこで交わされる日も近いのかもしれない。
ファインディ・下畠隆志──ユーザーの声を糧に成し遂げる進化と成長
2022年5月、Forkwell社の調査により「エンジニアは転職した方が給与が上がる」傾向にあることが判明し、話題になったことを覚えているだろうか。実際に、スキルの高い優秀なエンジニアの場合、転職を通じてステップアップし、自らのスキルも収入も着実に高めていることは多い。
そしてそうしたエンジニアたちのキャリアを支援するべく、数多くのエンジニア向け転職サービスが存在している。本章で取り上げるファインディは、そうした数多のサービスのなかで、「エンジニアの転職といえば」と真っ先に名前が上がる企業のひとつと言えるだろう。2022年4月にはシリーズCラウンドにて、約15億円の資金調達を行うなど、順調に成長も見せている。
同社からは、これまで紹介してきた経験豊富ですでにエースといえるPdMたちと異なり、今まさにエースとして成長しつつあるPdM、下畠隆志氏を紹介したい。2023年2月より同社のPdMとして活躍する下畠氏は、なんとPdMは未経験。2年間従事した同社のユーザーサクセス職(キャリアアドバイザー)からPdMへと転向した。
下畠氏も自身のブログで「気づいたらプロダクトマネージャーになっていた」と書いているように、たとえばPdMの選考を受けて入社したとか、社内公募に応募するような形で自ら志望したとか、そんな経緯でPdMとなったわけではない。当時同社が取り組んでいた開発プロジェクトが、たまたま下畠氏と業務と関わりが深かったために、開発ミーティングに入るようになったのがきっかけだった。そしてミーティングを重ねるなかで、結果的に下畠氏が企画を巻き取ることに。そうしていわば成り行き的にPdMにキャリアチェンジすることとなった。
どんなプロダクトであっても、PdMはユーザーの声を知ることが重要とされる。そして技術の移り変わりも速く変化が激しいエンジニア領域では、その重要性はとりわけ高い。いくら最新技術を駆使しても、ユーザーに受け入れられなければ意味がないからだ。プロダクトを開発するエンジニアだからこそユーザーのニーズを理解し、適切な技術選定とUXなどの設計を行うことが重要だろう。ファインディ社としてもユーザーインタビューを重視している。
その理由は、主力プロダクトである『Findy』がまさに、ユーザーインタビューから生まれたプロダクトだからだ。代表の山田裕一朗氏がユーザーの声を聞くなかで、エンジニアと採用担当との間にギャップがあることを知り、それを埋めるために『Findy』が生まれたのだ。こうした原体験を持つ山田氏の経営する企業だからこそ、同社にはユーザーの声を大切にする文化が深く根付いているのではないだろうか。そしてそれが、同社のエンジニアからの評価、ひいては成長につながっているのではないだろうか。
『Findy』には、GitHubとの連携によるスキル偏差値や年収予測の算出やユーザーサクセス面談などの独自の機能・サービスも多い。これらの開発背景には、深いユーザー理解があるはずだ。
その点下畠氏は、ユーザーサクセスの場で2年間ユーザーの声を聞いてきた人間だ。そしてPdMになって以後も、ユーザーインタビューに精力的に取り組んでいるという。これまでのユーザーと真摯に向き合ってきた経験と、そこで培われたユーザーの声を聞くスキルを武器に、彼はどのようなインサイトを捉え、どのようにプロダクトを進化させていくのだろうか。エンジニア未経験でありながらPdMとなった下畠氏だが、どうやら社内のエンジニア達からの信頼は厚いようだ。近い将来エースPdMとなるかもしれない彼の今後が楽しみである。
こちらの記事は2024年08月08日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。