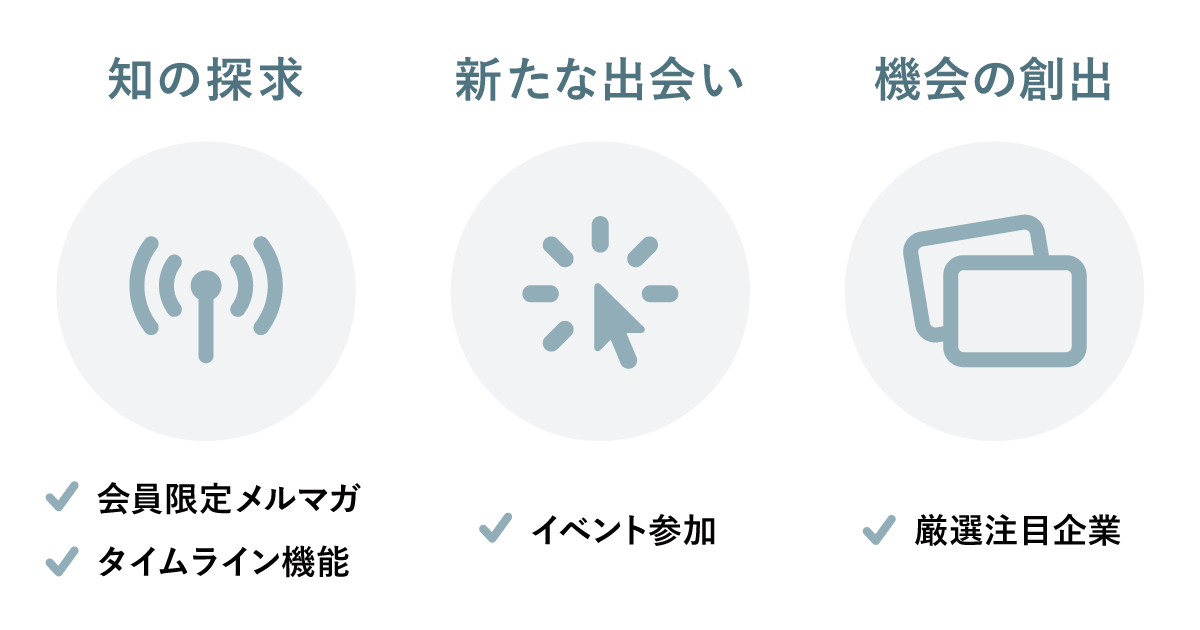ドローンで災害時の地図を作る青山学院大学・古橋大地教授の活動
災害時の地図「クライシスマップ」を作成しているのはボランティアの人々。青山学院大学の古橋大地教授はこの地図を作ってきた。作成のために今注目している技術は、ドローンという。
- TEXT BY KEI TAKAYANAGI
- EDIT BY MITSUHIRO EBIHARA
災害対策を支えるクライシスマップ
大規模な災害から身を守るために、最重要と言っても過言ではないのが安全な道や避難場所を知るための地図だ。しかし、普段使っている地図が災害時にも役に立つとは限らない。
例えば、大地震によって建物が倒壊した場合、安全な道と危険な道の区別はつかなくなる。また、洪水や火災の発生時にどの方面へ逃げれば安全か、火山の噴火などで溶岩や土石流が広がっているエリアはどこなのかといった情報はリアルタイムで変化するため、災害の状況をそのまま反映した最新の地図が必要になる。
この災害時の地図は「クライシスマップ」と呼ばれ、世界各地の大規模な地震などの際に、救助隊や被災者達に活用されてきた。
では、この地図を作成しているのは誰なのだろうか。実は、近年の世界各地における災害において活用されたクライシスマップは、国の公的な機関が常に提供しているわけではなく、「マッパー」といういわばボランティアの人々や非営利のチームが、その作成の多くを担っているのだ。
青山学院大学の教授として、市民参加型のオープンストリートマップについての研究や実践を進めている古橋大地氏は、そのマッパーの一人であり、またNPO法人クライシスマッパーズ・ジャパンの理事長でもある。

古橋私達マッパーは、被災地の状況が撮影された写真を使い、最新の被災状況を反映した地図をつくっています。マッパーは世界中に居て、インターネットで現地の情報を共有しながら作業を進めていきます。
マッパー達による地図づくりが活発になり始めたきっかけは、2004年に設立された「OpenStreetMap(OSM)」の存在が大きい。
OSMは、自由に編集、活用できる地図情報のデータベースをつくるプロジェクトとして、当時ロンドン大学に在籍していたスティーブ・コースト氏(現・Telenav Head of OSM)によって立ち上げられた。
アカウント登録をすれば誰でもが編集でき、利用だけであれば登録なしで利用できるプラットフォームにおいて、オープンソース系のエンジニア達を中心として常に世界中のどこかで、マッパーの誰かが地図の作成を続けている。
OSMがクライシスマップとして大いに注目を集めたのが2010年のハイチ地震。当時、インターネット上にはハイチの街の地図はなかったが、地震が発生した直後に、マッパーが自発的に地図を書き込み始めた。
最終的には2000人以上のマッパーが携わり、1週間かからずに詳細な地図ができあがっていったという。古橋氏も当時、マッピングを行い「情報さえ集めれば、現地にいなくともすぐに地図ができることを肌で感じた」と話す。
OSMでつくられたハイチの地図は、現地の避難や国連などの救援活動に活用された。その後、2011年の東日本大震災、2015年4月のネパールの地震でも震災後の正確な地図がつくられている。

古橋現在はマッパーの育成にも力を入れています。大学の授業の一環として地図づくりに取り組んだり、高校で数百人を対象にマッピングの講座を行いました。OSMにおける地図の更新は、つくっている時は目的は分からないけれど、災害に活用されたようにきっと何かの役に立つ時がやってくる。その時のためにマッパーを増やしていくことが必要と考えています。
迅速な地図作成に欠かせない情報入手
OSMの地図は、細かい路地や最新の状況を反映しているため、地元に住む人々や観光などでも非常に使いやすく、多方面で活用が進む一方、災害など迅速に地図を作成する必要がある際の情報入手が常に課題となってきた。
古橋地図を作成する時に、最初に必要になるのが、リアルタイムの状態が分かる画像データ。その画像はマッパーのコミュニティーで入手するのですが、現在では民間の人工衛星や軍事機関、JAXAなどさまざまプロバイダから情報が提供されます。
通常のマッピングであれば、それらの情報で十分なのですが、クライシスマップでは状況が異なります。もしヘリコプターや人工衛星で情報を得た場合、天候や衛生の軌道の問題で、画像の入手に1日以上かかるケースが多い。
東日本大震災の時も、一番最初に画像が入手できたのが発生の翌日。2016年の熊本地震の時は数日かかりました。
そこから地図を作成した場合、最新の状況が反映された地図は、更に半日以上経たないとできない。災害時に人命に関わる最も重要な時間は、発生から72時間と言われます。すぐに現地の画像が届いてマッピングを始められる仕組みをつくれないかと考えていました。

情報の入手方法を模索する中で古橋氏が注目したのが、ドローンであった。
ドローンであれば、地上からの手動操作や自動操縦により、洪水で浸水したエリアや、土砂崩れで人が入れないエリアでも、すぐに画像や映像を撮影できる。
このドローンを使った画像情報の入手と迅速なマッピングの仕組みとして、現在、クライシスマッパーズ・ジャパンが進めているプロジェクトが「ドローンバード」だ。
古橋現在、ドローンは個人の趣味だけでなく、測量や映像撮影のために企業が活用する動きも見られ、『空の産業革命』として物流などさまざまな分野での可能性が期待されています。しかし、災害時の救援活動にうまく活用できている団体はほとんどない。航空法などの法律や飛行時のルールづくりが問われているドローンですが、クライシスマップの作成など人道支援の観点で言えばすぐにでも活用を進めていくべき存在です。

ドローンバードで目標としている活動は、主に「操縦士の育成」とその画像をもとにした「迅速なマッピング」の連携。
現在、東京都心で約3000人のマッピングボランティアコミュニティーがあり、常時数百人が動ける状態にある。目標は常時1000人程度が稼働でき、災害時に発生後1〜2時間程度で都心全体の画像が入手できる体制をつくることだ。
一方、これらの仕組みを整えるため、災害時でなくとも街並みの撮影や測量の分野での空撮の依頼を受けたり、ドローンの販売などである程度の収益性も確保している。また行政と連携して、ドローンを使ったイベントや地域振興にも積極的に取り組んでいるという。
古橋マッピングやドローンの活用がもっと身近になることで、結果的に災害時に貢献できる可能性がある。現地でのボランティア活動や募金とは違う、災害支援の形になるかもしれません。

OSMのマッピング作業や、ドローンの操縦はある意味で“楽しめる趣味”のような一面も持つ。いつ起きるか分からない災害に、日頃から備える防災の新しいスタイルとして、今後どのように社会に浸透していくか注目したい。
こちらの記事は2017年11月26日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
次の記事
執筆
高柳 圭
編集
海老原 光宏
連載THE STARTUPS SAVE THE WORLD
6記事 | 最終更新 2017.12.17おすすめの関連記事
和製ユニコーンを創る。テラドローン関が明かす、世界基準のPDCA手法とは?
- Terra Drone 株式会社 取締役
「空の産業革命を牽引する」世界のドローンリテラシー底上げを目指す若き起業家 FLIGHTS峠下
- 株式会社FLIGHTS 代表取締役
スタートアップ、“国家プロジェクト”を背負う──被災地でも活躍、世界最小級のドローン企業・Liberawareが創る社会インフラ
- 株式会社Liberaware 取締役CFO
政府が託す、52億円の技術イノベーション──Liberawareエンジニアが牽引する、国家主導の鉄道インフラDX
- 株式会社Liberaware 取締役 技術開発部長