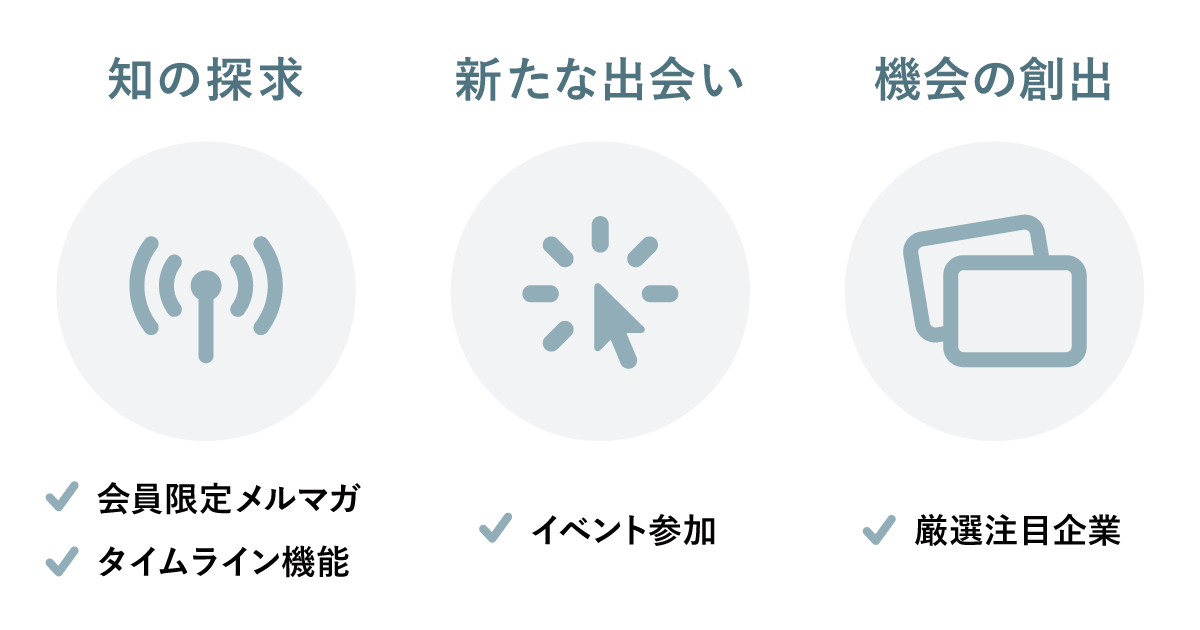焼き鳥屋も始める准教授、創業2年で3カ国展開のフードテック──データで探し、直感で選ぶ“異端児”な起業家たちが、日本の産業地図を塗り替える?
Sponsored「組織のはみ出し者こそが、本当のイノベーションを起こせる」──。
データドリブンな投資判断と“異端児”への共感。一見相反するその2つの要素を武器に、HAKOBUNEは日本の産業地図を塗り替えようとしている(詳細はパートナー対談記事を参照)。
では、彼らが見出した“異端児”たちは、実際にどんな変革を起こそうとしているのか。
カーボンクレジット取引所から大学改革、さらには焼き鳥店の経営まで──。従来の常識では理解しがたい多面的な展開を行う日本GXグループ。そして、植物工場での大豆生産からプラントベースフードの世界同時展開まで、食品業界の既存構造に挑むディッシュウィル。
この2社に共通するのは、既存の産業構造を根本から変えようという"型破り"な野心だ。しかも、その挑戦は決して場当たり的なものではない。
「普通のスタートアップだと選択と集中っていう言葉は死ぬほど言われるじゃないですか。手広くたくさんのことをやっていて遊んでるように見えるんですけど、ルールメイクをするための選択と集中を圧倒的にやってるんです」。日本GXグループ代表の細目圭佑氏はそう切り出す。
一方のディッシュウィルCEO中村明生氏も、13年の上場企業経験を経て36歳での起業を決意。世界市場での勝負を見据え、研究開発に異様なまでのリソースを投じる。
彼らの挑戦が示すのは、既存の常識を超えた"型破り"な戦略が、むしろ緻密な計算に裏打ちされているという事実だ。
今回、この2社に投資するHAKOBUNEの栗島祐介氏を交えた鼎談が実現した。そこで語られたのは、日本の産業構造を変えようとする“異端児”たちの、意外なまでに理にかなった野心の正体だった──。
- TEXT BY SHUTO INOUE
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
「データで探す“異端児”、直感で見抜くイノベーター」──HAKOBUNEが描く新しい投資の形
ビジネスの世界で最も難しい決断。それは、何もないところから可能性を見出すことだ。 シード期の投資というビジネスでは特に困難がつきまとう。事業の実績も、ビジネスモデルの検証も、市場の確からしさも──。判断に必要な手がかりがほとんど何一つない段階で、その可能性を見抜き、巨額の資金を投じる。
しかし、HAKOBUNEはその常識すら覆そうとしている。徹底的なデータ分析と、型破りな発想への共感。一見相反するその2つの要素を組み合わせることで、新たな投資の地平を切り開こうとしているのだ。
なぜ、今このタイミングなのか。HAKOBUNEのパートナー栗島祐介氏は、投資環境の劇的な変化を指摘する。
栗島今、決定的に変わったのは、スタートアップを取り巻く環境です。例えば、政治との距離。『LUUP』の電動キックボードがまさに典型例で、規制緩和とスタートアップの連携が、もはや当たり前になってきています。
大企業との協業も然り。わずか5年前なら“オープンイノベーション”という言葉自体にも違和感がありましたが、今や、誰も怪訝な顔をしないですよね?
特に注目すべきは、投資規模の劇的な変化だ。
栗島また、私たち投資家の目線でも、より大きな挑戦が可能になりました。少し前までは正直、数十億~数百億円規模の事業に向けた投資が多かったように感じます。でも今は違う。最近のスタートアップの調達金額を見ればわかると思いますが、100兆円規模の市場を狙っても、それを支える資金を調達できる。アメリカのような桁違いの挑戦が、日本でも現実的な選択肢になってきたんです。
こうした変化は、新たな投資機会を生み出している。では、それをどう見出し、育てるのか。
その最たる事例が、日本GXグループの共同代表細目氏の存在だ。
同社の創業以前から、大手上場企業の新規事業開発を外部で実証・実験・執行する「出島COO組織(既存事業・従来組織の制約を受けずにヒト・モノ・カネを投下するチームを別会社として組成する)」として、独自の新規事業開発手法を実践してきたのだ。

細目氏
細目日本GXグループの前身にあたる渋谷ブレンドグリーンエナジーという会社を立ち上げて、新規事業開発の世界に、まったく異なるアプローチを持ち込んだんです。
大手上場企業の新規事業って、“必ず成功させなければいけない”という縛りみたいなものがありますよね。だから大手コンサルティングファームとか大手広告代理店が入って、年間3,000万円ぐらいのプランで、かっこいい企画書をつくって「3年でPoCをやりましょう」と提案する。
でも、多くの場合、机上の空論に終わっちゃう。“失敗するとマイナス評価になること”が前提になっているためです。説明書や前例がない中で一定の正解に辿り着くためには、論理以上に執行を伴う徹底的な試行錯誤が必要なはずなのに。
だから私は敢えて出島というかたちで、大手企業の「失敗できる場所」をつくることにしたんです。全国に“秘密基地”なるものをつくって、チャレンジングな若者を集め、数十ヶ月で何百という失敗を重ねる。そうやって大量の実験を重ねることで、確率論的に大手上場企業の経営者の方々が唸る新規事業の正解らしきものに辿り着こうとしてきたんです。成功確率が1/100だとしたら、偏差値75の受験脳がなくても99の失敗を重ね続ければ正解1が生まれそうじゃないですか。真面目に不真面目をやる感じです。
この経験こそが、現在の日本GXグループの独創的な事業展開のDNAだ。カーボンクレジット取引所の設立から、国立大学改革、さらには焼き鳥店の経営まで──。従来の常識では理解しがたい多面的な展開の背景には、実は緻密な戦略がある(詳細は後述)。
細目氏を始めとした日本GXグループの行動力は、尋常ではない。数人のチームで証券取引所を立ち上げ、シンクタンク機能もつくり、GXコンサル事業も展開。半年で3つの事業を成立させるという離れ業を、まるで当然のことのように成し遂げた。
栗島細目さんこそ、我々が投資先として理想とする「異端児」そのものでした。十分な実績や経験を培った上で、既存の枠組みを超えて社会にインパクトを与えようとする。その行動力と専門性を兼ね備えた「大人起業家」。こんなチームに、出会うことは正直難しいですが(笑)。
一方のディッシュウィルは、食品業界が抱える根本的な課題に挑む。

中村氏
中村私は13年間、食品業界で新規事業開発に携わってきました。その中で痛感したのは、日本の食品メーカーが持つ可能性と、それを活かしきれていない現状のギャップです。例えば大豆加工品。日本は世界でも最高レベルの技術を持っている。でも、その技術を活かして世界市場で戦おうとする発想がない。
また、投資家サイドからからもよく言われるんです。「食品って、そもそもバリューが付きにくい。上場したフードテック企業の株価が伸び悩んでいるじゃないか」など……。プラントベース食品となると、なおさら懐疑的な目で見られます。でも、それは近視眼的な見方だと思うんです。
栗島多くの投資家が、足元の収益性だけを見て判断してしまう。でも、中村さんのご経験と問題意識、そしてその解決に向けた戦略の明確さに触れて、我々は投資するしかないと考えました。
食料問題は、今後10年の間に、間違いなく世界的な課題になる。気候変動、人口増加、環境破壊──これらの問題が顕在化した時、テクノロジーと日本の伝統的な食品加工技術を組み合わせた新しいアプローチが、決定的な意味を持つはず。むしろ、今このタイミングで投資できることは、我々にとって大きなチャンスですよね。
日本GXグループとディッシュウィル。一見、全く異なる領域で事業を展開する両社だが、その本質は驚くほど似ている。既存市場の構造的な歪みを見出し、そこに真っ向から挑む。しかも、その挑戦は決して場当たり的なものではない。
では、彼らはどのようにして、その革新的な構想を現実のものとしようとしているのか。
既存市場の“当たり前”に、真っ向から挑む──型破りな戦略の裏にある緻密な計算
日本GXグループとディッシュウィルには、まだまだ共通点がある。それは、既存市場の「当たり前」に潜む致命的な歪みを見出し、そこに切り込もうとする視座だ。
両社とも、現在の社会構造を変えようと、前例のない踏み込んだ事業展開を進めている。ディッシュウィルが対象としているのは、食料生産システムが抱える根源的な矛盾だ。
中村着目したのは、現代の大豆生産が抱えるジレンマです。
実は日本のODAが、ブラジルのセラード地帯の酸性土壌を改良するなどし、世界有数の大豆生産地に変えたんです。これ自体は文句なしに素晴らしい技術革新でした。でも皮肉なことにこの開発が、アマゾンの森林破壊の原因になっている。大豆の耕作地を広げるために、2023年だけでニューヨーク市3つ分の面積の森林が燃やされ、失われたんですよ。このジレンマを解決するには、生産システムそのものを変える必要があるんです。
その解決策として同社が選んだのが、植物工場を立ち上げて大豆を大量生産するという、スタートアップとしてはまだほとんど前例のない挑戦であった。「研究開発の現場を見ていただければ、私たちの本気度がわかると思います」という口ぶりからもわかる通り、ディッシュウィルの研究開発体制は異様とも言える充実ぶりだ。
なんと社員の60%以上が研究者で、日清食品の元プラントベースラーメン開発者や世界的企業ADMからの研究者も参画。その道10年以上のベテランばかりを揃えた開発チームは、2022年創業の若きフードテック企業というイメージを大きく覆すものだろう。
中村日本では、大手企業のプラントベース食品開発チームですら、多くてもメンバーは8人程度。しかもプラントベース経験者ゼロからのスタートなんてのがザラにあります。でも、そんな体制で世界と戦えるはずがないですよね。私たちは最初から、グローバル市場での勝負を見据えた人数規模と知見を集めた組織をつくっています。
その徹底ぶりは、すでに具体的な成果となって現れ始めている。大手外資ホテルの総料理長から直々に「自分たちのつくるプラントベース料理より美味しい」という評価もされたのだとか。

ディッシュウィルが開発したプラントベースのハンバーガー(同社提供)
中村品質や味について評価いただくことももちろん嬉しい。でも、より重要なのは、この品質を維持したまま大規模生産できる体制を構築できたことです。
日本の食品企業なら売上500億円規模でも大手扱いですが、私たちはその壁を超えて世界で戦えるはず。いや、こういったスタイルでないと、食品企業が世界で勝つことは難しいと感じています。
そして、日本GXグループが取り組むカーボンクレジット関連事業も同様に、構造変革の最たる例だと言える。
カーボンクレジットとは、企業のCO2排出量を相殺するための「環境価値」だ。例えば、再生可能エネルギーの導入や森林保全によってCO2排出量を削減した分を、クレジットとして取引できる仕組み。2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、その重要性は日に日に高まっている。しかし、日本の現状は深刻だ。
細目日本の上場企業約4000社のCO2排出量は年間約10億トン。この10年で日本国内で生み出されたカーボンクレジットはわずか約1,000万トン。2桁の差がある。脱炭素の取り組みが各社で増えていくわけなのですが、そうして年間排出量が減ったところで、「そのうち埋まるだろう」と楽観視できるような一時的な需給ギャップではないんです。もっと大きなギャップが存在しており、そう簡単に解決できない構造的な深い問題があるんですよね……。
その原因は、既存の事業構造にある。
細目それこそ、「出島COO組織」を運営していた頃に気付いたのが、大企業がサステナブル領域での新規事業を始めたところで、もしうまく立ち上がっても、結局2~3年でほとんどが頓挫してしまう、ということ。
なぜか。利益率の確保が難しいからです。既存の売上に対して、普通のコストに加えて、サステナブルに続けるためのコストが上乗せされる。でも売上はなかなか増えていかない。このジレンマが必ず立ちはだかりますから、構造から解決しない限り、サステナブル領域の市場は大きく育ちづらいんですよね。
その課題に対し、日本GXグループが選んだのは、取引所という「場」の創造だ。
細目しっかりとした取引所システムをつくろうとすると、外注するとざっくり5億円はかかる。これは創業期のスタートアップには非現実的な金額です。
でも、だからこそチャンスがある。我々は自らつくれちゃう仲間を集め、全て内製化することで、この参入障壁を突破しようと考えました。
栗島内製ならたしかに5億円はかからないとしても、普通なら資金以上に仲間集めのハードルが高くて諦める話ですよね(笑)。でも細目さんたちは、その制約すら突破口に変えてしまったんです。
「出島COO組織」で培った経験を活かし、システム開発の内製化を内省する。それが実現すれば、その後はむしろ大きな参入障壁として機能します。すでにGXコンサルティングや顧問参画といったかたちで大企業複数社との話まで進んでいます。ここまでの構想力と実行力を併せ持つチームは、本当に稀有だと思います。

栗島氏
両社に共通するのは、業界の構造的な歪みを見出し、そこに絶好のアプローチ手法と“異端者”とも呼べる狂気的な行動力で突破する力だ。それでいて、これらは単なる理想論ではない。むしろ、緻密なデータ分析と科学的アプローチに裏打ちされているのが面白いところ。
では、彼らはどのようにして、その革新的な構想を現実のものとしようとしているのか。その答えは、「市場を待つ」のではなく「市場を創る」という、独自の発想にあった。
「規制緩和待ち?それって他責では?」
ルールも仕組みも、全部自分たちでつくる
参入障壁は、見方を変えれば最大の機会となる。
従来型のスタートアップは、既存市場の分析から始める。市場規模(TAM)を測り、競合との差異化を図り、参入のタイミングを計る──。ただし、真にゲームチェンジングな事業にとって、そんな常套句は関係しない。むしろ、ルールや市場を自分たちでつくり出すというアプローチこそが必要になる。
細目規制緩和があるからうまくいく、規制緩和がないからうまくいかないとかって、確かに結果論としてはわかりやすいですが、現場の私たちにとってはそんなの他人事だと思っています。自分ゴト化して、世の中で必要だったら規制緩和されるし、すぐにそうなるわけじゃないのならもう新たな市場のためのルール自体をつくればいい。事業ができないと他責にするのではなく、自分ゴト化して、つくってしまえばいいんです。
世界の金融市場で、今まさに歴史的な転換点が訪れている。実際、日本と欧米の制度的な差異は、新たな市場を創出する絶好の機会となっているのだ。

細目カーボンクレジットは金融商品としての性質をもちつつ、現状、日本では棚卸資産や無形固定資産として取り扱うことができます。当時、金融商品になっていないカーボンクレジットを取り扱える会社は稀だったので、我々の存在意義は「いろいろな金融機関の“潜在的な出島組織”であるということ」なのだと考えました。だから私たちは、近い将来、自らが金融会社になることすら設計図として組み込んだスタートアップをやっているわけです。他の企業にはなかなかできない動きですよね?
東証さんのカーボンクレジット取引の推進についてきちんと勉強をさせていただきながら、上場企業様やカーボンクレジット創出者様のご意向を踏まえながら、ユーザー目線の未来の取引の形をプロトタイピングしていくわけです。
加えて、ここがポイントなんですが、来年2025年からは個人向けカーボンクレジット取引所も展開します。なぜか。現状、環境価値へのアクションは機関投資家や事業会社に限られている。でも、本当の意味での市場の厚みをつくるには、個人の参加が不可欠なんです。これは歴史が証明していますよね。
このように、空白期間に絶望するのではなく、チャンスを見出すんです。
この「市場を創る」という発想はディッシュウィルも同様だ。食品業界で革新を起こすため、既存の常識を覆す戦略を展開しているのだ。
中村一般的な食品メーカーは、まず国内市場で実績をつくり、それから海外展開を考える。でも、それでは世界で戦えない。私たちは最初からシンガポール、UAE、アメリカと、同時多発的に市場を開拓しています。
というのも、シンガポールでは、食料自給率が8~9パーセントしかないのですが、それを30パーセントまで上げようという重要な国家戦略がある。つまり、日本以上に国全体が総力を上げてこの課題に取り組んでいるんです。そこに、私たちの植物工場というソリューションが完全にフィットするはず。
また、アメリカでは一般消費者からのニーズが多く、今ちょうど有名ラーメン店との大規模な取引を進めているところです。
実際、他の国では半年で10万円程度の実績しかない市場もありますが(笑)、同時多発的に進めることは不可欠だと思います。
大事なのは、市場の反応を見ながらリソースを最適配分できる体制をつくることだと思いますね。
市場を創るということは、単なる新規参入とは次元が異なる。それは、産業の構造そのものに切り込む試みであり、“99回の失敗”も当然、覚悟しなければならない。いや、細目氏に言わせれば「99回の失敗は、絶対条件」なのだ。
では、彼らはいかにしてその圧倒的な失敗を積み重ね、そこから新たな価値を見出そうとしているのか。
意図的な“99回の失敗”が、イノベーションを生む──量子力学から生まれた破天荒な経営理論
「むしろ、99回の失敗を意図的につくり出す」という両者の発言の背後に、量子力学的な思考がある。もともと量子力学と有機合成化学が専門であった細目氏は、その知見を経営に応用しようとしている。
細目めちゃくちゃ難易度が高すぎて普通の人間では認知できないような問いがあるとして、量子力学には反復収束っていうアプローチ方法があります。最初に仮の答えを適当に設定して、それを元に計算してみる。最初はまぁ当然間違ってた答えが出てくるんですけど、それをまた方程式に代入してみる。諦めずに何度も繰り返して、少しずつ答えを修正していくと、最終的には確からしい答えにたどり着くんです。
この発想を経営に応用すると──。
細目これって新しい当たり前を生み出そうする過程と似てまして。最初から正解はわからない。だから、とにかく試行錯誤を重ねる。多くの企業は失敗を避けようとしますが、むしろ、意図的に99回の失敗をつくり出す。なにか1つの正解候補に近づける気がしませんか?さらに観点をもう一つ入れるとすれば、たくさん生み出してきたプロジェクトたちについて、「混ぜるな危険」を怖れず、カオスな組み合わせを楽しみたい。
その理念から導かれるアクションは、一般的な経営の常識を覆すものばかりだ。例えば細目氏は、宮崎大学の准教授として、従来の教育の概念を根本から覆す実験を始めている。その最たる例が、「謎解き教科書」プロジェクトだ。
細目私は今、宮崎大学で准教授として教鞭を執っています。でも、従来型の教育には限界がある。だから、まったく新しいアプローチを試みているんです。例えば、この教科書。
細目氏が取り出したのは、一見すると普通の大学の教科書……ではない。透明なケースに入れられたボールペン(のようなもの)だ。
細目普通の教科書は、文章の形で、なんページにもわたって説明が記載されていますよね。でも、この教科書は文章どころか、本ですらない。
面白いことに、小学生はこの“謎解き教科書”をかなり早いスピードで解いてしまうのですが、背広を着たビジネスパーソンにはなかなか解けない。大人は理由を求めすぎるんですよ。子供は純粋に試行錯誤を楽しむ。時には壊しちゃったりね。その違いが、おもろいくらいに謎解き正解率に反映されます。これからGXに関わる大学発ベンチャーも作っていくのですが、現地現物や手触り感を大切に一緒に企める学生チームがこういう教育プロセスから出来上がったら面白いな〜と。
宮崎大学生協にて謎解き教科書が本日より発売!
— yoshino | 未来ACE (@MiraiaceYo) December 9, 2024
宮崎大学 細目特別准教授の教科書として販売。ケースを開ける所からスタートして、教科書に辿りつくというギミックが仕掛けられています。
本ギミックを考案し制作・納品まで協力させて頂きました。 pic.twitter.com/5jN6fw96ry
実はこの教科書、1冊1万円という破格の価格で販売され始めている(気になればこちらで直接ご確認を)。「よく映画で、このボールペンを1万円で売ってみろ、というシーンがありますよね。あれを地で行ってみようと(笑)」。その真意は深い。学びとは何か、教育とは何か──その本質的な問いかけが、この一見突飛な実験の根底にあるのだ(種明かしをするわけにもいかないので、気になった読者は購入するほか、細目氏に直接コンタクトを取ったり、宮崎大学を訪れたりしてみてほしい)。
地方国立大学のあり方のアップデートに止まらず、日本GXグループを経営しながら焼き鳥屋事業も展開する破天荒な試みも行っているのが細目の“異端児”らしさを物語っている。
細目2024年冬に東京五反田で焼き鳥屋さんを、同世代の仲間と共同出資で立ち上げました。九州をはじめとした素敵な生産者さんから、備長炭や鶏、お酒、お茶を仕入れさせていただいています。
GXの本質は、これからのゆたかな時代に向けて、どうモノを作り、運び、使うか、つまりサプライチェーンの最適化をすることです。漁業、林業、畜産業、農業の方々と、生産性や後継者問題、カーボンクレジットなどの会話をさせていただく機会が多いのですが、やはり「おいしいものをどうつくるか、どう売るか」という話がメインになるですよね。
サプライチェーンの出口の一つとして飲食業を持つことは、生産者さんと本質的に対峙するための大切な装置なんです。焼き鳥屋さん、めちゃくちゃおいしいんでぜひ食べにきてください!愛がたっぷりなんで。
この「失敗を恐れない」という哲学は、ディッシュウィルの開発プロセスにも通底している。
中村あるラーメン店向けにプラントベースのチャーシューを開発した際、計96個の試作品をつくりました。面白いのが、二次関数のように徐々に完成度が高まったのではなく、91回目にして、ようやくブレークスルーが訪れ、良いものができたんです。採用されたのも96個目ではなく91個目でした(笑)。
もしかしたら、ここまで回数を重ねての試行錯誤をしている場合ではないと考える人もいるかもしれませんよね。「もっと早くできなかったのか?」なんて株主から言われてしまうかもしれない。でも、私たちには「完璧な1回」より「徹底的な複数回」の方が重要だとわかっていた。この粘り強さこそが、市場を創るための必須条件だと思います。
細目私たちのようなアプローチは、まだしばらく、なかなか理解されづらいかもしれませんね。
よく聞かれるんです。「なぜGXコンサルティングやカーボンクレジット取引所をやっているのに、焼き鳥屋まで手を出すんだ」とか「なぜ経営で忙しいはずなのに宮崎大学の准教授なんてやるんだ」と。でも、これらは全てただ、“市場をゼロから創るのに必要なこと”を実直にやっているだけなんです。
栗島カーボンクレジットは、結局は一次産業から生まれる環境価値ですもんね。農家さんや漁師さん、林業関係者の方々が、実際にクレジットを生み出す現場にいる。
でも、その方々は金融の専門家ではない。この現場の声を聞き、理解を深め、信頼関係を築かない限り、本当の意味での市場はつくれない。細目さんのように、焼き鳥店を通じて養鶏農家とつながり、大学の准教授として地域に入り込む。この「泥臭い」アプローチこそが、実は最も確実な市場創造の道筋だと感じざるをえません。
両氏に共通するのは、失敗を「意図的に」活用する視点だ。それは単なる試行錯誤ではない。むしろ、より大きなブレークスルーを生み出すための、戦略的な選択なのかもしれない。
とはいえまだここまでの話だけでは、「突飛なことをするアーリーフェーズの起業家は以前から存在しており、うまくいくとは思えない」と感じてしまっている読者もいるのではないか?そう感じた皆さんにこそ、もう少し読み進めてほしい。こうした型破りな手法から、大きな事業展開へと具体的につながる道筋もしっかり存在している。
「選択と集中」は不必要?
「複数の実験場」が織りなす新規事業創造スタイル
スタートアップの世界に存在する「選択と集中」という暗黙の前提。
しかし、既存の産業構造を変えようとするなら、その常識すら疑う必要があるのかもしれない。むしろ、複数の挑戦を同時並行で進め、その化学反応から新たな価値を生み出す──。そんなアプローチこそが、本質的なイノベーションを生むのではないか。
日本GXグループとディッシュウィルが選んだのは、まさにその道だった。
細目私は意図的に、複数の実験を同時に走らせています。例えば宮崎大学では、2024年4月の着任から半年でさまざまな官民学ステークホルダーと47件のプロジェクト原案を生み出しています。うち22件は既に設計完了していて、謎解き教科書や焼き鳥屋さん、ほかにも国立GX研究センター連携や藻場再生事業などがかたちになり始めています。
なぜこんなことをしているのか?実は大手上場企業や首都圏の大学と会話していると、実証・実装する場がそれぞれの現場に足りていないことが見えてきます。そこで私たちは、一つのアプローチとして、地方大学を執行チーム付きの実証実験の場として位置づけようとしているわけなんです。
宮崎大学でうまく進んでいる自負はあるので、どんどん他の地方大学も兼務しながら展開していきたいですね。

海藻養殖の実験を進める細目氏(同氏提供)
学生たちは、教室では得られない生きた知識と経験を手にし、地域の一次産業従事者さんたちは、最先端の研究知見にアクセスできる。そうして地域経済の活性化にも、スタートアップエコシステムの発展にも貢献する。この三方よしの構造こそが、プロジェクトがここまで拡大している所以と言えるだろう。
細目ちなみに、大学の授業要件をいじりながら、一緒に漁師さんや農家さんの現場に飛び込んでプロジェクトを進めてくれる学生たちに単位が付与される仕組みも構築中です。最近も授業を通じて大学公認サークルを作ってくれた学生たちが登場したんです。嬉しかったな〜。
従来の座学中心の教育の枠を、学生たち自身が超えていこうとする。これこそが私たちの狙いなんです。
教育に変革をもたらしながら、いくつもの事業を着実に生み出していっているわけだ。その蓄積が、社会に大きな変化をもたらすイメージも湧いてくるのではないだろうか?
一方のディッシュウィルは、より大胆な実験を、グローバル市場で同時多発的に展開している。シンガポール、UAE、アメリカという全く異なる3つの市場で展開を進めているのだ。先のも述べた通り、一般的な日本企業なら、まず国内で実績をつくり、段階的に海外展開するところ。しかし、「それでは世界で戦えない」と豪語するのが中村氏だ。
気になるのはなぜ、あえて同時多発的な展開を選んだのか。だろう。

中村プラントベースを食べたことがある人たちは、必ずプラントベースの弱点を探し出そうとします。日本市場はその傾向が特に強い。
一方で、アメリカの方30名ほどに、試食してもらった時の反応は「わお、何これクレイジー!」でした(笑)。アメリカでは、すでにプラントベースの商品が一般的になり、弱点よりも良い点に着目して評価しようという雰囲気が強いと感じます。
つまり、市場によって食文化も、プラントベース食品への許容度も全く違う。だからこそ、複数の市場で同時に実験を行い、その反応を見ながらリソースを最適配分していこうと思っているんです。シンガポールでの失敗が、UAEでの成功につながるかもしれない、その逆もあり得るかもしれない。学習の速度が、グローバル競争では決定的に重要になります。
栗島普通のスタートアップなら、リソースの分散を避けようとする。でも、この2社は違う。むしろ、複数の実験場を同時に走らせることで、想定外の化学反応を生み出そうとしている。この発想の違いが、既存の産業構造を変えられる可能性を生むんです。
「一点集中」ではなく「複数試行」を選択する姿勢。それは単なる試行錯誤ではない。データに基づく迅速な判断と、大胆な軌道修正を可能にする組織文化がある。
実験的なアプローチは、新しい価値を生み出すための方法論として着実と機能し始めているところだが、その先にある彼にとっての「豊かさ」とは、いったいどんな姿なのだろうか。
根底にあるのは、「新しい豊かさ」の探求
イノベーションという言葉は、ともすれば技術革新や効率化の文脈でのみ語られがちだ。しかし、本当の意味での革新とは、我々の価値観そのものを変えることにある──。
両社のことを深く知る過程で、次第に浮かび上がってきたのは、そんな根源的な問いかけだった。
細目今の時代、ゆたかさの定義自体を問い直す必要があります。私は、その定義を「おいしさと愛」と整理しています。一見、経営者の言葉としては突飛に聞こえるかもしれない。でも、現場に入ってわかったのは、これこそが本質的な価値なんです。

新規開店した五反田の焼き鳥店にて(細目氏提供)
その着想は、一次産業従事者との深い対話から生まれたものだ。
細目漁師さんや農家さんと対峙していると、命をかけて食糧を生み出してくれていることを実感できる。みんなにおいしく食べてほしいと言ってくださる。食文化を現場で支えてくれている。これをどうみんなに届けるか?ここが、グリーントランスフォーメーションの出番です。
燃料代や肥料代の高騰が、生産者のコストを圧迫しています。地球温暖化により、生産品種調整の要請があります。さまざまな面で、今までの当たり前が成立しない状態になりつつあります。
最終消費者のみなさんのことを考えた未来のサプライチェーンづくり、これこそが愛だなと感じています。人が人らしく生きていくための、全てのエネルギーの源は“おいしさ”です。みんなのおいしさを作るためには今までの当たり前にとらわれない愛ある挑戦が連鎖したサプライチェーンを生み出すわけですね。ボクが焼き鳥屋をやる理由はここにあります。
“おいしい”が安く手に入ることって、愛なんですよね〜。
中村海外でも日本食を食べることはありますが、成田空港に戻ってきた時のおでんの美味しさたるや──。この感覚になるたびに毎回“示唆深いな〜”と一人で想いを噛み締めています(笑)。
なぜ日本の食はここまで探求されるのか。なぜここまで世界中で愛されるのか。それは、単なる味覚の問題ではないはず。テクノロジーと職人気質が絶妙なバランスで融合しているのかもしれませんね。
そんな感覚をもって生まれた日本人である私だからこそ、「美味しさと環境負荷低減の両立」というコンセプトを目指せたのかもしれません。
一般的な代替肉は、どうしても「我慢して食べる」という印象が拭えないですよね。でも、日本にはすでに身近に「おいしくて、なおかつ環境にも良い」という発想がたくさんある。この価値観こそが、世界で戦える武器になるはずなんです。

ディッシュウィルのプラントベースフードにはスイーツもある(同社提供)
HAKOBUNEが両社に投資する理由も、まさにこの点にある。
栗島データなどを用いた戦略的な思考と、直感の融合。この2つの要素を両立できる経営者は稀有な存在です。でも、社会課題の解決と経済的価値の創造を本当の意味で両立させるには、この視点が決定的に重要になると感じます。
私たちが投資コンセプトとして“異端児”に注目する理由も、彼らが持つその特異な視座にあるのかもしれませんね。既存の枠組みの中で培った深い知見を持ちながら、その制約を超えようとする。そこから生まれる化学反応こそが、新しい産業の姿を描き出すと。
細目私は自分のことを「型破りだ」なんて全く思っていません。本来もっと自由に、もっとゆたかな価値を生み出せるはず。私たちは、気持ちのいい自然なかたちであり続けたいと思ってるだけなんです。
中村テクノロジーは、人々の暮らしをより豊かにするためにある。日本の食品産業には、その可能性を最大限に引き出せる土壌がある。探求心、職人気質、そして最先端の技術力。これらを組み合わせれば、世界を変えられる。
私も、その本質を見失わずに、しかし大胆に革新を起こしていきたい。それこそが、日本発のイノベーションの可能性なのではないでしょうか。
彼らの挑戦は、まだ始まったばかりだ。しかし、そこには確かな手応えがある。カーボンクレジットと焼き鳥、植物工場と伝統的な食文化──。一見かけ離れた要素が、新しい価値を生み出す触媒となり、産業の境界線を溶かし始めている。
我々は今、産業革新という歴史的な転換点に立ち会っているのかもしれない。データと直感、伝統と革新、効率と豊かさ。相反するように見えた価値が、ここで確かな調和を見せ始めているのだから。
こちらの記事は2024年12月27日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
井上 柊斗
写真
藤田 慎一郎
おすすめの関連記事
起業家のエコシステムは、意図的には生み出せない。StartupListが目指すコミュニティのあり方
- HAKOBUNE株式会社 Founding Partner
8か月で3回の資金調達に成功したタイミー・小川氏が語るその裏側──若手経営者3名が語った起業の本音
- 株式会社PoliPoli 代表取締役 兼 CEO
次のユニコーンは「暇の解消」から生まれる?──「Fortnite」を舞台に世界的IPと次々と手を組むNEIGHBORとHAKOBUNEの対談にみる、「日本発プラットフォーム」幻想からの脱却論
- HAKOBUNE株式会社 Founding Partner
VCも起業家も、“常識外れ”な挑戦がまだ足りない!大企業コンサルやデータ基盤提供に加え、ビルや街まで構想する「欲張り」なVC・HAKOBUNE木村・栗島の構想とは
- HAKOBUNE株式会社 Founding Partner