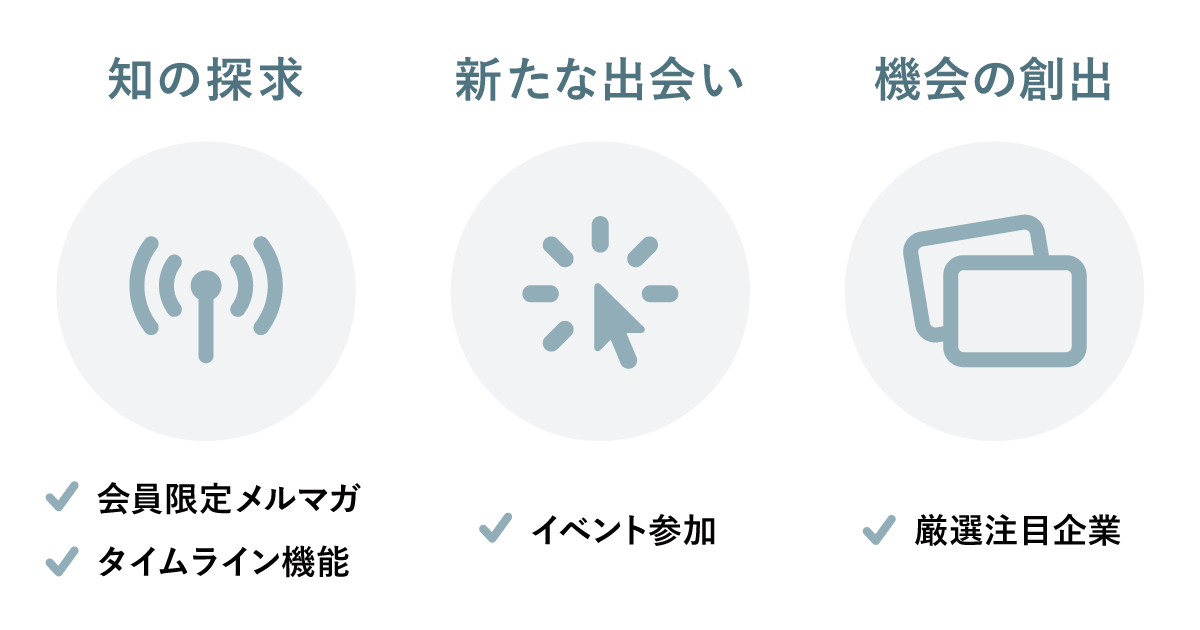社長ではなく、カルチャーにカリスマ性を持たせろ。人材輩出企業の創業者が語る、「強い組織」の作り方
Sponsored1990年代から「金融×テクノロジー」を追求し、今や日本金融界のフロント業務システム領域でNo.1プレイヤーとなったシンプレクス。最近では、シンプレクス出身の人材たちが数あるFinTechベンチャーでCxOを務めたり、外資系投資銀行のフロントデスクで要職に就くなど、トップリーダー輩出企業としての認知も浸透している。そこで、創業者の金子英樹氏に3度目の登場をお願いした。
過去2回の取材では、乱立するスタートアップベンチャーへの「喝」を中心に聞かせてもらったが、今回はベンチャーがメガベンチャーへと成長するための道筋について聞いた。
数名で始めたシンプレクスが、いかにして組織を拡大し、メガベンチャーへと成長できたのか。そして「強い組織」を作るために、創業者は何にどうコミットすべきなのか。持論を語ってもらった。
- TEXT BY NAOKI MORIKAWA
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
人材の見極めと魅力づけを徹底的に「科学」した創業期
「起業のスタートとしては悪くなかったと思います」。代表の金子がそう語るシンプレクスの創業は1997年。34歳のときだ。アクセンチュアやソロモン・ブラザーズでともに働いた同世代の仲間を中心に、同僚だったチームがそのままスピンアウトする形で数名で起業。次々に大手証券会社などを相手に、トレーダーらを支援するフロントシステムの開発・導入を直接受注し、業績を上げていった。
FinTechという造語が生まれるはるか以前から「金融×IT」をコアサービスとし、突出したテクノロジースキルと金融工学をベースにしたロジックを融合させ、オンリーワンとしての評価を高めていった。そのようにスタートが順調だった同社でさえ、創業後の数年間は組織づくりにおいていくつもの壁と戦っていたという。
金子シンプレクスの場合、スタートアップ時はスムーズに事が運んでいきました。創業メンバーはいずれも、世界トップクラスのサービスを、トップクラスのテクノロジーで提供する仕事に就いていた人たち。事業が急拡大したため、もちろんメンバーをどんどん増員しなければ追いつかない状況でしたが、30代中盤だった僕らよりも5歳ほど若いメンバーが順調に参画してくれました。
彼らにとっては、創業メンバーの僕らがそのままロールモデルになっていたわけですから、「先輩に追いつけ・追い越せ」と、経営陣が放っておいても人材は成長してくれたんです。
「ウォール街の帝王と称されたソロモン・ブラザーズで、フロントシステムの開発をリードしていた中心メンバーが日本で起業した」という情報は、業界内では話題を呼んでいた。そのニュースに反応したのが、同じ金融業界に在籍し、自身の成長に対しても閉塞感を覚えていた30歳前後の若手リーダーだった。
国内金融機関やそこにテクノロジーを提供する国内のシステムベンダーでは、外銀にどうやっても勝てないのではないか?と、グローバルと日本の技術や人材水準の歴然とした差を感じていた層だ。「よくあるスタートアップマジックというやつでしょう。そうした優秀で、ベンチャーマインドある若手が自動的にシンプレクスに集まってきた」。ただし、最初の組織的な壁は創業から3年のタイミングで現れた。社員数30〜40名の頃の「採用」だ。
金子お客様からの評価は上がり続け、案件も次々に決まっていく。創業メンバーと初期の中途入社組だけでは対応できないから、さらに若い世代の採用を試みましたが、上手くいきませんでした。
20代中盤から後半の人材は、今ほど転職に積極的ではなかったし、例えば外銀にいるような人たちは高い給料をもらっていますから、急成長中とはいえ、僕らのようなベンチャーに入ろうとする人はなかなかいません。一方、当時のIT業界の人材はどうかというと、僕に言わせれば「レベルが低かった」。ビジネスパーソンとしての総合力や資質の面で、当時の金融業界のエリート層のレベルには及ばない人が多数派でした。
そこで決断したのが、「一流集め」から「ポテンシャル採用・育成」への方針転換です。ポテンシャル重視の新卒採用を通じ、若者の潜在能力に賭けよう、と。JASDAQ市場に上場した2002年のことでした。

人事部門もなかった2002年以来、約10年に渡って金子は陣頭指揮で新卒採用にエネルギーを注ぎ続ける。業績を伸ばすのも経営者の仕事だが、それに耐えうる組織を作るのもまた、経営者の重要な仕事である。だが、サービスクオリティの高さで支持を得たシンプレクスだけに、ポテンシャル重視の新卒採用では苦闘が続いた。
金子「ポテンシャルのある学生を採ろう」と言うのは簡単ですが、パレートの法則、いわゆる2:8(にはち)の原則というのがありますよね?どんな集団でも本当に優秀な2割の人材が、残り8割を率いていくものだという原則です。僕らが欲しかったのは2割のほうですが、多数いる学生の中で誰がその2割にあたるのか、そしてベンチャーマインドを持っているのか。その見極めを「科学」しなければ、継続的に優秀な新卒人材を採用することは難しい。最初の数年は、ある意味、実験の繰り返しでした。
「人材の見極めを科学する」とは、どういうことだろうか。金子はまず、そのプロフェッショナルなキャリアで身につけた課題解決プロセスに則り、「優秀な人材」を定義づけた。水平思考力と論理思考力を高い水準で持ちうる潜在的才能を、多数いる学生から見つけ出そうとした。ここから、金子の「細部にこだわる」本領が発揮される。巷にあるいくつもの能力テストを取り寄せ、社内の若手に受験を促し、一つ一つのテストの社内での妥当性を試すような行為を繰り返した。
金子既成概念に囚われない柔らかい頭と、物事をロジカルに捉えて再現性のある言動に結びつけていける頭。双方を併せ持つ人を「地頭の良い人」だと規定しました。そして、世の中にあるテストを使えば、少なくとも論理的思考の潜在能力は測定できるはずだと考え、あらゆるものを試していったんですよ。
社内にいる人間で「あいつは論理思考能力が高い。こいつはその次くらいかな。そうすると3番目は……」というように、実務を通じて能力が把握できている社員たちに、取り寄せたテストを受けてもらいました。その結果、私が考えた社内の順位に一番近い結果が出ることがわかったテストを選考に用いるようにしたんです。

もちろん、頭の柔らかさのほうを見極めるためにも、様々な実験的なアプローチをしてきた。「理不尽な状況下でも自ら考え抜き、どこまでパフォーマンスが出せるか」を知るため、金子が率先して面接も行った。面接段階での面接官や評価内容と、入社後の数年間の成長スピードや業務成果と照合していくことで「入社前の評価内容と入社後の活躍」をトラッキングし分析も行った。
他の者が聞くと「社長がそこまでやるのか」と驚いてしまいそうなものだが、「そのくらい当然でしょ。ウチの最大の資産は人ですから」。「そもそも、本気でやるというのはこういうことでしょう」とさらっと言ってのける金子。たしかに、やると決めたときの徹底ぶりこそ、同社のDNAにある“コミットメント”の本質なのだろう。
このような徹底的な試行錯誤を数年がかりで繰り返したことで、自分たち流の「ポテンシャル人材を再現性を持って見極めるノウハウ」は獲得できた。しかし、「見極めた人材が全員入社してくれるほど簡単にはいかなかった」。
金子スピード上場を果たしたといっても、従業員数十名規模のベンチャーであることに変わりはありません。どんなに正確に学生のポテンシャルを見極めても、その人材が他社を選択してしまえば、採用には至らない。知名度の低いベンチャーが、その名前を知ってもらい、事業内容を理解してもらい、ミッションとビジョンに共感し、「入社したい」と思っていただかないといけないのが採用活動です。「人材の見極め」に加えて、「採用候補者に自社を魅力づけする」というプロセスも、徹底的にブラッシュアップしていきました。
これもまた「そこまで社長がやるのか?」と思いそうなものだが、「特別なことだと思うのは大きな間違い」だ。
金子採用であれセールスであれ、ベンチャーを自称するのであれば、会社にとって一番の命題に対して社長がプレイヤーとしてコミットするべきなんです。ベンチャーがチャレンジするのは企業を伸ばすためですし、社長のミッションは企業を伸ばすことですからね。
苦戦しながらも試行錯誤していた金子が、人材を見極めるノウハウに自信を得たのが2006年ごろ。前年、東証一部上場企業にもなり、「この頃から新卒採用の強化を意識し始めた」。そしてそれまで以上に、説明会等でのスピーチや学生との会話に金子自身が注力した。「もともとしゃべりには自信があったが、何度も練習をしてブラッシュアップしました」。
金子例えばスティーブ・ジョブズはプレゼンの上手さで世界中を魅了しています。彼を研究してみてわかったのは、「間の取り方」が特に素晴らしいということ。多くの人は、たくさんのオーディエンスの前に立って緊張した時や、思わずスピーチに熱がこもってしまった時、意識せずとも間延びしたり、早口になったりします。ですから、時間内にきちんと話し終えるように、どのスライドを何分で話すべきかを考え、時間を計測しながら徹底的に練習しました。
「魂は細部に宿る」と昔から言いますよね。採用活動のスピーチも同じ。万全の準備をするからこそ、魂が宿る。もしも「苦手だ」とか言っている経営者がいるのなら、それは単なる努力不足と危機意識の欠如。逆に、「自分は弁が立つ」と自信満々の人も、オーディエンスは毎回違う、という事実認識が欠けていると上手くいかない。
私は毎回プレゼン開始直後、オーディエンスに質問をいくつか投げかけ、トーク内容をその場で3つのタイプから使い分けていました。相手が変われば、話す内容も話し方も変えていかなければ、聞き手の気持ちはつかめませんからね。

優秀人材を自社に魅力づけするため、「話し方」を鍛える一方で、「プレゼン内容」にも金子はこだわった。「自分の会社を売り込むようなものの言い方はしない」と決めたのだ。働くというのはどういうことなのか、金融というのはどういうビジネスか、テクノロジーは今どうなっていて、今後どうなるのか――。世の中のことを若者に正しく伝えることだけに腐心した。
金子シンプレクスは、だまっていても応募が殺到するような有名人気企業ではないわけですよ。説明会の参加者が数人しかいない時だってありました。でも、だからこそ自分の会社を声高に大きく見せて、売り込んでいくようなことは絶対にしませんでしたね。入社しようと思ってくれなくても構わないから、「なんか無名企業の社長がしゃべっていたけど、ちょっと勉強になった気がする」と思ってくれたなら、それで良い。僕らがビジネスを通じて目指しているビジョンや理念、仕事に対して持っている価値観などに共感してくれる人が増えるような内容にこだわったんです。
常に個人を尊重し、誰に対してもこのようなリスペクトを欠かさない点が、金子と会った若者が彼に強く惹かれる所以なのだろう。「うちに来い」と言いたいはずなのに、無理強いは絶対にしない。
「優秀なヤツであるほど、自分がどうするかくらい自分で決めますよ」と話す金子は、大風呂敷を広げるようなセールストークが、むしろ逆効果になると知っている。説明会でも面接でも、誠実さを優先し、相手の知りたがっているテーマを中心に語りかけていく採用活動を愚直に続けた。その結果、2010年には約60名もの新人が入社。社員数300名規模にまでシンプレクスの組織規模は拡大する。
「異能を認める制度と風土」で組織力を最大化させた拡大期
「いかに優秀なメンバーを増やすか」の次にくる組織課題は、組織全体でメンバーのアウトプットを最大化すること。一人ひとり個別で見ると「優秀」であったとしても、各々が持つ異なる強みと特徴を上手くまとめ上げ、「強い組織」にしていくことに苦労する経営者やマネジャーは多い。ここについては、金子には持論がある。「異能を認められる制度と風土を作り上げれば、尖ったパーツだけを集めて一番大きな円を描くことができる」というものだ。
金子どんな企業でも、ビジネスはチームワークで臨みます。そして「何において優秀か」はほぼ全てのメンバーで異なりますよね。そんなチームの中で、一人ひとりの強みをしっかりと捉え、適材適所のチーム構成を維持するためには、それぞれのメンバーが得意とする尖った部分で勝負させてあげられる組織・評価制度、空気感を醸成することが不可欠。これらのパーツが組織内に全て揃えば、スキルバランスが凸凹のメンバーでも、結果的にチームとしては一番大きな円が描けるようになるんです。
スタートアップから成長期にあるベンチャーにおいて、経営者がコミットすべきもう1つの重要事がここにある。事実、シンプレクスは「尖ったヤツ大歓迎」という姿勢で採用活動を行い、人材評価においても「出世とは、マネジャーになること」というような画一的な評価制度を一切敷かず、各々の得意分野やキャリアプランに応じて、その範囲の中で成果を出した者をフェアに認めていく実力主義を貫いている。
その結果、エンジニアリングだけに特化した人材や、金融工学で高度なスキルを要する専門人材が、日系企業でありがちな「苦手分野の克服」に時間を割く必要なく、その強みを活かしたまま大きな裁量と高い給与を確保することができる。
金子グローバルではそういった評価基準のほうがむしろ一般的です。日本が特殊だっただけ。世界で勝負するなら、世界基準に合わせないと本当に優秀な人を採用し、組織に定着させることはできません。
「尖ったヤツ集まれ」とスタイリッシュな採用を仕掛けた挙げ句、組織制度と社内の空気感が追いつかず、不協和音で空中分解するようなベンチャーも多いのではないだろうか。熟考しながら精度の高いPDCAを繰り返し、それら企業と異なる道程を進んできたのがシンプレクスの組織づくり。繰り返しとなるが、「強い組織」を作る成功の秘訣は、「人材の長所を経営陣が理解すること」。そして、「彼らの最も突出した面を線でつないでいくチーム編成を実施すること」にある。
「それと」と金子が続ける。
金子色んな経営者と話していると、どうやら優秀な人が集まる企業ほどぶつかりやすい壁があるようなんですよ。それは「異能を認める」風土を社内に醸成すること。自分がデキるものだから、人の非にばかり目がいってしまって、「あいつより俺のほうがデキる」と思ってしまう、と。自分とは異なる才能を持つ人材を受け入れるのが、難しくなってしまうんでしょうね。

企業として最善の結果を出すためには、様々な才能の結集が必要になる。案件を獲得するための「売る才能」や、混沌としている現状を整理して問題を抽出していく才能も不可欠。いざプロジェクトがスタートすれば、クライアントとの間で有意義なコミュニケーションやネゴシエーションを実行していく才能も求められるし、良いモノを作る才能、動かす才能などももちろん必須となる。
「これら全ての才能を一人の人間が全て持っている必要はないんです。重要なのは、異なる才能をどうやってチームとして機能させ、全体としてのパフォーマンスを上げていくかを一人ひとりが常に意識することです」と言い切る金子。他者から学び、他者の持つ才能をチームに役立てようという意識で向き合っているのなら、仲間を頭から否定するようなセリフは決して出てこないはず、と断言する。
シンプレクスの組織力の強さの秘訣は、まさにこうしたMutual Respect(相互尊重)の精神が社員一人ひとりに浸透した、「異能を認める風土の醸成」にもあるといえる。
「起業家」ではなく「事業家」としての判断をした転換期、“MBO”は成長の選択肢
新卒採用のノウハウは確立できた。社内メンバーの持ち味を活かし、組織としてのアウトプットを最大化させる術も理解した。その2つの確信を得た金子が次に直面したのは、「上場を継続するか否か」という問題だ。
2012年からは採用の最前線への出陣を抑え、人事部門にそのノウハウの確立と向上を任せた。永遠のベンチャー、シンプレクスとしての最優先課題が「さらなる成長をいかに実現するか」へと大きくシフトしていたからだ。
創業以来、前年比30%台という猛烈な勢いで成長していた業績は停滞期を迎えた。事実、2011年3月期からの3期においては、成長率が急速に低下した。「これまでと同じことをしていたらマズい」。そう感じた金子は、2013年10月にMBO(マネジメント・バイアウト)を実施。自ら非上場企業へと舵を切った。
金子いつも言っている通り、企業としての新しいチャレンジをする時には経営者が先頭に立ってやるべき。そうでなければベンチャーではないと考えていたので、当然この時も口火を切ったのは私です。成長速度が鈍ったとはいえ上場を維持するべきか、長期的な飛躍的成長に集中投資するため上場廃止すべきか。悩んだ末に出した答えがMBOでした。
日本ではこれまでに200数十社がMBOを実施しているが、その後業績を向上させ、成功した例は1割程度だと言われている。MBO後に再上場する企業に関しては、数えるほどだ。プライベートカンパニーとなることで思い切った戦略に打って出ることは可能だが、上場時に得ていた資金調達面での選択肢は狭くなる。経営者としては大いに悩むところだが、最終的には株主もMBOの実施を認め、実行された。
金子忘れもしませんが、MBO発表直後に開催された株主総会で、「必ずまた上場して戻って来い。待っているから」と株主の皆さんには言っていただきました。本当に感謝しています。退職者も増えるだろうと覚悟を決めていたのですが、多くの社員が「辞めるわけないでしょう。むしろ辞めたいヤツがいるなら勝手にやめればいいじゃないですか」と言ってくれて、今も多くのメンバーが継続して活躍してくれている。社員にも足を向けて眠れません。

嬉しい副次効果もあった。MBOを断行したことで、「シンプレクスはこの規模になっても成長を追求する、真にベンチャースピリットで事業に挑んでいる企業だ」と再認識した人が多くおり、入社希望者が上場時よりむしろ増えたのだ。創業時と状況は違えど、20年以上変わらない金子の信念は、世代を越えて人に伝播し、「事業家」としての共感を得られている証拠だ。
金子私は元来、事業家というのは3つの要素にコミットする存在だと信じています。1つは、自分が起こした事業を継続的に成長させて本物にしていく責任。そして、自分の信念や夢に共感して集まってくれた人を育てていく責任と、そういう人たちで結成した組織を成長させていく責任。この3つを背負いきって、初めて「起業家」ではなく「事業家」であると言えると思っています。
起業家という言葉を最近ではよく聞くようになったし、これを目指す人が増えているのは良いことだと思います。しかし、起業家と事業家は根本的に異なる存在。私自身は事業家でありたいと思っているし、そうありたいと願うからこそ、将来の企業成長のためにMBOを決断し、今に至っているんです。
ここでも頭ごなしに否定しない金子であるが、昨今の風潮には独自の考えを持っている。「本当の意味で企業を成長させ、社会にインパクトを与えたいのであれば、起業家は事業家へと成長していくべき」というのだ。そのことは以前のインタビューでも語っている。
金子の持論はこうだ。「起業家」というのはゼロイチで事業を起こし、会社を立ち上げることに喜びを感じる人たちのこと。企業価値をある程度の水準まで伸ばしたら売却をして、その原資でまた異なる事業を起こす、シリアルアントレプレナーもここに分類される。
一方、「事業家」はというと、事業と人と組織にコミットし続け、自らが手がける事業を通じて社会に貢献したい、世の中を変えていきたいという強い信念をもつ人たちのこと。組織を率いるリーダーが「起業家」なのか「事業家」なのかによって、組織がどこまで大きく成長するかも規定される、という訳だ。
金子若い起業家が増えるのはいいことですよ。でも、事業家と呼べる人はどのくらいいるでしょうか。私としては、もっと長期的に会社の成長にコミットする若い起業家が増えてほしいという想いがあります。
そもそもベンチャーは「成長志向」が第一義。資金調達やM&Aはその手法の1つであって、二義的なものなはずです。本業とあまり関係ないM&Aを検討する起業家を見ると、「おまえ暇なの?事業伸ばせよ」と思ってしまいます。それこそ、事業を伸ばすことに興味がないなら、投資家に転向すればいいじゃないですか。

そんな金子だからこそ、メディアを賑わせる若い起業家に対し、「君は有名になりたいの?社会にインパクト与えたいの?」と問うことが多くある。
金子数億円、数十億円でイグジットして小金持ちになりたいなら、起業よりも楽な道がありますよ(笑)。起業の本当の楽しさは組織を強くするところにもあると思うし、そもそも、もっと本物の事業家が増えていかないと、ベンチャーシーンにおいて日本がグローバルでのプレゼンスを取り戻すのは難しいと思うんです。
「日本発、グローバルメガベンチャーになる」。こうした金子の想いが20年以上もブレていないからこそ、フランシス・ロングスタッフ氏のような、金融工学領域の世界トップレベルの研究者もシンプレクスを支援してくれているのだろう。
カリスマ性あるカルチャーの醸成。創業者なき時代でも「強い組織」で在り続けるために
このように、今ではスタートアップであるマネーフォワード社 CTO中出氏、NewsPicks社のCTO杉浦氏なども輩出し、「人材輩出企業」「強い組織」というブランドを確立しつつあるシンプレクスも、採用、制度設計、組織づくりにおいて20年以上、幾多の困難を越えてきている。
金子自身、「FinTech界隈ではシンプレクスOB/OGによる経済圏が生まれてきたと感じている」が、もちろんここで満足する男ではない。これからシンプレクスが、さらなる組織力強化に向けて何を課題に思っているかを尋ねると、「カルチャー」というキーワードが浮上した。
金子今、シンプレクスは業績面でも人材の採用面でも、スタートアップ、ベンチャーに相応しい好調さを示しています。一方、チャレンジの連続ですから、試行錯誤は今も続いています。そこで私が今まで以上によりどころにしているのが「Hello world, Hello innovation.」という企業理念と、「5DNA」と称して共有している価値基準なんです。
私はご存知の通り、言いたいことをストレートに口にする人間です。ただし、経営者となってからは、この理念や価値基準に基づいて説明責任が取れるような情報発信を心がけてきました。
先ほども言ったように、この会社には尖った変わり者も大勢いますが、一体感を持って走り続けていられるのは、皆がこの価値観やビジョンを共有し、共感できているからなはず。価値観やビジョンを共有し、カルチャーを身に帯びた組織にしていくこと。それもまた、事業家としての責任の1つだと考えています。

金子自身が大いに刺激と学びを得たというアクセンチュアやソロモン・ブラザーズにも、共通の理念や価値観があった。そして金子曰く、「それが強い組織の共通項」である。
金子例えば、私が在籍していたソロモン・ブラザーズでは、ボーナスを数十億円もらう超・切れ者もいれば、コミュニケーションが全く成立しないが驚異的な技術力を持ったスーパーエンジニアもいた。一見バラバラなように見えますが、それらの会社のOBやOGに会うと、すぐにわかるんです。「君はあそこの出身だよね」と。「強い組織」には、誰にも瞬時にわかる強いカルチャーがある気がしています。
たしかに、世の中にイノベーションを起こし、なおかつ長期に渡って尊敬を集めている企業には、必ず「●●社らしいカルチャー」というのが浸透している。そして、メガベンチャーであるサイバーエージェントやディー・エヌ・エー、リクルートなど、人材輩出企業と呼ばれる企業の出身者は「●●社っぽい」という評価で賞賛されているのは事実だ。
金子私もカリスマ経営者なんて言われることもありますが、本当のところ、経営者個人にカリスマ性があるかどうかなんてどうでもいいんですよ。その会社のカルチャーがカリスマ性をまとっているかどうか。究極的には、これが大切だと思うんです。会社がどんなに成長し、規模が膨らんで、経営者がいちいちすべてを見られなくなっても、カルチャーが浸透していれば、メンバー同士が切磋琢磨し、ミッションをブラさずに成長を続けることができる。
最近、ウチを卒業した人間があちこちで活躍していて、私自身は寂しい気持ちもなくはないんですが、「さすがシンプレクス出身者は違うね」と言われると誇らしい気持ちになります。彼らが外に出てもシンプレクスのカルチャーを体現してくれることで、この会社の価値を高めてくれています。
ですから今後も、私としては共有している理念に基づいてチャレンジをしていきますし、メガベンチャーを目指す事業家の方々には、カルチャーにカリスマ性が宿るところまで、トップがコミットし、徹底して組織内に共有していく姿勢を大切にしてほしいと思います。
そう若手起業家に喝を飛ばすと、最後に金子はぼそっとこう言った。
金子偉そうにいろいろ言ったけど、いまの俺に「オジサン、間違ってるよ」って何の気なしに言ってくる、俺が今まであったことないような尖った若手とも、どんどん大きな仕掛けをしていきたいんだけどね。

12/17(月)開催。金子流「メガベンチャーを作るリーダーの資質」を大公開
こちらの記事は2018年11月16日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
森川 直樹
写真
藤田 慎一郎
おすすめの関連記事
スモールIPOで満足する若手起業家よ。「俺たちにアガリはない」
- 株式会社ワークスアプリケーションズ 代表取締役最高経営責任者
「大手と提携して浮かれるな」メガベンチャーに学ぶ、日本発のFinTechイノベーションストーリー
- シンプレクス・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(CEO)
- シンプレクス株式会社 代表取締役社長(CEO)
「起業家ではなく、事業家たれ」FinTech界のカリスマ経営者が明かす、業界No.1で成長し続ける組織の作り方とは
- シンプレクス・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(CEO)
- シンプレクス株式会社 代表取締役社長(CEO)
「ジョブズすごい」と思っているならビジョナリーを目指すな──シンプレクス金子が説く、「強い企業」を創る7つの条件
- シンプレクス・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(CEO)
- シンプレクス株式会社 代表取締役社長(CEO)
「20代社員にはやりたいことなど聞かない」人材輩出企業シンプレクスの金子氏が説く、30代から2,000万円以上稼ぐビジネスパーソンを育てる秘訣
- シンプレクス・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(CEO)
- シンプレクス株式会社 代表取締役社長(CEO)
国内DX人材のレベルが低い、構造的な理由──MBOから再上場を果たしたシンプレクス金子が見出した「新卒人材育成」という高収益・高成長を維持する経営スタイルの全貌
- シンプレクス・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(CEO)
- シンプレクス株式会社 代表取締役社長(CEO)
現場にいる者こそが、意思決定者──年次も経験も関係ない!UPSIDERで非連続成長を担うのは「一次情報を最も知る者たち」だ
- 株式会社UPSIDER 執行役員 / VP of Growth
「支社配属=密度の濃さ?!支社だからこその強みがここには実在する」──就活生が気にするキャリアプラン。電通総研・広島支社に聞いてみた
- 株式会社電通総研 技術統括本部 バリューチェーン本部 PLM第4ユニット