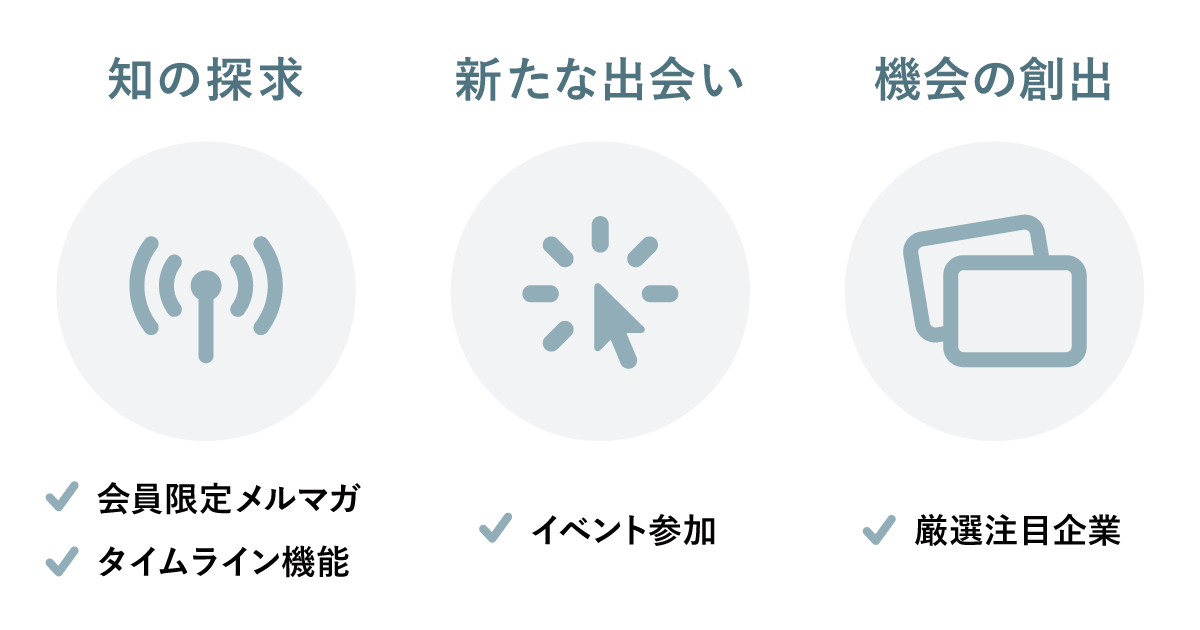「どのような世界観を描いていきたいか」──顧客への「価値」提供にこだわるプロダクト開発
SponsoredTwitterの価値は「呟けること」ではない。抽象化すると、例えば「人や情報に出会う、なめらかでスピーディーな体験」と言えるのではないだろうか。だから世界中で広まった。そんなプロダクトづくりをしている日本のスタートアップはあるだろうか、と考えていたところ、ビットキーが重視している「安全性・利便性・体験性の追求」という言葉を思い出した。
「スマートロックを最初にプロダクトアウトした企業」として認知されがちなビットキー。しかしスマートロックはあくまで、本格的な事業展開に向けたはじまりでしかなかった。あらゆる場所に備わっている「カギ」をきっかけに、大きな世界観でプロダクトを構想するのがこの企業だ。そんな話を代表の江尻祐樹氏から聞いた。その“大きなプロダクト”をつくる裏側に今回は迫り、「前例のないプロダクト創造」のノウハウと面白さを紹介したい。
話を聞いたのは、Workspace事業における主力プロダクトである『workhub』の開発・提供に躍動する3名。エンジニア組織のマネジャーとして主に技術面からリードしている菊地英太と、VPoP(VP of Product)の町田貴昭、顧客・営業・CSからの声を集約するビジネスサイドのマネジャー石政健人の3氏。
「A社の本社移転に伴う、新オフィスビルへの『workhub』導入」という、プロダクト開発の大きなマイルストーンとなったプロジェクトを事例に、世界を変えるためのプロダクト開発を紐解く。
- TEXT BY YASUHIRO HATABE
ビルの“まるごとスマート化”を実現させたプロダクト
スタートアップにおいて「プロダクト」と言われてイメージしやすいのは、PC上で動くシステムやスマートフォンアプリだろう。しかし今回取り上げるプロダクトは、そうではない。ビルで立体的に動くプロダクトなのだ。その開発は一体どのように進められたのだろうか。

町田Workspace事業の主力プロダクトであり、当社のオフィス内でもフル稼働しているコネクトプラットフォーム『workhub』は、エレベーターやセキュリティゲートなどの大きな既設のハードウェアとも連動するプロダクトです。
パートナーやお客様のニーズをふまえて、常に多数の機能開発を進めています。SaaSでは比較的珍しくない進め方かもしれませんが、ハードウェアと連携する製品としては珍しい進め方かなと思っています。
これまでの『workhub』を振り返ってみると、プロダクトの完成度が一気に高まったと言える導入プロジェクトがあるんです。それが「某A社の本社移転に伴う、新オフィスへの『workhub』導入」です。
当時も今も、僕はいわゆるプロダクトマネジャー的な役割で、『workhub』開発全体の設計をしています。菊地は、テックリードとして大量の機能をつくりました。石政は、お客様とのフロントに立ち、プロジェクト全体を管理する立ち位置です。
このプロジェクトは、ある大手企業A社の本社ビル移転に伴うものだった。新しい本社ビルを建設し、その際に『workhub』を建物全体に組み込むという、ビットキーにとって初めての壮大なプロジェクト。

菊地私は、建築物に設置する扉やエレベーター、制御盤やスイッチなど、ハードウェアがいくつも存在し、それらをプログラムするソフトウェアの動きに大きく関わる開発をリードしました。類似するシステムをつくったことのある大企業さんはそれなりにいると思いますが、スタートアップが挑戦するというのは、少なくとも日本国内でほとんど前例がないと思っています。
石政一緒にモノづくりをするという点も、プロジェクトとしてはハードルが高い部分でした。ビルともなると、私たちに直接発注をいただいたオーナー企業だけでなく、建設施工に関わる企業や、施設・設備の運用に関わる企業など、関わるパートナーがとても多くなります。
菊地の話の補足になりますが、建物自体の設備や設置されたハードウェア群に対して、私たちのソフトウェアから施錠・解錠に関する情報を送るところは、かなり慎重に進める必要がありました。制御盤側の仕組みづくりでは、常に他の企業さんを巻き込む必要があります。しかし、お互いのスピード感や使う言葉、持っている情報の粒度に違いがありますから、現場での事前調整や事後の情報共有まで綿密に進める必要があり、これも難しい点でしたね。
簡単ではないチャレンジだということが、ここまでの話だけでも感じられる。それをビットキーはどのように乗り越えたのか?プロジェクトストーリーは、思いもよらない展開をみせる。なんと、プロジェクトが半分ほど進んだ段階で、改めて原点に立ち返っての議論を始めたというのだ。

石政基本的な議論って、プロジェクトを進め始めた最初にやって、あとはとにかくゴリゴリとコードを書いていき、このビルをしっかり仕上げるというゴールに向かって進み続ける、という方法だと思います。
でも、大切なのは「自分たちがつくろうとしているプロダクトは、そもそもどういうものなのか?」という意識ですよね。ビジネスサイドの人間としては、顧客の要求仕様や納期に真摯に応えていくことは当然大切ですし、それを最優先でやってもらいたいですが、一方で、重要なのは、そこに汎用性を持たせられるか、標準化できるか、といった点です。
システム開発には、お客様の要望に応えるだけの受託開発というアプローチもありますが、ビットキーはそうではないアプローチを採っている。より多くの方々にとって価値があるプロダクトを、スピーディーに届けるために、開発においては、本来的なコンセプトやデザイン、そこにおける汎用性や標準的なモノづくりを常に意識してもらうことが大事だと思っています。このプロジェクトは、そのバランスを取っていくことを心がけていました。
町田プロジェクトを進めていくなかでも、「プロダクトとして、どのようにつくっていくべきなのか」といった原点に立ち返る時間は、プロジェクトの枠を超えて定期的にミーティングを組むようにしていました。
当然ながら、お客様から求められていることに短期的に応えていくということは念頭に起きつつ、その上で、お客様も気付いていないような本来的な課題解決や価値創出の仕方にはどのようなものがあるか、『workhub』が将来にわたって発揮し続けるべきバリューは何か、という点を改めて自分たちに問いかけていくんです。
プロジェクトにおけるお客様のニーズとともに、自社プロダクトの“コンセプト”をブラッシュアップし、より洗練された世界観をつくる。そして、まずはどのように実現すべきかという姿を“デザイン”する。ここまでを議論してようやく、開発を進めるにあたって、見ていくべき“仕様”が定まっていくという具合です。
菊地私自身はこの数カ月前に入社したばかりだったので、この時は正直、かなり驚きました。この問いかけは、プロダクトの話にとどまらず、もっと根本的な思想について、どんどん深まっていくんです。「オフィスとは何か?」「働くとは何か?」「人はなぜ働くのか?」みたいな(笑)。
お客様とのプロジェクトのなかでも、プロダクトをつくっていくための本質的な議論や検討をしっかりと重ねていくために、経営陣含め10人くらいで数日間、ひたすら議論をしていく時間をとりました。ビットキーという企業は、「“プロダクト”で社会を変えていくのだ」というこだわりと熱量を持っている、そう改めて強く感じましたね。
結果として、当初の想定よりも明らかに完成度の高いプロダクトの導入が実現できたと思っています。躊躇せずに根本を問い直すことの重要性を、改めて思い知りましたね。
ゴールの見極め、そして抽象と具体の行き来の繰り返し
スタートアップならば、常に未知のソリューションを提供するプロダクトを開発することになる。その難易度が、業種・業界の特徴や、事業・プロダクトのフェーズによって異なるだけの話だ。
ビットキーが進めたこのプロジェクトは、クライアントが大手企業であり、内容も「オフィスビル移転に合わせたプロダクト導入」というダイナミックなものだった。立ち向かうにあたり、どのような意識が重要になってくるのだろうか。
町田取り掛かっている仕事の規模が大きくなっていくと、方向性を見失う危険性がそれだけ大きくなります。このプロジェクトも、常にそうした難しさと戦っていました。何度も頭を落ち着かせて、ゴールの見極めを徹底して考えることが重要になります。
経験があるような仕事なら、ゴールの見極めも無意識にできるかもしれません。しかし、世の中のまだ誰も挑戦したことのない領域で、しかも規模も大きいプロジェクトの場合は、意識しすぎるくらいに意識すべきなんです。
菊地どこの企業も成し遂げたことのない価値提供を見据えたプロダクトが『workhub』です。だから、ビルへの導入を進める中で難しい対応も多かった。
先ほども話した通り、「顧客一社への導入だけがゴールではなかった」という点が、最も難しかったですね。「この先もスケールしていけるような、普遍的なプロダクトの姿に落とし込んでいくこと」も含めたゴールを設定して、ブレずに進めていく必要がありました。
町田例えば僕は、お客様からいただいた資料を定期的に読み返して、現在地を何度も再確認しています。それに加えて、当社の経営陣とも定期的に壁打ちして「目指すべきプロダクトの姿とズレはないか」や、「より良いプロダクトにできるチャンスやヒントはないか」といったことを探りながら進めていました。
ゴールは一度設定すれば十分、というわけにはいきません。ゴールを考えたら次は現在地を確認し、目先の進め方を考えたら次はまたゴールを考えてみる、そんな繰り返しですね。そうでなければ、普遍的なプロダクトの開発につなげるプロジェクトとしての成功はありません。
以前、代表の江尻氏が語った「具体と抽象の行き来が重要」という話を思い出す。視点を常に切り替え、ステークホルダー全員で共有できる理想のゴールを追求し続ける。「お客様から要望された通りに進める」だけでなく、「自分たちが考えた通りにつくる」だけでもなく、その両方でうまくバランスをとりながらの挑戦だからこそ、やりがいは大きいのだという。

菊地開発が進んでいくにつれて、ゴールの解像度がどんどん上がり、プロダクトのコンセプトが目の前に立ち現れていく様子が見て取れるようになっていくので、どんどんやりやすくなっていきました。プロジェクトに参加した当初は「できるか、できないか」といった単純な問いを抱えて悩むこともあったのですが、次第に「こうすればできる」という前提で進めるようになりましたね。同時に、ワクワクも大きくなっていきました。
たどり着いたプロダクトを通じて、実際にビルの扉が開くのを目の当たりしたときの感動は、やっぱりすごく大きかった。以前エンタメ系のソフトウェアをつくっていたときも、ユーザーに楽しんでもらえていることの感動はありましたが、それとはちょっと違うな、と。
当社の場合は、ソフトウェアもハードウェアも両方を通じて再現性をより具体的にイメージできる点が面白みでもあります。「目の前で物理的に何かが動く」というのは、何か身体に訴えかけてくるやりがいがあるなぁと感じます。
体験したら、必ず「欲しい」と思ってもらえるプロダクト
“スマートロック”という最近では市民権も得つつあるプロダクトから始まり、上述のようにオフィスビルという大きな舞台で、ハードウェア・ソフトウェアともに連動させるまでに進化したビットキー。ここまで創業から3年ほどというのにも驚かされる。
町田先ほど、当社のオフィスでもプロダクトがフル稼働していると話しましたが、このプロジェクトがあったからこそ出来た話でもあるわけです。
240名ほどの従業員規模に拡大し、スタートアップとしては異例の成長規模を見せるビットキー。オフィスを構える東京スクエアガーデンというオフィスビル全体にこの『workhub』が組み込まれ、ビル自体のエントランスやエレベーターなどの制御を可能にした。
そしてワンフロアを占有するビットキーのオフィス内では、受付や1人用のワークスペース、複数人用のミーティングルーム、フリーアドレスとなっている執務デスク全てに至るまで、ショールームのように『workhub』というプロダクトが張り巡らされているのだ。スマホ一つあれば予約や調整を簡単に行うことができる。扉は顔認証だけで解錠が可能だ。そのため、このオフィスでは、首から下げる社員証やカードキーといったものは一切不要になっている。

ビットキー本社オフィス。株主でもあるオカムラ製のパーソナルブース(写真左側)も、顔認証で利用できる(提供:株式会社ビットキー)
菊地オフィスにおいて、煩わしいことが限りなくゼロになっています。自分たちが毎日それを体感できているのが面白いですよね。「スマホと顔」という、必ず持ち歩いているものだけで、全てが済むというプロダクトです。もちろんまだまだブラッシュアップする余地はあるのですが、既に体験価値としては唯一無二のものになっていると思います。
石政基本的にビジネスサイド側の私の視点から見ても、先ほど説明したプロジェクトを通じて、他社さんではなかなか到達できない領域に到達できたなと思いました。
1年前までは、後付けのスマートロックをアプリで開けるというのが主な価値でした。それが今では、さまざまな認証方法で扉やカギを開けたり閉めたり、エレベーターまで制御をしてしまったりと、可能性が一気に広がったわけです。
プロダクトそのものを見て、体験してもらったら絶対に「欲しい」と思ってもらえるものが出来上がった。そんな大きな進化を、この1年の間だけでも強く感じます。
創業から3年にして、非連続的で異例な成長の大きなターニングポイントになった『workhub』の存在は非常に大きいと、3人は改めて振り返る。
石政『workhub』の完成度をここまで高められたからこそ、事業と組織の急成長を継続できているのだと、最近改めて感じています。背伸びをしたプロダクト開発とプロジェクト進行という見方もできたかもしれませんが、それをやり切れたことは、ビットキーの事業戦略上、非常に重要なマイルストーンだったわけです。
菊地GoogleやTwitterのように、生活を大きく変えるプロダクトを目指す、と謳うスタートアップは、日本にも増えてきている感じがします。でもそこへ向かう道がどんなものなのかは、なかなか想像できませんよね。私もそうでした。
でもこのプロジェクトを通じて実現させたプロダクトの姿と、今発揮している価値を見ると、「もしかしたらこの延長線上に、『世界を変える』があるのかもしれない」とワクワクします。
町田そういう将来を信じて、ガムシャラにやっていくことが、とにかく面白いんですよね。
プロダクト・マーケット・フィットを
実現し続けるための仕組み
ビットキーがプロダクトを汎用的・標準的につくっていくことと顧客の要望に応えることのバランスを取ることを重要視していることは前述の通りだが、定常的にそれを実践していくための仕組みがある。それが「PMFミーティング」という会議体だ。
『workhub』を所管するWorkspace事業と、住宅や街を対象としたプロダクト『homehub』を所管するHome事業のそれぞれで、定期的に開催している。要するに「ビジネスサイドと開発サイドが集まるミーティング」なのだが、そう聞くと「当たり前に行うべき会議体」のように感じるかもしれない。
しかし、ビットキーはシンプルな事業・プロダクトをバーティカルに広げていく形のビジネス形態ではない。顧客にはエンタープライズ(大企業群)も非常に多く、SMB(中小・中堅企業群)も含めて領域を問わず、いかに汎用的に、標準的につくりつつ、多くの顧客のニーズを満たす価値提供をしていくかを判断していく。その難易度は非常に高い。そのため、その難易度の高いジャッジメントを精度高く、迅速に行っていくために、社内における意思決定の仕組みづくりを工夫しているのだ。
PMFとはいわずもがな、プロダクト・マーケット・フィットのことだ。ビジネスサイドの営業・CS部門と、エンジニアリングを担うプロダクト開発の双方が参加し、それぞれ個性を持つメンバーたちが揃う形で行われる。
マーケットと向き合うビジネスサイドからは顧客のニーズをエンジニアサイドに共有する。エンジニアサイドはそれを受けて、共有されたニーズが汎用的に求められるものかどうかを吟味し、他の多くの顧客にも提供すべき価値があると判断すれば機能としてプロダクトに組み込んでいく。時には顧客ニーズを超えて、その先を行く機能をエンジニアサイドからビジネスサイドへ提案することもあるという。
今回、話を聞いた3人は全員このPMFミーティングの主要メンバーであり、Workspace事業のPMFミーティングには前回インタビューした営業の引地俊光氏(記事はこちら)も参加する。
町田僕はプロダクト開発部門の中でもどちらかというとビジネス寄りな立場で、石政とは密にコミュニケーションを取っています。菊地はテックリード的なポジションで、前面に立ってビジネス側とやりとりするというよりは、やや後ろに立ってエンジニアをリードしてくれるポジションにいます。
石政開発担当がモノづくりを進めるにあたって、いつ、どんな機能をつくって実装していくか、その“順番決め”は、丁寧に意思決定すべきことだと思っています。案件の数が多いと、いろんな営業担当がいろんなエンジニアに「これを急いでほしい」と依頼してしまって、どの案件の優先度が高いのかがわからなくなってしまう。こういった問題は、スタートアップで起きがちだと思います。
なので、ビジネス側はなるべく僕が情報を集約して、エンジニア側の声は町田のほうでまとめてもらって、PMFミーティングでテーブルに広げて議論する形をとっています。

PMFミーティングに臨むスタンスは、立場によってそれぞれ異なる。
石政プロダクトがマーケットにフィットしない、つまりマーケットのニーズを満たせないケースって2通りあると思うんですね。
1つは、私たちが「これだけやったら顧客の期待値を満たせるはずだ」と思っていたけれど、実際の期待値はそれよりもっと高かったというギャップ。もう1つは、顧客が「これくらいはできるはずだ」と思う最低限のニーズさえ満たせなかった場合。例えば、特殊な利用者による運用シーンの想定がずれていたとか、そういったケースのギャップです。
そうしたギャップが発生した際に、それぞれ開発陣にフィードバックして、エンジニアは機能をつくり、マーケットのニーズを満たせるようにする。PMFというと、そういう一連のサイクルをイメージしています。
菊地エンジニアの目線でいうと、開発の指針みたいなものを定めやすい場かなと思っています。プロダクト・マーケット・フィットというくらいなので、マーケットとしてどういうニーズがあるのかをプロダクト目線で知る、非常に重要な機会です。
そのニーズに対してプロダクトをどうすれば、マーケットに対してどれだけ価値が提供できるかをしっかり議論して認識した上で、開発の方針やスケジュールを検討していける。そういう指針を定める場だと私は思って参加しています。
町田僕の場合は開発の方向性やロードマップについて意思表示して、「これでお客様に話していいよ」とビジネス側に伝える場としてPMFミーティングの場を使っていますね。ここで共有したことは、同時にプロダクトチームのコミットメントになる。そういうイメージです。
「組織はまだまだ道半ば」と謙遜するが、こうした“部門を超えた対話”への本気度は十分すぎるほど窺い知ることができる。エンドユーザーと顧客が、価値を強く感じられる、そんなプロダクトをつくり続けるために必要な「対話」という仕組みを、率先して整備してきたのである。
「できない」ではなく「いつできるか」を考える
こうしたエンジニア側とビジネス側のコミュニケーションは、PMFミーティングの場だけで行われるわけではない。PMFを意識したコミュニケーションが常時、随所で行われているのだ。
町田こういう話は日常的にもよくしていて、Slackですることもあれば、ふらっと石政の席に行って話すこともあります。定例のPMFミーティングで議題に上げるのは、開発・ビジネス側ともに大きくリソースを割かなければいけないような案件や、これまでつくったことがない新しいものをつくる話が出てきたときなどですね。そこで経営陣も含めて一緒にジャッジします。
菊地普段は、石政から「顧客からこういう要望があるけど、現実的に可能なのか」という相談を直接受けることも多くありますよ。
例えばそこで、「できない」と判断されるとどうなるのだろうか。
町田いや、「できない」というのはないんです。例えば「2カ月後に実現してほしい」と言われたら、それはできないと答えることもありますが、代わりに「6カ月後ならできる」という話をします。
ビジネス側はエンジニアから「できない」と言われたら困りますよね。顧客が本来的に求めているのはどういうことなのだろう。どうすれば、課題解決ができるだろう。そこに対して、現実的に何をどこまでだったら実現できるか、というのを考えるのです。だから単純に「できない」というコメントはまずしないですね。
菊地あるいは「2カ月後には40%なら出せる」と答えるケースもあって、それはビジネス側とコミュニケーションを取る上では大事なことだと思っています。
仮に2カ月後に40%のものを出してお客様の満足度が満たせるなら、いったんそれで認識合わせをしてもらって、3カ月後に100%の機能を出すということもできるかもしれない。でも、その判断をする上で、エンジニア側はお客様の熱量がわからないので、石政のようにお客様と常にコミュニケーションを取っているメンバーの話を何度も聞きながら進めています。
あとは、ビットキーとしての中長期的なビジョン、つまり青写真みたいなものはしっかり描かれているので、それに結びつくものだったら、いつやるかは別として、「できない」という判断はしないですよね。
町田そうですね。それと、「この先3カ月はこの方向性で進もう」という意思統一をする全体ミーティングが四半期に1度あります。そこで事業の向かう先や、どういう価値をお客様に新しく届けようとするのか、ビジネス側もプロダクト側も一緒になって認識合わせをするんですね。
ビットキーが描く“コネクト”の世界観は
「自分の人生の時間を使うに値する」
ところでこの3人、どのような経験を積んできた人物なのだろうか。
町田氏は新卒でワークスアプリケーションズに入社し、エンジニアとして会計システム、ECシステムのソフトウェア開発を経験してきた。ワークスアプリケーションズ時代に江尻氏と仕事をしたことはなかったが、江尻氏が週末に行っていた研究会に参加し、モノづくりをしていたのだという。
町田この人の一番近くでプロダクト開発をしたら、プロダクトをつくる人間として、より成長するだろうなと思ったんです。それで、創業時にジョインしました。
石政氏も同社へ新卒で入社し、人事、会計、SCMなどさまざまなパッケージシステムの営業やプロジェクトマネジメントを経験した。
石政やったことのないことを扱ってみたいと思う性格なんです(笑)。新しいサービスの立ち上げも経験しました。その時に江尻と接点ができたのですが、ビジネスごとつくるみたいな経験を江尻と一緒に進めて、めちゃくちゃ面白いなと思ったんです。
その後、江尻がワークスアプリケーションズを去り、会社を創業したと聞いて興味を持ち、2019年4月にビットキーにジョインした。
3人の中で菊地氏は特にエンジニアとして、またはその枠を超えて、幅広い経験をしてきた。

菊地もともと学生時代からコードを書いていました。その後、新卒でソーシャルゲームをつくる会社に入ります。そこで新規事業の話があって、2014年にはVR動画配信の子会社立ち上げにも関わりました。
会社を立ち上げてからは、開発はほとんどしてなくて、残りはどちらかというと、プロジェクトマネジャーだったり、どうやって世の中にVRを普及させていくのか、実際に多くの人にVRに触れてもらうために何ができるかを考えて、イベントをやってみたり、マーケター的な動きをしていました。
2019年末に菊地氏は会社を離れ、フリーランスになる。
菊地前職時代は、VRに全てを注いでいたんですよ。自分たちのつくるコンテンツを世の中に対して出せればVRを流行らせられる、業界全体を大きくできるくらいに思っていて、4年間くらい必死に取り組んでいました。ただ、市場の環境や会社のフェーズが変わり、だんだん「自分の人生の時間を、このまま投資し続けることが正解なのだろうか」と思うようになってしまって。
それで、いったん会社組織から離れて、どこにも属さずにいろんなところを見てみようと思い独立しました。
その時点では、「もうサラリーマンには戻らなくていい」とすら思っていた菊地氏だったが、次の転機は意外にも早く訪れた。
菊地独立直後は、自分の顔を広げていこうと思って、退職を機に声を掛けていただいた会社を中心に30社ほど、いろんな会社の方に会って話を聞きました。その中の1社にビットキーがあって。でもまあ、会う前は「スマートロックの会社、IoTの会社なんだろうな」という程度の理解で、あまり興味なかったんですよね(笑)。
しかし、ビットキーで話を直接聞いたことで、その印象は一変する。
菊地そのときは採用担当の人と話をしました。そこで、「テクノロジーの力で、あらゆるものを安全で便利で気持ちよく“つなげる” 」というコネクトの世界観の話をしてもらって、すぐに「これはすごいな」と。ある種の社会インフラになりうると感じました。だから、自分の人生の時間を賭ける価値がある、と。
VPoEやCEOの江尻とも話をしたのですが、最初にまぶしいものを見せられたので、その後は「こういう人たちが働いてるんだな」くらいしか思わなくて(笑)。最初の時点で自分の心は決まっていて、むしろいつジョインするか、どういう形でここに対してコミットするか、それぐらいしか考えていませんでした。
そうして、「もうサラリーマンには戻らなくていい」とまで思っていたはずの菊地氏は、2020年8月にビットキーへ入社を果たしたのだった。
現在、菊地氏がテックリードとしてエンジニアリングを、町田氏とともに牽引しているのは先に紹介した通りだ。そして石政氏がビジネスサイドとの橋渡しをする。互いの信頼感がある中で、一人ひとりが強みを活かしながら、常にマーケットの状況やニーズを感じながら、プロダクト開発に邁進できる環境の良さが窺える。
「価値」を提供し続けるプロダクト開発組織であるために
今後、ビットキーが成長していく上で、さらなる新しいプロダクト開発をしていく余地はまだまだ大きい。そんな中で、プロダクトをつくる組織はどのように進化していくのか。3人にそれぞれの展望を聞いた。

町田僕が見ている今の組織は、一部で属人化している業務もまだまだあるので、それを解消して標準化していくことが喫緊の課題ですね。創業から3年の会社としては当然かもしれませんが、甘えてはいられません。
組織をスケールさせていく上では、さまざまな個性を持った人材が活躍できる必要があります。その意味で、教育コンテンツを整備したり、最低限の社内ルールを決めたりして、個人ではなく組織としてプロダクトの品質や価値のレベルを一定の水準以上に保ち続ける。そういうモノづくりのプロセスを構築していかなきゃいけないなとは思っています。
石政私は開発側の人間ではないので横から見て思うところですけど、組織の完成度はすでに結構高いと思っていて。ちゃんとプロダクトが世に出ているし、使っていただけてもいる。それが実績になって、ニュースにも出ている。これはすごいことだと思います。
人数が増えれば、入ってきた人のやりたいことやつくりたいものに応じてプロダクトも変わっていくと思いますが、「モノづくりで世にインパクトを与えたい」という人が社内に増えるといいなと思っています。
菊地自分がビットキーに惹かれて入社し、一定の高い視座とか目標を持って働いているのと同じように、全メンバーが自分たちのつくるプロダクトに対して、ワクワクできている組織がいいなと思っています。
エンタメ関連の仕事をしていたときにもそうでしたが、自分たちがつくったものが使ってもらえて、そしてそれを楽しんでもらったり、生活を便利にしたり。それが実感できると、すごく嬉しいんですよ。
私はいま『workhub』というtoBのプロダクトを扱っているので、友人に直接すぐに見せられるわけではないですが、いま、コワーキングスペースなどでの利用も広がってきているので、個人的に知り合いに直接Facebookで「使ってみてよ」と勧められますし、そこから「使ってみて良かった!」というレビューとともに、利用したユーザーから他の人に広がっていくことも考えられます。
そうやって、いろんな人の生活を便利にしているということを各メンバーが意識しながら開発できる組織にしたいと思っています。
こちらの記事は2021年11月29日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
次の記事
執筆
畑邊 康浩
連載その仕事は、ハイスタンダードか? 「世界を変える」へ一直線、ビットキーの秘密
5記事 | 最終更新 2021.12.24おすすめの関連記事
全ては理想的な患者体験のため。真の“シームレス”実現に向け、現場の業務設計から作り込む、Linc'wellのPdMによる妥協なき挑戦【FastGrow副編集長のプロダクト体験談あり】
- 株式会社Linc’well 執行役員 プロダクト統括
挑戦する新規事業を、「実現の難しさ」で選べ──事業を創出し続けるFintechイネーブラー・インフキュリオンが注力する「若手への機会提供」と、新プロダクトの開発ストーリー
- 株式会社インフキュリオン ビジネスデザイン室長
ユーザーファーストを突き詰めれば、PdMとマーケターは一体になる──リブセンスが試みる「P&M」という職種の定義
- 株式会社リブセンス 転職会議事業部 事業部長 兼 VP of Product & Marketing
このPdMがすごい!【第2弾】──時代をつくるエースPdMと、エースを束ねるトップ層のマネジメントに迫る
スタートアップ、“国家プロジェクト”を背負う──被災地でも活躍、世界最小級のドローン企業・Liberawareが創る社会インフラ
- 株式会社Liberaware 取締役CFO
政府が託す、52億円の技術イノベーション──Liberawareエンジニアが牽引する、国家主導の鉄道インフラDX
- 株式会社Liberaware 取締役 技術開発部長
半径1kmの地図を塗り替える──「広告ゼロ・1.5万UU」エンジニア集団イオリアが仕掛ける、大手プラットフォームの死角を突くスモールジャイアント戦略
- イオリア株式会社 CEO・エンジニア
「昇進より、技術者として勝負したい」──特殊冷凍のデイブレイクに集結した大手メーカーのエースたちが語る、決断の瞬間
- デイブレイク株式会社 TEC部門長