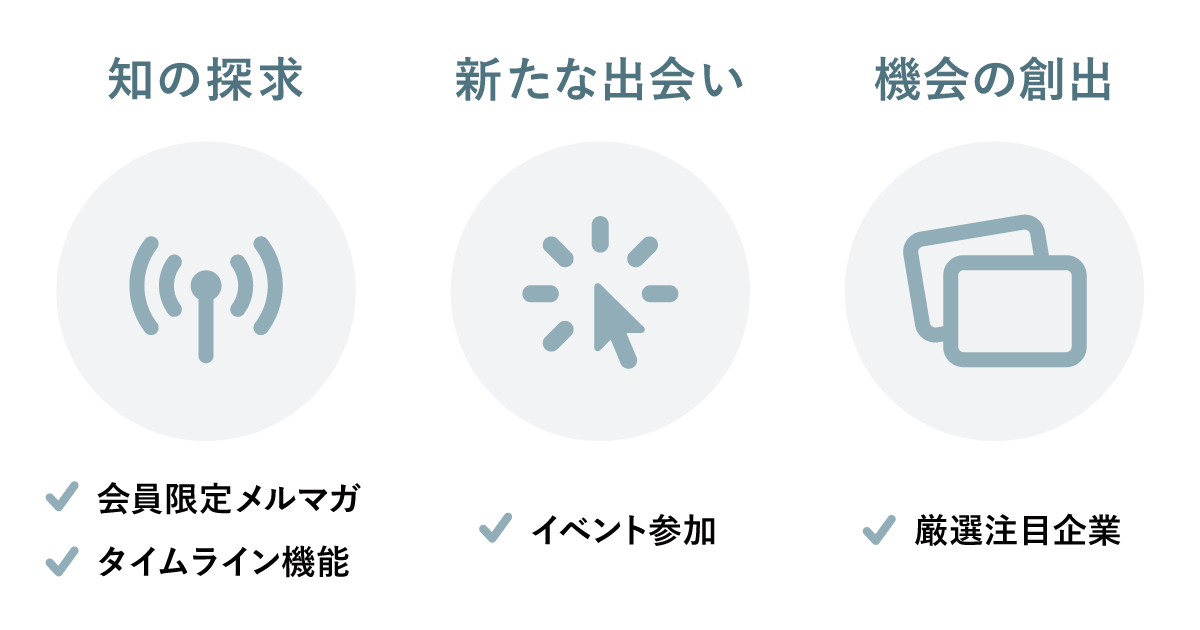Amazon Goを追随せよ!無人店舗元年に登場したスタートアップ3社
2016年、米国シアトルで無人店舗「Amazon Go」がオープンした。2018年10月時点で全米6店舗に拡大するに至っている。
第1号店舗オープンから約2年を経た今、世界中で無人店舗トレンドが進みつつある。たとえば中国ではAlibaba(アリババ)が運営する「Tao Cafe(タオ・カフェ)」や小売スタートアップ「BingoBox(ビンゴボックス)」「簡24(ジアン24)」が登場。日本でもパナソニックやJR東日本が交通系ICカード「Suica」で買い物ができる実験店舗を駅構内に開設した。
そして、2018年は米国スタートアップ市場でも無人店舗の分野が一挙に開花した年でもあった。今回は3つのスタートアップを紹介しながら、最新トレンドを紹介していきたい。
- TEXT BY TAKASHI FUKE
- EDIT BY TOMOAKI SHOJI
サンフランシスコで登場した無人店舗3社 ── 「Zippin」「Inokyo」「Standard Market」
Zippin(ジッピン)

最初に紹介するのはZippin(ジッピン)だ。2018年にサンフランシスコで創業し、現在1店舗を同都市に構えるが、Amazon Goの競合と目される。
まず、顧客は専用アプリをダウンロードし、クレジットカード情報を入力しておく。その後、入口のアプリ読み取り機にスマホをかざせば入店できる。あとは好きな商品を鞄や袋に詰めてそのまま退店するだけだ。天井に取り付けられたカメラが各顧客の動向をチェックし、自動支払いシステムを完成させている。配車サービス「Uber」の体験のように、面倒な決済登録の手間を先に終わらせてしまい、あとは必要な際にサービスを利用してもらう顧客ボーディングプロセスである。
『Wired』の取材記事にて、創業者はZippinをSaaS事業であると称している。カメラや店舗などハードウェアの技術はすぐに市場で普及されてしまうため、キャッシュレスな購買体験を実現するための仕組みを、どの事業者にも提供することがミッションであると述べている。
この点、Amazon Goは閉鎖的なサービスであり、他業者に技術の2次提供はしていない。Zippinは市場の無人店舗化ニーズは年々高まっていることから、店舗設計の仕組みを外販する戦略だ。
Inokyo(イノーキョー)

シリコンバレーに店舗を構えるInokyo(イノーキョー)も2018年に登場した無人店舗企業だ。サンフランシスコで創業し、著名アクセレーター「Y Combinator」のプログラムを卒業している。
顧客体験はZippinに近い。事前にアプリをスマホにダウンロードしておき、入り口でQRコードを読み込ませることで入店が可能。店舗内にあるカメラが各顧客の体型と洋服の色を記憶して動向を随時トラッキングする。出店時に再度QRコードを読み込ませると、自動でチェックアウトができる。
競合との差別ポイントとしてアピールしているのが顧客行動データの収集である。店舗内で各顧客がどの商品に興味を持ったのかを分析し、Inokyoのサービスを導入する小売事業者へとフィードバックする。陳列棚の位置を変えるだけで売上が向上するかもしれない商品提案、見向きもされない商品の仕入れ中止など、販売戦略に関わるデータを提供する点に重きを置いているのだ。
Standard Cognition(スタンダード・コグニション)

Standard Cognition(スタンダード・コグニション)
ここまで紹介した2社と技術面で競合優位性を保っているのがStandard Cognition(スタンダード・コグニション)が運営する無人店舗「Standard Market(スタンダード・マーケット)」である。同社は2017年にサンフランシスコで創業し、累計調達額は5,060万ドル(約56.2億円)を調達。Inokyoと同じくY Combiantorのプログラムを卒業している。
従来の無人店舗とは違い、QRコードの発行もない。来店客が店内でアプリを起動すると一瞬だけ画面が赤く光る。AIを搭載したカメラがこの画面を認識して顧客を識別。一度棚から取った商品を全く同じ場所に戻さなくてもバグは発生せず、誤請求が起きない仕組みを構築したのが特徴だ。
入退店認証プロセスさえ省いた点がStandard Marketの強みである。すでに日本上陸が決まっており、『日経クロストレンド』によると、2020年度までに3,000店舗の出店を目指すという。
利便性だけでは勝てない。無人店舗の生き残り戦略

2018年は、サンフランシスコを中心に店舗の無人化が進んだ年であった。米国のこうしたトレンドから日本企業が学ぶべき示唆がある。
ガラパゴス化を防がなければならない点だ。日本では、都心であれば徒歩10分圏内には必ずと言っていいほどコンビニがある。また、接客サービスの質や店内環境も非常にレベルが高い。顧客満足度が高いがゆえに、テクノロジーの導入が遅れる可能性がある。これは無人店舗技術だけでなく、最新小売トレンドから置いていかれる危険性があることを意味する。
たとえば、配車サービス「Uber」は日本での普及率が圧倒的に低い。法律面での壁もあるが、日本のタクシードライバーのサービスの質が圧倒的に高いゆえ、わざわざ頼む必要性が薄いことが要因の1つだと考えられる。では、なぜ海外で爆発的にサービスが普及したかというと、米国のタクシーは運転の質も悪く、料金が非常に高かったからだ。この点を解決したのがUberであった。
あらゆる面でサービスの質が高い日本は、顧客満足度が高いがゆえに、世界市場の流れに乗り遅れてしまう可能性がある。そのため、既存小売事業者が今の無人店舗の外販トレンドに乗じてキャッシュレス化や顧客体験の転換を一挙に進めることは、間違った戦略ではないだろう。
先に紹介した3社のスタートアップはいずれも自社で店舗数を拡大するのではなく、技術の外販を目指すことが考えられるため、日本企業はこうした企業へのアプローチは欠かせないはずだ。

また、無人店舗を導入したとしても、単なる滞在時間の短縮化や、購買体験の簡略化だけに目を向けるべきではない。2回目以降の来店を促し、購入体験を向上させる仕組みを提供することこそが、無人店舗の軸となるからだ。
Amazonのデータ戦略が好例だろう。Amazon Goでは顧客が入口でQRコードをかざした瞬間、「Amazon Marketplace」(以下、Marketplace)の購買データと店舗内での購買データを紐付ける接点が生まれる。オンラインとオフラインデータ連携のメリットは、店舗内で購入した商品データを基に、Marketplaceのレコメンド機能にも活かすことができる点だ。
たとえば、店舗で購入した生鮮食料品データを活かして、関連商品をMarketplaceでも提案できる。顧客がどの購買チャネルから訪れてもデータを獲得して、次の購買へとつなげる仕組みを完成させているのがAmazonの強みなのだ。もし、Marketplaceでの購買データを参考に、店舗スタッフが来店客に商品提案ができれば、さらに質の高い店舗体験を提供できるようになるかもしれない。Amazon Goにはオンラインとオフラインの両方の購買体験を上げる大きな可能性がある。
このように、無人店舗の運用は人件費削減や買い物時間を短縮させるだけではく、顧客満足度をテクノロジーで向上させる重要な戦略そのものであることを忘れてはならない。
今後、日本の小売企業の無人店舗化はさらに進むだろうが、単にトレンドに乗るだけで終わってはならない。リピートを促すための顧客体験向上にまで目を向けて、初めて長期戦略としての無人店舗の価値を最大化できるはずだ。
こちらの記事は2019年02月07日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
福家 隆
1991年生まれ。北米の大学を卒業後、単身サンフランシスコへ。スタートアップの取材を3年ほど続けた。また、現地では短尺動画メディアの立ち上げ・経営に従事。原体験を軸に、主に北米スタートアップの2C向け製品・サービスに関して記事執筆する。
編集
庄司 智昭
ライター・編集者。東京にこだわらない働き方を支援するシビレと、編集デザインファームのinquireに所属。2015年アイティメディアに入社し、2年間製造業関連のWebメディアで編集記者を務めた。ローカルやテクノロジー関連の取材に関心があります。
1986年生まれ、東京都武蔵野市出身。日本大学芸術学部文芸学科卒。 「ライフハッカー[日本版]」副編集長、「北欧、暮らしの道具店」を経て、2016年よりフリーランスに転向。 ライター/エディターとして、執筆、編集、企画、メディア運営、モデレーター、音声配信など活動中。
おすすめの関連記事
マイベスト、実は前代未聞の“データプラットフォーム企業”だった──「あの企業の“実は”ここがすごい」Vol.2
日本のビジネスパーソンも、自身の価値を「デューデリ」しよう──市場価値を最大化させる“投資家的”キャリア思考法を、日米の比較に学ぶ【対談:STUDIO ZERO仁科&渡辺千賀】
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
FinTech×EC支援で事業を連続創出できる理由とは?BASEのツーサイドプラットフォームに魅せられた山村・髙橋の躍動を追う
- BASE株式会社 上級執行役員COO
個人やスモールチームの可能性を最大限に広げるプラットフォームへ─GMV1,500億円超もまだまだ成長途上。BASEでさまざまなBizDevに挑戦できる理由とは
- BASE株式会社 BASE事業 Business Management Division Manager
2倍成長を続けるTOKIUMに学ぶ「最強のオペレーション戦略」とは──「壮大・緻密・柔軟」の3要素で、BPaaSとしての成長を実現した秘訣
大企業のR&D組織に「紙とペンの次」を授ける、前人未踏の挑戦──ストックマークのBizDevチームは未開の地に価値があるかを探究する「先遣隊」
- ストックマーク株式会社 CMO
勝ち筋は「国産の生成AIミドルウェア」にあり──Vol.1 miibo CEO功刀雅士氏【寄稿:DNX Ventures新田修平】
- 株式会社miibo 代表取締役