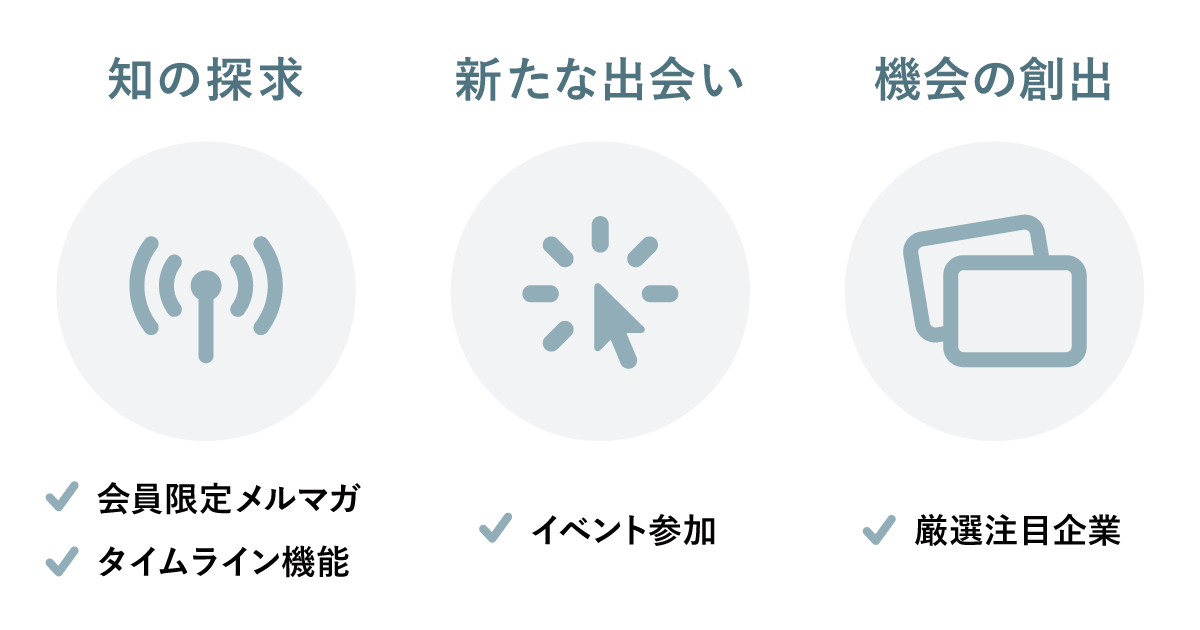海外拠点立ち上げの秘訣は「夢とヘッドハンティングだ!」──TOEIC250点で売上10倍を達成した富士フイルム20代社員の、ドバイ事業開発奮闘記
Sponsored富士フイルムが“奇跡のイノベーション”カンパニーであることは既報の通り。ではその“奇跡”につながる営みは、どこで誰がどのように行っているのだろう?
その一端を担ってきた代表選手の一人として登場してきたのが守田正治氏。一貫してメディカル事業のマーケティングを担当してきた守田氏の入社時のTOEICスコアは250点。それでも27歳の時、突然ドバイ駐在を任されたという。並み居る欧米列強企業がシェアを牛耳る中東・アフリカ地域は、健康診断や疾病予防等の医療文化が未成熟なエリアでもある。
そんな場所でカタコト英語の青年はどうやってチャレンジを成功させたのだろうか?
- TEXT BY NAOKI MORIKAWA
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
“おまえには絶対的な友達感覚がある”の一声で決まったドバイ駐在
大学卒業までサッカー三昧の日々を過ごしてきたという守田氏は、社会インフラに関わる仕事に関心を持ち、富士フイルムへ2005年に就職した。
配属先はメディカル領域の業務部門。創業時から強みとしてきたX線フィルム技術を起点にしながら、多様なテクノロジーが行き交う医療の世界にチャレンジしてきた富士フイルムでは、当時、医療用画像に関わる事業を次々に開拓しようとしていた。
前回の記事にもあったように、2000年代の富士フイルムは写真フイルム事業のみに依存しない経営体制を構築すべく、自ら創造的破壊者となりながらイノベーションの道筋を探っていたのである。
守田今では多彩な人間が同居し、メディカル系の同業他社からは「外資系のようだ(スピード感とダイナミズムがある)」と呼ばれ、再生医療にみられる新規事業への投資やM&Aを積極化させている富士フイルムですが、当時はまだ「良い意味で生真面目なしっかり者の集団」という印象が強い会社だったように思います。
それでも、新たなコア事業とするべく期待を集めていたメディカル分野には、独特の熱さが漂っていました。今もメディカル事業を率いている後藤禎一(現 富士フイルム常務)などは「立ち止まったら負けだと思え」と日頃から発破をかけていましたし、フィルムのことも医療のことも知らなかった私としても、このムードには自然と溶け込んでいきました。

ところが入社から2年ほどが経過したある日、運命を変える一声がかかった。声の主は海外マーケティングを担当していた部長。
「おまえは海外向きだ。うちに来て中東・アフリカ地域を担当しろ」と言われ、事業部内での異動が即決定した。
守田私の何がどう海外向きなのかわからず部長に聞きましたよ。「あの、自分は入社時のTOEICのテストで250点しか取れなかった男なんですけど」と(笑)。すると「語学力なんてものは勉強して伸ばせばいいんだ。そんなことよりも、おまえにはコミュニケーション力がある」という答えが返ってきました。
たしかにそれだけは自信がありました。サッカーをずっとやっていたせいか、先輩とも後輩とも良い関係を築く術のようなものを体得していたんです。「目上の人間は立てるべきだけれども、持ち上げ過ぎてもうまくいかない」とか、「同期や後輩とは夢や希望を語り合うことで絆を作っていける」とか、そういう経験が社内の人間関係でも活かせていたんです。
異動後の守田氏は、東京オフィスにいながら中東・アフリカ地域の拠点と連携していく立場に。当然、しばしば英語を使う場面があるため、自分なりに勉強もしていったという。
そうしてまた約2年が経過した頃、またしても部長から声がかかった。「海外の仕事にも慣れたようだしドバイに行ってこい。出張じゃないぞ駐在だ」と。
守田驚きましたよ。だって私はまだ27歳の若造でしたし、ドバイにはたしかに当社の事務所はありましたが、現場の人間は1人もおらず、中継基地的な事務所機能しかありませんでした。そんな場所に1人で行って、富士フイルムのメディカル事業の市場作りをゼロイチでやれる自信なんてカケラもありません。
恥ずかしながら本音としては「行きたくないし、しゃべれないし」だったんです。部長はどうやら私が英語を使いこなせるようになったと思い込んでいたようですが、ろくに上達していません。その証拠に駐在内定者が必須で受けさせられるTOEICの試験でも450点しか取れませんでした。
たしかに入社時よりは力がついていたものの、600点以上でなければ駐在員としては認めないという社内規定があった。TOEICばかりが英語によるコミュニケーション力を計るモノサシではないが、「最低でも600点」という基準はおそらく誰もが納得するラインだろう。
守田氏にしてみれば「ほら、私では無理なんですよ」という気持ちでこの成績を報告したのだが、部長は一歩もゆずらなかった。
守田点数を伝えた時には「マジかよ」と笑いながらあきれていましたが(苦笑)、それでも私のドバイ行きを押し通し、特例として駐在しても良いということにしてしまったんです。今度は私のほうがマジかよと思い(笑)、理由を聞くと「おまえには“絶対的な友達感覚”がある。だからやれる」の一点張り。
「またそれかあ」とは思いましたが、駐在経験のある先輩からも「俺も、おまえなら海外でやれると思うよ。そのコミュニケーション力が必ず武器になるし、必ず成長して帰ってこられるよ」と言っていただきました。自分でも「経験ある人たちがここまで言ってくれるならそうなのかもしれない」と思うようになって、引き受けることにしたんです。
誤解のないように書き添えておくと、守田氏が固辞すれば駐在を辞退することは可能だった。先人たちから後押しされたとはいえ、最終的に本人がその気になり、決意を固めた上でのドバイ行きだったのである。
それでも、ドバイ到着早々から空港やホテルでのやりとりに四苦八苦する始末。「本当に俺は海外に向いているのか?」という疑問はしばらく頭から消えなかったという。
しかし、上司や先輩が高評価したコミュニケーション力は、仕事と無関係の場でさっそく機能したようだ。
守田ちょうど2010年はサッカーのワールドカップが南アフリカで開催される年でした。言葉はうまく駆使できなくても、サッカーでならば楽に交流できます。地元のサッカーチームに入れてもらって仲間を作り、皆でワールドカップの試合のパブリックビューイングに出かけたりする中で、現地の人たちと次々に仲良くなっていきました。
しばらくすると、富士フイルム本社からも少しずつ駐在員が増えてきた。メディカル事業のみならず他の事業分野でも、中東・アフリカ地域はホットな新興市場として注目されだしたのだ。
デジカメ事業担当者が駐在員として到着すると、守田氏はともに現地法人を立ち上げた。単なる中継基地ではなく、ローカルに根づいてビジネスを展開するための第一歩である。その後もイメージング事業担当もドバイにやってきて、ようやく戦うための体制は出来上がろうとしているように見えた。だが、当の守田氏が担当するメディカル事業のアプローチは、そう簡単にブレークしなかったという。
“何度挑んでもあの人には勝てない。だったら仲間になってもらおう”。異文化の壁を打ち破った“守田流 ヒトたらしの術”
駐在員となった守田氏にとっての主力プロダクトは医療用X線画像関連の機器だった。マーケティング担当者としては、現地での販売を担ってくれる代理店との契約を拡大していき、主要病院など医療施設からさらなるビジネスチャンスを発掘していく必要がある。
だが、2000年代に入ってから急速に経済成長を成し遂げる国が続出した中東・アフリカ地域には、当然のごとく強力なライバルがすでに進出していた。
全世界の医療機器市場で圧倒的優位を築いていた米国企業や、写真フイルム全盛時代からのライバルでもある欧州企業など、欧米列強がこの地でもトップシェアを競っていたのだ。
守田右も左もわからない中、たった1人でカタコト英語を使いながらも頑張っているつもりだったんですが、何度チャレンジしても勝てなかった競合企業がありました。
特に、商談に出向いた先々で必ず聞かされた名前が「スービンさん」でした。競合企業の地域統括本社でヘッドを務めていたこの人は、無敵の強さで知られていたんです。そこで、この人に会っていろいろ教えてもらおうと思ったんですよ。
「伝説の営業マン」と言われるような人たちの武勇伝には、しばしば「最大のライバルにむしろ教えを乞うた」というエピソードが登場する。だが、くどいようだが当時の守田氏は、ビジネス経験そのものも乏しいカタコト英語の20代のマーケターである。
「よくもまあ、そんな度胸があったものだ」と失礼は承知で感想を漏らすと、当の本人も笑いながら「普通の日本の感覚だとそうですよね」とふり返る。
守田なりふり構っていられない、という心境だったこともあります。ただ、昔から私は相手を選ばず懐に飛び込んでいって、本音で言葉を交わし合うようなことをしてきた人間でしたから、そんなに特別な勇気をふるったような感覚もありませんでした。
それに、ドバイに来てまだ1年足らずの頃でしたが、現地のビジネスマンが皆、競合かどうかとは関係なくフランクに交流する様子を幾度も見てきましたので、気がついたらスービンさんに連絡をとっていた、という感じです。

“あの部長”による「絶対的な友達感覚」という言葉の意味が、話の行く末にじわりと漂い始めてきた。そう、部長はまさに守田氏のこういう才能を見極めていたのだろう。ここから豊臣秀吉を想起させるような守田氏の“ヒトたらし”が物語に急展開をもたらすのだ。
守田聞きたいことはいっぱいありましたし、スービンさんも私の質問に1つひとつ誠実に答えてくれました。ドバイでビジネスを拡大させようとしたら何をすべきなのか、競合他社にあって富士フイルムにないものは何なのか、今どういうところにチャンスが来ているのかなどなど、勉強になることばかりでした。
そうして幾度か会ううちに意気投合していき、「このかたをビジネスの師匠として採用したい」と思うようになりました。そこで単刀直入に私は、スービンさんに「ウチに来て一緒に働きませんか?」と話したんです。
驚いた。スービン氏は40代のインド人。ライバル会社の地域統括ヘッドであり、当地の関係者の間で知らぬ者などいない実績バリバリのスター的な存在である。その人物を新参の日本の若者がヘッドハントしたというのだから。さらに驚いたことに、スービン氏があっさりOKしてくれたというのである。
守田日本人の感覚でいったら掟破りもいいところです(笑)。でも、スービンさんとは本当に短期間で信頼関係ができていったので、本音を伝えたらきっと誠実に考えてくれると信じていましたし、結果としてOKをくれたんです。
あとから教えてもらいましたが、グローバルなビジネスの世界では戦略的にライバルのキーパーソンを引き抜くことは常套手段らしくて。一流ビジネスパーソンが働きたい組織を作ることが、企業にも求められていると言っていました。まあでも、それは後から聞いた話なので、我ながら「いい根性してるよな」とは思っていました。
なぜ異文化の大物相手に信頼関係を短期間で築けたのか、という部分については後で聞こう。守田氏の“人たらし”遍歴にはまだつづきがあるのだ。
守田スービンさんが来てくれた途端、数字はどんどん伸びて、富士フイルムの業績は彼の古巣を逆転しました。しかも、「あのスービンさんがいるならば、自分も一緒に働きたい」と他社の人間まで次々と当社にジョインしてくれたんです。
その後、私は西アフリカ地域の市場を開拓するためにモロッコへ飛んだのですが、ここでも圧倒的な強さで成果を上げている人物が同業他社にいることを知り、さっそくアポイントを取りました。それがアラビア系のイスマエルさん。彼とも意気投合して、富士フイルムに参画してもらえることになりました。
今度はレバノンの市場を開拓するべく現地に入り内視鏡事業を立ち上げようとメンバーを探した際、やっぱりここにもスタープレーヤーがいたんです。内視鏡関連機器のビジネスは世界中どこへ行っても業界ナンバーワンの競合他社の独壇場だった当時、中東だけはある別の会社が強かった。理由は、サリムさんという抜群の腕利きがいて、他の追随を寄せ付けない活躍をしていたから。
「じゃあ、そのサリムさんも富士フイルムに?」と尋ねると、「はい」と爽やか笑顔で守田氏は答える。
しかし、安っぽいサクセスストーリーのマンガでもあるまいし、そう簡単に各地のスターが仲間になってくれるものだろうか、と思ってしまう。「まさか、とんでもない高給を約束できたわけでもないですよね?」と確認すると「もちろん」という返答。ではいったい何があったというのか……。
ヒトがヒトを呼び、「Be No.1」でつながった鉄壁の信頼関係を構築。そうして皆でつかみ取った10倍成長
現地でのメディカル業界において富士フイルムは新規参入の後発組である。もちろん、もともとの強みであったX線フィルムの技術を出発点にしながら、開発部隊が急速に多様な領域にもチャレンジを実行し、イノベーションを目指し始めていた。
だが、2010年代の初頭はまだ黎明期。ましてやグローバル市場における知名度は確立されていなかった。にもかかわらず、各地のスターを仲間にできた背景には何があったのか?
守田最も大きかったと思うのは、ともに大きな夢を語り合えたこと。たしかに私の語学力はつたないものでしたが、将来の夢やビジョンを語る時の情熱は、カタコトであろうと伝わるんですよ。
スービンさんもイスマエルさんもサリムさんも、日本の富士フイルムという会社のことは知っていました。「写真の世界の王者だろ」と言ってくれたし「Fujiを知らない人間なんて世界中のどこにもいないよ」とまで言ってくれていた。
おかげで私は「そんなブランドを持つ富士フイルムも生まれ変わらないと生き残れない。必死なんだ」という話ができましたし、「写真フィルムの領域で手に入れた絶対的なクオリティの高さを医療の世界に持ち込んで、世の中を変えたい」という話にも共感してくれたんです。
ですから私は口の上手い“人たらし”だったわけじゃないです(笑)。むしろ同じ領域で純粋に似たような夢を持っていた大物たちが、「彼らに天下を取らせてみようじゃないか」と意気に感じて参画してくれた、というのが真実だと思っています。

守田氏は、昔の青春ドラマにあるような心理背景が追い風になったのではないかと、当時の出来事を分析する。つまり、弱小サッカーチームを見た歴戦のスタープレーヤーたちが「こいつら、全然まともに戦えていないけれど、その姿勢と情熱には賛同できるものがある。じゃあ俺も入って、こいつらを一番にするゲームを楽しんでみるか」と思い始めるような、そんな流れだったとふり返る。
守田そのせいかどうかはわかりませんが、スービンさんが参画を決めてくれた時、「何か気のきいたことを言ってくれよ。そうだな、じゃあ、俺たちは何を目指す?」と言い始めたんです。
私としては冗談のつもりで人差し指を立てて「ナンバーワン!」と言い切ったら、思い切り真顔で「そうだよな。お前なら言ってくれると思っていたぞ!」というリアクション(笑)。
「えー、マジかよ」と思ったんですが、他の仲間たちも嬉しそうに笑っているので、その後、私たちチームのキャッチフレーズは「Be No.1」になり、皆で写真を撮る時は必ず全員で人差し指を立てるようになってしまいました(笑)。
でも、いいですよね。どこか子供じみているように見えるかもしれませんが、私たちは本気でそう思うようになったし、夢と希望で多国籍のチームが結束すると、実績もどんどん伸びていきました。
もちろん、青臭い理想論だけの結束ではない。守田氏によれば、スターたちにはスターたる所以の力が身についており、それらが富士フイルムのチーム力を引き上げていき、泥臭く数字につなげていくことができたのだという。
守田スービンさんは組織というものの大切さを知っていました。自身が他社でリーダーを務め、ライバルである企業を見つめてもきた人ですから、勝てるチームにするための体制作りを特に教えてもらいました。また、IT領域にも強い人でしたから、その後の富士フイルムがIT技術を絡めたメディカル製品を売っていく局面でも、大きな力になったんです。
イスマエルさんには、地域の情勢を見極め、頭をつかって賢くビジネスチャンスをこじ開けていくようなノウハウを見せてもらい、これもまた実績を上げていく上で大きな追い風になりました。
サリムさんはというと、海外の名経営者のように、何事にも用意周到なプランを緻密に立てる名人でしたから、これもまた大いに学ばせてもらい戦略実行に役立てました。
そして3人から共通して学んだのは、「グローバルな市場と向き合う時にはこうしたコアパーソンの存在がものを言う」のだということ。彼ら自身がハイパフォーマーであるだけでなく、チームを引き上げるパワーも持っているし、彼らの存在が優秀な人材を惹きつけるという作用もある。
そんな風に思えるようになり、数字もついてきたことから、いつの間にか私も楽しくてしょうがなくなり、あっと言う間に6年が過ぎていたんです。
中東・アフリカでの売上は、守田氏の駐在期間に10倍にまで急伸していた。 たった1人で乗り込んだドバイの地には、40人以上の従業員が集うようになってもいた。
帰国後も、今に至るまで東京のオフィスでグローバルマーケティングに携わり、自身がドバイで吸収してきた様々なバリューを若手に伝達しているというが、守田氏はもう1つ重要なミッションを任されてもいる。それが新規事業の開拓だ。
モノ売りではなくサービスまで提供する。世界中の人々に健康を届けるため、政府をも動かした
海外に行った元気いっぱいの青年が仲間を集めて大成功……という話で終わらせるわけにはいかない。守田氏にはどうしても実現したい夢があるのだ。そしてそれはドバイ駐在時代に芽生えたもの。
「恵まれた医療先進国ニッポンに張り付いていたら決して気づかなかった世界の実態」を目のあたりにしたことから始まった使命感ともいえるものだ。
守田収益が伸びていくことを皆で喜んでいた反面、中東での生活に慣れ、ビジネスを通じてもこの地の実情を深く知るようになった結果、新興国ならではの大きな課題が存在することに気づかされたんです。 イランやカタールといった国々では、医師や病院という存在は体調を崩してから対応してもらうためのもの。そういう文化が長年浸透しています。つまり、身体の異変を早期発見するために病院へ行き、検査・診断をしてもらったり、予防のために必要なことを教えてもらったりするような習慣がありません。 「それがこの国の文化であり価値観だし、皆も健康にすごしている」というのなら何も言うことはありませんが、そうではない。経済的に発展をしているといっても、今なお癌や心筋梗塞などで亡くなるかたが増えている実情があります。 一方、欧米や日本からビジネスチャンスを求めて進出してきた企業は、病院というお客様にモノを売ることだけを使命にしており、売れたらそれで終わり、というスタンスに終始しているように見えたんです。少なくとも、この実情を変えるようなアクションを誰も起こしていなかった。これじゃあいけない、と思いました。
最初のきっかけはカタール。乳癌検診に用いられるマンモグラフィを売っていこうとしたところ、「乳癌を治療する機器ではなく、検査をする機器」というものの必要性をなかなか理解してもらえなかったのだという。
そこで、カタール政府とPPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ。官民が一体となって公共事業を進めていくための取り決め)を結び、まずは当地のドクターたちを米国や日本に招待した。
乳癌検診がいかに女性の健康のために不可欠なものなのかを啓発するところからスタート。その上で病院にマンモグラフィを納入するばかりでなく、検診のためのオペレーションも担っていくという、メーカーである富士フイルムにとって新しいビジネスモデルを守田氏らチームは作り上げていったのだという。
守田一国の健康に対する意識を変えたり、医療文化を変えたりするわけですから、手間もかかりますし、お金もかかるし、国を動かすような交渉事も出てくる。でも、その気になれば可能なのだという手応えをもって、私は帰国しました。 ですからその後も、例えばイラン政府に働きかけて、リーズナブルな値段で検診ができるようなモデルを提案。予算がないのであれば、イラン政府のほうから日本政府に呼び掛け、ODA等を活用する術を探ってもらうようなアプローチをしています。同時に、富士フイルムの開発陣にも相談して、例えばAI技術の活用等で機器やオペレーションのコストを下げていくための試行錯誤も始めています。 そして、この夢の部分でもスービンさんと「いつかは私たちの手で、新興国をはじめ世界中の人たちに、健康を届けるような仕事を確立していこう」と語り合い、議論しているところなんです。
最後に「富士フイルムはどういう会社で、これから参画しようという若い層にどんなメッセージを伝えたいですか」という質問を投げかけると、守田氏は想像通りの快活さと熱さで答えてくれた。
守田私のドバイ行きの経緯でもわかると思いますが、大企業とは思えないほどの無茶ぶりはあるものの(笑)、とにかくズバッと大きなチャンスをくれる会社です。 もちろん途方にくれる局面は幾つも経験しましたが、前に進もうとする時にはいつも背中を押してもらいました。そうでなければ、異国であんなにやんちゃな行動はできません。ある意味、送り出す時から私以上に私のことを理解し、その強みを発揮できるステージを用意してくれたのかもしれないな、と思ってもいます。 また、スービンさんたちと仲間になる時に痛感したのが、富士フイルムというブランドの強さです。異領域のビジネスマンであっても、かつて写真フイルムの市場で当社が何を成し遂げたのかを知ってくれていた。 「アグレッシブにイノベーションを起こして世界市場のトップまで駆け上がった会社だ」とまで知られていました。そうでなければ、「メディカルの世界に俺たちでイノベーションを興そう」と口説いても、彼らは力を貸してくれなかったかもしれません。

「イノベーションを興せる会社しか生き残れない」という時代の声が高まることで、ともすれば「かつて成功をおさめた大企業」が変革のために努力していても、その営みを軽視する傾向が一部にはある。だが、いかに過去の事であろうと、特定の領域でその力量を明快に示してきた企業には、日本人が思う以上の信頼と尊敬を世界の人々は向けているのだ。
遠い中東で孤軍奮闘してきた守田氏の言葉だけに、重みを感じる。そして実際、先人が築いたブランド価値をテコにして異領域でイノベーションを進めているのが富士フイルムなのだ。
守田私が最後に口にした夢なんて、普通なら大きすぎて無理だと思い、話すこともはばかられるはずです。新興国に理想の医療を、とか、世界中の人々に健康を、とか、そのためには国だって動かしますよ、とか。 でも、この会社でなら言えるんです。富士フイルムは、こういう夢を真顔で言える会社だし、事実チャレンジさせてくれる会社です。 最初からキレ者じゃなくても夢を追いかけられる、ということは今日の私の体験談でわかってもらえたと思います(笑)。ですから、このような富士フイルムのスタイルに共感してくれるようなハートを持った方たちに、どんどん参画してほしいと思っています。
守田氏によれば、それぞれの事業部門に守田氏とはまた違ったキャラクターと生き方を持つ「サムライ」がごろごろいるのだそうだ。夢を持つ者も、夢が見つからずにいる者も、こんな大企業があることは知っておいたほうがいいだろう。
こちらの記事は2019年11月26日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
森川 直樹
写真
藤田 慎一郎
おすすめの関連記事
現場にいる者こそが、意思決定者──年次も経験も関係ない!UPSIDERで非連続成長を担うのは「一次情報を最も知る者たち」だ
- 株式会社UPSIDER 執行役員 / VP of Growth
“移民版リクルート”目指し、ブルーオーシャン市場で成長率350%──LivCo佐々氏が描く「外国人が暮らしやすい日本」実現までの道筋とは
- 株式会社LivCo 代表取締役
【トレンド研究】外国人材紹介事業──TAMは今の4倍超へ。HR産業の最後のブルーオーシャンがここに?
隠れテック企業「出前館」。第2の柱は32歳執行役員から──LINEヤフーとの新機軸「クイックコマース」に続く、第3の新規事業は誰の手に?
- 株式会社出前館 執行役員 戦略事業開発本部 本部長
【トレンド研究】デリバリー市場の裏に潜む革命──クイックコマースと最新技術が変える「生活の新常識」
- 株式会社出前館 代表取締役社長
あのRAKSULで「セールス」の存在感が急騰!──既存の顧客セグメントから拡張し、数兆円規模の法人市場の攻略へ
日本のビジネスパーソンも、自身の価値を「デューデリ」しよう──市場価値を最大化させる“投資家的”キャリア思考法を、日米の比較に学ぶ【対談:STUDIO ZERO仁科&渡辺千賀】
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
日本発グローバルスタンダードは、“介護”から──「複雑×長期×規制」極まる社会課題。ユナイテッド × KAERU / CareFranはどう挑む?
- ユナイテッド株式会社 投資事業本部 キャピタリスト マネージャー