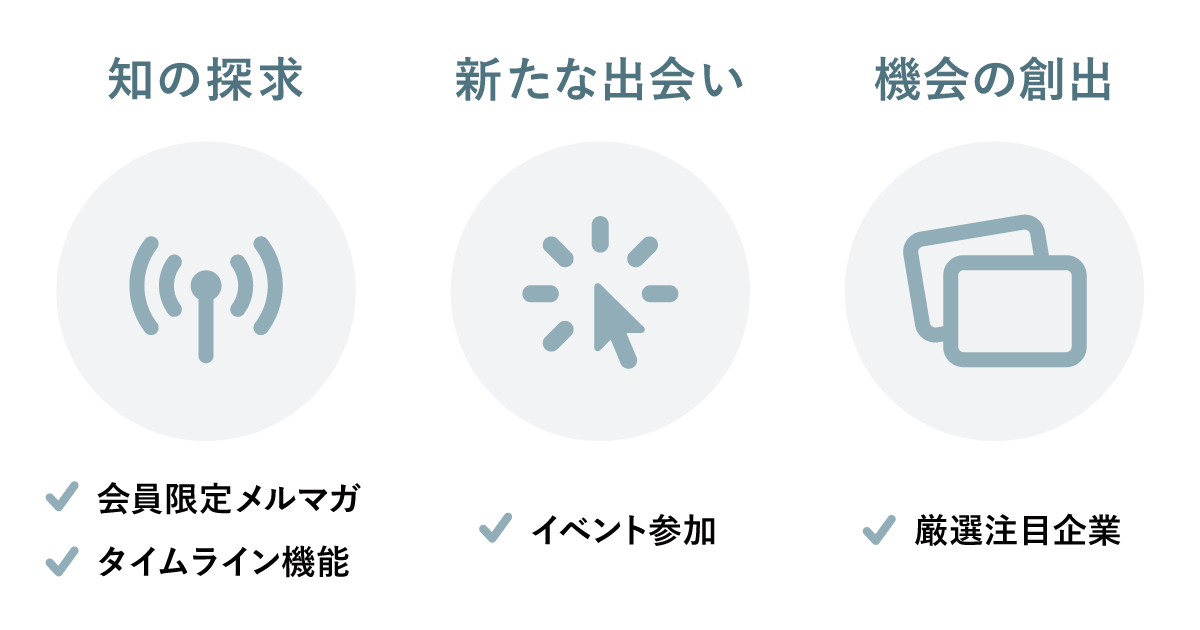名ばかりでない“インキュベーション”の世界が、ここに──事業家を志す者が集い続ける、事業・コンサルの「いいとこどり」成長環境の秘密
Sponsored「新規事業など必要ない」と考えている経営者は少ないだろう。さまざまな産業が成熟し、新たな収益の柱を求めて大企業、スタートアップ問わず領域を超えた新規参入が増えている。そんな現状にあって、新規事業を生み出し、推進する事業家を求める声は高まるばかりだ。
しかし、経験豊富な事業家を採用するのは容易なことではない。「新規事業に取り組みたいが、人材もノウハウも不足している」企業をサポートしているのが、Relicだ。新規事業開発・イノベーション創出支援に取り組む同社の特徴は、上流から下流まで一気通貫で事業創造を支援する点にある。
FastGrowではこれまで、代表取締役CEOの北嶋貴朗氏にその経営哲学と事業の全容を聞いたインタビューや、主に0→1を担うインキュベーション事業本部で本部長を務める大丸徹也氏と、1→10フェーズを担当するグロースマネジメント事業本部長・倉田丈寛氏に対するインタビューを掲載してきた。
本記事でお届けするのは、0→1を担い活躍する4名の声だ。「インキュベーション」という言葉を冠する組織や場は日本でもかなり増えてきている印象があるが、それを最も突き詰めているのがここかもしれない。そんな想いを抱かせる取材を、これでもかという長さと濃さで記録した。
インキュベーション事業本部を構成する2つの事業部がどのように活動しているのか。そして、いかにしてクライアントの0→1を成功に導いているのか。話をじっくり聞く中で見えてきたのは、「戦略立案から実行、そして事業の成長まで」クライアントをサポートすることに対するこだわりと、そのこだわりから生じる、唯一無二の成長環境だ。
- TEXT BY RYOTARO WASHIO
「戦略構築」が「実行」の前工程だとは限らない
「『インキュベーション』という名前がついている通り、僕たちのミッションはクライアントの想いを孵化させ、形にすること」と、小森氏はインキュベーション事業本部のミッションを説明する。
ここ数年、この「インキュベーション」という言葉を耳にする機会は増えてきた。スタートアップから大企業、さらには行政に至るまで、さまざまな場で使われている。そもそもincubateとは、「卵を孵す(孵化させる)」という意味の英語だ。転じて、「起業家の育成や新規事業の支援に積極的に取り組むこと」(新明解国語辞典第八版より)という表現として一般化してきた。
ここで問いたい。「起業家の育成や新規事業の支援」がなされれば、良いのだろうか?正直、少し物足りない。やはり事業は、しっかりと立ち上がり、グロースしていくところまで進んでこそ、だ。FastGrowの読者はみな間違いなく、そう感じているだろう。この文脈で考えれば、やはり「インキュベーション」の本場は、Relicという企業の中にこそある、そう感じさせられる。
さて、同事業本部は2つの組織で構成される。ストラテジックイノベーション事業部(以下、SI事業部)とビジネスディベロップメント事業部(以下、BD事業部)だ。まずは、それぞれの事業部がどんな役割を果たしているのかを紐解くことで、起業や新規事業の本質を確かめたい。
SI事業部は、「どんな事業をつくるか」の前段階にある、「いかに事業をつくるか」の検討段階からクライアントに伴走する役割を担う。「新規事業を立ち上げたい」と考えてはいるが、そもそもどんな手順でプロジェクトを進めるべきか、どれくらいの時間軸で、どんな目標を追うべきかすら見当がついていない企業も少なくない。そういったクライアントに対して、新規事業の立ち上げにおける戦略策定、仕組み構築のサポートを提供し、実際に立ち上がりグロースさせ始めるところまで徹底的に支援している。
対して、BD事業部は事業を形にすることをメインミッションとしている。事業アイデアを具体的に検討し、収益化が可能か検証。また、事業を推進するための体制や、オペレーションを構築する。
一見すると、SI事業部が上流を担当し、BD事業部がバトンを引き継ぐ形で事業化を進めるといった役割分担に見えるが、実はそうではない。「SI事業部が『前工程』、BD事業部が『後工程』担当というわけではない」とSI事業部長を務める小森氏は言う。

株式会社Relic 執行役員 インキュベーション事業本部 ストラテジックイノベーション事業部長 小森拓郎氏
小森新規事業は上流の戦略や仕組みづくりがすべてではありません。ときには、緻密な戦略ではなく、力技も必要になる場面もある。つまり、必ずしも戦略が実行に先立つわけではないということです。
クライアントの中にすでに事業案があるのに、それがなかなか形にできておらず困っている場合もある。そういったクライアントの場合、まずはBD事業部の出番になる。事業をある程度形にしてから、上流を整えていくというやり方もあるわけです。SIとBDの関係は、「上流と下流」あるいは「前工程と後工程」ではありません。
一口に「新規事業を立ち上げる」といっても、その過程で生じる課題は企業、あるいはプロジェクトによって千差万別だ。クライアントが抱える課題に応じて、SI事業部とBD事業部は「前」と「後」を入れ替えながら、あるいは同時並行で、それぞれの役割を果たしているのだ。
過去のインタビュー記事などを読んでいればとっくにご存知だろうが、Relicは自社内においても新規事業をいくつも創造している。そんな唯一無二の企業が、ビジネスとして仕組みを構築しているこの新規事業創出フローは、すべてのビジネスパーソンが知っておいて損はないものだと言うことができよう。さあ、更に深く、その真髄を味わっていこう。
「1年後の収益化」だけでは当然足りない。
意識すべきは「20年ワークし続ける戦略」
SI事業部で事業プロデューサーを務める大西氏は、同事業部での業務のポイントを「大局観を持つこと」と「再現性を担保すること」だと語る。
大西クライアントの既存事業とのバランスを鑑みながら「いかにリスクを取るのか」という点をしっかり踏まえて、新規事業の戦略を考案します。その企業が抱えている事業の全体像を見ながら、どのように新たなチャレンジを進めていくかを提案しているわけです。大局観を当たり前のように持ちながら、個別の事業戦略を構築しなければなりません。
また、個々の事業を成功させるのは当然重要ではありますが、その成功をいかに次に繋げていくかも同時に大切です。そのためには、成功を収めた新規事業が「いかに生み出されたのか」、あるいは「なぜその事業に取り組む判断を下したのか」を常に明確にしています。「新規事業」を専門に活動する存在として、当然の責務です。
つまり私たちは、「事業案そのもの」ではなく、「事業案を生み出すための戦略」を磨き込む必要がある。先ほど小森が言ったように、SI事業部の業務は「いかに事業を生み出すか」といった部分からクライアントに伴走します。そういった意味で、SI事業部が担っているのは、クライアントの新規事業の成功に再現性を持たせることだと言えると思っています。

株式会社Relic インキュベーション事業本部 ストラテジックイノベーション事業部 事業プロデューサー 大西圭佑氏
本来であれば、企業内起業を支援する際にも、このような思考や判断が必要になるはず。それは、社内で納得性のある投資判断を行うために、あるいは株主をはじめとしたステークホルダーへの説明責任を果たすために、間違いなく必要なものと言えるだろう。だが、徹底できている企業はきっとそれほど多くない。
なぜか?そこには、新規事業はある意味で「成功する可能性が決して高くないもの」と捉えられているという背景がある。失敗した際の後始末を自社内で完結させられるのであれば、「えいや」と勢いで判断し、「うまくいけばラッキー」と考えることも可能になってしまうのだ。その事業が成功すれば問題ないと考える人もいるだろうが、やはりそれでは「再現性」が不足していく。
新規事業の創造を通したクライアントの短期的な成功ではなく、長期的な成長のために伴走する──それが、SI事業部が果たしている役割だ。だから「再現性」こそ重要だ。小森氏は、「クライアント企業の『課題を捉える時間軸』を変えること」を大切にしていると表現する。
小森中長期的な事業戦略を描き、実行している企業もありますが、現実的には多くの企業が「顕在化している課題を短期的に解決すること」で手一杯になっていると思います。
もちろん、それも重要なことではありますし、我々も「1年以内にアクセラレータープログラムを始めましょう」といった提案をすることもあります。ですが、そういった短期的な課題解決策と同時に、クライアントと共に20~30年後の理想像を描くことが、僕たちのミッションだと思っています。
そして、描いた姿に到達するためには、どのような課題があるのか、それをどのように解決していくのかを考えなければなりません。SI事業部に求められているのは、そういった長期的な理想を実現するための課題解決だと思っています。
新規事業を成功に導く“地図”を描き、更新し続ける
そんなSI事業部には「既存事業とは違う領域で、新たな収益の柱となるような事業を立ち上げたいが、そもそもどのように進めるべきかわからない」といった依頼が寄せられることが多いそうだ。つまり、多くのプロジェクトは「何もない状態」からのスタートになる。
SI事業部はいかにしてクライアントを「新規事業の成功に再現性を持たせる状態」へと導くのだろうか。大西氏が具体的な事例を交えて、その仕事の面白さを前のめりに語る。
その事例もまた、「トップから新規事業の創出と収益化を求められているものの、どのようなプロセスでそれを実現すればよいか考えあぐねている」という、ある一人の担当者からの相談からスタートした。
その企業は安定的に利益をあげることが期待できる事業を展開していた。そこで大西氏は、中長期的に利益を創出していくことを当然の前提とした新規事業を生み出すことで、安定した企業運営と新たな領域へのチャレンジを両立させるプランを提案。
大西実行したことは大きく二つ。一つはインキュベーション戦略の立案です。どのような事業開発フローを新たに構築し、どのような領域で事業を立ち上げるのか、そして、どのような組織設計でそれを進めていくのかについて提案しました。
もう一つは、「事業を生み出すための方法」の検討です。結果的には、社内から事業案を募るためのプログラムを設計することに落ち着き、そのプログラムを推進していくことになりました。

しかし、いきなりプログラムが開始されたところで、具体的なアイデアを持っているメンバーは少なく、アイデアが集まらなければ担当者としても不安を感じるだろう。だからこそ、どのようにアイデアを集め、事業化に至らしめるのか、その具体的な道筋を提示する必要がある。「応募者にはどのようなインセンティブを与えるのか」「事業アイデアの審査については、誰がどのように行うのか」といった詳細まで自ら手を動かして設計してきた。「担当者が迷わなくても済むように“地図”を書くことが重要」だと大西氏は力を込める。
この取り組みで、事業が立ち上がるだけでなく、同時に「ボトムアップで事業開発を進める文化」を根付かせるきっかけにもなったと、クライアントから喜びの声が届いた。
こうした成果を収めるための重要な要素は「柔軟性」だと語る。
大西新規事業を生み出すためのプロセスを細かく設計し、それを基に進めていきますが、その設計通りに進むことなんてほとんどありません。「次の一手」を柔軟に変え続けることが大事なんです。この事例でも、クライアントの事業や組織の状況に応じて、プランを柔軟に変更しながら実行していきました。
クライアントからは「頼んだことしかやってくれない会社もある中、とても柔軟に対応してもらえて助かった」と。戦略を描くだけではなく、共に実行し、状況に応じてプランを変えていく。それがRelicらしさですし、大きなバリューを提供できる一つの要因になっていると思います。まあ、新規事業を常につくってきているので、当たり前と言えば当たり前の動き方・考え方なんですけどね。
健全な「多産多死」こそ、必要な仕組み。
新規事業創出への、正しいコミット法
大西氏が手掛けた事例のように、SI事業部が「アイデアを生み出すための戦略を描く」ことをメインミッションにする。一方、BD事業部は「生まれてきたアイデアを形にする」フェーズのサポートをしている。
BD事業部でマネージャーを務める眞嶋氏は、同事業部が担っている役割をこう説明する。
眞嶋クライアントから「こういったアイデアがある」、あるいは「この技術を生かした新規事業をつくりたい」といった相談を受け、そのアイデアや技術を事業として形にしています。
我々が目指すのは、あくまでも「事業化」です。その目標に向かって、できることはなんでもやる。もちろん、すべてのプロジェクトが実を結ぶわけではありません。新規事業は、数々の失敗の上に成り立っています。アイデアが形にならなかったときは、「なぜうまくいかなかったのか」をクライアントと共に検証し、次のチャレンジに生かしていく。
いわば、事業の健全な「多産多死」を実現しながら、きちんと「事業化」にコミットするのが、僕たちの役割です。

株式会社Relic インキュベーション事業本部 ビジネスディベロップメント事業部 マネージャー 眞嶋伸明氏
新規事業のアイデアなら、今やそこら中にあふれている。さまざまな場でアクセラレータープログラムやコンテストが行われている。つまり差がつくのは「事業化を実現できるかどうか」しかない。Relicはひたすら、この点を突き詰めている。
だからBD事業部マネージャーとしての眞嶋氏には、果たすべきもう一つの重要なミッションがある。それは、事業家の育成だ。これまで見てきたように、Relicはクライアントの新規事業創造を上流から下流まで一貫してサポートしている。そういった事業の根幹を支えるのは、メンバーたちの事業家としての能力だ。
眞嶋先ほど「多産多死」という言葉を使いましたが、もちろん失敗を前提にしてプロジェクトを推進しているわけではありません。しかしながら、仮説検証の中で進めてきた事業をクローズさせる、もしくはピボットする判断を下さなければならないときもある。
事業を成功に導くことはもちろん、適切なタイミングでクローズやピボットの判断を下せるかどうかが、事業家としての腕の見せどころだと思っています。そういった部分も含めて、メンバーたちの事業家としての能力を伸ばさなければならないと考えています。
そのためにはやはり、「とにかく多く、良質な事業立ち上げ経験を積むこと」が良いでしょう。私たちはほかのどの企業に属するよりも、多くの事業立ち上げに関わるチャンスを得ることができています。これが差別化につながる一番の秘密ですね。
このことが、ほかのメンバーからも繰り返し語られる。事業について考え、実際に戦略を策定し、その実行を試み、必要な変化を検討してはまた実行していく。このサイクルこそが、事業家を育てるわけだ。
眞嶋Relicの成長のキードライバーは「事業家として十分な力を備えているメンバーの数を増やすこと」。だからこそ、マネージャーとしての僕のミッションは、事業家育成だと捉えています。
そして、社内で事業家を多く生み出した先には、支援先の企業それぞれにおいてもさらに事業家人材を育てていけるかもしれません。そうやって波が広がっていくことも楽しみに感じながら取り組んでいます。
「緻密な戦略が書かれた膨大な資料」に価値はない
そんな眞嶋氏の下でプロジェクトリーダーを務めているのが永渕氏だ。同氏のミッションは「とにかく新規事業を立ち上げ、その成功確度を高めること」。具体的には、どのようなプロジェクトを手掛けてきたのだろうか。「印象的な事例」として、永渕氏は次のような事例を挙げた。
連続的に新規事業を生み出していくことを目標とするクライアントから、「毎月10本前後の事業アイデアを出してほしい」というオーダーを受けた永渕氏。「連続的にアイデアを出し、事業の種を生み出し続けるための仕組み」も含め、提案することになった。
「シェアリングエコノミー」といった特定のテーマを定めて事業案を出す方法など、複数の仕組みを考案し、アジャイル開発のような形でそれらを短期間のうちに実行。クライアントとのディスカッションを繰り返し、理想の形を模索していった。
そうして行き着いたのが、海外スタートアップの事例を参考に、新規事業の種を生み出す方法だ。この方法によって数々のアイデアが生み出され、実際に複数の案が事業化に向けて着実に歩みを進めている。
このプロジェクトには「Relicらしさ」が反映されていると永渕氏。どのような点が「らしい」のだろうか。

株式会社Relic インキュベーション事業本部 ビジネスディベロップメント事業部 プロジェクトリーダー 永渕貴煕氏
永渕この一連のプロセスの中で、PowerPointのスライドなんて一枚も書いていないんです。いわゆる新規事業コンサルティングを行う企業であれば、まず膨大なスライドの資料をつくり、プレゼンテーションをした後に、プロジェクトを進めると思います。
もちろん、クライアントに求められれば資料もつくりますが、そうでなければ資料をつくらずにプロジェクトに入ります。僕たちが提供する価値は「丁寧につくられたボリュームのある資料」ではなく、あくまでも「新規事業を成功させること」ですからね。
それに、コンサルティングファームであれば、クライアントから要件を聞いて、あとは社内で検討を進めるのが一般的な方法でしょう。つまり、クライアントからはその思考過程が見えない「ブラックボックスの中」でプロジェクトを進めるわけです。そうではなく、クライアントと対話し、修正と改善を繰り返しながら事業化に向けさまざまな施策を実行するのが、Relicのやり方。
先程申し上げた事例でも、柔軟性を持ってさまざまな方法を試しながらプロジェクトを進められたからこそ、短期間で事業化が期待できる複数のアイデアを生み出せたと感じています。
Relicがクライアントにもたらすのは、「壮大なストーリー」や「大きなビジョン」が描かれた“美しい”資料などではない。あくまでも、Relicは「実行」を通して「新規事業の創出」という大きなバリューを提供しているのだ。
だから、永渕氏をはじめとしたコンサルティングファーム出身者も多く集まり、大きなやりがいを日々感じながら過ごす。過去の経験を存分に活かしつつ、新たに直面する難しい課題に四苦八苦することも含めて楽しんでいる。一人ひとりが仕事について語る充実した表情を見ていると、そんな様子が目に浮かぶようだ。
Relicが事業家を目指す人にとって最適な環境である理由
永渕氏は複数のスタートアップで新規事業開発に携わったのち、独立系コンサルティングファームの戦略部門に転じ、主に新規事業開発支援を担当した経験を持つ。スタートアップ、コンサルティングファーム、そしてRelic。さまざまなステージで新規事業にコミットしてきた同氏だからこそ語ることのできる今の面白さについて、せっかくなので詳しく聞いてみたい。
永渕スタートアップで新規事業に携われば、「自ら事業をつくり、動かしている」という手触りが感じられますし、事業が当たったときは金銭的な見返りも大きく期待できますよね。その一方で、「数」についてはあまり期待できません。「社会に価値を提供する事業に携われる機会の多さ」と言い換えてもいいかもしれません。
スタートアップにおいては、複数年にわたって一つの新規事業にコミットすることが一般的です。3年をかけて一つの事業を社会に送り出し、何かしらのインパクトを与えられれば万々歳でしょう。でも、現実的には何年も細々と続けた事業が、社会に大きな価値を提供する前にクローズになってしまうこともある。
もちろん、その失敗に意味がないとは言いませんが、僕は新規事業に携わるのであれば、たくさんの事業を送り出し、世の中に価値を提供したい。その点、Relicであれば何度も「新規事業を通して、新たな価値を創造する」体験ができるんです。
一つのプロジェクトが3カ月スパンだとすれば、1年に4本。それに、Relicでは本人の希望次第で同時に複数のプロジェクトに参加できるので、1年でコミットできる新規事業の数は10件を優に越えます。

また、前職であるコンサルティングファームとの違いは「新規事業に携われる可能性」と「コミットメントの濃度」にあるとする。
永渕以前勤めていた会社はイノベーションファームを標榜していたのですが、実際に新規事業のサポートに携われる機会は限定的でした。みんな新規事業案件に憧れを持っているものの、実際に担当できるのは一部のメンバーでしたから。Relicの場合は、業務のすべてが新規事業に関するものなので、「新規事業に携わりたかったのに……」ということは起こり得ません。
もう一つ違いがあるとすれば、クライアントに対するコミットメントの濃度の差でしょうか。無論、コンサルティングファーム時代も全力で業務にコミットしていましたし、同僚たちもそうでした。しかし、これは僕の感覚ですが、事業の内容など本質的な部分の検討に割くのはリソースの2割程度で、あとの8割は検討した内容をうまく伝えるためのペーパーづくりに充てなければならなかった。
個人的にはそこにフラストレーションを感じていました。きれいなペーパーを書くよりも、事業の成功確度を上げるために時間を使いたいのに、それがなかなかできない環境だったんです。
先程も言ったように、Relicでは基本的にすべてのリソースを「新規事業を立ち上げ、成功させるため」に費やせる。そういった意味で、コミットメント濃度が違うと感じていますし、この環境を選んで良かったと心の底から思っていますよ。
「縦横無尽に」新規事業に携われるチャンスがある
眞嶋氏が言葉を重ねる。新規事業を立ち上げるために必要なのは、「何もないところに踏み込み、前に進むこと」だとする。その「何もないところ」には「きれいな因果関係」すらも存在しないのだ。
眞嶋新規事業とは、「無」の状態から「有」を引き出す行為だと感じています。文字通り、始めは「何もない状態」からのスタートで、その時点では物事の間に因果関係なんて存在しない。だから、ロジックを組み上げ、アクションの正しさを説明するための資料をつくってもしょうがないと思っています。
大事なことは、何もないところに足を踏み入れ、とにかく行動すること。そして、その行動が正しかったかどうかをクイックに検証することです。そのためには、分厚い資料なんて必要ありません。エクセルやスプレッドシートのようなものを使ってリアルタイムで検証を重ね、クライアントに報告すれば十分にわかってもらえますし、スピードも担保できるんですよ。
永渕氏と同じく、コンサルティングファーム出身の小森氏は、「自由度の高さ」をRelicの特徴として挙げる。戦略コンサルティングファームは、さまざまな領域にまたがり事業戦略の立案を手掛けられるが、実行フェーズまで伴走することは難しい。一方、実行フェーズにまで携わることもできる経営コンサルティングファームは、関われる領域が限られる。
小森氏が過去所属していたコンサルティングファームでは、例えば「製薬会社の組織人事」という領域で専門性を磨くことはできるが、反面、その外に飛び出す機会は少なかったと振り返る。
小森Relicは戦略立案から実行と“縦”に深く新規事業の立ち上げをサポートできます。また、業種業界を問わずさまざまな企業からの案件が舞い込み、メンバーの「専門」は限定していないため、さまざまな領域のプロジェクトにチャレンジできる。
まさに縦横無尽に新規事業に携われる機会があるわけです。

大西氏は、Relicの体制面に魅力を感じていると話す。これまで見てきたように、プロジェクトによって順番は前後することもあるが、たとえばSI事業部が戦略を描き、BD事業部がバトンを受ける形で事業のアイデアを形にしていく。
Relicの支援はそこで終わらない。その後プロジェクトマネージャーやシステム開発担当をアサインし、クライアントの事業が「立ち上がるまで」ではなく、「成長するまで」伴走するのだ。
こういった体制を敷き、一気通貫したサポートを提供しているからこそのやりがいと、事業家としての成長を感じていると大西氏。
大西事業が成長するまで添い遂げられることが重要だと思っていますし、このことが事業家としての成長につながっていると感じています。新規事業を立ち上げ、成長させるまでにはさまざまな段階を経なくてはなりません。戦略立案、事業企画、組織構築、オペレーション設計など、そのどれもが事業の成功には欠かせない要素です。
Relicではすべてのフェーズを自分ごととして体験できる。つまり、プロジェクトが終わったのちに、総体的に振り返ることができるんです。しかも、その経験を多く持つ先輩や同僚が社内に多くいるので、フィードバックももらい放題(笑)。
仮に失敗に終わってしまったとしても、戦略が正しくなかったのか、組織設計に穴があったのか、はたまた事業のオペレーションに不備があったのか、すべてのフェーズを振り返り、PDCAを回すことができます。これは一気通貫したサポートを提供しているRelicならではなのではないでしょうか。
メンバーが主体的に新規事業に取り組むことが「当たり前」の環境
会社として一気通貫したサポートを提供していようとも、自らの頭と手を使ってプロジェクトにコミットしなければ、事業家としての成長は望めないだろう。しかし、4名の言葉の端々からは、メンバーの一人ひとりが新規事業を立ち上げ、成長させる主体者としての実感と矜持が見える。
そんな感想をぶつけると、眞嶋氏は「一般的なスタートアップなどと比べても、個々のメンバーに与えられている裁量は大きいのではないか」と応じた。その理由はこうだ。
眞嶋新規事業の立ち上げには、不確実要素があふれています。すべてのプロジェクトが社内の誰も経験したことのないものですし、役員だろうがマネージャーだろうが若手だろうが、正解なんて誰にもわかりません。
それに、先程も言ったように新規事業の立ち上げに失敗はつきものです。だからこそ、「正解を出してね」と裁量を渡すのではなく、「不正解でもいい。その代わり、そのプロセスを次につなげてね」と裁量を渡すことができるわけです。
新規事業に特化しているからこそ、そういった裁量の渡し方ができる。そうして、すべてのメンバーが主体者としてさまざまなチャレンジに挑めるからこそ、事業家としての成長が期待できるのだと思っています。
また、クライアントワークだけではなく、社内での事業立ち上げにチャレンジする自由度も極めて高いという。実際に、永渕氏は自らが担当している案件の他に、Relicの新規事業として複数のプロジェクトを推進しているそうだ。
永渕ボトムアップで新規事業を立ち上げる文化の定着度合いは、企業によってまちまちだと思います。事業を立案するための制度すらない会社、制度はあるものの活用されていない会社もあるでしょう。Relicの場合は制度を利用せずとも、直接社長に提案できるようになっていますし、実際に僕もこれまでいくつもの事業プランをぶつけてきました。
現在、その中のいくつかのプランを事業化に向けて進めています。もちろん、自ら事業案を提案し、プロジェクトを推進しているのは僕だけではありません。Relicにはメンバーが主体的に新規事業を立ち上げ、推進する文化が根付いているんです。

「インキュベーション事業本部内に、事業化に向けて進んでいるメンバー発信のプランはどれだけあるのか」という問いかけに対する小森氏の答えに、「Relicらしさ」が表れている。
小森10以上はあると思うが、誰も把握していないんです(笑)。
把握する必要のないほど、Relicにとってメンバーが主体的に新規事業に取り組むのは「当たり前のこと」なのだろう。自由に、そして深く、新規事業を突き詰めることのできる環境がここにはある。
こちらの記事は2022年05月30日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
次の記事
執筆
鷲尾 諒太郎
1990年生、富山県出身。早稲田大学文化構想学部卒。新卒で株式会社リクルートジョブズに入社し、新卒採用などを担当。株式会社Loco Partnersを経て、フリーランスとして独立。複数の企業の採用支援などを行いながら、ライター・編集者としても活動。興味範囲は音楽や映画などのカルチャーや思想・哲学など。趣味ははしご酒と銭湯巡り。
特別連載挑戦者と共創するインフラとなり1000の大義ある事業と大志ある事業家の創出を目指す
7記事 | 最終更新 2022.07.27おすすめの関連記事
機会の「バリエーション」と「場数」こそが価値の源泉──リクルート新規事業開発PdMに訊く、個の経験値を左右する組織構造の真実
- 株式会社リクルート 事業開発領域プロダクトデザイン部 部長
プラットフォームは、「ステークホルダーの結節点」を押えよ──“オセロの角戦略”を起点に市場創造を行うHacobuとセーフィーが明かす、事業の意思決定軸
- 株式会社Hacobu 代表取締役社長CEO
現場にいる者こそが、意思決定者──年次も経験も関係ない!UPSIDERで非連続成長を担うのは「一次情報を最も知る者たち」だ
- 株式会社UPSIDER 執行役員 / VP of Growth
事業家人材が望むのは「アクセルをベタ踏みできる環境」「地に足の着いた経営」の両立──入社半年で、10倍成長の事業責任者を務めるX Mile安藤が明かす、“コンパウンド化”の過程のリアル
- X Mile株式会社 物流プラットフォーム事業本部マネージャー
大企業の課題を「ワクワク」感を持って共に解決する。──“そのパワフルな動き方は、小さなアクセンチュアや電通”と形容するpineal。大手企業の基幹戦略を内側から変革するマーケティング術とは
- 株式会社pineal 代表取締役社長
そんな事業計画、宇宙レベルで無駄では!?プロ経営者と投資家が教える3つの秘訣──ラクスル福島・XTech Ventures手嶋対談
- ラクスル株式会社 ストラテジックアドバイザー
隠れテック企業「出前館」。第2の柱は32歳執行役員から──LINEヤフーとの新機軸「クイックコマース」に続く、第3の新規事業は誰の手に?
- 株式会社出前館 執行役員 戦略事業開発本部 本部長