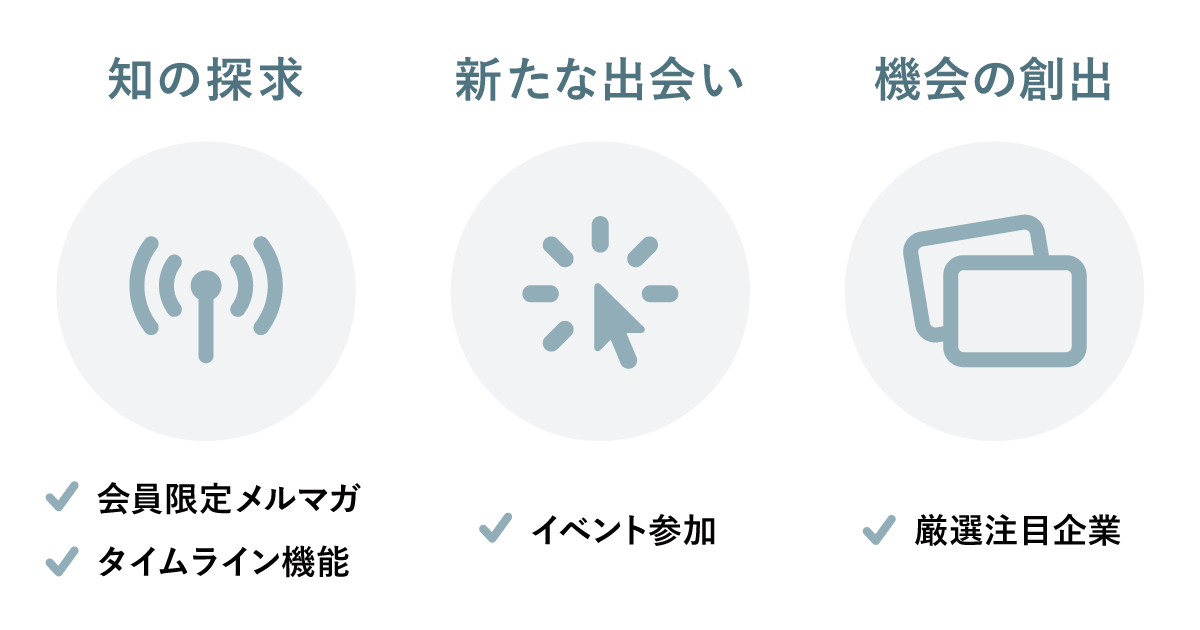想いを具現化することで「ナナメ上」へ連れて行く。
イノベーション担当からの依頼が絶えないメソドロジーファーム、アンドゲートの5ヶ年計画
Sponsored
極めて属人性が高く、ロジックに基づく体系化は不可能とさえ思われていたのが、プロジェクトマネジメントの領域。そこに持ち前の“方法論”化する思考と高度なテクノロジーの注入とで一石を投じたアンドゲート。2017年の設立以来、大手クライアント企業からのオファーが相次ぎ、この2年で業績は確実に拡大した。だが創業者である田村謙介氏によれば、まさに七転八起の日々だったとのこと。
オンリーワンの強みを持っていようとも、スタートアップが成長ステージを一段上げていくのは容易ではないことを痛感したリーダーは、ようやく骨太な力強さを得た今、何を思い、どんなビジョンを描いているのか。
- TEXT BY NAOKI MORIKAWA
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
「中小企業のままではなく、でっかいことを成し遂げる」。急な組織拡大での失敗を糧に、ビジョン・ミッションを策定
アンドゲートが2017年に誕生した時、田村謙介氏と北川雅弘氏、岸上健太郎氏が目指したのは、あらゆる企業が営むプロジェクトのマネジメント局面に携わりながら「問題解決をする“方法”のシンクタンクとなる」ことだった。
属人性が高い従来のプロジェクトマネジメントに、クラウド系の先進技術をはじめとする数々のテクノロジーと、ロジカルシンキングや当時は今ほど注目されていなかったデザインシンキングといった思考法・方法論とを持ち込むことで変革を起こしていくというアプローチ。その斬新さと独自性に期待を寄せてくれる企業は順調に増え、人も増え、組織は拡大していく……つもりだったのだが……。

田村そもそも「でっかいことを成し遂げる」と意気込みながらも「仕事はあるのか?どう成長させていくか?」という不安もあったのですが、北川、岸上という心強い同志とともにスタートしてみたところ、すぐにクライアントから支持を得て慌ただしく仕事をしていました。
忙しさの波にもまれる中で社員として参画してくれる者も増えていき、10人規模では視界良好という感覚だったのですが、その後一気に採用を進め15人ほどの編成になったタイミングから内部の一体感に歪みが現れ始めたんです。
数千人〜数万人規模の企業でしか働いたことのない者にはピンと来ないかもしれないが、10人の集団がある日から15人になったということは、組織の規模が突然1.5倍になったということ。その変化は大きかった。
田村アンドゲートでは「コンサルティング・プロジェクト推進・テクノロジー」の3つを連携させながらサービスを提供することで、独自の強み・競争力が生じて、支持を得ていたわけです。
その背景には“方法論”が存在する考え方は重要で社内のトレーニングにも取り入れていました。ところが既存メンバーが“結果にコミットする”面に重心を置いていたのに対し、新たに加わったメンバーの中には“プロセスや共感”に重きを置く価値観の持ち主が多かった。
“方法論”はプロセスに注目するものではありますが、結果が出せなければ意味がない。目的があっての手段であることを伝えきれず大切な部分がすっぽり抜け落ちていた。議論をして折り合えるような次元にないことを知った時、CEOとして大いに反省をしました。
勘違いしないでいただきたいのは、この田村氏の性格からすると、意見衝突や激しい議論はウェルカムなはずなのである。
そもそもクライアント企業が新しい難題にチャレンジしようとするようなプロジェクトに関わっていたアンドゲートだけに、前例によって証明されている「正解」はなく、ディスカッションは問題解決のために必要不可欠なプロセスではあった。
だが、各自の根元的な価値観に大きな相違があっては、何度話し合っても全員で納得できる意思決定にはつながっていかない。人材採用における自身のワキの甘さを田村氏は思い知った。だが、このことが前進につながるきっかけになったともいう。
田村去っていく人たちの置き土産に「そもそも、この会社は何を実現するためにあるのか」「ここにいる皆で何がしたいのか」というメッセージがあり、改めて自分の考えを明文化しメンバー同士で話し合いをするようになりました。
設立から1年ほど経過したタイミングでしたが、「今きちんとビジョンやミッションの再考、再確認、再共有をしなければ、アンドゲートとしてやっていく意義や価値がなくなる」という危機感がありました。

早期から注目されたスタートアップ企業が、短期間で急成長を果たしたにもかかわらず空中分解するケースは少なくない。もちろんその理由は様々だが、アンドゲートが体験したような「業績順調であるがゆえの組織拡大が不協和音を生んでしまう」というリスクは、どんな企業にもあり得るものだ。「今食い止めなければ」という危機意識は大きかった。
田村様々なことを考え、話し合いましたが、例えば「プロジェクト運営において、理想と現実をどれくらいのバランス感で共存させるか」というようなテーマ。微妙な感覚値に左右されがちなこうした部分を、全員で話し合いながら揃えていく過程を踏むことができたのは、実に大きな収穫でした。
その結果「クライアントが自身だけでは行けない地点へ連れて行く」「クライアントの業績グラフを右肩上がりにする」「あえて斜に構えていたい」という意味を込めて「ナナメ上の世界をつくる」というビジョンができあがりました。
その他にも、会社の性格やブランドを表すキーワードを決めたり、社内・社外それぞれに向けたチャレンジを明文化してみたりと、自分たちが何者かを見つめ直す良い機会になりました。
私としては、もともと「SIerのように、人の頭数で商売をする時代ではない」という持論もあってアンドゲートを設立したところもあるので、今後順調に実績が伸びていっても、いたずらに社員数を増やしたりはしないつもりです。
それでも、クライアントからの仕事のオファーにしっかりと結果を出していこうとすれば、70~100名規模は必要だと考えています。ですから、設立1年後に痛感した思いと、そうならないための営みというのは、決して忘れてはいけないと心に誓っています。
結果を基準とした価値観を持つ人材をしっかり見極めたうえで仲間になってもらうこと、そしてメンバーとの間でビジョン・ミッションの共有をすること。その重要性を思い知った田村氏は、継続的課題として肝に銘じながら次なる成長ステージに向かおうとしている。
VUCA時代に真価を発揮するのが「イシューを言語化できる集団、アンドゲート」
2年前のFastGrowのインタビューでは、「方法論」「ロジカル」「シンクタンク」といった言葉の印象が強かった田村氏だが、今回のインタビューでは「魂」「想い」といった対照的とも言えるエモーショナルなワードを多用している。
そのことを指摘すると「たしかにそうですね。まあ、創業時だって魂や想いを重視していたんですけれども」と笑う。「今度は対外的な環境や、実際のビジネスにおける変化について教えてください」と尋ねた時に、このキーワードは連発されたのである。

田村一言で現状のビジネスシーンを表現すれば、「社会の変化が早くなり、複雑性が急速に高まったことにより、物事を整理しなければいけない必要性が格段と上がった」。私はそう捉えています。
そして、「その整理こそが事業が解くべきイシューの起点となるのに、その整理のスキルを持つ人間が世の中にあまりいない」。つまりこの状況こそが、アンドゲートのチャンスが急拡大している理由なんだと考えてもいるんです。
田村氏は立ち上がり、世の中のプロジェクトというものがどういうプロセスに整理できるのかを、下記のようにホワイトボードに書き込んで示してくれた。

[想い]→[要求]→[要件]→[設計]→[開発・構築]→[運用]。
例えば通常、IT系のプロジェクトであれば3つ目の[要件]を定義するところが最上流になってプロジェクトは進んでいく。そもそも案件の発注主であるクライアント企業の多くは [要求]は持っているものの、それをどう形にすればいいのかわからなくて悩んでいたり、形にする技術力を備えていなかったりする。
そこで、プロジェクトの実質的な進行者としてIT系コンサルティングファームやSIerと総称される企業群に期待をかけ、[要求]をぶつけていき、彼らはそれをより具現化した[要件]へと定義していく。しかし、既にそこから問題が発生している……田村氏はそう指摘する。
田村 [想い]を[要求]にする時点で間違いが生じていたり、そもそも要求分析をしていなかったりすることが多くあります。「本来やるべきことが抜けていた」ということを恐れるあまり、他社事例や他案件をコピーし、網羅的な[要求]を揃えて満足しているのです。
しかし、それでは「不必要な[要求]」が混ざっており、その分無駄な検討事項や開発・構築が増えるので提供するまでのスピードが落ちることにつながります。
「いる・いらない」で言えば「いる」、だが「重要ではない」といった温度感を整理することで、本来実現したい[要求]が明確になり、それは[想い]から通じていると考えています。
アンドゲートが提供しているサービスである「コンサルティング」「プロジェクト推進」「テクノロジー」をそれぞれ人の「頭」「骨」「肉」に置き換えて説明することがありますが、[想い]を生み出す「魂」そのものになることはできません。
「[要求]から考えて欲しい」との要望も多いのですが、何をしたいかはクライアントしか決められませんので、我々は「頭」を提供して「魂」を見つけるお手伝いをしています。
あまり良い事例とは言えないが、実際に多方面で行われているパターンとしてDXがらみのチャレンジを例にとればわかりやすい。
「デジタルで変革を起こさないと当社も生き残れない、という号令がトップから出ているので、うちもDX的なことをしようと思うのだけれど、何から手を着ければいいのかさっぱりわからない」という企業は非常に多い。
「デジタル技術を導入する」という発注企業の[想い]らしきものは、それで叶うのかもしれないが、こんなことでその企業に最も適したDXが実現するはずもないことは明らかだ。
「想い」あるクライアントとのディスカッションを通じて、「ナナメ上」に事業を持っていく。これがアンドゲートの正攻法
田村その企業の未来を左右する、本当に時間をかけて向き合わなければいけないものは [想い][要求]といった[要件]以前の段階なのに、気がつけばそのプロセスが「最初から正しい」という前提に立ち、きちんと向き合わないままプロジェクトが進んでしまう。
曖昧な[想い]を具体性のある[要求]に落とし込む努力をしていない発注企業が悪いのかというと、そうとは言い切れませんし、[要件]以後のプロセスで収益を上げるモデルしか持ち合わせてこなかったSIerに非があるとも言い切れません。
これまでは、こんな歪みのある構造でも一定の成果につながってきたのでしょう。ただ「このやり方では駄目だ」としっかり理解している企業が今、増えている事実もあるんです。不確実で先の見えないこの時代だからこそ[要件]以前の段階に本当の価値がある、と気づいている。
でも問題は、じゃあいったい誰に相談すれば良いのか、なんです。
アンドゲートはまさにこうしたニーズに適合できる、ということである。「売りたい自社プロダクトや独自技術」を豊富に持っているわけではないが、技術的なリテラシーは世のコンサルやSIベンダーに負けてはいない。プロジェクト推進に付きまとう泥臭い局面も熟知したメンバーもいる。
そしてデザインシンキングを駆使したプロセスコンサルティングも含め、「ものの考え方」を整理して課題抽出を行う専門性の担い手もいる。すなわち「頭(コンサルティング)、骨(プロジェクト推進)、肉(テクノロジー)」を兼ね備えたアンドゲートが本領発揮できるビジネスチャンス到来というわけなのだが、「どんな案件でも受ければいいわけではない」と田村氏。事はそんなに単純ではないようだ。
田村ゆくゆくプロジェクト発注側となるはずの事業オーナー企業の多くが、「相談したいことがあるのに、相応しい相談相手が実はいない」ことに気づき、アンドゲートに着目してくれる機会が増えていることは、本当に嬉しいことです。
ただ、いくつかの企業にお会いしてみてわかったのは、どんな企業にも[想い]があるのかというとそうではないということです。
先に例として挙げたような「上の経営陣が何かやれ、と言ってくるからどうにかしないと」というレベルでは、田村氏の言う[想い]にはほど遠いようだ。
どんなに抽象度が高くてもいいから「自分が描くビジョンの達成のために、こういうことができたら、自社のビジネスでこういう効果や成果につないでいくことができる」というようなものがなければ、貢献しようがない。
田村声をかけていただければ喜んでうかがいますし、[想い]以前の状況だったとしても、可能な限り相手の思考を図解しながら整理をして、コンサルティングをしていきますが、結果としては他社のコンサルティングファームやSIerに案件を委ねるような取り組みになるケースが多くなります。
結局[想い]といえるものが事業オーナーから出てこなくて「あとはコンサルティングファームやSIerに任せたほうがコスト面も含め得策」となれば、その時点でアンドゲートとしてはその案件から退く他ない。
「それでもその潔さが信用につながって、また声がかかる機会になるのだから嬉しい」と田村氏は言うものの、やはり[想い]のある事業オーナーとの取り組みで、アンドゲート本来の価値を創出していくことが本流だ。

田村実は声をかけてくださるのは事業オーナーばかりではなく、SIerや開発会社からも相談を持ちかけられる機会が増えたんです。
「我々はシステムのことならば自信はあるけれども、要件定義以前の部分をお客様から相談されても、ビジネスの知見に通じたプロフェッショナルがいるわけではない」ということから「その不得手な部分で相談に乗ってほしい」というお話しです。
私たちが事業オーナーと直接つながるのではなく、そのSIer・開発会社側の人として向き合うことになれば、最終的にその会社が売ろうとしているソリューションや製品に着地させる方向へ話しを持って行かざるを得なかったり、余計な政治的判断が入り込んだりします。
裁量をいただける会社さんとはとても良い関係ですが、条件の多い環境ではパフォーマンスが十分に発揮できないことがわかってきました。
ただし、以上のような歯がゆいケースばかりではない。ここ数年で[想い]をしっかり持った事業オーナーが増え、そうした企業から声がかかるようになったのである。
その代表例が、2020年2月のインタビューに登場した中野氏や佐川氏が参画する動画配信事業に絡むテレビ局各社だという。
田村こうした事業オーナーである企業と直接向き合った取り組みで成果を上げ、継続的な関係にもつなげることができたことから、これこそアンドゲートの真価を発揮できるスタイルなのだということがはっきりしました。
もちろん、プロジェクトの全てのプロセスにアンドゲートが最後まで関わるケースばかりではありません。先ほども言ったように、きちんと[想い]を整理することから見えてきた[要件]が、もしも特定のベンダーやSIerが得意とする領域であれば、そこから先の実作業は依頼したりもしますし、我々がプロジェクト推進にコミットしてPM機能を果たすべきであればそうします。
ともかく、いったんは事業オーナーからすべての[想い]をアンドゲート側に伝えてもらう。そのうえでどうすればアンドゲートが志す「ナナメ上」の成果、つまり事業オーナーの[想い]を超えるほどの効果につなげて、世の中の仕組みを変える次元にまで持って行けるかを考える。
現実と理想が隣り合わせになっている局面が来たら、アンドゲートで共有している価値観をベースにして最善策を提案する。2年が経った今、こうして事業の進め方がようやくしっかりとかたまってきた手応えを感じています。
「クライアントが憑依した気持ちで提案する」。眼前の利を追わないスタンスで信頼を築く
田村氏は重ねて言う。「私たちは“魂”を持った事業オーナーが“想い”を実現する速度を上げ、その成果を着実なものにしていくうえでのパートナーになっていく存在」だと。
そうなれるのは、「頭(コンサルティング)、骨(プロジェクト推進)、肉(テクノロジー)」を持ち、短期的な利害関係抜きで[想い]に寄り添う姿勢を示しているからに違いないが、他にも何か要因はあるはず。その点を尋ねてみると、またしても「メソドロジーファーム」らしからぬ表現で答える田村氏。

田村とにかく事業オーナーと向き合う時、とりわけ「こうあるべき」という提言をする時には、相手が憑依しているくらいの心境で臨みます(笑)。どうすればこの人たちの[想い]により早く到達できるのかを考え抜きます。そうすると見えてくる景色が違うんですよ。
例えば「最初のチャレンジではアンドゲートをとことん使い尽くしてレールに乗せるけれども、そこから先はウチだけで自走できる」なんて発想が、憑依しているからこそ浮かんできます。そうしたら、それをそのまま伝えるんです。
逆に、既存のクライアントからの無茶な要望を聞き入れることだってあります。「明日からこのサービスでキャンペーンを実施するからアクセスが急増する」「新規にVPNを構築できないか?」といったような話ですね。
「餅は餅屋」ですので全ての要望を受けることはできませんが、[要件]を整理したり実現できるパートナーを探したりすることはできますよね。その「次のステップ」を後押しする相談役になることがクライアントに寄り添うことだと思っています。
いずれの場合も、たとえアンドゲートとしての収益がその場は小さくなったり、本当は断るべき類の仕事の依頼であったりしても、それがクライアントとってベストの選択ならば、私たちは「信頼構築できる行動」に徹したほうが、中長期ではビジネス的にもメリットがある。そういう信念で仕事を行っています。
一緒になってとことん考え抜いた最良の結論が、「結局今はまだ着手できないことになった。ただいつか必ず動き出す」というものであっても構いません。
先行きが不透明な現代のビジネスではありますが、だからこそ「それでもなんとか見通せる範囲の未来」についての理想を、「信頼できて、共創できるパートナーだ」とクライアントに認識してもらうことに、絶大なる価値があると思っているんです。
スタートアップだけでなく、社員とも共創する。自分が生み出した事業で一生稼ぎ続けられる仕組みを、社員にも提供したい
田村氏はアンドゲート自体もこの「見える限りの未来」像を固めつつあるのだと語る。
田村今はとにかく固まり始めた当社の事業の姿を確立して、サービス開発を進めていくのが課題です。これまでよりも具体性のあるサービスメニューを発信して、アンドゲートという会社の輪郭をよりクッキリと打ち出し、支援できるクライアントの数を増やしていきます。
そしてこのサービス開発の目標をきちんと達成しながら3年後を迎えたなら、クライアントだけでなく、社員とのレベニューシェアの仕組みを作り上げていきたい。そして5年後には、70名規模にまで組織も育て上げ、スタートアップとの取り組みをインキュベーション事業(ベンチャー投資事業)としてスタートしたいと考えています。
お金はないけれど、アイデアも想いも持っているスタートアップが多数あって、そういうところと一緒にチャレンジをしていきたい気持ちは今でも重々あるのですが、まだ早いと捉えることにしました。
というのも、これまでの2年間で何度か試してみたんです。その結果、目先の収益に繋がりづらいスタートアップを支援する上では、我々の資金力を含めた企業体力に不足を感じた経緯もあったので、「やるならばしっかりコミットできるノウハウ、人材力、資金力を蓄積してから」と決意しました。
ですから5年後に本当にチャレンジすることになれば、資金調達の手段としてのIPOについても、その時点で明確に意識するかもしれません。
最後に田村氏は、冒頭話していた反省事項について再び触れ、今度こそ明快なビジョン共有をベースに、どのようにアンドゲートの組織体制の拡大を進めていくかの意向を示した。社外企業だけでなく、社員とのレベニューシェアの仕組みに今後挑戦するのも、より多様な人材が思う存分アンドゲートを利用して、稼いでくれるようにしたいからでもあるという。
田村今日は「魂」とか「想い」とか、うさんくさい単語を何度も使いましたよね(笑)。しかし、プロジェクトのマネジメントは時代が変わっても血の通う仕事が求められる場ですから、ロジックやテクノロジーと同じように今後も大切にしていきたいと思っていますし、だからこそメンバーにも、クライアントと対面で触れ合える場を持ってもらうように工夫しています。
ただし、昔のような働き方や稼ぎ方に執着はしているわけではありません。むしろアンドゲートが発端となって、いろんな「次のアタリマエ」を創っていきたい。
たとえば、「会社を好きじゃなければいけない」なんてことはありません。「会社が好き」という感情は、働いているうちに芽生えてくるものだと思っているからです。
あとは、社員には「魂」を込められる事業を生み出すスキルを身に着けて、どんどん卒業していってほしいと思っています。そしてアンドゲートで事業を立ち上げてくれた卒業生には、その事業で生まれる収益の一部を、半永久的に還元する仕組みも創ってみたいと思っています。会社員として働きながら将来の不労所得の源泉を創造できるって、カッコいいと思いませんか?(笑)
そういう先進的な取り組みに興味がある、次世代のタレントが集ってくれるために必要な組織的仕組みを、私も起業家として創造したいと思っています。なぜなら私自身、会社をステップアップの場として活用し、いま稼げるようになった人間ですからね。
アンドゲートも早く、優秀で、事業をつくれるポテンシャルのある人たちにとって「踏み台」にしたくなる会社にしたい。クライアントだけでなく、社員から見ても信頼できる、好きになれる会社を創ろう。そんなことを考えながら、アンドゲート自体も「ナナメ上」の発展と拡大を目指していきます。

こちらの記事は2020年04月13日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
森川 直樹
写真
藤田 慎一郎
連載新たなPMのカタチの確立を目指す ──アンドゲートの挑戦
6記事 | 最終更新 2020.04.13おすすめの関連記事
「天才じゃなくていい。最強の二番手にとっての天国がココにある」──他社を巻き込みイノベーションを創出する「プロジェクト推進役」の担う価値
- 株式会社アンドゲート 代表取締役 CEO
現場にいる者こそが、意思決定者──年次も経験も関係ない!UPSIDERで非連続成長を担うのは「一次情報を最も知る者たち」だ
- 株式会社UPSIDER 執行役員 / VP of Growth
FinTech×EC支援で事業を連続創出できる理由とは?BASEのツーサイドプラットフォームに魅せられた山村・髙橋の躍動を追う
- BASE株式会社 上級執行役員COO
個人やスモールチームの可能性を最大限に広げるプラットフォームへ─GMV1,500億円超もまだまだ成長途上。BASEでさまざまなBizDevに挑戦できる理由とは
- BASE株式会社 BASE事業 Business Management Division Manager
2倍成長を続けるTOKIUMに学ぶ「最強のオペレーション戦略」とは──「壮大・緻密・柔軟」の3要素で、BPaaSとしての成長を実現した秘訣
「支社配属=密度の濃さ?!支社だからこその強みがここには実在する」──就活生が気にするキャリアプラン。電通総研・広島支社に聞いてみた
- 株式会社電通総研 技術統括本部 バリューチェーン本部 PLM第4ユニット
徹底的な「憑依力」でキャリアを拓く──エンプラセールスからデロイト、VCを経て起業。Matilda Books百野氏が実践する“自分自身の売り方”
- 株式会社Matilda Books 代表取締役