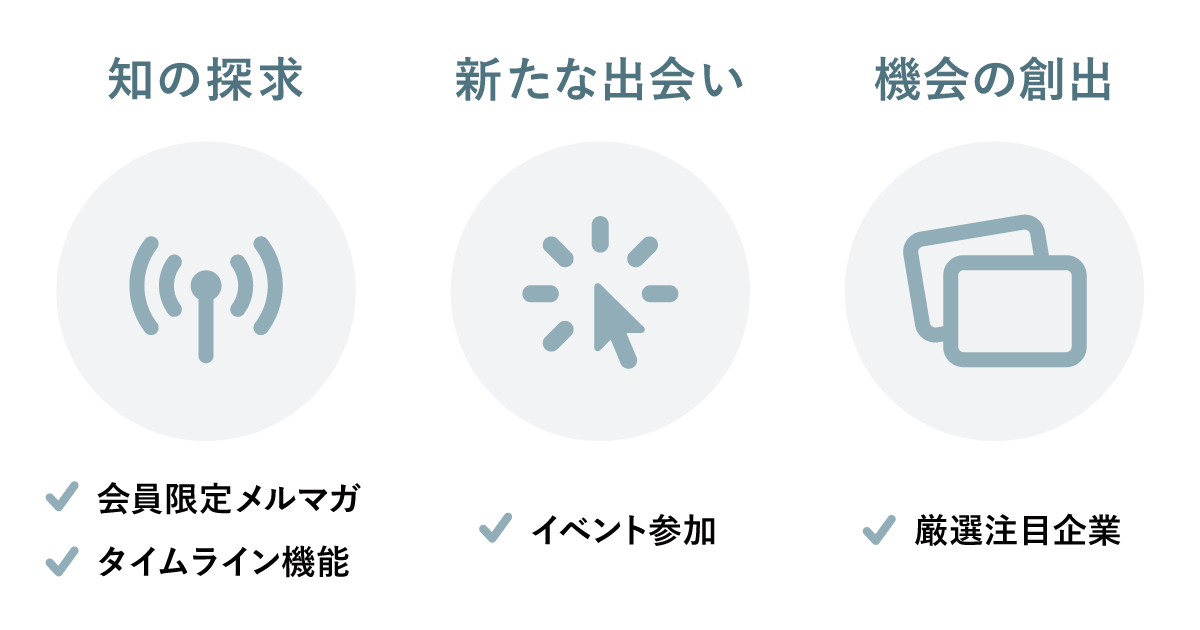「優秀な人を集めるだけでは、良いプロダクトはつくれない」──カオナビCTOが明かす、機能するボトムアップ組織のつくり方
Sponsoredボトムアップな組織をつくる──口で言うのは簡単だが、その実現は意外に難しい。メンバーの主体的なアクションを起点にすることは、組織としての一体感をなくし、スピード感を失うことと紙一重だ。
この難題を解く方法を探るときに参考になるのが、クラウド人材マネジメントシステムを提供するカオナビのエンジニアマネジメントだ。現場起点でのJavaScript用ライブラリの変更、スクラム開発の定着、さらには全社向けのスプリントレビュー……カオナビでは、ボトムアップによるプロダクト開発が実現している。
本記事では、カオナビのエンジニアを率いるCTOの松下雅和氏に話を伺った。松下氏は複数のSIer企業、サイバーエージェントを経て、スマートフォン向けアプリを提供するトランスリミットでCTOを務めた後、2020年2月にカオナビへとジョイン。同年9月にCTOに就任した。
エンジニアが開発上流から主体的に携われる環境、その背景にある徹底したプロダクトアウトの思想に迫る。
- TEXT BY RYOTARO WASHIO
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
- EDIT BY MASAKI KOIKE
「優秀な人さえ集めれば、良いものがつくれる」は誤解
松下スキルの高い人を集めさえすれば、自然と良いプロダクトができるわけではありません。一体感があるチームをつくることが必要不可欠なんです。
過去に、非常に高いスキルと推進力を持つエンジニアを集めたゲーム開発プロジェクトに、途中から参加したことがあります。個々のレベルは非常に高く、ほとんどがリーダー経験者で、CTOとして声がかかってもおかしくないレベルでした。
当然のように、それぞれが自らの役割を理解してすぐに開発をスタート。しかし、プロジェクトのゴールや進め方に関するコンセンサスを得ないまま、個別に開発が進んでしまったため、時間をかけて作り上げたシステム構成をたびたび見直す必要が出てきたり、PoCでいち早く検証すべき機能がいつまでも検証できなかったりと、さまざまな問題が発生しました。結果として、本来の開発期間を大幅に超えてリリースすることになり、競合サービスに対して大きく遅れをとってしまいました。
松下氏がカオナビでの組織づくりで意識しているのは、「一体感のあるチームづくり」。過去プロジェクトでの失敗経験を糧に、メンバーの目線を合わせ、一体感の醸成を最重視しているという。

株式会社カオナビ CTO 松下雅和氏
松下メンバー全員が「なぜこのチームでプロジェクトを進めるのか」「チーム内での自らの役割は何なのか」を理解している状態をつくることを心がけています。
例えば、現在進めているプロジェクトでは、企画段階からインフラ担当もアサインしました。我が社では通常、インフラ担当はプロジェクトの後半にアサインされていました。でも、企画段階からインフラ観点の意見も取り入れたほうが、参加メンバーが、企画からリリースに至るプロジェクトの全容をより高い解像度で理解できるようになると思ったんです。
メンバーの理解度を重んじ、主体的に参加してもらうことを大切にする背景には、代表取締役社長 CEOの柳橋仁機が重んじている「相互選択関係」という経営哲学がある。
会社とメンバー、どちらかが搾取されるような構造ではなく、常にフラットな関係を築き、互いに貢献しあう。メンバーは会社の成長のために個性を発揮し、会社はメンバーが個性を十分に発揮しながら成長できる環境を整える──こうして会社とメンバーが「相互選択関係」を築くことを、企業運営の理想としているのだ。
プロダクトへの共感が、ボトムアップ開発の礎
新機能開発のスタイルからも、ボトムアップ型の組織カルチャーであることが見てとれる。「ユーザーが何を求めているか」ではなく、「カオナビをどのように活用してほしいか」、すなわちメンバーの意志を起点に新機能が考案される。以前、柳橋氏に取材した際に語られていたように、創業時からプロダクトアウトの思想が貫かれているのだ。
ビジネスサイドのメンバーが開発チームへ機能開発を依頼する際も、「こんな機能がほしい」といった抽象度の高いオーダーが多いそうだ。プロダクトオーナーやデザイナー、エンジニアといった現場のメンバーたちは、なぜその機能が必要とされているのか、プロダクトとしてどのような形で提供すべきなのかを、自ら判断。そして、細部のUIや導線の設計、プロジェクトの進め方や開発スケジュールまで決め、機能の開発にあたる。ときにはチーム同士がお互いに調整しあい、メンバー構成を変更することもあり得るという。

結果として、「現場のメンバーたちが主体的にプロダクト開発を推進する必要性が生まれている」と松下氏。ボトムアップな開発を支えるのは、プロダクトへの共感だ。カオナビのエンジニア組織でも『カオナビ』を使用していることが大きく働く。
松下どんなプロダクトになれば組織運営に貢献できるのか。自分たちもユーザーだからこそ、その体感をもとに考案できる。『カオナビ』によってチームビルディングが円滑に進んでいることを実感しているから、プロダクトの価値をより高めて、多くのユーザーに届けたいと思えるんです。
全社向けスプリントレビューで、他部署からの意見も取り入れる
ボトムアップ型の組織カルチャーは「全社向けスプリントレビュー」からも感じられる。スクラムを導入しているカオナビでは、それぞれの開発チームがスプリントごとの成果物を確認する場としてスプリントレビューを開催している。
特徴的なのは、チーム内だけでなく全社向けのスプリントレビューも実施している点だ。それぞれの開発チームの状況を全体共有し、第三者から意見を募る機会となっており、頻度も週1回と積極的。営業やマーケティング、ときには人事部など、開発には参加していないメンバーからの意見も聞き入れる。例えば、営業メンバーからの「売り方を考えると、この機能だけでも先に完成させられないか」といった要望をもとに、開発の優先順位を入れ替えることもあるそうだ。

スプリントレビューが行われるのは、オフィス執務エリアのほぼ中央に位置するこのスペース。ただ、松下氏のジョイン後すぐに新型コロナウイルス感染拡大の影響で原則在宅勤務になり、オンライン開催にシフトしたという。松下氏は「対面でのスプリントレビューは、まだ数回しか参加できていません」とさみしげに話す。
松下毎週、開発チームから全社に向けて、機能開発の進捗を報告しているんです。スプリントレビューへの参加は任意ですが、開発に携わっているチームメンバーはもちろん、部署を問わず、普段は全社員の3分の1ほど、多いときには半数以上が顔を出します。
会議室ではなく、執務エリアで実施しているため、気軽にのぞけるようになっています。作業をしながら耳を澄ませ、気になることがあったら発言をしてくれる人もいますね。
チームや部署の垣根を越え、全社でプロダクト開発に向き合う姿勢は、カオナビの特徴だという。松下氏がこれまで所属した企業では、リリースした機能をビジネスサイドへ共有することはあっても、開発段階で他部門の意見を取り入れる環境はなかったと振り返る。
松下開発業務はエンジニア組織の中で閉じてしまうことが多いものです。だからこそ、カオナビに入社したとき、全社で進捗を共有し、部署を超えてプロダクトを良いものにしていこうという姿勢に驚かされました。
新たにジョインしてくれたエンジニアの中には、「他部署と交流し、議論しながら開発を進められることが嬉しい」と言ってくれる人もいます。全員でプロダクトを良くしていくことに向き合う環境は、エンジニアにとっても大きなやりがいにつながるんですよ。
なぜ、スクラム開発を定着させるのは難しいのか
スクラム開発の定着度合いにも、松下氏は驚いたと語る。アジャイル開発の代表的な手法であるスクラムは、スプリントと呼ばれる1〜4週間程度の期間を設定し、その期間内で開発からリリースまでを終わらせる。スプリントごとに方針を転換できるので、顧客や他部署の要望を取り入れ、優先順位を柔軟に入れ替えながら開発を進めることが可能になる。
しかし、「スクラム開発を組織に定着させるのは簡単ではない」と松下氏。なぜなら、経営層の理解を得られない場合が多いからだ。松下氏のこれまでの経験でも、トップが決定した開発の優先順位を現場判断で変えることは許されず、定められた手順通りに進めがちだったそうだ。

松下CEOの柳橋をはじめとする経営層が、スクラムの意義を理解している。経営層が現場の判断を信じて任せなければ、スクラム開発は実現できません。
「社長が言ったから」ではなく、現場のエンジニアたちが「プロダクトとしてどうあるべきか」を考えて開発を進める環境が、カオナビにはある。入社直後にそう感じましたね。
サービスで利用する技術も、現場の声を起点に変革してきた。その例として挙げるのが、JavaScript用ライブラリ『React』の導入だ。カオナビではもともと、JavaScript用ライブラリとして『jQuery』を使用していた。しかし、「フロントエンドを、よりデザインと親和性の高いコンポーネントベースで構築できるようにすべきではないか」と考えたメンバーが、『React』への切り替えを提案し、採用されたという。利用技術の変更は、かかるコストやリソースの割に、短期的な費用対効果が見えにくい。現場メンバーの提案を起点にJavaScript用ライブラリが切り替えられたことは、異例といえるだろう。
松下経営層が長期的な視点で考えているからこそ、この判断ができたのだと思います。利用技術のアップデートや移行は、短期的な会社の利益にはつながりません。むしろ、これまでの環境を変えることによって、一時的に開発スピードが遅れるといったデメリットが生じる可能性もあるため、後回しにしようとする経営者も少なくない。
でも、中長期的にプロダクトの質を高めていくためには、適切な技術へのアップデートは必須ですし、その必要性を最も痛感するのは現場のメンバーです。肩書や組織内の階層に関係なく、プロダクトの未来にとって正しい選択であれば、誰の意見でも採用する。その判断が下せるのは、カオナビの強みだと思いますね。
マイクロサービス化を推進し、日本最大の人材データプラットフォームを目指す
ボトムアップでプロダクトを磨き上げる開発組織を武器に、カオナビは今後、人材データの新たな活用方法を模索していく。
松下『カオナビ』の導入社数は約1,800(2020年3月時点)社。この膨大な人材データをどのように活用し、どんな価値をクライアント企業やその先のエンドユーザーに提供するのかを考えなければいけない。より大量で多様なデータを保有するプラットフォームになるべく、『カオナビ』の機能拡充、そして新たな事業にもチャレンジしていきたいです。
具体的なKPIとしては、2024年までに年間売上を100億円(2020年8月現在、四半期売上7.5億円)、今から約3倍強の規模まで拡大したいと意気込む。達成するには、これまでに蓄積した技術的な負債の解消にも取り組んでいくという。そのカギが「マイクロサービス」化だ。


松下現状の『カオナビ』の開発基盤は、単一で分割されていないモノリシックな構造です。システムのある部分を改修しようとすると、他の部分にも影響を与えてしまう。そのため、コードが古くなっているにもかかわらず、手がつけられていない箇所もあります。
この問題を解消するために、マイクロサービス化を推進していきます。マイクロサービスとは、複数の小さなサービスをAPI連携させる構造のこと。『カオナビ』を構成する機能を独立させ、それらをつなぎ合わせることで一つのサービスとして提供するイメージです。
マイクロサービス化が実現すれば、それぞれの機能が独立した構造になるため、改修や機能追加を容易かつスピーディーに進められるようになります。
カオナビが2019年3月に東証マザーズに上場してから1年以上経つが、より一層チャレンジングな経営スタイルをとるようになっている。ハイスピードな事業拡大のためには、大規模なサービスでもアジャイルに開発を進めていく必要がある。そのため、求めているのは、ボトムアップなプロダクト開発を加速すべく、主体性を持って開発に取り組めるエンジニアだ。

松下「上から言われたからやる」ではなく、課題解決のためのアクションを主体的に起こせる方がマッチすると思います。
また、技術トレンドに敏感な人も仲間になってほしいですね。僕たちも常に最先端の技術をキャッチアップしているつもりですが、「こんな技術があるから、導入してみましょう」と積極的に提案してくれる方をお待ちしています。
こちらの記事は2020年09月24日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
鷲尾 諒太郎
1990年生、富山県出身。早稲田大学文化構想学部卒。新卒で株式会社リクルートジョブズに入社し、新卒採用などを担当。株式会社Loco Partnersを経て、フリーランスとして独立。複数の企業の採用支援などを行いながら、ライター・編集者としても活動。興味範囲は音楽や映画などのカルチャーや思想・哲学など。趣味ははしご酒と銭湯巡り。
写真
藤田 慎一郎
編集
小池 真幸
編集者・ライター(モメンタム・ホース所属)。『CAIXA』副編集長、『FastGrow』編集パートナー、グロービス・キャピタル・パートナーズ編集パートナーなど。 関心領域:イノベーション論、メディア論、情報社会論、アカデミズム論、政治思想、社会思想などを行き来。
1986年生まれ、東京都武蔵野市出身。日本大学芸術学部文芸学科卒。 「ライフハッカー[日本版]」副編集長、「北欧、暮らしの道具店」を経て、2016年よりフリーランスに転向。 ライター/エディターとして、執筆、編集、企画、メディア運営、モデレーター、音声配信など活動中。
校正/校閲者。PC雑誌ライター、新聞記者を経てフリーランスの校正者に。これまでに、ビジネス書からアーティスト本まで硬軟織り交ぜた書籍、雑誌、Webメディアなどノンフィクションを中心に活動。文芸校閲に興味あり。名古屋在住。
おすすめの関連記事
戦略シミュレーションゲームを社会実装する──「ゲーミフィケーション」で人材データを活用するカオナビのプロダクト戦略
- 株式会社カオナビ CDO(Cheif Design Officer) / ブランドデザイン本部長
現場にいる者こそが、意思決定者──年次も経験も関係ない!UPSIDERで非連続成長を担うのは「一次情報を最も知る者たち」だ
- 株式会社UPSIDER 執行役員 / VP of Growth
急成長企業の5つの鉄則──隠れテック企業・出前館に見る、挑戦と革新の舞台裏
「支社 = チャンスがない」は誤解──全社表彰を連発する電通総研の中部・豊田支社。秘訣は“立地”と“組織構造”にあり
- 株式会社電通総研 製造ソリューション事業部 製造営業第5ユニット 豊田営業部
【独自解剖】いまスタートアップで最も“謎”な存在、キャディ──SaaS×データプラットフォーム構想によるグローバルテックカンパニーへの道筋
「稼ぐ理由が、君の天井を決める」──ソルブレイン櫻庭×STUDIO ZERO仁科対談。利益の先にある、経営者の使命
- 株式会社ソルブレイン 代表取締役社長
「実際、支社と本社って“違い”がありますよね?」──新卒が抱く配属の悩み。電通総研・関西支社の答えが意外すぎた
- 株式会社電通総研 技術統括本部 エンタープライズ第二本部 エンタープライズ開発ユニット ITコンサルティング2部
「支社配属=密度の濃さ?!支社だからこその強みがここには実在する」──就活生が気にするキャリアプラン。電通総研・広島支社に聞いてみた
- 株式会社電通総研 技術統括本部 バリューチェーン本部 PLM第4ユニット