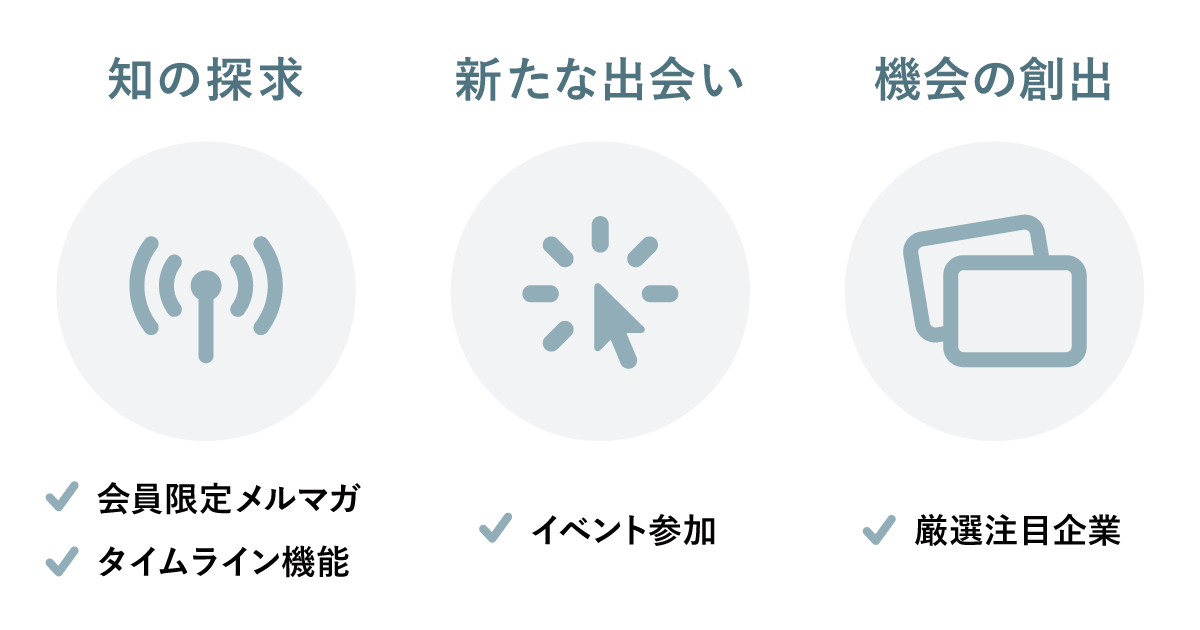「稼ぐ理由が、君の天井を決める」──ソルブレイン櫻庭×STUDIO ZERO仁科対談。利益の先にある、経営者の使命
Sponsored利益を追求すべきか、価値を重視すべきか──。
このジレンマに、多くの企業が向き合い続けている。利益なくして企業の存続はありえないが、同時に社会的価値を無視した経営は持続可能な成長は望めない。
この課題に対し、異なる視点から明確な答えを示す経営者がいる。仙台を拠点に、グロースマーケティング事業で急成長を続けるソルブレイン代表の櫻庭 誠司氏。そして、大企業や行政機関の新規事業開発から組織変革まで、「産業と社会の変革を加速させる」をミッションに掲げるSTUDIO ZERO(プレイド内の社内起業家集団)代表 仁科 奏氏だ。
創業当時まだ浸透していなかったSEOを主としたWeb事業のビジネスモデルに金融機関からの理解が得られず、結果的にノンバンク5社からの資金調達で創業期を乗り切った櫻庭氏。前職CFO時代にコロナ禍でキャッシュフローの危機に直面し、今は利益創出と社会価値創出のサイクルを磨き込む仁科氏。異なる事業領域で苦難を乗り越えてきた二人が、厳しい局面で向き合った利益の本質とは何か。そして、その先に見出した価値とは──。
その経験には、次世代のリーダーたちが見失いがちな重要な示唆が込められていた。
- TEXT BY YUKO YAMADA
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
- EDIT BY TAKUYA OHAMA
ノンバンク5社の返済に追われる日々。
「利他の精神なんてなかった」
創業期の経営者にとって、利益を追求することは事業の生存をかけた戦いである。2008年に仙台でSEO対策やWeb制作の事業を立ち上げたソルブレイン代表の櫻庭氏は、創業期の厳しい現実を振り返る。

ソルブレイン 代表取締役 櫻庭 誠司氏
櫻庭当時、仙台にはベンチャーキャピタルがなくて、銀行や日本政策金融公庫からお金を借りるしか選択肢がありませんでした。ところが、銀行や金融公庫の人に相談したら「SEOって何ですか?」「融資?いやいや、難しいですね」と全然相手にしてもらえなくて。特に地方では、Web関連のビジネスモデルへの理解を得ることが難しかったんです。
結果的に、ノンバンク5社から総額1,250万円の資金調達を余儀なくされた。各社の借入上限は250万円。返済日は毎月4週目の金曜日だったり、25日だったりとバラバラで、エクセルで日繰り表を作って「この日までにいくら入金しないと会社が存続できない」という綱渡りの日々が続いた。
櫻庭まずは自分の生活を安定させることで精一杯で、当時は「利他の精神」なんて微塵もありませんでしたね(笑)。
この極限の経験を経て、利益追求の先にある価値を考えるようになる。事業が軌道に乗り、2期目、3期目と黒字が出て少しずつ余裕が生まれてきたとき、「一人で儲かっても意味がないな」「どんなに稼いでも無人島に行けば何の役にも立たないぞ」という気づきを得たのだ。
櫻庭東北では、地域の主要企業の多くが東京など大都市に本社を置く企業の支社なんです。つまり、地域の経済活動が他地域の企業に依存している状況で、その結果、優秀な人材も高い報酬や良い環境を求めて大都市に流出してしまう。
そんな環境の中で気づいたんです。一企業(自社)の成功だけでなく、地元発の企業をもっと増やし、地域全体の経済力を高めていく必要があるのではないか、と。当時の私はまだ30代。この閉塞感を打破するのは、時間もエネルギーもある自分の役目だと考え、「東北経済を変革し、日本を変える」と決意したんです。
利益は事業存続の絶対条件である。しかし、それは目的ではなく手段でしかない。創業期、5社のノンバンクから借入れ、返済期限との戦いを続けた櫻庭氏はその極限の経験から、シンプルな真理を学んだ。「稼ぐ」ことは大切だが、「何のために稼ぐのか」という問いにこそ、本質があった。
MBAで学んだだけでは掴めない、「Cash is King」のリアル
数字上の成果と実態は、時として大きく乖離する。STUDIO ZERO代表の仁科氏は、前職、法人向け採用マーケティング支援サービスを提供するPR Table(現:talentbook)のCFO時代に、その現実に直面することになる。
コロナ禍の影響で企業の採用広報予算が一気に縮小し、半年でマーケットが激変。仁科氏は、P/Lでは粗利が見えていても、実際のキャッシュフローが回らないリスクを感じる事態に直面したのである。
仁科これまでセールスフォース・ジャパンやプレイドにおいて、私はセールスとして常に「売上」だけを見ていて、契約条件や支払い条件はリーガルチームに任せきりでした。MBAで「Cash is King」と散々学んでいたのに、その本質を理解できていなかったんです。

STUDIO ZERO 代表 仁科 奏氏
マーケットが好調なときは、契約条件の甘さに気づきにくい。しかし、不況期には支払いの延期や契約の解除、時には意図的な契約不履行といった事態も起こりうる。この経験を経て、仁科氏は契約書の細部まで確認し、曖昧な条件や安易な妥協を一切排除するようになった。
仁科 契約を守り、支払い条件を明確にし、安易な妥協をしない。こうした基本的な取り組みが、長期的な信頼関係を築き、持続的な価値を生み出すのだと学びました。
近年、潤沢な資金調達を背景に急成長を遂げるスタートアップが増えている。しかし、「赤字は次の資金調達で穴埋めできる」という発想に依存しすぎると、短期的な売上拡大に集中し、顧客への本質的な価値提供や事業モデルの収益化といった根幹部分の整備が後回しになりがちだ。特に資金調達額が企業評価の指標として注目される環境では、この傾向が顕著になる。
仁科エクイティファイナンスの魔力や落とし穴は半端ないですからね。特に上場後に顕著になります。上場時には華々しく注目を集めても、その後の業績が伸び悩み、市場での存在感が急速に薄れていく企業も少なくありません。
「どうやって売上を伸ばすか」は理解していても、「どうやって非連続的な利益を生み出すか」という仕組みが確立できていない。これは、スタートアップだけに絞ってみても少なくない印象があります。資金調達に依存しすぎた結果なのかもしれませんね。
事業成功の本質は、売上を伸ばせる構造を理解するだけでなく、いかに利益を生み出す仕組みを確立できるかにある。しかし、利益の追求だけでは企業の成長は持続しない。利益を生む仕組みを基盤としつつ、それをどのように活用し、社会にどのような価値を還元するのか。この問いに向き合うことが、次の成長のステージへ進むために欠かせない視点だ。
では、企業は利益の先に何を目指すべきなのか。その存在意義とは何か。両氏はそれぞれの視点から、独自の答えを導き出していた──。
「三方良し」と「正しい納税」。
時代を超えて受け継がれる、商いの矜持
仁科私にとって価値の本質は「インパクト」を出すことです。ZEROのメンバーにもよく話していますが、企業の存在証明は社会にどれだけインパクトを与えたかでしか測れないと思っています。
CSR活動として大企業と連携するといった取り組みも、社会に意味のある成果をもたらしている。ただし、仁科氏が目指すのは、一過性の社会貢献に留まらない、より本質的な企業のあり方だ。
具体的には、まず営利企業として利益を生み出すことが大前提となる。これは経営者としての絶対条件であり、これができなければ「経営者失格」と語気を強める。しかし、それは目的ではなく手段に過ぎない。この考えの根柢には、日本の伝統的な商いの精神がある。
仁科江戸時代の近江商人たちによる、「三方良し」という哲学がありますよね。
「売り手良し、買い手良し、世間良し」。
つまり、商人は社会の一部として存在し、得た利益を再投資することで、より大きな価値を生み出しながら社会を前に押し進めていく。これこそが企業の存在意義だと私は考えています。

仁科その上で、私がインパクトと呼ぶのは、「利益を出す力」と「社会を前に押し進める力」の掛け算。これこそが企業価値であり、企業が果たすべき使命。この両要素を共に大きくしていくことが、企業の存在証明になると考えています。
一方、櫻庭氏は「利益を出すことは企業としての基本的な役割」とした上で、より具体的な視点を示す。
櫻庭学生から「どんな社会貢献をされていますか?」と聞かれることがありますが、私はいつも「正しい雇用」と「納税」だと答えています。これこそが社会における営利企業の基本的な役割であり、持続可能な地域社会の実現に直結するからです。
特に地方では「東京より人件費が安い」という理由で、ディスカウントされた形で雇用されるケースが少なくありません。しかし、それは働く人たちの価値を正当に評価しているとは言えない。たとえ地方都市であっても、マーケット基準で報酬を支払うことで、社員のモチベーションが上がり、結果的に地域社会全体の経済活性化にもつながると考えています。

事実、ソルブレインは仙台に本社を置きながらも、新卒採用を含めすべての従業員にマーケット水準の報酬体系を用意している。
櫻庭そして、企業として適切に納税を行うことは、地域社会の基盤を支える重要な役割です。特に地方では、中小企業が納税の多くを担っており、その動向が地域経済全体に直接的な影響を及ぼします。
もちろん、ベンチャーが成長を目指して一時的に赤字を出すことはあるでしょう。しかし、単なる節税目的で意図的な赤字経営を続けることは、結果的に地域経済の活力を奪うことになる。企業には、利益を生み出し、正しく納税を行うことで地域の健全な成長を支える責任があると考えています。
両氏が語る価値創造の本質。それは、利益という基盤の上に、確かな社会的インパクトを築き上げることだ。しかし、この理念を実現するには、それを担う人材の育成が不可欠となりそうだが──。
「6年かかった成果を3ヶ月で」。
ソルブレインが仕掛けた、若手育成の大転換
理念を体現する組織づくりにおいて、特に注目すべきはソルブレインの若手育成の仕組みだ。これまでFastGrowの取材でも取り上げてきた通り、同社では新卒社員が大きな裁量を持ち、事業を牽引している。この「裁量を前提とした若手育成」の仕組みは、櫻庭氏の試行錯誤の末に生まれた。
櫻庭現在も「顧客事業のバリューチェーン全体を最適化する」という基本方針は変わりません。しかし、当初のグロースマーケティングは理想が先行し、概念的な部分に重きが置かれていました。そのため、実務に落とし込むのが非常に難しく、社員一人ひとりが膨大かつ多岐にわたる業務を抱え込む形となり、若手が成果(ここではP/L貢献の意)を出すまでに最短でも6年を要する状況でした。
優秀な社員であってもこれだけの時間がかかるなら、「これは誰にも実現できないな」と痛感し、抜本的な見直しに着手した。そこで同社が取り組んだのが、業務の徹底的な「細分化」だ。

櫻庭プロジェクトごとに業務を分けて、さらにその中の役割を細かく切り分けていきました。例えばマーケティング部門なら、インサイドセールスチームをつくり、その中でも新規顧客への一次接触に特化した役割を設けるといった具合です。
そして、プロジェクトの細分化に加えて成果の可視化にも注力しました。ただし、これは単なる分業化ではありません。まずは一つの領域で確実に成功体験を積んでもらい、そこから段階的に裁量を増やしていく。さらに複数領域に跨った役割を任せるなど、常に新しい挑戦の機会を用意しています。つまり、やるべきことは明確でありながら、難易度は常に変化し続ける。そんな成長の仕組みを作り上げているんです。
この取り組みにより、若手社員の成長スピードは劇的に向上。早い人では入社3ヶ月で収益へのインパクトが可視化されるようになった。
一方のSTUDIO ZEROは、異なるアプローチで若手の成長を促す。2024年度から開始した新卒採用では、明確な期限を区切った目標設定を重視している。
仁科新卒採用で私たちが重視しているのは、「30歳までに新規事業を立ち上げたり、起業するんだ!」「30歳までに親の会社を継いで経営をするんだ!」などといった明確な野心を持っているかどうかです。これは単なる目標設定ではありません。実際にそこに向かって、具体的な準備をし始めているのかどうかを見ています。
実際、新卒入社したメンバーたちは、「30歳まで残り何年しかない」という意識を持って日々の業務に取り組んでいます。この時間的な危機感は、往々にして成長の原動力になります。例えば、通常なら3年かけて学ぶような業務知識を1年で習得しようとする。そういった高い目標設定ができる人材が、結果的に非連続的な成長を遂げていくんだと思っています。
しかし、明確な期限を区切った目標設定だけでは、個人としての持続的な成長は望めない。そのためには、短期的な成果を求めるだけではなく、自分の行動や選択を深く振り返り、「何のために努力をしているのか?」を問い直すプロセスが必要となってくる。
「何のために稼ぐのか」。
自己理解から始める成功設計
「お金も大事だけど、その前にあなたは何したいんですか?」。
これは若手と向き合うとき、櫻庭氏がよく投げかける問いだ。その背景には自己理解が不十分なまま「お金」や「社会的な成功」だけを追い求めることへの強い危機感がある。
櫻庭冒頭から利益やキャッシュの重要性を語っていましたが、これはとても難しい問題なんです。よほど本人の人間性がしっかりしていて、周りの大人がしっかり見ていないと、若者は「お金」という目先の数字や、そこから得られる快楽に引っ張られてしまうんですよね。
これは単なる懸念ではない。櫻庭氏は実際にそういった若者たちを見てきた。
櫻庭目先の楽しさに流されると、長期的な成長や社会的な価値提供といったことを忘れてしまいがちになる。だからこそ、「自分は社会にどんなインパクトを与えたいのか」「どんな人生を描いていきたいのか」を考え、その意志を醸成できる環境をつくることが大事だと考えています。

仁科とても共感しますね。日本は長期間にわたってデフレが続いて物価が安く、国民皆保険などの社会保障制度も整っています。新卒の初任給だけでも最低限の生活には困らない環境が整っている。だからこそ、ただお金を稼ぐために働くのではなく、自分は「何を成し遂げたいのか」「何が譲れないのか」を見つけることが大切です。それによって金銭的な豊かさだけでなく、人生体験としてより豊かな人生を送ることができるはずですよね。
では、具体的にどうすればよいのか。仁科氏は若手や新卒学生との対話で、「喜怒哀楽の言語化」を勧めている。何が自分にとって喜びや楽しみとなるのか、逆に悲しみや怒りを引き起こすのかを明確にすること。この自己理解を深めることで、自分が何を目指し、どう生きたいのかが見えてくる。
仁科人生は「喜びと楽しみ(プラス)」と「悲しみと怒り(マイナス)」で構成されていると捉えると、死ぬときにプラスがマイナスをできるだけ大きく上回っていれば「良い人生だった」と言えるのではないかと思うんです。
自分の喜怒哀楽を把握したらあとは喜びと楽しみを増やす方法を突き詰めて考えて、悲しみや怒りを抑える方法を探せばいいだけですから。しかし、私の感覚では“自分のトリセツ(取り扱い説明書)”を分かっていない人が実に多い。ここはきちんと内省して言語化した上で、日々の人生の意思決定を実施した方が良いのではないかと思っています。
自分のトリセツがわかっていれば、起業する、家業を継ぐ、地方で働く、主婦になるなど、どんな生き方でも自分にとって正解になり得る。一方で、自己理解が浅いまま「お金がほしいから」などの表面的な理由で進路を選んでしまうと後から行き詰り、他人や環境を責めることになりやすい。「そうなると辛い人生ですよね…」と仁科氏は続ける。
さらに、仁科氏はマズローの欲求階層と振り子のような考え方を使って自己理解の深め方を説明する。

仁科人が成長して自己実現に向かう過程では、段階的に欲求を満たしながら次の段階に進んでいきます。成長の初期段階では自分の欲求を満たすことが優先される。「良い暮らしをしたい」「いい体験をしたい」という気持ちは自然なことです。自分には着るものがないのに、他の人の着るものをつくるというのは、私は違うと思っています。まずは自分の基礎的な欲求を満たすことが正しいのではないでしょうか。
そしてこれは振り子のような考え方でもあるのですが、最初は「自分のために」行動したことが偶然にも他者を喜ばせる経験につながっていく。それはまだ振り子の動きは小さいものですが、「ありがとう」と感謝される経験から少しずつ「他者への貢献」に目が向いていくんです。そして、この振り子の動きが大きくなると経営者や政治家のように大きな影響力を持つようになる。
だから、まずは自分と向き合うことが何より大事だと若者には伝えたいですね。
良い行いが感謝を生み、それが自身の幸せにつながっていく。その繰り返しの中で、自分自身の理解もより深まっていく。それは両氏が自身の人生経験から導き出した確かな教訓だった。
まずは自分を満たし、その行動がふとした瞬間に相手のためになる。そして、相手の感謝を受け取ることで、自分自身もさらに大きな喜びを得る。このサイクルが広がっていく中で、自己理解と利他の精神が同時に育まれていく──。
では、両氏自身はどのようにして自己理解を深め、現在の価値観を形成していったのか。その過程には、それぞれの挫折体験が大きく影響していた。
「偏差値では測れない勝負がある」。
挫折が教えた、新たな物差しの作り方
仁科氏が下すさまざまな意思決定の背景には、子ども時代から変わっていない「ジャイアントキリング」と「極度の飽き性」という2つの志向がある。まずは「ジャイアントキリング」。小さな存在が強大な存在に勝利すること。ここに対する想いは、1つ年上の優秀な兄との関係性から生まれた。
仁科兄は勉強もスポーツもできる。常に私よりも先を行く存在でした。家の中でも常に比べられ、偏差値至上主義という物差しの中で、私は劣等感を抱えていたんです。
しかし、兄が大学進学した翌年、仁科氏も大学進学で上京。アルバイトでは自分の働き方や考え次第で収入が増え、周囲からの評価も得られた。これまでの「偏差値」という単一の物差しから解放され、自分の力で成果を生み出せる場面が増えていった。
仁科久しぶりに会った兄から、「なんか、俺よりも勝ってるね」と言われたとき、偏差値だけではない勝負があると気づいたんです。それは単純に一つの側面で兄に追いついたという話ではなく、物差しの見方を変えるだけで新しい価値を生み出せるという大きな発見でした。私が「ジャイアントキリング」というテーマに目覚めるきっかけになった原体験です。

そして、もう1つの「極度の飽き性」という特性は、新たな価値を創出するエネルギー源となってきた。
仁科20歳の頃、自分のためだけに生きるのに正直、飽きてしまったんです。当時は物価が安く、数百円の牛丼で満足できる生活でした。一方で、「自分は何のために生きるんだろう」という問いが浮かんできまして。
その答えを探る中で、自分を中心に、家族や友人、仕事仲間とのつながりを広げ、それぞれの関係性を質の高いポジティブなものに磨き上げていく。例えるなら円錐状のイメージが浮かんだんです。そこから、「50歳で、新しいインフラをつくる」という目標を掲げました。その目標を達成するには、少なくとも30歳までに小さい企業の経営者になる必要があるのかなと思って、ざっくりとした年齢別の目標設定をしました。そう考えた私は、そこから逆算してキャリアを設計するようになりました。
以後のキャリアは、この目標に向けた計画的な布石となる。まずNTTドコモでインフラ構築の基礎を学び、セールスフォース・ジャパンでいちプレイヤーとしての力を磨きながらSaaSビジネスを伸ばすための基礎を学ぶ。そして、プレイドではSaaSビジネスを伸ばしていくための構造を試行錯誤しながら構築していった。その後はMBAで経営知識を習得し、PR TableではCFOとして財務戦略を担う。
そしてコロナ禍、プレイドの創業者にファイナンスの相談に乗ってもらった時に感じた強い恩を受け、同社の第二創業期に参画を決意。「恩を返さないのは人として不義理だ」という信念に基づく選択だった。インフラ、営業、経営、財務。一見、異なる分野を横断するキャリアだが、これらの経験はすべて新たな価値創造のための必要な要素となっていったのだ。
一方の櫻庭氏は、自身を形容する言葉として「惰性」と「反抗」を挙げる。「もう何もしたくない、できる限りラクして効率よく生きていきたいと思うタイプでした」と笑う。
外資系企業に勤める父と進学校出身の母を持つ家庭で育った櫻庭氏は、大学まで進学こそすれど、勉強への反発から、日銭を稼いでは遊び回る生活を送っていた。そんな最中、転機は19歳の時に訪れる。「このままでは人生が積むな…」という危機感に襲われていたとき、友人に誘われて始めたのがバンド活動だった。

櫻庭音楽には、偏差値とか点数はつけられませんよね?みんながみんな、互いの音楽をリスペクトし合うんですよ。決して、ディスるといったことはしない。私にとってはこの経験がいい意味でとてもショックでした。
音楽の世界では、「みんなで認め合いながら、努力して頑張ろうぜ」だったんですよ。その世界が自分にはすごくかっこよく見えて、自分もこういう大人になりたいと思い、音楽の世界で頑張ってみようと走り出したんです。
その後、櫻庭氏のバンドは日本を代表する大物ロックバンドと同じ事務所との契約をこぎつける。しかし、プロの世界の現実は厳しかった。
櫻庭バンドとして下積み時代をほぼ経ずに一気にプロの舞台に進んでしまったため、プロのレコーディングだったり、求められるライブの水準が辛すぎましてね…(笑)。
「もう、音楽やりたくないな」と正直思っていたんですよ。ただ、互いをリスペクトし合いながら切磋琢磨していくことにはある種の憧れがあり、何らかの形では体現したいなと。その結果、音楽にこだわる必要はないなと思い、今に至ります。
そこから、自分が持っているステータスの中で何ができるかなとか考えたときに、私は営業が得意だったんでそれをやりたいなと。ただ、入りたい会社が仙台になくて、だったら自分でつくってしまおうと考え、起業しました。
両氏が挫折や困難を乗り越えて培った価値観と使命感。それは、単なる経験談にとどまらず、次世代のリーダーたちに挑戦の場を提供する原動力となっている。その原点には、「なんのために働き、どのように価値を創出するのか」という問いへの深いこだわりがあった。
こうした問いに対する答えは、両氏それぞれの事業への取り組みや、描く未来のビジョンに表れている。単なる利益追求ではなく、社会への長期的な価値提供を目指すその姿勢は、彼らの事業を通じて具体化されている。
「なんかやってたね」で人生を終わらせたくない。
君は何を成す?
これまでの対談を通じて浮かび上がってきたのは、利益を追求しながらも、社会に長期的な価値を提供し続ける事業のあり方だ。その実現に向けて、両氏はそれぞれの視点から具体的なビジョンを描いている。
仁科氏が率いるSTUDIO ZEROは、プレイドの事業開発組織として、大企業や自治体との共同事業開発から新規事業の立ち上げまでを手がける。その活動を通じて、仁科氏は次のようなビジョンを描く。
仁科「『善く生きる』人を増やしたい」。それが私のミッション(*)です。ここでいう「善く」とは、単なる経済的な成功を意味するものではありません。自己効力感、つまり自分には成し遂げる力があるという感覚を持ち、利他の精神で社会に貢献できる人を増やしていきたいんです。
ZEROの活動は、あくまでもそのための手段。企業、自治体、アカデミアとの協力を通じて成功事例を生み出し、それを見た人たちが「自分にもこんなことができるかもしれない」と気づくきっかけを提供したい。
行動を起こせる人が増えれば、社会全体が変わる可能性が広がるんです。そして、挑戦する人たちが増えることで顧客やパートナー企業の成果も向上し、結果的にZEROのリピート率も上がっていく。一石三鳥で持続的な成長を実現するサイクルを構築したいですね。
*……仁科氏のライフミッションについて深く語られたFastGrowでの以前のインタビューがこちら
一方の櫻庭氏は、地方からの社会変革を掲げる。
櫻庭地方では、若者が東京に出て行かなくても挑戦を続けられる環境を整える必要があります。地元で起業し、成果を上げることで、次世代の挑戦者たちがそれを目指せるような道筋をつくりたいと思っています。
地方には独自の魅力や可能性がありますが、一方で、商圏の規模がどうしても限られてしまうという現実がある。例えば、仙台で企業買収の話をすると、未だに20年前のピーチ・ジョンが記録した売却額(約150億円)が上限のような状況なんです。これって「地方にいると、事業規模を拡大するのにはどうしても限界があるよね」と思ってしまう人が多い理由の一つなんですよね。
その結果、地元で頑張りたいと思っていた人たちも、最終的には「やっぱり東京に行こう」となる。これが現実なんです。だからこそ、地方にいながらでも「こんなことができるのか!」と挑戦できる環境をつくることが、ソルブレインの役割だと思っています。それは地元の若者だけじゃなくて、首都圏にいる人たちにも「地方でチャレンジできる」選択肢を見せることでもあるんです。
ZEROが全国規模で挑戦者を増やすビジョンを描くように、ソルブレインでは、地方で挑戦を続けられる仕組みをつくることで、未来のリーダーを育てる。その両方が互いに補完し合う形で、多様な挑戦が生まれる環境が実現する。
こうした挑戦を成し遂げるには、やはり「人」が鍵となる。組織が掲げるビジョンや使命は、結局のところ、それを実現する人材次第だ。両氏の考える事業や社会への貢献を具体化し、次世代へとつなげていくために、どのような人材が求められるのかは極めて重要なポイントとなる。
対談を通じて互いの企業文化への理解を深めた両氏に、それぞれの視点から相手の会社に向いている人材像を聞いた。

仁科ソルブレインは、新卒や若手が会社の中核として育ち、カルチャーを創り上げていこうとしている環境が印象的です。
ですので、「でき上がった仕組みや風土の中で活躍するのではなく、若い自分たちの力で事業を伸ばし、会社の組織風土すら主体的に創っていきたい」と思う人にはオススメですね。一方で、"学びにくる"人は合わないでしょう。年齢経験を問わず、事業に貢献して利益を出すんだという気概はマストですね。
櫻庭おっしゃる通りですね(笑)。では、私からも仁科さん率いる「STUDIO ZERO」について一言。仁科さんのように、営利組織の根幹である「利益創出」を、「社会的価値」と両立しながら真摯に追求している経営者は稀少だと感じました。なので、ビジネスをやる上で最も重要な「営利」を出すことにこだわりたい人は迷わずいくべきではないでしょうか。
というのも、都内には多くのベンチャーがありますが、先ほども挙げたように資金調達によって営利の追求を後回しにしてしまっている企業が多いと思うんです。そうした中で「社会的価値」ばかり追っていると、実はビジネスパーソンとして重要な、「営利」を生む力は得られていないといった事態に陥るリスクがある。それって、最終的にはその場を成長の機会として選んだ人にとっては、望まぬ結果を生むことに繋がりますからね。
ソルブレインもSTUDIO ZEROと同様に、1人でも多く、利益と社会的価値の両方を創出できる人材を増やしていきたいと思います。

仁科まさに!私の個人ミッションへの共感もいただけたみたいで嬉しいです!お互い頑張りましょう!
「仮に100歳まで生きたとして、死ぬときに『まあ、人生なんかやってたよね』と終わるのでは悲しい。“なにか”で終わらせずに、“なにを”成し遂げたのかを証明したい」という仁科氏の言葉に、櫻庭氏も深く頷く。「そう、挑戦するからには足跡を残したいですよね」と。
利益と価値の両立、それは決して不可能な課題ではない。しかし、それを本気で追い求められる環境は、現在の日本のベンチャーやスタートアップの中ではまだ多くはない。
そんな中、ソルブレインとSTUDIO ZEROのように、利益を出しながら同時に社会的な価値を創出することに真摯に向き合う場は貴重だ。もし新卒〜20代からこうした環境で挑戦を積むことができれば、その後のキャリアにおいて圧倒的な強みとなるだろう。
事業を創る力、価値を生む力、そしてその両方を両立する力──。これらを兼ね備えたビジネスパーソンは、どの時代でも求められる存在になる。
利益と価値。その両方を追い続ける挑戦こそ、次世代のリーダーたちが第一歩として踏み出すべき道だ。この挑戦が、未来を切り拓く確かな基盤となるだろう。
こちらの記事は2024年12月18日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
山田 優子
写真
藤田 慎一郎
編集
大浜 拓也
株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。
おすすめの関連記事
日本のビジネスパーソンも、自身の価値を「デューデリ」しよう──市場価値を最大化させる“投資家的”キャリア思考法を、日米の比較に学ぶ【対談:STUDIO ZERO仁科&渡辺千賀】
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
大企業の新規事業が、日本を変える──「失われた30年」を乗り越えていく提案を、新規事業家・守屋実とSTUDIO ZERO・仁科奏が語り合う
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
「環境選び」で妥協しない──STUDIO ZERO上田氏・新井氏らから学ぶ、大きな変革を最短距離で生み出すキャリアの歩み方
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
【ソルブレイン櫻庭×UPSIDER宮城】僕らが20代なら、どうやって入社企業を見極めるのか?
- 株式会社ソルブレイン 代表取締役社長
事業も組織も、「善く生きる」人を増やすために──社会へのリーダー輩出に邁進するSTUDIO ZERO仁科の経営思想
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
「そのアドバイス。老害かもしれないですね」──50人の壁突破に向けた若手経営人材への投資術を、ソルブレイン代表・櫻庭氏に訊く
- 株式会社ソルブレイン 代表取締役社長
“トレードオン”は、意外と難しくない──一人ひとりが新たなチャレンジを続ける『STUDIO ZERO』3名のキャリア実例に、「WANT TO」の重要さを学ぶ
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
非線形の成長を続ける合言葉は「面白いことをやろう」──多様なケイパビリティを発揮し、大手企業とコラボレーションを生み出すSTUDIO ZEROの“楽しさ”に迫る
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO事業本部 CX Director
「業務提携」という名の罠にハマるな──三井物産 × ソルブレインに学ぶ、大企業とベンチャー / スタートアップによる共創の成否を分つ点
- 三井物産株式会社 執行役員 ICT事業本部長
大手企業も、「ワクワク」があれば変えられる━ベンチャーから来た30歳の若手が、大手企業を“内側”から変革し、わずか一年で受注数を数倍に。プレイドの新事業『STUDIO ZERO』の全容に切り込む
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
スタートアップが「極大インパクトの主体」となる最短経路の進み方とは?──プレイド仁科氏が描く社会変革の“フェーズ2”『STUDIO ZERO』の全容に迫る
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
「セオリー通りのSaaS」では、社会変革など生み出せない──プレイド倉橋×仁科が描く、未来創造のためのスタートアップ進化論
- 株式会社プレイド 代表取締役CEO
「最先端技術を扱う会社」を「テックカンパニー」とは呼ばない──Gakken LEAP CTO山内&ソルブレイン櫻庭が提唱する「成長し続けるテックカンパニー」の定義
- 株式会社ソルブレイン 代表取締役社長
「顧客満足を追求するなら、KPI達成で喜ぶな」──バリューチェーンの最適化で顧客の売上108倍UP?ソルブレイン櫻庭氏が提唱するグロースマーケティングとは
- 株式会社ソルブレイン 代表取締役社長
メンバーに“作業的な仕事”をさせない方法──ソルブレイン櫻庭誠司の「やめ3」
- 株式会社ソルブレイン 代表取締役社長
SaaSセールスの精鋭たち、ノウハウを一挙公開。急成長SaaSスタートアップ6社が集結
- atama plus株式会社 共同創業者・取締役