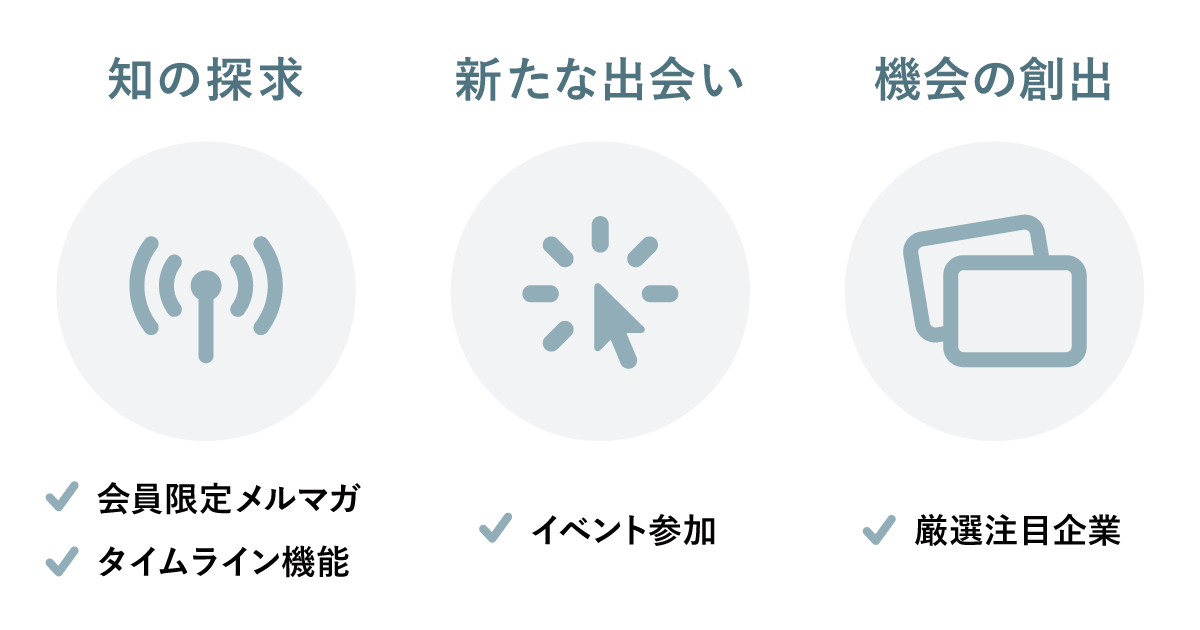事業も組織も、「善く生きる」人を増やすために──社会へのリーダー輩出に邁進するSTUDIO ZERO仁科の経営思想
Sponsored少子高齢化、経済停滞、地政学リスクの高まり。今、日本社会は数多くの課題に直面している。この閉塞感を打ち破り、新たな未来を切り拓くには、社会全体を俯瞰しながら変革を推し進める「次世代のリーダー」の存在が不可欠だ。
そんな中、独自の視点から“リーダー輩出”にフォーカスするプレイドの社内起業組織がある。『STUDIO ZERO』だ。代表の仁科 奏氏は、「善く生きる人を増やす」というセルフミッションを掲げながらも、その実現には「リーダーシップの質」こそが鍵を握ると考えてきた。そして、その危機感から、新たなリーダー像を体現する組織として『STUDIO ZERO』を立ち上げたのだ。
「善く生きる」とは何か?どうすれば変革をなす仲間を増やせるか?そして、自己実現を促す環境とは?こうした根源的な問いに向き合いながら、仁科氏は事業と組織の拡大に挑んでいる。 今回、FastGrow編集長の西川ジョニー雄介(以下、ジョニー)氏が、その哲学の核心に多面的に迫った。
成長フェーズごとに立ちはだかる障壁への具体的な処方箋から、リーダー像を巡る深い洞察まで。先回りして手を打ち続けられるのは、「事業を伸ばす」よりも上段に「社内外のメンバーの自己実現を本気で後押ししよう」という強い信念があるからだ。その思想と実践は、次世代のリーダーを志すすべてのビジネスパーソンに、深い学びと新たな視座を与えてくれるはずだ。
- TEXT BY MAAYA OCHIAI
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
足りないのは、“リーダー”ではなく、“リーダーシップ”
仁科世の中を見渡して、ふと思うんです。本当に優れたリーダーシップがあれば、気候変動、格差の拡大、地政学リスクのような深刻な社会課題に対しても、もっとスピーディに解決の道筋を描けたんじゃないかと。
でも現実には、「リーダーシップ不在」の状態が続いている。もちろん各国・各組織のリーダーたちも皆、懸命に努力を重ねています。でもどこかで限界を感じずにはいられない。バラバラに頑張っているだけでは、社会全体の変革には繋がらないのではないかと......。

プレイドの社内起業組織『STUDIO ZERO』代表の仁科氏は、世界中で頻発する社会課題を見つめる中で、リーダーシップのあり方そのものを問い直す必要性を感じているという。戦争やテロ、パンデミック、経済の停滞。ニュースで目にする社会課題は、どれも複雑に絡み合い、簡単には解けない。直面する課題の規模が大きくなればなるほど、国家や組織といった旧来の枠組みに囚われることなく、広く緩やかに人々を導き、変革を実現させていくリーダーシップが求められる。
ジョニー世界のリーダーたちも、決して無為無策でいるわけではありませんよね。むしろ、グローバルな課題解決に向けて、あらゆる英知を結集させようと努力しているはず。それなのに、なぜ限界を感じさせるような現状に陥ってしまっているのでしょうか。
仁科根本的な問題は、個々のリーダーの力量不足というよりも、社会の仕組みにあるのではないでしょうか。特に「拡大を是とする資本主義の論理」ばかりに目が向いてしまうと、個人も組織も、目の前の損得にばかり囚われがちになります。そうして大局観を失い、長期的な課題に向き合って解決策を考えたり実行したりすることが困難になっているのだと感じます。
非難したいわけではなく、ただ旧来の「なんとなく当たり前」と思える価値観に基づいた社会構造に起因するさまざまな問題が、真の意味でのリーダーシップ発揮を阻んでいるように感じてしまうんですよ。
この危機感を抱える中で、仁科氏は「自分に何ができるのか」を真剣に考え抜いてきた。やがて辿り着いた一つの答えが、「リーダーを生み出す“媒介”となる事業や組織をつくる」ということだった。
仁科『STUDIO ZERO』のミッションは、「産業と社会の変革を加速させる」。そのために、社会変革の最前線に立つリーダーを輩出し、そのリーダーシップを通じて社会課題の解決に挑もうとしています。一つの事業体という枠を超えて、志を同じくする人々がつながり、持続可能な形での価値創造を追求する。そこでは、これまでの資本主義の限界を超えた、新しいリーダーシップのあり方が求められるはずです。
その理想を体現するため、『STUDIO ZERO』では「営利組織に働きがちな一般的な力学」と一定の距離を置く。常に自社の利益のみを追求するのではなく、社会全体の利益との調和を図ろうとする姿勢だ。
仁科もちろん、自分たちの利益を度外視するつもりはありません。当然、常に最速での最大化を目指します。
ですが、利益とはあくまで、ミッション実現のための資本です。変革を加速させていくために、資本となる利益を拡大していく必要がある。だから営利組織という手段を選び、事業をしているともいえるわけです。
常に「何のための利益か」を問い続けることで、目先の数字だけを追い求めず、社会との関係性を意識した事業展開を進めています。目指す先は、持続可能な形で社会課題を解決し、新しい価値を生み出していくこと。その本質を見失わないことが大切ですね。
利益の最大化と持続的な成長、そしてスピードと持続性。一見、相反するようなこれらの価値観を高い次元で両立させる。それこそが、『STUDIO ZERO』の理想とするリーダー像だ。ジョニーは、その在り方を「農耕型リーダーシップ」になぞらえる。

ジョニースタートアップと一言で言っても、その在り方は多種多様ですよね。例えば、短期的な利益追求や市場シェアの獲得を重視する企業がある一方で、長期的な視点からステークホルダーとの共生や持続可能性を重視する企業もあります。
前者の考え方では、競争に勝ち残ることが至上命題となり、時に「弱肉強食」的な状況を生み出すこともあります。一方、後者の考え方では、特定の企業や個人が短期的に利益を独占するのではなく、長期的にあらゆるステークホルダーが満たされる状態を目指します。ここでいう「あらゆるステークホルダー」には、自然環境や社会全体も含まれるんです。
『STUDIO ZERO』の経営は、どちらかというと後者の考え方に近いように感じました。「狩猟型というよりも農耕型」とも表現できそうです。あらゆるステークホルダーとの共生を重視し、諦めず、腰を据えて事業を営んでいく。伝統的な資本主義の中で散見されていた短期的な利益追求とは一線を画した、新しい在り方を探っているように感じます。もちろん、スピード感でいえば、従来の1年に1回だけ収穫がある農業よりも遥かに速いのですが(笑)。
仁科確かに、農業で例えるなら「四毛作くらい爆速でやっていく」というイメージかもしれません(笑)。おっしゃる通り、『STUDIO ZERO』の目指す道は、単純な規模の拡大や短期的な利益追求だけではありません。立場や所属組織を問わず、志を同じくするプレイヤーを多く巻き込みながら、社会全体の持続的な発展を追求する。ブレークスルーを起こすイノベーションにも果敢に挑戦しつつ、自然環境や社会との調和を大切にする。そんな「農耕型リーダーシップ」の先進事例となれたら、嬉しいですね。
事業を通じて新たな価値を生み出す先に、自然環境や社会全体との共生がなされる。そんな従来の成功法則と、共生や持続可能性を重視する姿勢。その融合こそが、これからの時代に求められる経営の在り方なのかもしれませんね。私たちは、そうした新しいバランスを模索しながら、持続可能な成長を追求しています。
社会をより良くしたいと願うのは、誰しも同じはずだ。しかし、その想いを自らの使命と位置づけ、行動に移し続けるのは容易ではない。されど、仁科氏の眼差しは本物だ。その背景には、生い立ちに根差した独自の思想がある。仁科氏にとって、リーダーシップの探求それ自体が「セルフミッション」なのだという。
リーダーシップは、同心円状に広がる
社会変革の理想を掲げることは容易い。しかし、その理想をどう具現化するのか。組織として、人としてどう行動すべきか。仁科氏の思索はさらに深いところへと向かう。
仁科実は僕には「『善く生きる』人を増やしたい」という個人的なミッションがありまして。ここでいう「善く生きる」人とは、個人の自己実現と、集団における調和の両立を意味します。
人は社会的な生き物である以上、ある程度の規範やルールに沿って生きる必要がある。しかし、だからと言って自分を殺してまで集団に迎合する必要はない。むしろ、自分の人生に真摯に向き合い、自己実現を追求していく中で、自然と利他の精神が芽生えてくる。「自分のしたいこと」が「世の中を良くすること」に繋がっている。そんな生き方ができれば素敵だなと思うんですよ。
ジョニー僕も最近、「誰もが輝き社会も善くするwell-beingの追究」というセルフミッションを掲げ始めたんです。でも、目の前の事業との結び付きを整理し切るのがなかなか難しいと感じることが多いです。そんな僕から仁科さんの言動を見ると、すべてがきれいにつながっているように見えて驚かされます。
仁科氏曰く、「善く生きる」とは、自分らしく生きながらも、社会貢献意欲を兼ね備えた人ということ。だが、そんな人を増やしていくには、一体何が必要なのだろうか。その鍵となるのが「自己効力感」だ。
仁科自己効力感の低い人は、新しいチャレンジに対して「自分には無理」「今はできないから、できるようになったらやります」と尻込みしてしまう。対して自己効力感の高い人は、「できるかどうかわからないけど、やってみたい」「チャンスは逃したくない」と一歩を踏み出す勇気がある。
この差は、仕事だけでなく、人生のあらゆる意思決定に影響します。自己効力感が低いままだと、チャレンジを避け続け、いつしか閉塞感に苛まれるようになる。でも、もし一人でも多くの人が、ほんの少しでも前向きな挑戦を選択できるようになれば、きっともっと充実した人生を送れるはず。そう信じて、僕は行動しているんです。
ジョニー自己効力感がより善く生きるための土台になっていくということですね。すごく納得する考え方です。
ですが、組織からポジティブな影響を与えて自己効力感を高めようとするのは、簡単なことではないですよね。多くの経営者が悩んでいると思います。
仁科はい、なのでそもそも『STUDIO ZERO』のミッションや事業モデルを、自己効力感が高まっていくようなものにしています。「産業と社会の変革を加速させる」と掲げ、そもそも自己効力感の高い人たちを集めながら、その力を組織の内外に伝播させるのが当たり前になるような事業にしているんです。
チャレンジしたいけれど、ノウハウがわからず二の足を踏んでいる。過去の失敗にとらわれ、前に進めずにいる。そんな人たちの背中を押し、一緒にリスクを取りながら挑戦を後押ししていくのが日常なんです。
ジョニーまさに今の話とも繋がると思うのでここで聞かせてください、仁科さんが『STUDIO ZERO』から生み出したいリーダー像というのは、どういったものなのでしょうか?

仁科まず思い描くのは、おっしゃる通りこのミッションから紐づいてくる話なんですけど、「物事を導く人」ですね。そうでなければ、産業や社会の変革を加速させるという大きなインパクトを創出できない。
そして、これが文字通り「リーダー」という表現に変わってくるんですけど、そのリーダーというのは、別に会社のリーダーである必要はないんです。
例えば家庭のリーダーとして家族を導くのも素敵だと思うし、学校の先生や校長、大学の教授もそう。起業家や経営者、政治家や議員であってもいい。肝心なのは、誰かの心に熱狂を伝播させて火をつけ、物事を一緒に変えていく仲間を増やせる人間であること。『STUDIO ZERO』は、まさにそれを日々の事業の中でやっているんです。
だから、せっかく人生の多くの時間を『STUDIO ZERO』に投じてくれるメンバーには、その経験を通じて、何かのリーダーになっていってほしいと思っています。たとえ、そのエッセンスの一部でも自分の人生に活かしてもらえたら、それほど嬉しいことはありませんね。
さまざまなフィールドで活躍するリーダーを輩出していく。それが仁科氏の理想とする組織の姿なのだ。とはいえ、その理想を実現するには、もう一つ乗り越えるべきハードルがあるという。
仁科ただ、ここで大切なのは「分断を生まないこと」なんです。自己効力感の高い人ばかりが集まって盛り上がっているだけでは、社会全体の活力にはつながりません。自己効力感の高い人、低い人の二極化が進むと、一部の人だけが突き抜け、多くの人が取り残されてしまう。それでは先ほどの資本主義の論理と同じです。
僕たちがやりたいのは、そうではなく、自己効力感の高い人が持つ力を周囲に伝播させること。そうすることで初めて、社会全体に自己効力感が根付き、誰もがエンパワーメントされるはずなんです。

仁科氏がセルフミッションをブレイクダウンしたメモ
仁科『STUDIO ZERO』は、まさにこの整理における最下部「前向きなインパクトがある取り組みを同時多発的に実現したい」というビジョンを体現する組織なんです。『STUDIO ZERO』という共創の場は、新しい社会インフラになりうる可能性を秘めている。その先にあるのは、人々の自己効力感を高め、利他の精神を養う世界。つまり、「善く生きる人を増やす」ことなんですよね。
ただし、ここで大切なのは、この理念を一方的に押し付けるのではなく、多様な価値観を認め合いながら、緩やかに共有していくことだ。
仁科もちろん、一番上の「善く生きる」の定義は、人それぞれだと思うんです。だからこそ、この理念を表層的に言葉で説くよりも、日々の実践を通じて体現していく。一人ひとりが異なる人生を歩みながら、『STUDIO ZERO』という場で重なり合う。その中で互いに影響を与え合い、新しい価値観を醸成していく。そんな関わり方ができたら素敵だなと。
理念を押し付けるのではなく、実践を通じて「体現」する。多様なバックグラウンドを持つメンバー同士が織りなす化学反応の中から、新しい価値観を創発していく。仁科氏の描くリーダーシップは、そんな有機的なものなのかもしれない。
個人のセルフミッションを起点としながらも、それを『STUDIO ZERO』という組織のビジョンと地続きのものとして昇華させていく。利他の精神を自分事化し、社会に実装していく。仁科氏はこれらの「リーダーシップ」を、同心円状に広げていくことを目指しているのだ。
その思想に触れてみると、そこには仁科氏の独自のリーダーシップ観が貫かれていることがわかる。だが、本記事の目的は、ひとりの経営者の理念を称賛することではない。むしろ、その思想をいかに組織の隅々にまで浸透させ、カルチャーや風土に昇華させていくのか。そのリアルな実践論に焦点を当てていきたい。
“Willへの挑戦”は不安の裏返し。
ベテランメンバーをも潰しかねない落とし穴
まず気になったのは、「リーダーシップ」を組織の隅々にまで浸透させ、メンバーの日々の行動に落とし込んでいくための具体的な方法だ。「善く生きる人」を増やすという仁科氏の人生のミッション。その実現のためには、何よりもまず、一番身近にいるメンバーたち自身が「善く生きる」ことが大前提となるわけだが……。
仁科まず、入社直後のメンバーにはめっちゃ密着します(笑)。
最初の3ヶ月間は、少なくとも2週間に1回のペースで僕との1on1を30分から1時間行う。それに加えて、日々の業務の相談役としてメンターを付け、密なコミュニケーションを取ってもらう。戦略やWillに関わる話は僕が受け止め、日常的な業務の悩みはメンターに相談してもらう。そうすることで、組織の方向性から足元のオペレーションまで、隅々まで理解を深めてもらえるんです。
メンバーには、この『STUDIO ZERO』という “船” に乗ってもらったわけですから、その選択と挑戦に対して、感謝の気持ちを伝えた上で、全力でサポートしていきたい。それに、選考で最終的に採用を決めたのは僕です。だったら、入社後もその人の成長に責任を持つべきだと思うんですよ。数ある選択肢の中から、わざわざここを選んでくれた。その一歩を当たり前だと思わずに、しっかりと受け止めたい。だからこそ、相応以上のコミュニケーションをしたいんです。
仕事の話に留まらず、人生や将来のキャリアについて一緒に考える。日常の何気ない相談ごとにも耳を傾け、腰を据えて向き合う。メンバーからの何気ない相談から、結果3時間にも及ぶディスカッションに発展することも日常茶飯事だという。
そんな仁科氏の哲学は、メンバーのアサインにも色濃く反映されている。

仁科メンバー一人ひとりの「Can(できること)」と「Will(やりたいこと)」を見極め、その実現を後押しするのは経営者としては当たり前のことですよね。当然アサインも、そのバランスを踏まえて決めていく。 特に入社直後は、まずCanを多めに配分し、早期に活躍の場を掴んでもらう。自分の居場所を確立し、自信を持って働ける環境を整えるんです。その上で、徐々にWillの要素を増やしていく。
一方で、難易度の高い案件にも果敢に挑戦したいというメンバーもいる。そうしたWillを持つメンバーには、ホームランを狙える機会を意図的に用意するようにしていますね。ただ、Willを強く表明する態度の裏には、不安や懸念が隠れていることもあります。だからこそ、細やかな心理面のケアが不可欠になってくる。
そうしたメンバーには、僕自身が頻繁に声をかけ、とにかく小さな変化も見逃さないよう気を配りますね。何か困ったことがあれば、すぐに相談に乗れる体制を整えておく。時にはホワイトボードに一緒に書き込みながら、本人の考えを引き出すこともあります。
どんなに高い能力を持つ経験豊富なメンバーでも、何らかの芽が出るまでの期間は人それぞれですよね?その間に「あのメンバーはWillを達成している」と他人と比較して焦る気持ちを抱え、次第にストレスが蓄積して、本人が気づいた時にはダウンしてしまうリスクもあるかもしれない。だからこそ、一人ひとりのWillに真摯に向き合い、適切なタイミングでフォローしていくことが重要なんです。
ジョニー仁科さんは「『善く生きる』人を増やしたい」というセルフミッションを掲げながら、それを自らの組織のメンバーから始めようとしている。 人材育成は、「事業成長のための手段」ではない。むしろ、メンバーの成長こそが第一義だと。だからこそメンバー一人ひとりに手厚くコミットできるんですね。
とはいえ、肝心の事業がままならない状態では、崇高な理念も絵に描いた餅になりかねないですよね。しっかりとした業績があって初めて、メンバーも心からミッションと向き合えるはず。そう考えると、事業成長と組織づくりは、まさに「鶏と卵の関係」とも言えます。 仁科さん自身が、この二つの課題にうまく時間を配分している印象があります。その裏側についてもこの後、聞かせてください。
事業と組織。一見すると相反する課題にも見えるこの2つの要素の両立に頭を悩ます経営者は多い。当然組織規模の大きな会社であれば、機能分割が最適解ということになるだろう。しかし、アーリーフェーズ、特にSTUDIO ZEROのような30人前後の規模の組織のリーダーはどうすれば良いか。そこで重要となるのが「時間軸を意識したマネジメント」だ。
時間軸を捉えるマネジメント術──「凡事徹底×爆速」
『STUDIO ZERO』の設立初期、具体的には1年目から2年目にかけては、仁科氏は自身のリソースの60〜70%を事業に、30〜40%を人材と組織の構築に配分していたという。
しかし現在は、事業における主要な意思決定のほとんどをメンバーに委譲し、仁科氏自身は採用や組織マネジメント、そして新規事業の立ち上げなどに90%以上のリソースを配分するように舵を切った。事業の成長フェーズに合わせて、リソース配分を機動的にシフトさせてきたのだ。
仁科もちろん営利企業なので、事業は全ての源泉です。最速で最大の利益を生み出すのは当然のこと。メンバー一人ひとりにも、「我々は利益を出すために存在しているのだ」と常に伝えています。ビジネス、エンジニアリング、クリエイティブ、どの領域であっても、全員が“商人”としての意識を持つべきなんです。
その上で、リーダーたる者は、さらに先を見据えなければならない。常に次の一手、また次の一手を打ち続ける。それが理想的な頭の使い方かなと思います。
例えば僕の場合だと、常に18ヶ月先を見据えて、目標とする成長を実現するために、今どれだけのバッファが必要かを考えています。その中で見えてきた課題は、たとえ小さなものでも「リスク」と位置づけ、最悪の事態を想定した上で対策を立てる。そして、その瞬間から即座に行動に移す。目標達成よりも少し前倒しになるよう、自分に圧力をかけるんです。そうすることで、常に先手を打ち続けられる。たとえ想定外の事態が起きても、俊敏に軌道修正できますからね。
STUDIO ZEROでは、中長期的な事業目標を見据えて綿密な計画を立て、それを着実に実行していくことで着実な成長を遂げている。その一例が採用実績だ。事業の持続的な成長を実現するには、優秀な人材の確保が不可欠。だからこそ、事業計画と採用計画を連動させ、必要な人的リソースを適切なタイミングで獲得していく必要がある。
仁科上期に計画していた採用人数がありましたが、下期は人材の流動性が低下することを想定し、上期に前倒しして採用人数を計画し直しました。改めて計画を見直してみると、当初の想定よりはるかに多くの施策を打つ必要がある。であれば、新たな採用チャネルを開拓したり、社内の採用リソースを増強したりと、今すぐ手を打たなければならない。
そう考えてすぐに動くことで、結果として上期だけで年間目標に近い採用数を実現し、年間計画を前倒しで達成することができました。
もちろん、これは採用戦略の一例に過ぎません。大切なのは、事業目標達成のために必要な手を、先んじて打っていくこと。リスクを適切に評価し、チャンスを逃さない機敏な判断力が問われますが、思考は至ってシンプルであとはそれを爆速で進めていくだけです。
18ヶ月先を見据えた計画を立て、そこから逆算して今やるべきことを導き出す。時には目標達成に向けて、意図的に「圧力」をかける。そして、課題にはあえて「リスク」というラベルを貼り、できる限り早期に対策を打っていく。事業環境が刻一刻と変化していくアーリーフェーズでは、そうした先手を打つ姿勢が競争力の源泉になると考えているのだ。
ジョニー経営者としては、リスクを過小評価してしまう心理が働くこともあるとは思いますが、あえて「リスクは大き目に捉える」のはなぜでしょう?

仁科僕は物事を決める際はめちゃくちゃ“石橋を叩く派”、つまり徹底的にリスクを洗い出す主義なんです。楽観的に見られることも多いですが、実はかなり慎重派。リスクは常に大きく見積もるようにしていまして。
一方で、メンバーに何かを伝える時は、リスクの捉え方を相手に合わせて調整します。もちろん、プレイドやSTUDIO ZEROの経営陣に報告する際は、かなり精緻にリスクを分析した上で、適切な粒度で率直に伝えるようにしています。
でも、メンバーに対しては、あまりリスクの話はしないですね。小さいことだよ、大したことないよと。だって、産業社会を変革するためには、リスクなんてものは乗り越えるべき対象でしかないんですから。だから、「このリスクは、貴方なら十分に乗り越えられる」というメッセージを込めて、適度にリスクを伝えるんです。
リスクの捉え方は、相手によって使い分ける。メンバーのモチベーションを維持しながら、しっかりとリスクを認識してもらう。そのバランス感覚が、リーダーには求められるんだと思います。
とはいえ、事業を優先するからこそ「稼いだ先にどんな未来を創るのか」という問いを常に意識し続けることが重要だと仁科氏は付け加える。短期的な利益だけを追い求め、その先の未来を見失ってはならない。利益を通じて、より良い社会と人材を生み出すこと。その志を失わない限り、事業と組織の両立は可能なのだと。
実際、『STUDIO ZERO』では「ミッションドリブンを維持したまま拡大する」ことを前提に、さまざまな施策が打たれているという。
仁科今年1月に開催したオフサイトミーティングでは、まだメンバーが20名ほどの段階で「ミッションドリブンを維持したまま拡大するには何が必要か」を全員で議論しました。組織の成長段階で必ず直面する「あるある」の課題に、どう先手を打つか。そんな問題意識を共有する場だったんです。
例えば「30人の壁」という言葉も、ベンチャー・スタートアップ界隈では当たり前の常識ですが、大企業出身のメンバーは「初めて聞いた」と言う人も多い。数万人規模の会社にいた人からすれば、あまりピンとこないのも無理はないですよね。
だからこそ、「誰かの常識は誰かの非常識」という前提に立って、丁寧な言語化が欠かせません。「組織にはこういう成長段階があって、各段階でこんな課題が起きやすい」。それを事例を交えて説明していく。
よくある話ですが「うちは大丈夫」と根拠のない自信を持つ経営者も少なくないですが、それは幻想でしかない。自社も必ず何らかの壁にぶつかるという前提で、いかにダメージを最小限に抑えるか。その予防と対策を早めに講じることが重要となります。「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という言葉があるように、他社の経験から学ぶ姿勢が大事です。
実際にそのオフサイトミーティングでは、『STUDIO ZERO』が「スタートアップ30人の壁」を乗り越えるために言語化、型化を不可欠と捉え「STUDIO ZEROらしさ」を定義していった。さらに、業務プロセスを標準化し、オンボーディングの仕組み化も徹底。既に50人、100人規模だけでなく、1,000人規模までを見据えた課題を整理し、オフサイトでメンバーにオープンに伝えている。また、ミドルマネジメントへの権限委譲など、さらに先を見据えた仕組みづくりにも着手し始めているという。経営者としての先見性と透明性が際立つエピソードだ。
ただし、仁科氏は、こうした取り組みも、事業が順調であることが大前提だと念を押す。

仁科ミッションと整合性を保ちながら、爆速で組織開発を進められるのは、何より事業が順調だからこそ。その原動力は、強固な事業基盤にあるんです。
事業環境が悪化し、業績が低迷している最中に、いくら人材育成や組織改革に力を注いでも、その効果は限定的なものにとどまりがちだと思います。どんなに施策を打ち出しても、後手後手に回ってしまうことが多いんですよね。そんな状況下では、メンバーからも不平不満の声が挙がるものです。
肝心の「カネ」の問題を置き去りにしたまま、「ミッション」や「組織」といった上位概念の話をしようとしても、上滑りしてしまう。だからこそ、順序が大事なんです。まずは事業にコミットして成果を出す。その土壌があって初めて、ミッションや組織文化についての議論が活きてくる。
事業の勢いがあってこそ、メンバーもミッション実現や自身のWillにしっかりと向き合える。今の『STUDIO ZERO』が、本気で組織づくりに取り組めているのは、ひとえに事業成長があればこそなんです。
事業が好調な今だからできること、やるべきことがある。組織の基盤を整え、一人ひとりの成長を最大化する。ミッションを言葉だけのスローガンで終わらせず、メンバー全員の血肉にしていく。その取り組みに、仁科氏は自らの時間の大半を投じている。
仁科もちろん、事業もまだまだ発展途上なので、僕自身もまだまだ成長に向き合わなければいけませんが(笑)。ただ、この事業の柱となる考え方だけは、ブレずに持ち続けたい。
「凡事徹底×爆速」という言葉がまさにそれですね。小さなことにも全力で取り組み、そのスピードを最大限に上げていく。シンプルな方針ですが、これからの『STUDIO ZERO』の成長を支える大きな力になると信じています。
リスクを先回りして捉え、できる限り早期に手を打つ。その積み重ねが、環境変化の荒波を乗り越える競争力の源泉になる。「凡事徹底」のマインドを持ちながら、「爆速」でPDCAを回す。その二つの言葉に、リーダーとしての仁科氏の哲学が凝縮されている。
高い志と現実とのギャップをどう埋めるかがリーダーの役目
ここまで約1万字に渡り、今の時代に求められるリーダーシップとは何か、仁科氏の思想と、それをどのように組織に落とし込んでいくかを探求してきた。
最後に改めてジョニーから、「仁科氏にとって、リーダーシップの本質とは何か」を尋ねた。
ジョニー仁科さんは大手企業にも在籍され、創業期のスタートアップにも携わり、今は『STUDIO ZERO』を率いています。ミッションやビジネスモデル、社会のマクロ環境などに合わせて、ご自身のリーダーシップスタイルを変化させているのでしょうか。それとも、今の仁科さんのリーダーシップは、『STUDIO ZERO』のミッション達成のために意図的に取っているものなのでしょうか、あるいは、本来の仁科さんのスタイルなのでしょうか?

仁科基本的には、本来の自分のスタイルだと思います。ただ、例えばコロナ禍の際に取るべきリーダーシップと、コロナが落ち着いて社会情勢が上向きになりつつある今のリーダーシップでは、求められる意思決定の強度や濃淡は大きく異なりますよね。
コロナ下で「多額の借り入れをします」とか「人員削減に踏み切ります」といった判断は、「そりゃそうだ」と納得を得られやすい。しかし平時にそれをやろうとすれば、相当に丁寧な意思決定プロセスを経ないと「なんで!?」と反発を招く。つまり、リーダーシップを発揮する上での自由度は、外的環境の影響を少なからず受けるものなんです。
環境変化に合わせて、リーダーシップのスタイルも柔軟に変えていく必要があると。しかし、だからこそブレない軸を持つことが大切なのかもしれない。そう考えると、仁科氏の「根底に流れる軸」とは一体何なのだろうか。
仁科会社はそもそもなぜ存在するのか。社会に対してどんな貢献をするのか。その道標となるミッションやビジョンがあり、それを実現するための行動規範や価値観がある。その上で事業を通じて利益を生み出し、その利益をさらなる成長の源泉たる人材や新規事業に投資していく。こうした好循環を生み出し、ミッション達成を加速させていく。これこそが、営利組織が社会の中で存在意義を発揮するための基本ルールだと考えています。
その基本に立ち返れば、あとは目指すミッションの規模や難易度に応じて、必要な経営資源も変わってくる。だからこそ、その都度最適なコミュニケーションとマネジメントを心がける。『STUDIO ZERO』の場合、「産業と社会の変革を加速させる」というミッションを掲げているからには、それを実現するためのビジネスモデルや、組織のあるべき姿、人材のポートフォリオなどを常に意識しているんです。
ミッションドリブンな組織運営。それは確かに、高い志を持つリーダーが理想とするスタイルと言えるだろう。しかし、現実の組織が直面する課題は山積みだ。志と現実をどうすり合わせていくのか。そこでは、かなりのリーダーシップ力量が問われるはずだ。
仁科例えば、優秀な人材をどう惹きつけるか、入社後にどうオンボーディングすれば、強い個性も発揮しながらチームワークを発揮できるか。あるいは、高いパフォーマンスを発揮し続けるためにどんなフォローが必要か。時には退職のケースだってあるでしょう。そんな時、どんな旅立ちの仕方が望ましいのか。 こうした、組織運営におけるミクロな意思決定を、常に大局観を持って最適化していく。個人のミッションと組織のミッションを重ね合わせ、メンバー一人ひとりが自分の人生とシンクロする形で組織の成長に関わっていけるよう、日々アプローチを磨いているんです。
ジョニー界隈を見渡すと、代表取締役やCEOという肩書の方々の“個人的な関心”の比重に違いがあるように感じます。多くの場合、「この課題を解決したい」「大きな企業、事業を創りたい」という志が先行し、人材育成や組織づくりへの注力度合いには個人差がある。もちろん、人や組織に興味がないわけではないのですが、役割分担として、CEOは事業サイドに注力し、人や組織の面は信頼できる共同創業者や経営陣に一任しているケースも存在するように思います。そういった中で、仁科さんのように、ここまでピュアに人の活躍や組織のあり方の優先順位を高く置き、深くコミットされているのは、かなり特徴的なスタンスだと感じます。
仁科そうですね。もちろん、300人、1,000人規模になると、ある程度の機能分化は不可欠です。経営者層の右腕となる人事責任者を置いて、組織開発に専念してもらう。無理に全てを抱え込む必要はない。 しかし、僕らのようなアーリーフェーズの組織こそ、リーダー自らが組織と人材の課題に深く関与すべきだと僕は思います。そのフェーズにおける最大の資産は「人」に他ならないですからね。
その人的資産にどれだけ投資できるかが、組織の伸びしろを大きく左右すると思うんです。コミットが足りないと、どこかでボトルネックが生じて、「こんなはずじゃなかった」なんてことにもなりかねません。 だから僕は、人と組織に向き合うことにたくさんの時間を使います。もちろん大変な部分はありますが、事業にも必ず好影響を及ぼしてくれる。だからこそ、全ての経営者、特にアーリーフェーズの経営者には、ぜひ組織と人の課題に正面から向き合ってほしいと思いますね。

ジョニーなるほど。仁科さん自身が人と組織を育むリーダーシップを発揮し続ける限り、『STUDIO ZERO』からは次々と「産業と社会の変革を加速させる」リーダーが輩出されていくのではないでしょうか。
多くの企業では、事業目標の達成が最優先され、人材育成や組織づくりが後手に回りがちです。しかし仁科さんの場合、「善く生きる人を増やす」という個人のミッションが先にあり、そのミッションを実現するための手段として『STUDIO ZERO』という組織を作られた。そして「善く生きる人を増やす」という個人ミッションの持ち主がトップを務めているからこそ、STUDIO ZEROの組織ミッションは「産業と社会の変革を加速させる」と定めた。
なぜなら、この組織ミッションにピュアに邁進することは、事業としての継続的な成長はもとより、STUDIO ZEROのメンバーや、クライアント企業や影響範囲にいるユーザーなどの人々が「善く生きる」ことに繋がり、実現に近づくから。
このアプローチにより、仁科さんは短期的な利益追求に囚われることなく、より長期的かつ大局的な視点で組織を牽引していけるのでしょう。事業の成功と人材の成長を同時に追求することで、持続可能な組織づくりを実現しています。こうした「人の成長」を中心に据えた組織だからこそ、真のリーダーシップが育まれ、次代を担う人材が輩出され続けるのだと腑に落ちました。
仁科このことは、自身のキャリアを考えることが多い中途メンバーのみならず、新卒採用の場でも常々伝えています。そもそもキャリアとは、自己実現の手段に他ならない。だったら会社は、自分の人生を歩むためのツールとして“使う”くらいの気概を持とうと。
だから就職活動では、自分が本当は何をしたいのかという根源的な問いから出発しなければならない。 そうすると自ずと、ミッションドリブンな思考に基づいて会社選びをするようになる。事実、『STUDIO ZERO』に入ってくれた新卒のメンバーの多くが、そういう意識を持ってくれています。
個人の持つポテンシャルを最大化し、集結させ、社会変革を巻き起こす。これこそが、仁科氏が追求し続けるリーダーシップの真髄だ。まずは自らの行動を通じて「STUDIO ZEROらしさ」を体現し、常に高い目標に挑み続ける。個人と組織、事業と人材をつなぐ架け橋となり、変化の荒波を乗り越えて新たな価値を生み出していく。
その過程では、個人と組織が一体となり、互いの成長を加速させあえる環境づくりが不可欠だ。マネジメントを通じて、一人ひとりの内なる情熱を引き出し、組織の力に昇華させていく。リーダーシップとは、そうした化学反応を巻き起こす触媒なのかもしれない。
100人、200人、さらにはその先を見据えながら、事業と人材の両輪で挑戦を続ける『STUDIO ZERO』。その実践の軌跡は、これからの時代に求められるリーダー輩出組織の在り方そのものを示唆しているのかもしれない。個人の力を信じ、組織の力を最大化する。その先に、社会の新しい価値創造が待っていると信じて。
こちらの記事は2024年06月28日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
落合 真彩
写真
藤田 慎一郎
おすすめの関連記事
「個性を見つけ最適配置するから、事業が伸び続ける」──カオナビ流・セールス起点のキャリアグロース実例を徹底解説
- 株式会社カオナビ ヨジツティクス事業室 室長
日本のビジネスパーソンも、自身の価値を「デューデリ」しよう──市場価値を最大化させる“投資家的”キャリア思考法を、日米の比較に学ぶ【対談:STUDIO ZERO仁科&渡辺千賀】
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
「稼ぐ理由が、君の天井を決める」──ソルブレイン櫻庭×STUDIO ZERO仁科対談。利益の先にある、経営者の使命
- 株式会社ソルブレイン 代表取締役社長
大企業の新規事業が、日本を変える──「失われた30年」を乗り越えていく提案を、新規事業家・守屋実とSTUDIO ZERO・仁科奏が語り合う
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
採用戦略の真髄は“狭報”にあり──インキュベイトファンド×DNX Ventures×FastGrow スタートアップ支援者が見る採用強者の共通項
- インキュベイトファンド株式会社 コミュニティマネージャー
「環境選び」で妥協しない──STUDIO ZERO上田氏・新井氏らから学ぶ、大きな変革を最短距離で生み出すキャリアの歩み方
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
“トレードオン”は、意外と難しくない──一人ひとりが新たなチャレンジを続ける『STUDIO ZERO』3名のキャリア実例に、「WANT TO」の重要さを学ぶ
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
非線形の成長を続ける合言葉は「面白いことをやろう」──多様なケイパビリティを発揮し、大手企業とコラボレーションを生み出すSTUDIO ZEROの“楽しさ”に迫る
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO事業本部 CX Director
大手企業も、「ワクワク」があれば変えられる━ベンチャーから来た30歳の若手が、大手企業を“内側”から変革し、わずか一年で受注数を数倍に。プレイドの新事業『STUDIO ZERO』の全容に切り込む
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
スタートアップが「極大インパクトの主体」となる最短経路の進み方とは?──プレイド仁科氏が描く社会変革の“フェーズ2”『STUDIO ZERO』の全容に迫る
- 株式会社プレイド STUDIO ZERO 代表
「セオリー通りのSaaS」では、社会変革など生み出せない──プレイド倉橋×仁科が描く、未来創造のためのスタートアップ進化論
- 株式会社プレイド 代表取締役CEO
「チャレンジする上で、大企業もベンチャーも関係無い」若手経営人材の2人が語る採用広報の重要性。SNSデータ起点で企業の「B面」を魅せよ。
- 株式会社No Company 代表取締役
クライアントに寄り添う“創意工夫の鬼”マネジャー渡辺が語る、「単価の振れ幅が大きいセールス」とFastGrowの秘密
「コロナ収束後も採用はフルリモート?」注目ベンチャーCxOが6人集結したFast Movers Online初開催!Withコロナを勝ち抜く戦略とは
- 株式会社ABEJA 取締役CPO
学生起業するなら、成功した起業家が集うコミュニティに参加すべし。テックピット山田氏×FastGrow編集長対談
- 株式会社テックピット CEO
「ジョブズすごい」と思っているならビジョナリーを目指すな──シンプレクス金子が説く、「強い企業」を創る7つの条件
- シンプレクス・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(CEO)
- シンプレクス株式会社 代表取締役社長(CEO)
SaaSセールスの精鋭たち、ノウハウを一挙公開。急成長SaaSスタートアップ6社が集結
- atama plus株式会社 共同創業者・取締役
優秀な人材を転職「前」から刺す方法──リクルートメント・マーケティングを実践する2社の採用戦略
- ウォンテッドリー株式会社 Recruitment Marketing Evangelist / Business Hiring Manager
VCこそコンテンツを発信せよ。メディアを活用した新しいスタートアップ支援のかたち【Coral Capital×FastGrow】
- Coral Capital Founding Partner & CEO
【事例】「決め手は起業家フォロワーの質」企業変革に挑むオプトが、FastGrowを選択した理由とは
- 株式会社オプト 人事戦略部 新卒採用担当
「目立たなくていい。カルチャーを作れ」働き方が多様化する現代に求められる、理想のリーダー像を語る
- 株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース 代表取締役
「日本のイノベーション・エコシステムを補完する」来たる共創社会に向け、FastGrowは何を目指すのか
- スローガン株式会社 執行役員 兼 FastGrow事業部 事業部長・編集長
起業家のエコシステムは、意図的には生み出せない。StartupListが目指すコミュニティのあり方
- HAKOBUNE株式会社 Founding Partner
大企業出身者よ、「土地勘」を武器に業界を変革せよ!アプリコット・ベンチャーズが投資を決める理由
- 株式会社アプリコット・ベンチャーズ 代表取締役
2年間で12の事業を創造。Y Combinatorを踏襲した、起業家的20代を輩出する仕組みとは
- ファウンダーズ株式会社 代表取締役