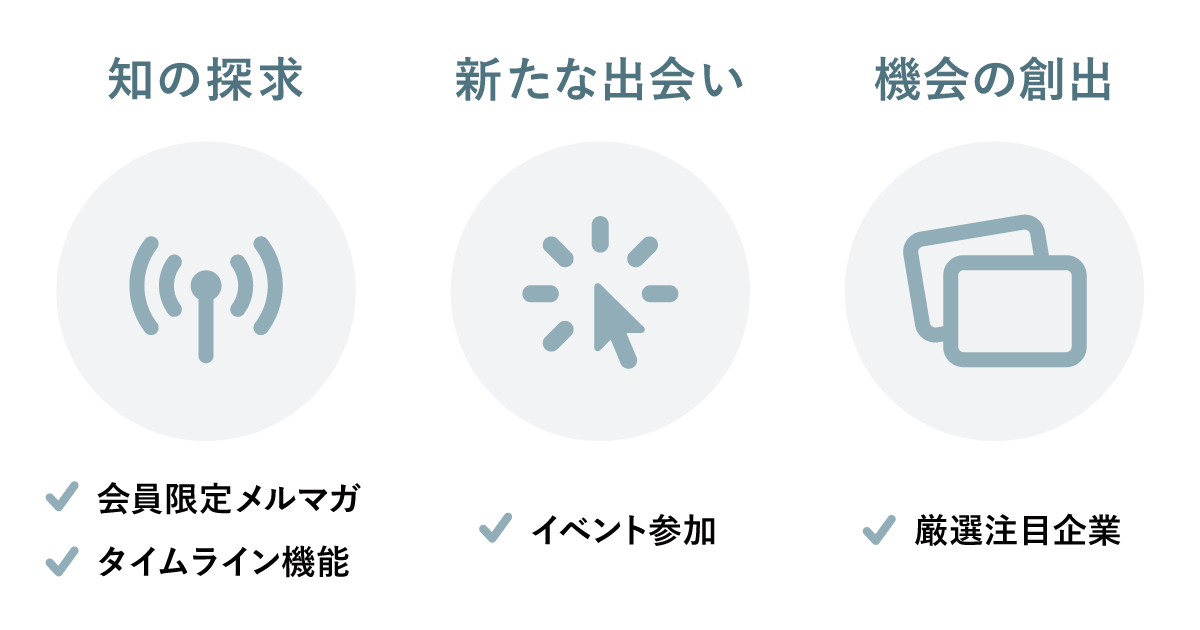イノベーションのために必要な「創造性の3つのレイヤー」とは?
Mimicry DesignとDONGURIが提案するファシリテーションとデザインを活かした新たなアプローチ
近年、コンサルティングファームによるデザイン会社やクリエイティヴエージェンシーの買収が起きている。デザイン会社もコンサルティング機能を強化するなど、経営コンサルティングとデザインの結合は大きなテーマだ。
上記のトレンドは、デザインとコンサルティングを組み合わせ、イノベーションを生むために起きている。こうした流れの中で、Mimicry DesignとDONGURIの2社は、新たなアプローチに挑戦する。
両社は、資本業務提携を通じて経営におけるデザインのパフォーマンスを最大化しようとしている。提携の背景にある国内市場におけるイノベーション課題、どのような手法でその解決に臨んでいくのか、Mimicry Design代表取締役 安斎勇樹氏、DONGURI代表取締役 ミナベトモミ氏の2人に話を聞いた。
- TEXT BY TAKESHI NISHIYAMA
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
- EDIT BY JUNYA MORI
組織が過去の成功に囚われているとイノベーションは起こらない

創業当初からコンサルティングとデザインをサービスとして提供してきたDONGURI。ワークショップデザインとファシリテーションの研究と実践を推進してきたMimicry Design。
DONGURIは、スタートアップベンチャー/東証一部上場企業まで、様々な規模の事業変革や組織変革の実績がある。Mimicry Designは、資生堂や花王、サッポロビールなどの企業に対して組織開発や事業開発を支援してきた。
さまざまな企業のイノベーション創出を支援してきた両社が資本業務提携によって目指すのは、社会におけるイノベーション課題の解決だ。研究と実践を往復しながら、国内市場におけるイノベーション課題を解くべく、企業に対してコンサルティングを行なっていくという。
彼らは、国内市場においてイノベーションが生まれにくい理由を3つに分けて捉えている。
- 組織が過去の成功に囚われ、既存事業の安定成長ばかりに注力
- チームの関係性が固着化し、「対話的なコミュニケーション」が不足
- 個人の内側から湧き上がる「衝動」が蔑ろにされている
ミナベ日本では多くの企業が、既存の事業を効率よく伸ばすことばかりに集中してしまっていて、新規事業が生まれにくい傾向があります。これは大企業でもよく課題として挙げられます。
スタートアップは新たな事業をつくり、短期間で急成長を目指す存在です。そのため、新たなイノベーション創出の担い手としても期待されます。しかし、スタートアップも持続性という点では課題を抱えている。
PMFをしたあとは、IPOなどのゴールに向けて短期的な市場最適に走りがちになっている。ほとんどの事業は一定規模まで成長すると、頭打ちになります。上場後のスタートアップは、次の事業をつくり、育てなければならなくなります。
ですが、ほとんどのスタートアップは事業が中から生まれるための組織作りを行なっていないので、創業者のセンスによってしか次の事業が生み出せていないケースが多い。
スタートアップであっても、イノベーション創出は過去の成功体験に縛られてしまう、属人化してしまうという課題を抱えています。

DONGURI代表取締役 ミナベトモミ氏
「日本企業全体が、“知の深化”に偏重しすぎている」そうミナベ氏は語る。“知の深化”とは、チャールズ・A. オライリー とマイケル・L. タッシュマンの共著『両利きの経営』で度々用いられる言葉だ。
この著書は現在、クリステンセン教授のベストセラー『イノベーターのジレンマ』に次ぐイノベーション理論のスタンダードとして、世界で受け入れられている。
『両利きの経営』では、自身が得意とする既存の事業領域の知を磨き込んでいく行為を“知の深化”、実験的に新規事業を開拓し、自身の組織能力を拡張させていこうとする行為を“知の探索”と定義。そして、その2つをバランスよく行なえていることを“両利きの状態”と呼んだ。
この状態がキープできている企業ほどパフォーマンスが高く、イノベーションを起こし続けられると評価されている。あらゆる会社組織は、この“両利きの状態”を作っていくべきだとミナベ氏は語る。
ミナベスタートアップにとって、IPOも含めて資金調達など次のステージに進むための動きが組織の崩壊のトリガーにつながることが本当に多い。それは、組織の内部構造のデザインと関係性の開発に早期から投資をしていないから。
イノベーションの芽を育てることと、それが収益になるようにアレンジしていくこと……双方のバランスを取れる組織を増やしていかないと、社会全体がよくなっていかないんです。
イノベーションの種を見つけるための個人と組織の創造性が枯渇している
“知の深化”に偏重していることがイノベーションを阻害している。であれば、“知の探索”を行なう組織へと作り替えることができれば、イノベーションが創出される組織になるのだろうか。
“知の探索”を可能にする組織とはどのようなものなのだろう?『両利きの経営』では経営トップの強いリーダーシップや、探索を担当するユニット連携などが提案されているが、安斎氏はワークショップやファシリテーションを起点とした、ボトムアップ型のアプローチが有効だと語る。
安斎実験による開拓である"知の探索"は、私たちの誰もが子どものころから経験してきたように、本能に近い活動です。トップに命令されてするものではない。
組織内でイノベーションの種が育たない状態とは、「自分たちの理念はこれだ」と過去のアイデンティティに縛られたまま、個人の内側から湧き上がる「衝動」に蓋がされている状態です。
衝動を発揮させるワークショップを企画し、チームの対話の場をファシリテートすることで、現場からボトムアップに新たな発見が生まれてくるようになる。
そうした土壌を作ることで、企業のアイデンティティがアップデートされ続ける原動力になります。

Mimicry Design代表取締役 安斎勇樹氏
例えば、スタートアップの場合、強力なプロダクトがある。プロダクトのビジョンやミッションが、そのまま企業としてのビジョンやミッションになっていることも多い。だが、プロダクトが成長限界に達したとき、それらを再解釈しなければならなくなる。
加えて、組織規模が大きくなり、会社の歴史も積み重なると、分業による役割の固定化や会社理解のばらつきなども発生する。「そもそも、自分たちのパーパスとはなんだったのか」を考え、コミュニケーションできる関係性が組織の中に必要だ。
「意味のイノベーション」や「対話型組織開発」といったイノベーション創出の理論を参照しても、組織のイノベーションは常にチームの対話から生まれる「意味」が起点になっているとMimicry DesignとDONGURIは考えている。
また、イノベーションを生み出すには個人の熱意が必要だとも言われる。Mimicry DesignとDONGURIは、ここに「遊び心」も加えていくべきだという。
安斎衝動起点の"知の探索"は、人間にとって本質的に楽しいものであるはずです。
ところが企業では効率ばかりが重視され、外側から正解を探すような"イノベーションプロジェクト"が増え、個人の「衝動」が蔑ろにされています。
組織と事業を創るプロセスに本来的な「楽しさ」を取り戻すような、Mimicry DesignとDONGURIが創業期から大切にしてきた「遊び心」を大切にするアプローチは、組織に創造性を取り戻すために有効な手段だと考えています。
「組織、チーム、個人のそれぞれの階層において、創造性が失われている状態こそが、イノベーションが生まれにくい要因だ」と安斎氏は語る。Mimicry DesignとDONGURIは、アプローチする対象を3つの層に分けて、イノベーションが生まれる組織の状態を作ろうとしている。

「創造性の土壌を耕す」、イノベーション・マネジメントの新たな手法

事業と組織は密接に結びついており、組織もレイヤーが分かれている。複雑な事業と組織の状況に対して、外部から介入するのは至難の業だ。
Mimicry DesignとDONGURIは、クライアントの潜在課題に多面的にアプローチできるよう、事業コンサルティング、組織コンサルティング、デザイン、ファシリテーション、研究の5つを新結合したコンサルティングを提供。イノベーションマネジメントの新たな手法を確立しようとしている。
Mimicry DesignとDONGURIが考えるイノベーションマネジメントのために新たに開発されたフレームが「Creative Cultivation Model(以下、CCM)」だ。

安斎CCMは、これまで10年以上かけて研究してきた、個人とチームの創造性を活かすワークショップデザイン・ファシリテーション論を基盤に、組織イノベーションの関連理論を統合することによって開発しました。
CCMは、イノベーションを生み出し続けるために、必要な組織の状態を定義したものです。
クライアントの潜在課題を探りながら、個人の衝動は発揮されているか?事業を運営するために、単なる分業になっていないか?チームの日々の対話が事業をアップデートさせているか?組織構造と事業構造は結びついているか?などと、創造性の土壌を定性的に診断し、イノベーションのレバレッジポイントを探るのです。
CCMのフレームワークを実際の企業に対して適用しようとすると、どのようなケースが考えられるのだろう。
安斎たとえば、新規事業のアイデアはいくらでもありますが、担当者の熱量がなく、アイデアが机上の空論のままアクションに結びつかない大企業の場合。
担当者の衝動を引き出すワークショップを通して「実現したい!」と思えるアイデアを生み出し、さらにそれをWEB/CI/プロダクト/グラフィック/映像などのクリエイティブに落とし込み、さらに事業戦略設計までして一気にスケールさせてしまうプロジェクトとして展開することができる。
あるいはたとえば、求心力を失いかけているベンチャー企業にの場合。
組織の現状とビジョンについて全員が本音で話し合える対話型のワークショップを企画し、そこから課題を炙り出します。
課題に対して、組織デザインの手法を組み合わせて、適切な業務の割り振りや、階層やコミュニケーションライン、評価制度など組織の構造設計をリデザインし、理想的な状態を定着させていくことができる。

組織の規模やフェーズによって、生じる課題と適切なアプローチは異なる。CCMは、ワークショップとデザインコンサルティングという2つのアプローチを組み合わせることで、企業にイノベーションをもたらそうとしている。
安斎ワークショップ型の事業開発・組織開発のファシリテーション技術と、持続的に事業と組織を成長させるインターフェースと構造をかたちづくる事業デザイン・組織デザインにおけるデザインコンサルティング技術の、双方を組み合わせることで、クライアント組織にCCMを実現していくのです。
そしてその方法論を最新の学術研究によって絶えずアップデートし続けるところが、CCMを活かした"Creative Cultivation Consulting"の強みです。
ボトムアップとトップダウン、事業と組織、研究と実践。それぞれにアプローチしてきたMimicry DesignとDONGURの強みを掛け合わせることで、このモデルが実現可能になると考えています。
マネジメント層を変え、社会全体をクリエイティブに
CCMを用いて組織をイノベーション体質に変えていくにあたって、両氏は“とある役割”を担う人材の育成が、大きな指針になると見込んでいる。それは「クリエイティブ・カルティベーター」だ。
安斎僕らがつくったCCMのモデルを使いこなし、社内に創造的対話を生み出していける人材を育てていきたい。それを「クリエイティブ・カルティベーター」と名付けています。個人間やグループ間を繋ぎ、知の相互交換を促すナレッジブローカー兼ファシリテーターのような存在ですね。
このクリエイティブ・カルティベーターを担うポジションとして育成対象と見込んでいるのが、主に組織のマネジメント層だ。
ミナベほかの国と比べて、日本はプレイヤーの比率が20%くらい多いんですよ。
現状としてマネージャーの母数も少ないし、「プレイヤーを充分に生かせるマネージャー」というと、もっと少なくなる。どんなに優秀なプレイヤーが多くても、それを生かせる人材がいなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。
事業や組織へのコンサルティングは、現状抱えている問題解決の手段として、確かに有効だろう。
しかし、それは対処療法的な処置であることが多く、外部のコンサルティングに依存し続けていては、自社の組織の課題解決力は一向に高まらない。
次々と湧き出でる新たな課題に打ちひしがれない組織になるためには、組織内に変化と自走を促し続けらえる人材が必要だ。
安斎マネジメント層がみんなCCMの使い手になれば、組織においても個人の衝動はフタをされません。グループ内での対話も日常的に生まれ、“知の探索”の芽が組織全体で枯れずに育っていきます。
彼らをクリエイティブ・カルティベーターにしていくことで、組織に持続的でサステナブルな変革をもたらせるはずです。

CCMによって組織の創造性が耕されることは、個人のそれも耕されることと必ずセットだ。個人が豊かになれば、組織が豊かになり、そして社会が豊かになる。
この新たなイノベーションマネジメントの手法を生み出し、提供可能な状態を作るために2社は資本業務提携を行った。そのプロセス自体に彼らが重視している「プレイフルさ」があった。
後編では、資本業務提携、互いのトップがボードに参加しあう横断経営、新たなフレームの開発の裏側にあったストーリーに迫る。
こちらの記事は2020年03月16日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
西山 武志
story/writer。writerという分母でstoryを丁重に取り扱う生業です。「よい文章を綴る作業は、過去と未来をしっかりと結び合わせる仕事にほかならない」という井上ひさし氏の言葉を足がかりに、私は一つひとつ書き残すことで、歴史に参加していきます。
写真
藤田 慎一郎
1987年生まれ、岐阜県出身。大学卒業後、2011年よりフリーランスのライターとして活動。スタートアップやテクノロジー、R&D、新規事業開発などの取材執筆を行う傍ら、ベンチャーの情報発信に編集パートナーとして伴走。2015年に株式会社インクワイアを設立。スタートアップから大手企業まで数々の企業を編集の力で支援している。NPO法人soar副代表、IDENTITY共同創業者、FastGrow CCOなど。
おすすめの関連記事
2人の経営者は何を思い、意思決定したのか。Mimicry DesignとDONGURIが異例の「横断経営」に乗り出すまで
- 株式会社ミミクリデザイン 代表取締役
なぜ、スタートアップに事業の深化と探索を両取りする「両利きの経営」が求められるのか?
- 株式会社DONGURI CEO
- 株式会社ミミクリデザイン COO
「両利きの経営」でスタートアップの新規事業を加速させる、3つの組織的アプローチ
- 株式会社DONGURI CEO
- 株式会社ミミクリデザイン COO
現場にいる者こそが、意思決定者──年次も経験も関係ない!UPSIDERで非連続成長を担うのは「一次情報を最も知る者たち」だ
- 株式会社UPSIDER 執行役員 / VP of Growth
急成長企業の5つの鉄則──隠れテック企業・出前館に見る、挑戦と革新の舞台裏
「実際、支社と本社って“違い”がありますよね?」──新卒が抱く配属の悩み。電通総研・関西支社の答えが意外すぎた
- 株式会社電通総研 技術統括本部 エンタープライズ第二本部 エンタープライズ開発ユニット ITコンサルティング2部
「支社配属=密度の濃さ?!支社だからこその強みがここには実在する」──就活生が気にするキャリアプラン。電通総研・広島支社に聞いてみた
- 株式会社電通総研 技術統括本部 バリューチェーン本部 PLM第4ユニット
徹底的な「憑依力」でキャリアを拓く──エンプラセールスからデロイト、VCを経て起業。Matilda Books百野氏が実践する“自分自身の売り方”
- 株式会社Matilda Books 代表取締役