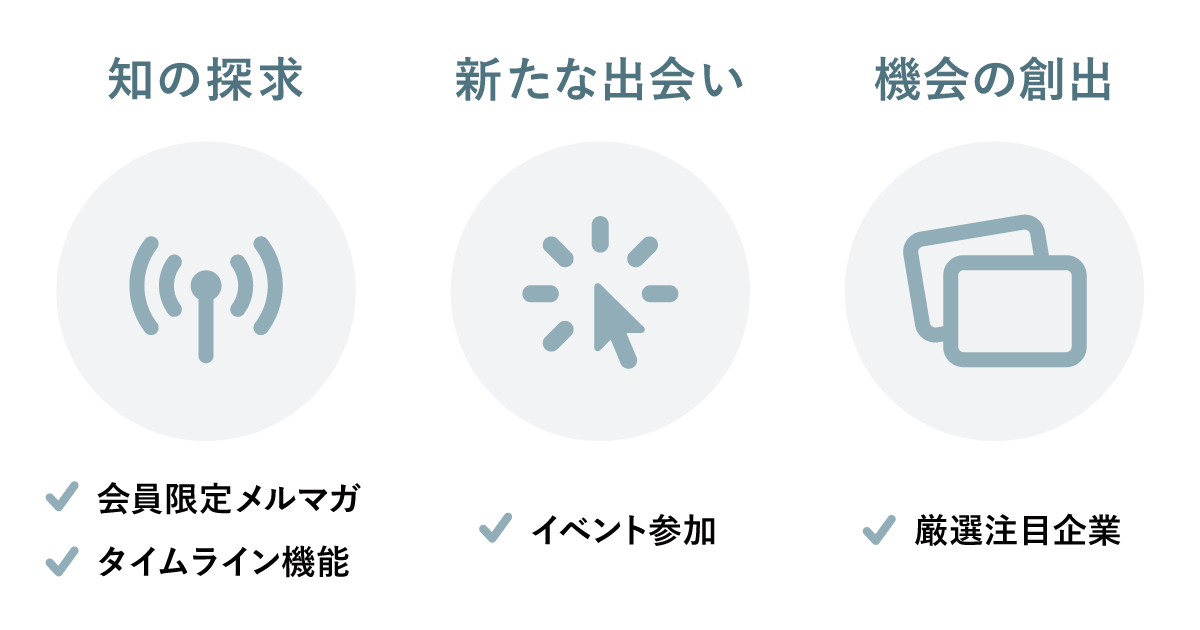なぜあの企業は伸び続けているのか?──急成長企業のビジネスモデルに込められた経営者の覚悟
トレンドの移り変わりが早い今の世の中で、伸びていく企業と伸び悩む企業、その分岐点はどこだろう。伸び続ける企業には、他とは違う根本的な強みや特徴があるに違いない。
そこで、今回は他社にはないユニークなビジネスモデルで急成長を遂げるベンチャー/スタートアップを4社ピックアップした。
本記事では、それらの企業が今のビジネスモデルにたどり着いた経緯や、そのビジネスモデルに込める想いや覚悟を紹介していく。
急成長企業が急成長企業たる所以とは──。
本記事を読めばきっとその答えが見えてくるはずだ。
- TEXT BY YUKO YAMADA
- EDIT BY TAKUYA OHAMA
ソルブレイン──「顧客への価値提供(=売上 / 利益の向上)なくして、自分たちが存在している意義はない」

「どんな仕事でも、顧客に価値提供ができなければプロじゃない」と強い信念を貫く起業家がいる。その名は、新進気鋭の急成長ベンチャー、ソルブレイン代表の櫻庭氏だ。
ソルブレインは、同氏が提唱する『グロースマーケティング』を武器に、データドリブンで顧客のバリューチェーン全体の最適化を推進し、顧客の継続的な売上 / 利益を追求するビジネスモデルを展開している。このグロースマーケティングの詳細について気になる読者は、櫻庭氏の著書『未来をつくるグロースマーケティング』や、櫻庭氏の単独取材を見ていただきたい。
そもそも、なぜソルブレインはグロースマーケティングに取り組んでいるのか?
それは、徹底した顧客志向に他ならない。
ソルブレインは2008年創業以来、一貫してマーケティングの課題に向き合っている。当初、同社はSEOサービスを主としており、集客にはそれなりの自負があった。ところが、先方の希望どおり検索エンジンで上位表示を達成できても、なぜか契約が打ち切られてしまう。それも一度や二度ではなかった。
ここで読者はこう思うだろう。「きちんと結果を出しているのに、なぜ?」と。それは櫻庭氏も同じだ。何がいけないのか。どうすればいいのか。理由を深く探っていくと、自分たちの提供している価値が、顧客の売上 / 利益につながっていないのではないか…?という事実に直面したのである。つまり、提供している施策の目標が達成できていたとしても、ビジネスの最終ゴールである顧客の売上 / 利益に貢献していないのであれば、「そこに投資する価値がない」と顧客に判断され、契約が打ち切られていたのだ。
顧客満足を得て、継続的な自社の事業成長にもつながる価値貢献とは何か──。
悩みながらも諦めず追求し続けた結果、たどり着いたのがグロースマーケティングである。櫻庭氏は、顧客の事業成長、すなわち顧客の売上 / 利益の向上にとことんコミットしていくことこそ、顧客にとって真の価値につながると見出した。
こうして同社は、局所的な最適解の追求ではなく、全体的な最適解、すなわち顧客事業のバリューチェーン全体をデータ起点で俯瞰した上で解くべき課題に向き合い、売上 / 利益の向上にコミットするスタイルを確立していった。以降、現在に至るまで顧客からの解約はゼロに近いという。
しかしどうだろう。読者の中にはまだイメージが掴みきれていない者もいるかもしれない。ここでもう少し、分かりやすい例を挙げてみる。

例えば、ある顧客が「集客」に課題を抱えていたとする。それをマーケティング施策で解決したところ、今度は問い合わせが増えて「オペレーション」が回らなくなってしまった。これでは顧客の課題を解決したとは言えない。そこで、今度はオペレーションを改善する施策を取り入れる。すると今度は、「顧客満足度」を高めるためにオペレーターのスキルを高めようと考えるかもしれない。
このように次から次へと移り変わるボトルネックをデータから見出し、テクノロジードリブンで最適解を実行し続けることで、顧客の持続的な成長を実現していく。バリューチェーンの中で特定の部分だけの最適化を担うのではなく、文字通り事業のバリューチェーン全体の最適化を図る。これこそがグロースマーケティングなのだ。少しはイメージが湧いただろうか?(そこに秘められている同社の「テクノロジーとビジネスの融合」の秀逸性についても語りたいが、それはまた別の機会に…)
ソルブレインのゴールはあくまでも顧客の持続的な事業成長である。前回の対談では「顧客の利益を創出できていなければ、自分たちが存在している意味はない」と語り、プロフェッショナルとして成果にこだわる姿勢を我々に見せてくれた同社。
真摯に、かつ直向きに顧客への提供価値にこだわり続けるソルブレインが、市場の中で選ばれ続けるのは当然の結果ではないだろうか。
ロジレス──「現地現物で得たものこそが真実。だからこそ顧客との対話は欠かせない」

「ロジレスは組織が拡大して事業が伸びている今でも、昔と変わらず現場を大事にしてくれる。そこが、ロジレスのサービス(『LOGILESS』)を使い続けたいと思える理由ですよ」。
そう話すのは、ロジレスのプロダクト導入によって、自社業務の80%の工数を削減することに成功し、更には2年間で40社以上の新規顧客を獲得した、とある倉庫事業者だ。(詳しくはコチラ)
EC事業者と倉庫事業者をつなぐシステムの一元化により、ほぼ完全な自動出荷の仕組みを実現するロジレス。同社は、慢性的な人手不足の課題を抱える物流業界にとって、まさに救世主となる存在である。
そんなロジレスの特徴は、一つのプロダクトで“EC事業者”と“倉庫事業者”、2者の課題を同時に解決するといったタフなソリューションを提供している点だろう。
「2者の業務と課題を理解しながらプロダクトをつくることは、並大抵のことではない」と、同社に出資をしているALL STAR SAAS FUNDの前田 ヒロ氏や、Coral CapitalのJames氏は語る。通常、SaaSを扱うスタートアップは、一つのステークホルダーに対して一つのプロダクトを磨いていくのが一般的だからだ。
そういった難度の高い事業にもかかわらず、なぜ、ロジレスは急成長を続けることができるのか?その理由は、ロジレスが「現場」を起点としたプロダクトづくりを徹底しているからに他ならない。
ここでロジレスの歴史を少し紐解いてみよう。もともとロジレス代表の足立氏は、新卒で楽天に入社し、そこでEC事業の基礎を身に付けた。その後、ロジレスの前身となる企業でEC事業に携わる中、受注〜出荷までに生じる煩雑なアナログ業務に課題を感じたことが、のちの『LOGILESS』誕生に繋がる。
というのも、一般的にEC事業者が扱う受注管理システム(OMS)と、倉庫事業者が扱う倉庫管理システム(WMS)はまったく別物のシステムとして存在しているため、2つのシステム間でうまく情報連携ができず、EC事業者と倉庫事業者の間で無駄なオペレーションが発生していたためだ。
「受注〜出荷までシームレスに繋がるシステムをつくりたい」と考えた足立氏は、楽天時代の同僚であり、現ロジレスのCTO・田中氏と共に、2017年に今のロジレスを立ち上げる。だが、当時はまだ現場の課題が明確に見えていなかった。

そこで、自らの目で確かめるべく、創業から約3年間、倉庫事業者やEC事業者の現場に足繁く通い、現場の人たちと同じ目線で現場作業に取り組んだ。そうすることで、「何が問題なのか」「どんな解決策を必要としているのか」と、顧客のペインやその解決の糸口を高い臨場感で掴めると考えたのだ。
そんなロジレスの現場起点の姿勢は、創業から6年目の今も変わらない。同社は今も顧客現場に足を運び、困りの声が上がればすぐさま対応する。事業が大きく成長してもなお、一貫して現場起点の姿勢を崩さない理由は、「常に顧客と伴走しながらプロダクトをつくり、成長してきた」という想いがあるからだろう。
“ECロジスティクスを変革し、日本の未来をスケールする”というミッション実現に向けて、ステークホルダーと共に手を取りながら着実に歩を進めていくロジレス。革新的なプロダクトはもちろん、その愚直な姿勢こそが顧客から絶大な信頼を集める所以なのだと、FastGrowは確信を持っている。
カミナシ──「ニーズがない…悩んだ末のピボット。その結果、事業が加速した」

2023年3月29日にシリーズBラウンドで約30億円の資金調達を実施したカミナシ。(参考)
同社は、全国に約3,900万人といわれるノンデスクワーカー(食品製造や飲食、ホテルなど現場で働く人たち)の業務を効率化する現場プラットフォーム『カミナシ』を展開している。すでに導入現場数は、累計7,000ヶ所以上に及ぶ。
一見、順調に事業を拡大してきたかのように見えるカミナシだが、かつて苦難の末、ピボット(事業転換)していることを読者はご存じだろうか?ここでは、今のビジネスモデルに至るまでの道のりを紐解きたい。
カミナシ代表の諸岡氏は、リクルートを経て、空港やホテルの総合管理、ビル清掃業、食品工場などの事業を展開する実家の会社に入社した。だが、各現場では、当たり前のように“紙”ベースで業務が行われており、アナログな作業が深夜まで続くことも…。
現場の環境を変えたい──。そこで諸岡氏は、あえて食品工場のバーティカルSaaSというニッチな領域にターゲットを絞り、2016年12月、カミナシの前身となる会社を設立。ところが、実際に事業を進めていくとターゲットとしていた市場は想定していたよりも遥かに小さく、自身が望む事業成長は得られなかった。
このままではいずれ事業が立ち行かなくなる。本来ならば、いったん立ち止まって市場を選定し直すべきなのかもしれない。だが、「食品工場の生産性向上と、労働環境の改善」というビジョンに共鳴して集まったメンバーや投資家がいる中、今さら道を引き返すことはできずにいた。では、その状況からどうやって抜け出すことができたのか?
きっかけになったのが、創業3年目、共同創業者の何気ない一言だった。「諸岡さん、もう今の事業はやめて、違うことをしませんか」と。自分からピボットを言い出せずにいた諸岡氏は、その言葉に背中を押されるように現状を素直に認め、別の方向に踏み出すことができたのだ。
諸岡氏は過去取材の中で「負け続けた3年間だった」とその心情を吐露している。だが、その3年間は決して無駄ではない。事実、現プロダクト『カミナシ』では、過去の失敗を活かし、幅広い業界で利用できるようになっている。
食品工場のバーティカルSaaSから、どんな現場でも使えるホリゾンタルSaaSへの転換。その判断が功を奏し、事業を軌道に乗せることができたのだ。
Relic──「地図を描くだけの第三者では、新規事業は導けない」

技術の進歩や社会のニーズの変化により、世の中は著しく変化している。いまや新たな開発やイノベーションに取り組まなければ、企業は現状維持すら困難だと言われる時代だ。その中で、「新規事業×コンサルティング」という独自のポジショニングを築き、大企業からスタートアップまでの新規事業開発支援に取り組んでいるのが、Relicである。
Relicの事業は大きく3つ。1つ目は、新規事業開発やオープンイノベーション支援に特化したSaaS型のプラットフォームやテクノロジーを提供する「インキュベーションテック」。2つ目は、新規事業開発やオープンイノベーションの戦略立案から実行、プロダクトやサービスの開発、グロースまで一気通貫で支援する「事業プロデュース/トータルソリューション」。そして3つ目が、投資やJV、協業を通じて事業を共創する「オープンイノベーション」だ。
創業から8年、新規事業開発という領域においてトップクラスの規模や成長率を実現してきたRelic。だが、北嶋氏が現在のビジネスモデルに辿り着いたのには、前職「コンサルタント」や「事業責任者」として感じていた課題意識が大きく影響していた。どういうことか。
一般的に「新規事業開発の支援」と言えばコンサルティングファームが想起されるだろう。だが、コンサルティングファームの実態を紐解けば、外部の立場や視点からの「戦略立案」などに留まり、事業の立ち上げや成長にコミットできていないケースが少なくないという。
しかし、新規事業開発というのは、事業戦略や企画の立案だけではない。仮説の検証や、プロダクトの開発、改修。他にも社内の調整や他社との連携など、泥臭い仕事もこなしながら事業を推進していかなければならない。
「それら(現場の苦労)に寄り添えず、地図を描くだけの第三者では、新規事業は導けない」「クライアントに寄り添い、新規事業開発を上流から下流まで支援する存在が必要なのではないか」。
そこでRelicは、当事者意識を持って新規事業開発を行える人材を「事業プロデューサー」とし、全体の最適化を意識しながら戦略と実装ができる少数精鋭チームを形成する。
あくまでも、外部からの部分的な支援やリソースの「手段」としてではなく、新規事業やイノベーションの共創という「目的」に対してコミットする。そんな“事業共創カンパニー”としてソリューションを提供できる体制を構築したのだ。
詳しくはぜひ下記の記事を読んでもらいたい。
こちらの記事は2023年05月31日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
山田 優子
編集
大浜 拓也
株式会社スモールクリエイター代表。2010年立教大学在学中にWeb制作、メディア事業にて起業し、キャリア・エンタメ系クライアントを中心に業務支援を行う。2017年からは併行して人材紹介会社の創業メンバーとしてIT企業の採用支援に従事。現在はIT・人材・エンタメをキーワードにクライアントWebメディアのプロデュースや制作運営を担っている。ロック好きでギター歴20年。
おすすめの関連記事
現場にいる者こそが、意思決定者──年次も経験も関係ない!UPSIDERで非連続成長を担うのは「一次情報を最も知る者たち」だ
- 株式会社UPSIDER 執行役員 / VP of Growth
マイベスト、実は前代未聞の“データプラットフォーム企業”だった──「あの企業の“実は”ここがすごい」Vol.2
VCも起業家も、“常識外れ”な挑戦がまだ足りない!大企業コンサルやデータ基盤提供に加え、ビルや街まで構想する「欲張り」なVC・HAKOBUNE木村・栗島の構想とは
- HAKOBUNE株式会社 Founding Partner
FinTech×EC支援で事業を連続創出できる理由とは?BASEのツーサイドプラットフォームに魅せられた山村・髙橋の躍動を追う
- BASE株式会社 上級執行役員COO
個人やスモールチームの可能性を最大限に広げるプラットフォームへ─GMV1,500億円超もまだまだ成長途上。BASEでさまざまなBizDevに挑戦できる理由とは
- BASE株式会社 BASE事業 Business Management Division Manager
2倍成長を続けるTOKIUMに学ぶ「最強のオペレーション戦略」とは──「壮大・緻密・柔軟」の3要素で、BPaaSとしての成長を実現した秘訣
勝ち筋は「国産の生成AIミドルウェア」にあり──Vol.1 miibo CEO功刀雅士氏【寄稿:DNX Ventures新田修平】
- 株式会社miibo 代表取締役