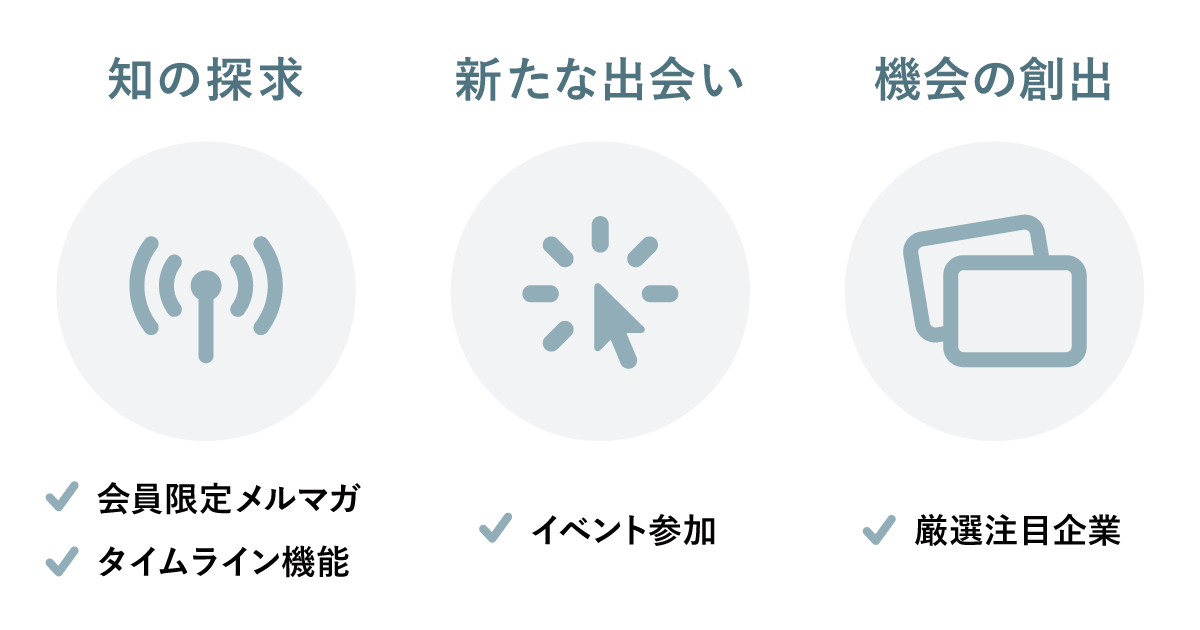「中長期的な非連続成長の基盤」を、エンプラ支援・協業でつくる!──4社を厳選、注目すべき急成長スタートアップの事例まとめVol.2
顧客(ユーザー)をどのように定め、どのように展開していくか。その戦略は、企業によって千差万別、さまざまな工夫が凝らされてきた。だが、実際に取り組む中で、非常に大きなインパクトのある事例を実現したり、レバレッジを効かせて非連続的な拡大を実現したり、と言ったことを考えるのならば、いわゆる“エンタープライズ”とどのように手を組むかこそ、重要となるだろう。
読者からのニーズも多かったこの観点について、以前まとめたVol.1に引き続き、さっそくVol.2としてスタートアップ4社の事例を改めてまとめてみた。その中で見えてきたのは2点。一つは、「これまでの急成長を生み出したカギが、エンプラへの対応だった」ということ。そしてもう一つは、「これから描く壮大なビジョンは、エンプラとの関係性によって生み出されていくのだろう」という期待だ。
FastLabel、PKSHA Technology、hacomono、OLTAという4社の事業戦略に、学ぶことは多い。事例も含め、じっくり読んでみてほしい。
エンプラの定義は「国内時価総額トップ100」──FastLabel
次に紹介するFastLabelも、サービス正式リリース後わずか1年半というスピードで、ソニーグループやトヨタグループをはじめとした国内最大手の企業に導入実績を誇るスタートアップだ。
そんなFastLabelのエンタープライズ企業の定義とは、AI開発に積極投資できる日本法人(従業員3万名以上目安)、さらに具体的にいえば「国内時価総額トップ100の企業」だという。
ただし、同社が挑むのは、一般的な「AIスタートアップ」というワードから想起される 「アルゴリズムの開発」ではない。AI戦争の鍵を握る“もう半分”の市場と言われる「アノテーション」という領域を主戦場としており、既に国内リーディングカンパニーとしての一角を築いている。
「アノテーション」についてご存知ない読者は、同社代表がそのポテンシャルについて言及したこちらの記事を参照いただきたいが、一言でいうと、「*AIに学習させるための教師(正解)データを作成する作業」だ。
*例:「街中の写真からクルマや人をAIに検知させるサービスを作ろう」と考えたとき、“これがクルマ”、“これが人間”といったように、データ一つひとつにラベルを付けて、AIに学習させるデータを準備するプロセス。
先に挙げたような国内最大手のエンタープライズ企業への導入実績にしては、派手さがない?侮ることなかれ。アノテーションとは「世の中に水がなければ困るのと同様、AIが市場さらに盛り上がる中で絶対になくてはならない“データ”を担う存在」である。
しかし、米国などのAI先進国に比べ、AI後進国と言われる日本において、このアノテーションという領域は“プロダクト単体”だけでは解決できない。なぜなら、アノテーションは未だにアナログに行われているのが主流であり、さらにはアノテーション専門人材が不足しているため、高品質な教師データを大量に作ることができないからだ。これら状況に加え、多くの企業では未だアノテーションに関するシステム基盤がなく、テクノロジーが介入する余地も非常に大きい。
そこでFastLabelは、AIプロジェクトに専門性を有するプロジェクトマネージャーと専門教育を積んだアノテーターによる高品質なアノテーション代行と、SaaS型AIデータプラットフォーム『FastLabel』の提供という両輪でAI開発企業を支援している。

BPOサービス事業とSaaSプロダクト事業を両輪で回していることこそが、国内屈指の企業から支持を得る所以と言える。多くの企業がAI開発プロセスの入り口であるアノテーションにつまずくことが多く、アウトソーシングやシステムで効率化したいというニーズが顕在化しているのだ。
事例を詳しく見てみよう。デンソーはミニ房トマトの自動収穫ロボットを開発するプロセスにおいて、房の位置や、切断点を検出するためにAIを用いていた。しかし、ソフトを開発するエンジニアがアノテーションに従事していたため、リソースが不足するという深刻な課題を抱えていた。
そこで、SaaS型AIデータプラットフォーム『FastLabel』の導入により、アノテーションデータをクラウドで一括管理し、開発効率を向上。また、BPOサービスも並行して利用することにより、リソース不足も解消した。結果的に、ソフトウェアの開発のサイクルスピードが格段に向上したのだ。画像認識の性能という観点でも、20ポイント(30%)近く向上が見られたことも忘れてはいけない。
もちろん、FastLabelのユニークネスは上記に挙げたBPOサービスに止まらない。日本人 × 非エンジニアでも利用しやすいUI/UXを追求している点や、PoC(スモールスタート)、共同開発提案も可能といった点も評価を集める所以だ。
先に触れたソニーグループやトヨタグループ(デンソー他)だけでなく、通信、インフラ、総合電機、医療、製薬、建設といったさまざまな業界のエンタープライズ企業で導入が進んでいる。

そんなFastLabelは、これまで紹介した「アノテーション事業を展開する会社」ではなく、「アノテーションからモデル開発に至るまで、AI開発プロセス全体の顧客体験を変える会社」へと現在進行形で変化を遂げている最中だ。
同社がこれまで培ってきたノウハウや技術力を活かし、時価総額トップ100の企業と、デファクトスタンダードをつくり挙げていく過程をFastGrowでも注目していきたい。
合わせて読みたいページ
エンタープライズ企業にフォーカスしたAI SaaSの圧倒的成長──PKSHA Workplace
三菱商事、三井不動産、セブン&アイ・ホールディングス、国土交通省……と、名だたる大企業・官公庁への導入実績を積み重ねているベンチャー企業がある。PKSHA Technologyだ。今回はそのグループ内でAI SaaSを展開するPKSHA Workplaceの事例に迫る。
連結従業員数は400名を超え、2022年9月期連結決算での売上高は115億円と拡大しつつも、PKSHA Workplace自体は少数精鋭とも言える規模。そんな陣容で、大手企業に負けないシェアの獲得や導入実績を残している。
PKSHA Technology採用資料から引用(※そのため、PKSHA Workplaceだけでなく、グループ全体の実績)
事例を詳しく見てみよう。大手商社・三菱商事が「Digital Workplace構想」として全従業員を対象に行っている「あらゆる業務のデジタル化」において、重要な役割を担ったのがPKSHAのソリューションだ。大企業も含め10社のコンペを、PoCで示したAIの高精度によって勝ち抜いた。そうして社内の問合せ窓口をAIチャットボット化し、リリースから約2ヶ月で月間3,000~3,500名のの利用を実現している(事例記事はこちら)。
本格導入時には認証基盤システムとの連携をじっくりと進め、具体的な社内運用を視野に、きめ細かなサポートで対応。もちろん、AI精度がさらに向上していることも、満足度につながる重要な部分だ。
これにより、商社で働く人材一人ひとりが、新たな事業を構想するための時間をさらに捻出していくことが可能になる。日本経済に与えるインパクトが、じわじわと大きくなっていくだろう。
また、KDDIエボルバの事例では、社内問合せ窓口(ヘルプデスク)に対して『PKSHA AI ヘルプデスクfor Microsoft Teams』を提供。このプロダクトは、Microsoft Teams上でシームレスに連携する有人チャット・ヘルプデスク・FAQ自動生成・チャットボットを提供するもの。Teamsを利用している大企業にとっては非常に受け入れやすいかたちとなっている。従業員の利用は爆発的に増え、社内問合せの電話受付を完全廃止するに至っている。大企業の現場で、なくてはならない存在となり、本質的な全社のDXに貢献している。(事例記事はこちら)。
前述の国土交通省における導入事例も同様に、Teamsと合わせてPKSHAのプロダクトを活用したものだ。導入担当者が「精度の高さは圧巻でした」と振り返る(事例記事はこちら)。
さて、ここまでに触れた「AIの精度」については、PKSHA Technologyグループが東京大学・松尾豊研究所から生まれたこと、そして5,500万を超えるユーザーの学習データを基にしていることなどがその背景にある。また、開発スピードも特徴的で、わかりやすい例で言えば『PKSHA AI ヘルプデスク for Microsoft Teams』はすでにChatGPTとの連携を開始しており、2023年3月には大規模言語モデルの社会実装を加速させる『PKSHA LLMS』をリリースした。
PKSHA Technologyが持つ技術力との連動も活かし、業種・業界を問わずあらゆるエンタープライズを対象に、R&D・ソリューション・プロダクトとさまざまなビジネスモデルで価値提供を広げている。つまりホリゾンタルに研究開発と事業開発の取り組みを進めている。一方で、教育機関や金融機関といった注力領域においては、バーティカルに掘り下げるチームも設置している。
このように、どの事業においてもエンタープライズへの価値提供が重視されるため、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスといったポジションすべてで、ホリゾンタルへの幅広い知見と、エンタープライズへの深いナレッジが求められる。公表されている導入事例を読むだけでも、非常に多くの学びがあるだろう。
合わせて読みたいページ(再掲含む)
FastGrow『【PKSHA上野山】AI×SaaSが高成長を続ける理由を、「共進化」に学ぶ──創業からの事業展開ヒストリー』
事例記事『三菱商事株式会社 ― 全従業員への展開、Digital Workplace構想で余白時間を作り出す』
事例記事『国土交通省 中国地方整備局 ー 働き方改革の基盤整備を促進、Teams × AIチャットボットによるインフラDX | エンタープライズ向けAI SaaS』
業界大手のほぼ全社に導入進む圧倒的シェア──hacomono
2022年に取締役COO平田英己氏のインタビューで明かされた「業界大手総合フィットネスのトップ10社のうち9社が顧客である」という驚きの事実。ここに、hacomonoというスタートアップが急成長を続けている背景が見える。
フィットネスジム向け基幹システムとなるSaaSを展開する同社は、当初から大企業への導入に注力し、「Must Have」なプロダクトをつくり上げようと腐心してきた。その結果として、前述の圧倒的シェアを実現している。平田氏はその強みを、こう表現する。
チャーンレートがとても低いんです。店舗ごとに細かく見ても、キャンセルする店舗はほぼありません。明かしてしまうと、ゼロにならない理由は、「業界からの撤退」があるためなんです。だから実質、プロダクトに不満があっての解約はゼロです。
客観的に見ても、プロダクトが圧倒的に強いとわかります。
──FastGrow『BizDevとは、“接点”の創出と最大化である──ウェルネステック急先鋒・hacomonoのCOO平田と、産業変革の心得を考える』から引用
では、どのような提供価値に注力しているのか?そのビジョンが見えてくるのが、このスライドだ。「Whole Product戦略」と名づけ、顧客体験・スタッフ体験の向上を念頭に置いた開発を進めている。特に平田氏も強調していたのは、「フィットネスジムのスタッフ」の業務を支援対象としながらも「顧客体験が良くなるもの」を常に優先度高く開発するという考え方だ。
導入事例も見てみよう。ただ、スタンダードなかたちは、会員登録や入退館といったまさに“基幹”と呼べる部分をスムーズに行う部分での導入となるため、紹介しても内容がやや地味になってしまう。そこで、「大手企業が新規サービスを始める」という大きな価値を提供した2事例を見ていく。
コナミスポーツは、新たなサービスとしてオンラインフィットネスのレッスン提供を始める際に、hacomonoのプロダクトを活用した(事例紹介ページはこちら)。「直接ジムに通う」以外の選択肢をエンドユーザーに提供し、それによってコナミスポーツクラブの新展開をスムーズに実現したという点で、象徴的な事例と言えるだろう。
同様に大手企業のルネサンスは、すでに提供していたオンラインエクササイズレッスンの基盤としてhacomonoを導入し、リニューアルを図った(事例紹介ページはこちら)。従来のシステムとAPI連携を進めることで、既存会員に対しては安価なプランを提供したり、Zoom発行をスムーズに行ったり、レッスン参加状況を会員情報と紐づけて管理できるようにしたりと、さまざまな付加価値を感じられるよう設計されている。
まさに「痒い所に手が届く」というようなプロダクトを実現していることから、こうした事例が増えているのだと考えられる。
さらに今後はフィットネス企業だけでなく、スポーツ関連のスクールや公共施設への導入を進めつつ、町全体(つまり行政)を対象とした「社会インフラ」としての展開を進めていく。
今後、どのような事例が出てくるか、さらに注目してみていきたい。
金融機関との提供多数、「安心」のプロダクト展開の理由は──OLTA
2023年6月に約25億円の資金調達を発表したOLTA。「クラウドファクタリング」というビジネスを国内でいち早く実現し、あらゆる中小・零細企業の運転資金需要に応えるプロダクトを提供している。
そのグロースのカギとなったのが、金融機関との提携だ。いわゆる“エンプラ”とは異なると見る向きもあるとは思うが、これだけ全国規模で提携を進められるスタートアップはそう多くないであろうことから、最後に取り上げたい。
資金調達リリース時には提携数28へと増えている
国内でオンライン型ファクタリングを提供する法人として、この提携数はNo.1だという。もちろん、まだまだ拡大予定だ。その結果として、サービス提供開始から5年弱で、ユーザーから合計1,000億円以上のファクタリング申し込みを受けている。
なお、OLTAが進めるのは金融機関との提携だけではない。この2023年5月には、ジェーシービー(JCB)との資本業務提携も発表。クラウドファクタリングではなく、SMB向け入出金管理プラットフォーム『INVOY』において、JCBカードとのシームレスな連携が可能となった。さらに今後、さまざまな提携が検討される。
JCBはさらなる事業成長を見据え、法人向けサービスの拡充を進めている。そんな中で、OLTAの理念やアントレプレナーシップに強く共感し、パートナーとして選定したわけだ。そんな熱い想いが見てとれる代表取締役会長浜川一郎氏のコメントも掲載されているので、プレスリリースも是非一読してみてほしい。
OLTAは今後、資金繰りだけでなく、経営をより広く支援する企業となるべく、プロダクトやサービスの拡充を進める方針だ。その中で、金融機関やJCBを始めとした大きなアセットを持つパートナーとの提携は、さらに大きなレバレッジとなっていくであろう。展開を注視していきたい。
こちらの記事は2023年06月23日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
おすすめの関連記事
マイベスト、実は前代未聞の“データプラットフォーム企業”だった──「あの企業の“実は”ここがすごい」Vol.2
VCも起業家も、“常識外れ”な挑戦がまだ足りない!大企業コンサルやデータ基盤提供に加え、ビルや街まで構想する「欲張り」なVC・HAKOBUNE木村・栗島の構想とは
- HAKOBUNE株式会社 Founding Partner
FinTech×EC支援で事業を連続創出できる理由とは?BASEのツーサイドプラットフォームに魅せられた山村・髙橋の躍動を追う
- BASE株式会社 上級執行役員COO
個人やスモールチームの可能性を最大限に広げるプラットフォームへ─GMV1,500億円超もまだまだ成長途上。BASEでさまざまなBizDevに挑戦できる理由とは
- BASE株式会社 BASE事業 Business Management Division Manager
2倍成長を続けるTOKIUMに学ぶ「最強のオペレーション戦略」とは──「壮大・緻密・柔軟」の3要素で、BPaaSとしての成長を実現した秘訣
なぜ「美容医療」市場で、メルカリ並みのtoCサービスが生まれるのか?MGP長澤氏とトリビュー毛氏が語る、toCプラットフォーム急成長・3つのカギ
- MINERVA GROWTH PARTNERS 創業パートナー
勝ち筋は「国産の生成AIミドルウェア」にあり──Vol.1 miibo CEO功刀雅士氏【寄稿:DNX Ventures新田修平】
- 株式会社miibo 代表取締役