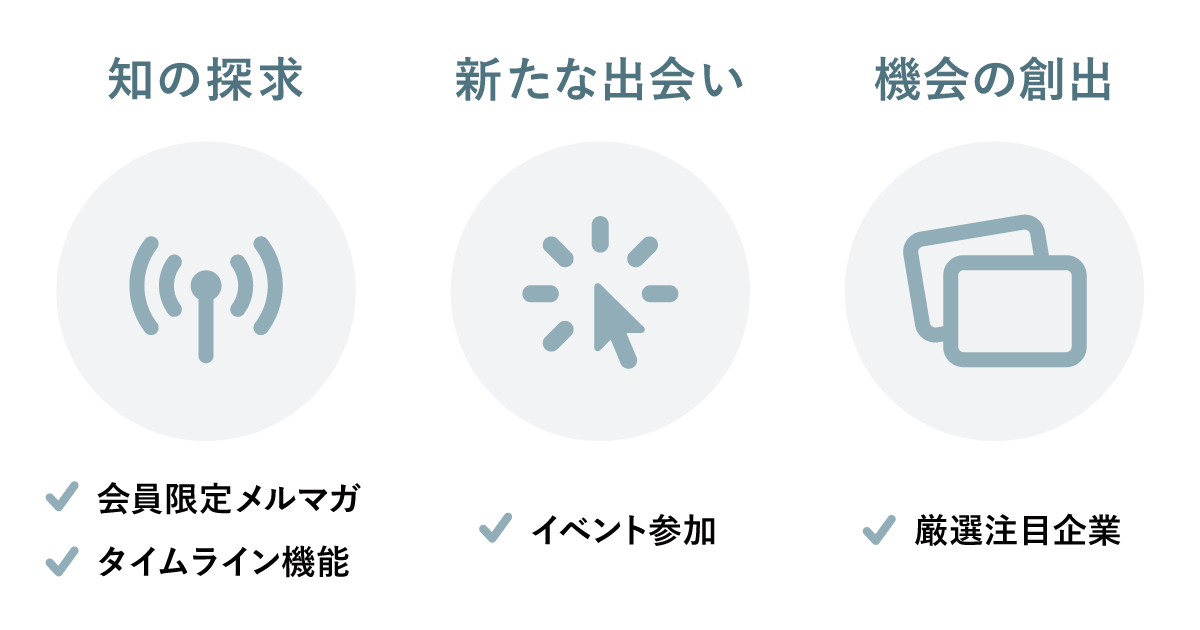“入社直後の体験”を高速進化させるオンボーディング術──その最前線で奮闘する3人の対話から紐解く、STUDIO ZERO流「入社後活躍」と「心理的安全性」の両立法
Sponsoredスタートアップの急成長フェーズで直面する最大の課題の一つが、優秀な人材の獲得と、その潜在能力を最大限に引き出すタレントマネジメントだ。規模の拡大スピードに組織の成熟度が追い付かず、個人と組織の間で齟齬が生じるのは珍しくない。多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルたちをいかに共創へと導くか。採用と育成、マネジメントの再定義が急務となる。特に採用後の組織への受け入れ方法や体制は、どの企業でも課題を感じているのではないだろうか。
これらの課題に、独自のアプローチで挑戦を続けているのがプレイドの事業開発組織『STUDIO ZERO』だ。メンバーの自律性や多様性を重んじながら、個人と組織のミッションをすり合わせて組織としての一体感を保ち、スピードとパワーが発揮できる文化。その文化を体現し続けるための仕組みの一つにあるのが、進化を続ける「入社オンボーディング」だという。
新メンバーの立ち上げ支援にとどまらず、ベテランの学び直しにも活用される柔軟なオンボーディングシステム。メンバー一人ひとりの個性に寄り添った知見とノウハウの詰まったその仕組みは、入社するメンバーの声を取り入れながら常に進化を遂げている。メンバー主導で改善を重ねることで、オンボーディングシステムは組織内の共通言語となっているのだ。個人の成長と組織の変革を同期させる鍵は、現場の声にこそある。
事業の立ち上げと成長に注力しながら、いかにしてチームビルディングのサイクルを回すのか。組織の急拡大期に直面する難題を、どう克服していくのか。事業現場のみならずオンボーディングシステムの最前線に立つ3人の対話から、STUDIO ZERO流の人材育成術の神髄に迫る。
- TEXT BY KANA MAKINO
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
多様性を強みに変革を加速するSTUDIO ZERO
プレイドが2021年4月に立ち上げた事業開発組織STUDIO ZERO。立ち上げ初年度からめざましい成長を遂げ、その勢いは年々加速している。2024年度においても、年間の事業目標を前倒しで達成するなど、まさに勢いに乗っているチームだ。組織の規模拡大も順調に進んでおり、変革の真っ只中にある。
そんなSTUDIO ZEROには、これまで歩んできた道のりも、得意分野も大きく異なる多様なメンバーが集結している。
人事・広報畑を歩んできた秦野優子氏、SaaSビジネスで顧客の営業変革を支援してきた前垣円花氏、行政機関を経てアーリー期のスタートアップを経験した小坂優希氏。一見すると接点のなさそうな彼女たちが、同じチームで日々の業務に携わっている。

秦野多分普通に生活してたら同じ部署にはならないだろうなって人でも、その垣根を越えて一緒にプロジェクトに取り組むことが多いんです。これまでのキャリアは私が主に人事で、前垣さんが主に営業だったら、普通なら部署は違いますよね。同じ組織に、違う背景や哲学が混じり合い、ビジョンに向かって協働する。それがSTUDIO ZEROです。
人事のスペシャリストとしてのキャリアが長い秦野氏にとって、営業の最前線で活躍してきた前垣氏と机を並べ、時には同じプロジェクトを近い立場で進めるというのは、これまでにない刺激的な体験であろう。
交わることの少ない多様な価値観が日常的にぶつかり合う。その一例として印象的だったのが、この取材の場で改めて交わされた「売上や利益に対する捉え方の違い」についてのやり取りだ。行政機関職員からアーリーフェーズのスタートアップへ転身した来歴を持つ小坂氏が、凛とした口調でこう語る。
小坂語弊を恐れずに言えば、私は金銭的な利潤の追求にはあまり興味がありません。お金そのものに大きな意味を感じないからです。むしろ人生や組織のあり方を考える上で重要なのは、「何をしたいのか」という根本的な問いだと思うんです。
ただ儲けるだけでは、人も組織も本当の意味では成長できない。もちろん、利益を無視するわけではありません。事業を通じて社会全体の利益につながる価値を生み出していくことが肝要だとするスタンスをとっています。
小坂氏の淡々とした物言いからは、行政の世界で培ってきた確固たる価値観が伝わってくる。一方で、営業経験の長い前垣氏は売上というものに対して、全く逆の価値観を語り始める。
前垣小坂さんとは対照的ですが、私は売上が大好きなんです(笑)。何故かというと、売上はお客様に提供した価値の証だと考えているからです。
売上は価値の総和であり、利益は工夫の総和である、という言葉がありますが、まさにその通りだと思います。お客様の役に立つ価値を提供できれば、売上は伸びていく。お客様の売上を最大化することが、ひいては自社の成長にもつながる。つまり、顧客や自社の売上が上がるということは、それだけ世の中に価値を創出できた証なのです。だからこそ、売上をつくるための営業活動が大好きなんです。

利益を追い求める者もいれば、そうでない者もいる。STUDIO ZEROには多種多様な価値観が混在している。
だが、そんな一見相反する思考が、絶妙に響き合うことがある。前垣氏の「売り上げは価値の総和」という発言を聞いた小坂氏は、大きく頷きつつ次のように語った。
小坂前垣さんが「売り上げは価値の総和」だって話をしてくれた時「私とは真逆の考え方だけど、めちゃくちゃ面白い!」って直感的に思ったんです。違いを拒絶したり、合わないと感じたりするのではなく、むしろ好奇心が沸々と湧いてきて、まるで留学に来たかのような新鮮な気分になりました。
前垣小坂さんの言葉を聞いて、「売上は価値の総和」という私が大切にする考え方が、真逆に近い考え方を持つ人と、むしろ相互理解や共感につながることもあるんだと気づかされました。違いがあるからこそ、互いの視点に興味を持ち、理解を深められる。「留学生のような新鮮な気持ち」、すごく理解できる気がします(笑)。
自分とは正反対の意見でも、それを純粋に面白がり、学ぼうとする姿勢。その柔軟性こそが、多様性を支える秘訣なのかもしれない。
小坂そもそも、どちらの考え方が正しいかなんて議論する必要はないと思うんです。私自身は金銭的な利潤の追求には個人的な関心が強くありませんが、前垣さんのように売上の最大化にこだわるメンバーがチームにいることを心強く感じています。お互いの価値観の違いは当然のことであり、それを認め合えるからこそ、STUDIO ZEROは居心地がいいんですよね。
互いの違いを認め合い、時には衝突しながらも、それを強みに変えていく。そんな光景が、ここでは日常茶飯事なのだ。
秦野一般的に組織って、営業や人事、広報といった同じ経験や知識を持つ人たちが集まりがちじゃないですか。でもSTUDIO ZEROは全然違う。本当にいろんなスキルや経験を持つ人たちがワイワイやってる感じ。だからこそ、型破りなことにも挑戦できるんだと思います。
各分野のプロフェッショナルが垣根を越えて集うこのチームでは、既成概念に縛られない斬新なアイデアが飛び交っているに違いない。
そんなSTUDIO ZEROの使命について、小坂氏は熱を込めてこう語る。

小坂もうそろそろ、この国も変わって欲しいなって思うんです。でもそれを一体誰が担うのか──。
今の資本主義の枠組みに依存していては限界があるでしょうし、かといって行政だけで変化を起こそうとするのも難しい。だからこそもっと別の方法を探るべきだと思うんですよね。多様な才能を持つ人たちが集まって、一緒に解決策を見つけていく。STUDIO ZEROの掲げる大それたミッション「産業と社会の変革を加速させる」には、そんな意味が込められているんじゃないかな。
小坂氏の言葉からは、大きな使命感と、それに挑む強い意思が感じられる。
メンバーたちの多様な個性を糧に、社会の変革に挑むSTUDIO ZERO。個性を存分に発揮しながらも、統一された理念のもとで協働するには、“共通言語”とも言うべき仕組みが不可欠だ。そのための強力な武器となっているのが、独自の入社オンボーディングシステムである。メンバーの成長と組織の進化を同時に実現する、その秘訣に迫っていきたい。
しかし、その前に一つ見逃せない視点がある。STUDIO ZEROのミッションは、単に組織内部の変革に止まらない。むしろクライアントとの共創を通じて、産業や社会の変革をこそ加速させることが、彼らの存在意義なのだ。次章では、“スタジオとしての顔を持つ”チームが、どのようにしてクライアントに価値を提供しているのかを探っていく。
クライアントとの共創を通じた価値提供
STUDIO ZEROは、その名の通り、クライアントとの共創を通じて新たな価値を生み出す“スタジオ”としての役割を担っている。
小坂私たちの仕事は、クライアントの変革を後押しするための“スタジオ”のようなものだと捉えています。いろんな機材や人材が揃っていて、それらを駆使してクライアントの課題解決に取り組む。まさに“スタジオ”という名称がピッタリなんです。強いて言えば、スタジオという箱の中に留まらず、もっとオープンな場所、例えば公園のようなイメージも私は持っていますけどね。
“スタジオ”というと、どこか閉鎖的な空間を連想してしまうかもしれない。だが、STUDIO ZEROは常に外に開かれた存在でありたいと考えているようだ。
小坂スタジオに来たクライアントの魅力を最大限に引き出すのが、我々の仕事。より輝いてもらうために、時にはスタジオの外に連れ出すことだってあるかもしれません。そういう意味で、私たちはクライアントとともに共創するスタジオなんだと思います。STUDIO ZEROという名前には、そんな思いが込められている気がするんです。
秦野私が好きな言葉に「チェンジエージェント」というのがあるんです。クライアントの変化を加速させるための触媒みたいな存在ですよね。単にサポートするだけじゃなくて、もっと能動的に関わっていく。そういうスタンスがSTUDIO ZEROにはあるんだと思います。
クライアントの変革に寄り添い、ときに先導する。そんな使命感を胸に、日々の仕事に臨んでいるのだ。
しかし、変革の道のりは決して平坦ではない。一朝一夕に成果を出すことは難しく、長期的な視点を持って取り組む必要がある。その点について、小坂氏は採用面談の場でこんな話を聞いたという。

小坂入社前の面談で、「STUDIO ZEROでは、スプリントではなくマラソンを走っているんだ」と教えてもらったんです。
例えば事業の期間を、12ヶ月ではなく18ヶ月を一つの区切りとして捉えている。半年かけて種をまき、その後の1年で結果を出す。そういうサイクルを回している、と。長期的な目線を持って、腰を据えて取り組んでいるんだと感じました。
秦野氏も、STUDIO ZEROの代表である仁科氏の姿勢に触れながら、組織の長期的な展望について言及する。
秦野仁科は常に課題意識を持ち続けていて、例えば「人的資本経営をSTUDIO ZEROの中で実現するためには何が必要か」みたいなことをずっと考えているんですよね。
普段のSTUDIO ZEROはとにかくスピード感がある。でも、そういった難しいテーマに関しては、むしろ腰を据えて中長期的に取り組もうとしている。もちろん、並行して目の前の案件もバリバリこなしていくんですけどね。メリハリをつけて、長期と短期のバランスを取っているんだと思います。
大手企業の成熟した事業であれば、「18ヶ月」という時間軸で物事を捉えるのは当然のことかもしれない。だが、まだ30名ほどの組織規模であるSTUDIO ZEROが、現段階でそのような長期的視座を持とうとしている点は注目に値するだろう。
クライアントの変革支援には継続的コミットメントが不可欠であるがゆえ、短期的な成果主義に陥ることなく、あえて「18ヶ月」の時間軸で物事を思考しながら先手を打っていく。そのスタンスこそ、“STUDIO ZEROらしさ”を体現していると言える。
だからこそ、クライアントとの強固な信頼関係を築くことに力を注いでいるのかもしれない。訪ねていくだけでなく、スタジオに招き入れたり、時にスタジオの外に連れ出したりしながら、ともに手を携えて変革の道を歩むのだ。
では、STUDIO ZEROという組織を支え、進化させ続けている原動力は何か。次章では、その鍵を握る「オンボーディング」に焦点を当て、個人と組織が共に成長するための仕組みを探っていく。いかにしてメンバーの多様性を活かしながら、皆が同じビジョンのもとで協働する組織カルチャーを育んでいるのか。その秘密に迫る。
個の強みを引き出すオンボーディングの誕生
仁科氏は、事業の急成長に伴い、今後ぶつかるであろう組織の壁を意識し、早期にオンボーディングシステムを確立することの重要性を強く認識していた。多くの組織では、その整備が後手に回りがちだ。さらに、その内容もトップダウンで決められることが多い。
しかし、STUDIO ZEROでは異なるアプローチを取っている。まだメンバーが10〜15名ほどの段階で、つまり新たな仲間が継続的に加わり始めた時点で、いち早くオンボーディングチームの発足に踏み切ったのだ。しかも、その運用を担うのは、オンボーディングを受ける当事者と、受けたばかりの入社数ヶ月のメンバーたち。この点はまさに、ユニークな部分と言えるだろう。
組織の規模拡大と分業の進展を待つことなく、オンボーディングの重要性を見据え、当事者主導で立ち上げる。そんなSTUDIO ZERO流のアプローチについて、現在チームメンバーの一人である前垣氏は振り返る。
前垣もともとSTUDIO ZEROでは、採用スピードをそこまで上げていなかったんです。それが2023年の後半に入り、事業拡大に伴って新卒採用や中途採用を加速させることになった。2024年の1月以降は、私も含めて月に4~5名ものペースで新メンバーが入ってくることが見込まれて、その受け入れ体制の整備が喫緊の課題として浮上したそうです。
そこで、2023年10月にオンボーディングチームを立ち上げることになったんですよ。
新メンバーの入社ペースが一気に拡大するようになった3ヶ月前から、オンボーディング・プログラムの作成と並行して、プログラムをテスト運用するためのチームも徐々に組成されていったという。
試行されたのは、既存の研修プログラムの踏襲ではない、独自色あふれるオンボーディングシステムだった。各メンバーの強みを活かしながら、新たなプログラムが構築されていったのである。
秦野オンボーディングの内容は、言ってしまえば至ってシンプルなんです。入社後に行うべきタスクを可視化し、To Doリスト化することで、もれなくかつ効率的に習得できるようにしているんです。
でも、肝心なのはオンボーディング自体が目的化しないこと。あくまでもこれは「助走」に過ぎません。本当の目的は、一人ひとりの経験やケイパビリティを存分に発揮し、活躍してもらうこと。だからこそ、その助走期間をいかに効果的に、そしてスピーディーに進められるかが勝負なんです。
そのためにも、オンボーディング設計や改善は入社直後の有志メンバーが担うのが一番だと考えています。当事者目線で、本当に必要なエッセンスを凝縮できますから。
この取り組みの立役者の一人が、小坂氏だ。2024年3月に入社した小坂氏は、1月入社のメンバーとタッグを組み、オンボーディングの新たな設計に携わったのだ。
前垣オンボーディングで活用する新たなコンテンツを作っていた際の動きを見て驚きました。小坂さんは情報をまとめるスピードが速く、内容も的確なんです。誰が見てもわかりやすい資料を、あっという間に作り上げてしまう。
まるで畑を耕すみたいに、土台づくりをしながらコンテンツを磨き上げていく感じですね。
小坂私はそれを「草むしり」って呼んでるんです(笑)。まさに、畑を整えるイメージですかね。
STUDIO ZEROのオンボーディングが際立っているのは、メンバー一人ひとりのこれまででの経験を存分に活かせる環境が整えられている点だ。

秦野それぞれのバックグラウンドをすごく尊重してくれるんです。「前の会社ではそうだったかもしれないけど、ウチではこうだから」と押し付けることはありません。
例えば、「リクルートではこういうケースにどう対応していましたか?」と、私の前職での経験を、メンバーが率先して聞いてくれるんです。自分がこれまで積み重ねてきたキャリアや、培ってきたケイパビリティを、改めて「本当に価値があるんだよ」と認めてもらえる。そんな風に、一人ひとりの強みを引き出して全体にも活かそうとする姿勢が、STUDIO ZEROにはあるんですよね。
前垣そうですね。みんな今までのキャリアをベースに、得意分野から着実にプロジェクトを進めていく。自分なりの強みを遺憾なく発揮できる場所なんだと思います。
小坂ここでは、一人ひとりがこれまで積み重ねてきたキャリアが何より尊重されるんです。その延長線上で、得意分野から着実にプロジェクトを進めていく。だからこそ、思い切った新しいチャレンジにもトライできるんだと思います。
メンバーそれぞれの個性に光を当て、その力を最大限引き出すための地ならし。それこそが、STUDIO ZERO流オンボーディングの真骨頂なのだ。
常に進化を続けるオンボーディングシステム
STUDIO ZEROのオンボーディングシステムが際立っているのは、常に進化し続けている点だ。
前垣オンボーディングチームのメンバーは常に入れ替わり続けるんです。オンボーディングを受けたばかりのメンバーに次々とその役割を引き継いでいくんです。
新陳代謝を繰り返すことで、常にフレッシュな視点を取り入れられ、自分はその分、次の案件や役割に取り組む。そうやって、すごいスピード感でバトンをつないでいるんですよ。
変化の激しいスタートアップの世界。オンボーディングの内容も、刻一刻と変わるビジネス環境に合わせて柔軟にアップデートしていく必要がある。その点、STUDIO ZEROでは参加者の声を随時取り入れることで、プログラムの質を向上させ続けているという。
秦野直近の当事者からのフィードバックが何より重要ですよね。ある程度時間が経ってしまうと、どうしても古い情報になりがちじゃないですか。だから、新陳代謝が大切だと思うんです。
例えば直近の3月入社の人、4月入社の人にどんどん話を聞いていくと、「ここはわかりづらかった」とか、「ここは特に不満はない」といった肌感覚の意見が集まってくる。そうしたリアルな声を反映させることで、常に最良のプログラムを提供できると考えています。
権限委譲とオーナーシップの徹底も、STUDIO ZEROのオンボーディングの特色だ。メンバー一人ひとりが高い当事者意識を持ち、自らプログラムをより良いものにしていこうとする姿勢が、随所に見られる。

前垣オンボーディングの設計について、代表の仁科と大枠の方針はしっかりとすり合わせています。その上で、「こういう手法を取り入れたい」「これをやってみたい」と柔軟に提案できる環境なんです。アイデアを出せば、ほとんどのことは裁量と責任をもらえますからね。
もちろん、チームでも集まって、オンボーディングの目的を再確認したり、基本的な部分は共有しながら進めていきます。メンバーの自主性を尊重しつつ、全体の方向性は揃えている感じですね。
メンバーの創意工夫に委ねつつも、全体の方向性はチームでしっかりとすり合わせる。それが、オンボーディングの質を担保するSTUDIO ZERO流のやり方のようだ。
小坂みんな高い課題意識を持って、主体的に動いているから、細かく指示しなくても大丈夫なんです。むしろ、それぞれのやりたいこと(will)を尊重するのが大切だと考えています。
特にオンボーディングは、メンバーの“現在のwill”とは多少ズレている部分があって当然。でも、やりたいことと、やらなきゃいけないこと、その全てを完璧にこなすのは難しい。だから、“willからずれているタスク”に関しては、基本的にマイクロマネジメントを控えるのが、STUDIO ZERO流なんです。
「誰でも取り組めるが、オンボーディング時のToDoのような重要な仕事」は、なるべく指示出ししない。基本的には「自分で判断して、やりたいようにやりな」というスタンスですね。
オンボーディングの内容自体は、入社後に必要な基礎知識のインプットが中心ではある。しかし、そのプロセスを通じて、新メンバーとベテランメンバーとの信頼関係を早期に築き、心理的安全性を担保することに重きが置かれているのだ。
画一的なマニュアル通りの研修ではなく、メンバー同士の主体的な関わり合いを重視したオンボーディングプロセスそのものを通じて、多様なバックグラウンドを持つメンバー一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、入社後の早期活躍を実現する。それこそが、STUDIO ZERO流の人材育成の真骨頂と言えるだろう。
新メンバーにも、ベテランと変わらぬ「ヘルシーな期待値」を
STUDIO ZEROには「初速でインパクトを出す」ことを重視する文化がある。スタートダッシュを決め、存在感を示すことが何よりも大切にされているのだ。
前垣オンボーディングチームはもちろん、STUDIO ZEROのメンバーはみんな初速が尋常じゃないんですよ。小坂さんはもちろん、秦野さんも2024年3月入社でありながら、STUDIO ZEROの広報領域の仕事を一気に巻き取って動いてくださっている。
私のメンターも、常に「初速でインパクトを出すのが重要」って言っていましたが、ホント、そのとおりだなって。
小坂私も、信頼を得るには、まずは早くアウトプットすることが重要だと思いますね。どこまで仕事が進んだのか、途中経過でも構わないからどんどん共有する。別に最初から完璧なアウトプットをする必要はないんです。
5割、6割できたら「ここまでやりました」と報告して、足りない部分は後から修正すればいい。そうやって1週間、2週間のサイクルで、どんどん精度を高めていく。私に限らず、STUDIO ZEROのメンバーはみんなそれらを高いレベルで実現できてますよね。
アジャイルに動くことを重視する文化が見て取れる。メンバーの主体性を尊重し、一人ひとりに大きな裁量が与えられているからこそ、そうした働き方が可能になるのだろう。
その象徴的な例が、メンバーの早期抜擢と、当事者主導の運営体制である。その一例として小坂氏は入社からわずか3日でオンボーディングチームに抜擢されたのだ。
小坂私がまさにオンボーディングを受けている最中に、いきなりオンボーディングチームに入ることになっちゃいまして(笑)。
前垣小坂さんは、入社2日目には、社内のオンボーディングタスクを一通り終えてたんですよね。その上で自分なりのオンボーディングの気づきを次々と提案してくれて。「彼女のスピード感やスキルはオンボーディングの改善活動に絶対に必要!」ってすぐに直感したんです。
また取材では、STUDIO ZEROでは新メンバーに対しても、ベテランと変わらぬ期待を寄せていることが読み取れた。小坂氏はそれを「ヘルシーな期待値」と表現する。

小坂みなさん、新人の私にもものすごく温かいんですよ。例えば、私と前垣さんの入社時期の差は、2ヶ月程度。僅かな期間で積み上げている前垣さんの実績には目を見張るものがありつつも、新人の私に対して「この人、本当にできるかな」なんて懐疑的な目線を向けるメンバーは誰一人としていないんです。
むしろ、「ヘルシーな期待値」を持って接してくれる。学ぼうとする姿勢を歓迎してくれるんです。すごく働きやすい環境だなと感じています。
秦野私たちも、新しく入ってきたメンバーに「教えなきゃ」なんて意識は全然ないですね。むしろ、一緒に働く中で、その人の強みを吸収したいという気持ちが強いんです。だってSTUDIO ZEROメンバーは、みんな個性豊かでスゴ腕ぞろいなんです。この人たちから何を学べるかな、ってワクワクしながら仕事してます。
ベテランも新人も関係ない。個人の力量を認め合い、フラットな目線で向き合う。そんなSTUDIO ZERO流の「ヘルシーな期待値」が、メンバーの成長を加速させているのかもしれない。
こうした「スピード」と「インパクト」を重視する働き方が、当たり前のように実践されている。そんな組織文化を支えているのが、「零道(ぜろみち)」と呼ばれる行動指針だ。一人ひとりが自律的に動きながら、同じ方向を向いて協調するための羅針盤となっている。
変化の激しいビジネス環境の中で、組織としての俊敏性を保ちながら成長を続けるには、スピード感を持った挑戦が欠かせない。しかし、それを個人の力だけで実現するのは難しい。チームとしての一体感、規範とすべき価値観の共有が不可欠となる。その基盤となるものとして設計されているのが「零道」だ。
変化を恐れず、常に前進し続ける組織文化
一般的には「バリュー」と呼ばれる内容となっているのが、この「零道(ぜろみち)」だ。13のワードで構成される零道は、メンバーの行動や価値観に自然と浸透し、組織の礎となっているのだ。
秦野零道に、「まずは率先して自分たちがワクワクする」とか「熱狂を伝播する」という言葉があるんですけど、そういう生き方や心構えが、STUDIO ZEROのメンバーにはしっかりと根づいているんですよね。みんな、わくわくしながら仕事してるし、そのわくわくを周りにもどんどん広げていく。そんな雰囲気があるから、自然と挑戦的になれるんだと思います。
零道は、メンバーの行動原理であると同時に、STUDIO ZEROが目指す組織のあり方そのものを表している。
もちろん、自らのみで理想の組織を追求するのみならず、他社の失敗も積極的に取り入れ、そこから学びを得ていく姿勢も特徴の一つだ。
前垣例えば「30人の壁」「50人の壁」などと言われる組織拡大におけるテーマは有名ですよね。指針があいまいな状態だと、拡大に伴って組織に不信感が募ってしまう。結果、創業者への信頼も揺らぎ、「この会社、一体どこに向かっているの?」という状態に陥りかねない。
そういう事態を避けるために、私たちはまず「30人の壁」が近づいた段階で、先手を打って零道を導入したんですよね。
思い返せば、私が入社した直後に参加したオフサイトミーティングの場で、ちょうど零道を導入することが議論されていました。組織の課題をオープンに共有し、全員で備えていこうとする姿勢に、正直驚きました。スタートアップ特有の課題にも、このような形で対処できているのは、STUDIO ZEROならではだなと。ビジョン実現に向けての本気度が、ひしひしと伝わってきました。

一方で、強い信念を持つ組織であればあるほど、時に自己満足に陥るリスクも孕んでいる。その点については、冷静に自らを見つめ直す姿勢も大切だと、小坂氏は指摘する。
小坂客観的に見ると、STUDIO ZEROの仕組みってかなり良くできているんですよ。「これ以上ないんじゃない?」って思うぐらい。でも、そこで満足しちゃダメなんです。今のやり方を維持していくだけでいいのか、今後どんな課題が出てくるのか。そういうことにもアンテナを張って、常に次の一手を考えなきゃいけない。変化の兆しを捉えて、すぐさま軌道修正する。そういう意識を常に持ち続けることが肝要だと、みんなが理解しているんです。
秦野STUDIO ZEROらしいアプローチというのは、とにかく「やってみよう」と即断即決すること。そして、熱狂を伝播しながら実際にトライしてみる。反応を見ながら軌道修正していく。そんな柔軟なスタンスが、新しい組織のあり方につながってるんだと思います。
前垣アジャイルですからね、我々は。
前垣氏のこの一言に、STUDIO ZEROのエッセンスが凝縮されている。
常に変化を求め、挑戦を楽しむ組織文化。メンバー一人ひとりが「自らわくわくする」ことを大切にしながら、ともに熱狂を生み出していく。そんなカルチャーが、メンバーの成長を加速させるだけでなく、組織を進化させ続ける原動力にもなっているようだ。
「産業と社会の変革を加速させる」
このSTUDIO ZEROのミッションは、多様なバックグラウンドを持つメンバーが集う組織ならではの強み、そして存在意義を体現していると言えるだろう。
ミッションは、自分なりに咀嚼せよ
「産業と社会の変革を加速させる」──。ところでこのミッションは、メンバーたちの心の中で、どのような意味を持っているのだろうか。秦野氏は、自身の捉え方をこう語る。
秦野実は、「産業と社会の変革を加速させる」っていうのが具体的にどういうことなのか、正直最初はよくわからなかったんです。あまりに大きすぎて、想像もつかなかった。
でも、単純に「いいことだよね」「できたら素晴らしいよね」っていう気持ちはありました。漠然とではあるけど、そういう理想には共感してたんです。
秦野氏にとって、STUDIO ZEROのミッションは、一種の “理想” として存在していたようだ。それは、現状の日本社会に対する危機感とも結びついている。
秦野日本って、昔は「Japan as No. 1」なんて言われてたじゃないですか。それが今や、GDPでも中国やドイツに抜かれている。様々な分野でプレゼンスが下がっているのを見ると、なんだか悔しい気持ちになって。
グローバルで活躍する日本企業にさえ、世界の目は厳しいように感じます。時代の流れなのかもしれないけど、とてももったいないなと。だって、戦後のあの状況からここまで驚異的に這い上がってきた国なのだから、そのポテンシャルをもう一度引き出せないのかな、って。
その思いが、STUDIO ZEROへの期待につながっているのかもしれない。
秦野日本の大企業を変革していくことで、日本全体を変えていく。そういう流れが生まれたらいいなって漠然と思ってます。正直、何ができるかはまだわからない部分も大きいですけど。でも縁があって、この一員になれたことは、自分にとって良いキャリアの選択肢だったんじゃないかな。だから、ワクワクしながらミッションに向き合えてるんだと思います。

前垣私も、STUDIO ZEROに入る際は、秦野さんと同様、「産業と社会の変革を加速させる」というビジョンの大きさがゆえに、まだ自分ゴトとして咀嚼できていなかったです。
ただ、そのビジョンの大きさには惹かれたんです。会社のビジョンってのは、その会社の限界を決めるものだと思っているから。だから、世の中に大きなインパクトを残したいと考えている自分としては、STUDIO ZEROのミッションにすごくワクワクしたんですよね。
一方の小坂氏は、行政や自治体での経験を踏まえ、ミッションを自分なりに咀嚼している。
小坂私は行政機関で働いた経験があるので、「産業と社会の変革を加速させる」っていうのは、すごくストレートに受け止められるんですよね。「公益に資する」っていう感覚は、もともと自分の中にあったので。
だから、シンプルに「いいミッションだな」って。営利目的の企業だけが社会を変えるわけではないですからね。もちろん、行政だけでもダメだと思います。
加えて、秦野氏は、そのミッションの意義に加え、難易度についてもさらに掘り下げる。
秦野自分たちが変革を起こすのはまだしも、それを加速させる側になるっていうのは、すごく難易度が高いことだと思うんです。そうそう経験できることじゃない。
だからみんな、唯一無二の答えを求めて試行錯誤してる。その過程で、行動の指針となるのが「零道」だったりするんですよね。それを一つひとつ積み重ねていけば、いつかきっと理想の頂に辿り着ける。そんな思いを胸に、未踏の領域に挑んでいるのが、私たちSTUDIO ZEROなのかもしれません。

「産業と社会の変革を加速させる」──。この崇高なミッションを胸に、STUDIO ZEROのメンバーたちは今日も果敢に挑戦を続けている。理想の未来を見据え、その実現に向けて邁進しているのだ。
オンボーディングを経て個々の力を発揮し、メンバー一人ひとりが飛躍的な成長を遂げる。そして、その変化の波は組織全体に広がり、STUDIO ZERO自体の大きな変革を促していく。
そして、これらの挑戦のすべては、日本の産業と社会に革新をもたらすための一歩にほかならない。STUDIO ZEROの先進的だが、ほんの小さな取り組みは、人材育成の難題に悩む多くの日本企業にとって、道標となるはずだ。
組織を成長させ、より良いものにしていく。その延長線上に、日本社会そのものの変革があると信じて。同社のメンバーたちは、そんな自負を胸に秘めながら、日々の仕事に全力で取り組んでいるのだ。こうした実践から、私たちは何を学べるだろうか。
こちらの記事は2024年05月10日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
牧野 花菜
写真
藤田 慎一郎
おすすめの関連記事
現場にいる者こそが、意思決定者──年次も経験も関係ない!UPSIDERで非連続成長を担うのは「一次情報を最も知る者たち」だ
- 株式会社UPSIDER 執行役員 / VP of Growth
急成長企業の5つの鉄則──隠れテック企業・出前館に見る、挑戦と革新の舞台裏
「支社 = チャンスがない」は誤解──全社表彰を連発する電通総研の中部・豊田支社。秘訣は“立地”と“組織構造”にあり
- 株式会社電通総研 製造ソリューション事業部 製造営業第5ユニット 豊田営業部
”渇き”こそ、スケールアップの原動力だ──X Mile渡邉×SmartHR芹澤による、急拡大企業の組織マネジメント論
- X Mile株式会社 Co-Founder COO
【独自解剖】いまスタートアップで最も“謎”な存在、キャディ──SaaS×データプラットフォーム構想によるグローバルテックカンパニーへの道筋
経営陣の覚悟こそ、前例のないハイグロース企業をつくる核──新CHROが語る、事業統合の“ゆらぎ”を経た第二創業期の組織づくり
- キャディ株式会社 最高人事責任者 CHRO
「実際、支社と本社って“違い”がありますよね?」──新卒が抱く配属の悩み。電通総研・関西支社の答えが意外すぎた
- 株式会社電通総研 技術統括本部 エンタープライズ第二本部 エンタープライズ開発ユニット ITコンサルティング2部
「支社配属=密度の濃さ?!支社だからこその強みがここには実在する」──就活生が気にするキャリアプラン。電通総研・広島支社に聞いてみた
- 株式会社電通総研 技術統括本部 バリューチェーン本部 PLM第4ユニット