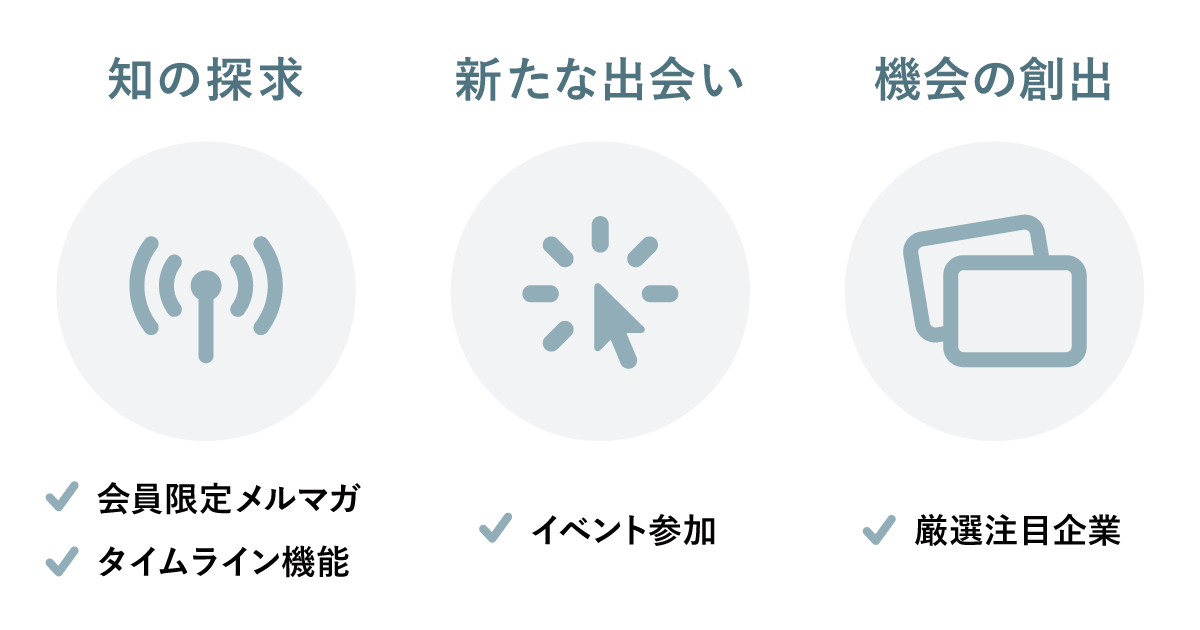投資家の目に魅力的に映るスタートアップの条件とは?──VC出身のCFOが語るX Mileの面白さ
Sponsoredスタートアップとは急成長である。急成長こそがスタートアップをスタートアップたらしめる所以であり、短期での急成長を実現するために様々な面で通常と異なる設計がなされる。そして成長の実現の仕方は各社様々だ。「どのようなリスクをとり、どのような不確実性に賭けるのか。そしてどのように山を登るのか」。市場の見極め、事業戦略、リーダーシップチーム、ファイナンス戦略。これらの要素を兼ね備えたスタートアップだけが、Going Concernを築き上げることができる。
投資家やアドバイザーとして数多のスタートアップに関わってきた経験者をして、「面白い」と思わせるのはどのようなスタートアップなのか。FastGrowが今回注目するのは、ベンチャーキャピタル(VC)からの転身を遂げ、X MileのCFOに就任した松尾侑紀氏だ。大手投資銀行やVCで多くのスタートアップのIPOや投資に関与した経験を持つ松尾氏が、なぜスタートアップの参画を選んだのか。本インタビューでは、その意思決定の背景を掘り下げる。
X Mileについて「マーケットの不変性及び将来性、事業と組織の作り方、成長への道筋の描き方。その全てにおいて、X Mileは魅力的なポテンシャルを有している」と松尾氏は語る。
特に強調したのが、山の登り方だ。市場構造を的確に捉え、その流れに沿うための戦略を最初から展開できている点に、X Mileのユニークさがある。またシンプルな戦略を泥臭く実効できる組織の強さこそが、同社の最大の強みとなっている。
VCからCFOへ。まだまだ国内では稀有なこのキャリアパスが、日本のスタートアップとVC双方に与える影響とは。そして、投資家としてではなく、入社したいとまで感じた「魅力的なスタートアップ」とは。松尾氏への単独インタビューを通じて、成長企業の本質に迫る。
- TEXT BY MAAYA OCHIAI
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
「令和のメガベンチャー」の条件とは?
投資家目線で見出したX Mileの魅力
「X Mileは、今後変わることのない日本の構造的な課題を捉え、それに応えるための戦略を初期から打ち立てている。それこそが圧倒的な魅力だと感じました。」
そう語るのは、2024年にX MileのCFOに就任した松尾侑紀氏だ。新卒で野村證券の投資銀行部門に入社、続いて大手ベンチャーキャピタルであるグローバル・ブレインで経験を積んだ同氏。数多くのスタートアップに関わってきた中で、X Mileへの参画を決めたのには、他社には見られない魅力を感じ取ったからに他ならない。 松尾氏によれば、物流や建設業界は市場規模が大きく、DX化の遅れも大きいことからスタートアップにとって魅力的な市場であり、実際に参入を狙うスタートアップは数多い。しかしその大半が、ノンデスク業界特有の構造的な課題に直面する。
松尾SaaSに代表されるデジタルサービスはノンデスク産業の現場にとって即座に必要不可欠なものとは認識されにくいのが現状です。前提として、物流や建設といったノンデスク産業では9割以上が中小企業・小規模事業者で占められており、労働集約なビジネスモデルであることから従業員の方の大半は現場業務を行っています。
そのような背景から既にアナログに最適化されたプロセスが確立されていることに加えて、「自社に人材がいない」「検討する時間がない」「現場社員のオペレーションを変えたくない」といったノンデスク産業に特に見られるDX化の障壁が存在しており、デジタルサービスは「あれば便利」という壁を中々超えられないのが実情です。
また、中小企業・小規模事業者がメインであることから、企業規模に併せて低単価なプライシングを行う一方で、導入までには一定のコストと期間が必要になってしまうことが往々にして起こっており、当初想定していた産業規模と見える景色ががらりと変わってしまうこともスタートアップにとっての難易度の高い領域となる要因です。

ノンデスク産業の課題は「人手不足」と「デジタル化の遅れ」だが、独立した課題ではなく、双方が絡み合った複雑性の高い課題である。単に利便性の高いデジタルサービスの提供のみではノンデスク産業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めることは難しく、IT導入支援が行える人材の不足、業務プロセスの複雑性、現場への浸透などを組み合わせたノンデスク事業者のニーズを満たすサービスが必要だ。
松尾X Mileは、ノンデスク産業のDXを進めるにあたって戦略的に段階的なアプローチをとっています。また、業界の特性や顧客ニーズを深く理解し、事業展開の優先順位を明確化した後に、シンプルで泥臭い部分にしっかりとコミットして実行できるところが魅力です。この山の登り方とそれにあわせた組織の設計、企業文化の醸成は不可逆なものであり、X MileがDay1から創り続けてきた強みだと感じています。
特に松尾氏が着目したのは、事業における打ち手の順番だ。詳細は後述するが、まずはHRプラットフォーム事業で基盤をつくり、顧客との信頼関係を構築し、その後に積み上げた顧客網を起点にデジタルサービスへと移行していく。この段階的なアプローチにより、ノンデスク事業者の最重要課題である人材不足の解決から着手し、信頼を獲得した上でDX推進へと自然に導いていくのだ。松尾氏は、この打ち手の順番と推進力がX Mileの魅力であると説明する。

取材を基にFastGrowにて作成
さらに、将来的な差異になることから創業当初よりデータベースへの投資や拡大を支えるオペレーションの作りこみにフォーカスしてきたこともX Mileの特徴である。中でも特筆すべきは、複数事業体制への移行を見据えたシステム設計だ。
これにより、事業拡大の際に手戻りなくデータ連携が進み、効率的かつ継続的なスケールアップが可能となる。同時に、オペレーションの効率化とデータの戦略的資産化を両立させている。この先見性ある取り組みこそが、将来の競争優位性を生み出す源泉となるだろう。
このように、数多くのスタートアップを見てきた松尾氏の目に留まったX Mileの強み。ノンデスク領域の構造的課題を正面から捉え、戦略的なアプローチで着実に事業を成長させるその姿は、投資家の目にも非常に魅力的に映ったのである。
その背景には、どのような経緯や想いがあったのか。松尾氏のキャリアの変遷をたどりながら、X Mileへの参画に至る道のりに迫っていく。
格差意識から関心を持ったスタートアップというビジネスモデル
「いずれはスタートアップで働きたい──」 そのような想いを胸に秘め、松尾氏は大手証券会社でキャリアをスタートさせた。そこで培ったファイナンスの知見、そして次に所属するベンチャーキャピタルでの経験が、スタートアップの世界への扉を開く鍵となった。
松尾氏がスタートアップに関心ができたきっかけは、大学時代のこと。地元の高知から東京に上京し、都会と地方の格差の大きさに衝撃を受けたことによる。
松尾何かをするにあたって東京の人たちは選択肢が多いなと思いました。例えば、中学生や高校生の段階で当たり前のように進路として海外進学が存在したり、参考書を執筆している先生が直に授業を行っている塾があったりと。
一方地方では、何をするにしても知らず知らずのうちに選択肢が限られていたんだなと。選択するのは本人の自由ですし、調べたら出てくるというのはその通りなのですが、情報へのアクセスの容易さは選択肢を持つ上で重要な要素だと思います。そもそも選択肢として知らないと選択すらできないですし。そういった情報の非対称性があることを多々感じて、こういった格差がなくなればいいなと思っていました。
日本の教育格差は、地域間だけでなく学校間でも顕在化している。私立高校と公立高校の間には、大学進学率に明確な差が存在することが広く知られている。こうした教育機会の偏りは、将来の収入や社会的地位の格差にもつながっていく可能性がある。
そんな中、松尾氏が大学入学を迎えた頃、受験生向けの動画アプリなどのサービスが登場し始めた。インターネットの力で情報の非対称性を解消するソリューションの出現は、松尾氏にとって大きな転換点となった。
松尾こうしたサービスがどんどん生まれてくれば、自分の生活はもっと便利になる。そう感じたことも、スタートアップに興味を持ったきっかけの1つです。

在学中に、UberやAirbnbといったシェアリングエコノミーのサービスに触れたことも、松尾氏の想いに拍車をかけた。テクノロジーが生み出す圧倒的な利便性を体感することで、スタートアップへの興味が加速し、スタートアップの可能性にワクワクしていた。大学時代は同時に日本社会全体の停滞を感じる期間でもあり、個人レベルのスタートアップへの期待を超え、社会システム全体を俯瞰する視点へと松尾氏を導いた。特に意識したのが、企業間に横たわる深い溝だった。
松尾日本の企業は99%が中小企業・小規模事業者であり、付加価値ベースでも約5割のシェアを持っています。一方でテクノロジーへの投資余力やDXを主導できる人材にも乏しいことから、大手企業が当然のように導入しているデジタルサービスの恩恵を受けられていない状況でした。
イノベーションの力を目の当たりにし、日本の産業においてもテクノロジーの力はこれまで大企業のみが享受できていたサービスを中小企業・小規模事業者にも解放することを可能にするものだと感じ、ひいてはそれが日本全体を活性化するピースの一つになるではないかなと考えていました。
インターネットの魅力の1つはコストの低下による非対称の解消であり、これまで偏在していた恩恵を誰しもが体感でき、世の中を前進させる力があると思っています。そしてそれをスピード感をもって実現し、社会そのものを変えていくのがスタートアップという存在であると知りました。
実際に、フィンテックサービスを手がけるスタートアップでインターンを経験した松尾氏。特に、会社を牽引していたCFOに憧れを抱いた。事業を支え、成長を加速させるための仕組づくりやCEOのビジョンを実現させるために両輪としてのコーポレート機能を推し進める存在に、心を惹かれたのだ。
松尾自分はビジョナリーなタイプではなく、特定の事柄に強烈な不満があるわけでもなく、怒りに近い感情があるわけでもありません。社会全体が豊かになれば良いなと思う中で、強いWillのある起業家のビジョンを実現するサポートができれば結果的に世の中をよくしていくことに繋がるし、そちらの方が向いていると感じました。そのための武器を身につけたい。そう思って関心を持ったのがCFOという存在で、金融・ファイナンスの分野でキャリアを積むことを決めたきっかけです。
志望先に選んだのは、IPOの*リーグテーブルで圧倒的なプレゼンスを誇っていた野村證券だった。IPOというスタートアップにとっての初めての資本市場を利用した資金調達を支援し、社会の公器となるプロセスを実現に導くアドバイザーとして、コーポレートファイナンスのスキルを習得する。それが、起業家のビジョンを支えるための第一歩となったのだ。
※リーグテーブル:引受業者の引受実績のランキング表を指す。IPOの場合、証券会社が務めた販売金額や案件数などに基づいて順位付けされる。これにより、各証券会社の市場シェアや競争力を比較することができる。
IPOにまつわる情報の非対称性が生む課題。
VCへの転身で見えた業界の構造
IPOを目指すスタートアップの支援を通して、松尾氏はスタートアップエコシステムに存在する課題に直面するようになる。特に感じたのが、「IPOにおける情報の非対称性」だった。
松尾今でこそシリアルアントレプレナーの方も増加してきていますが、それでもなお、ほとんどのスタートアップの経営陣にとって、IPOは初めての経験です。
アドバイザーの選定から、上場準備、プライシング、オファリングに至るまで、手探りで進めざるを得ません。インターネットで調べようにもそのような情報は存在せず、先輩起業家に相談しても、ケースバイケースの場面が多かったり、会社によって対応が違うケースも存在し、何が最適解なのかわからないのがIPO準備の実情です。後になって「あの時こうしておけば」と後悔することも少なくありません。
一方で、証券会社サイドは年間10社以上のIPO案件に関与し、最新のマーケット情報をアップデートしており、社内には数百社分の過去のIPO事例が蓄積されている。この部分に大きな情報の非対称性が存在しているのだ。
松尾私自身、アドバイザーとして、本則(いまでいうプライム市場)に直接上場するような大企業のIPO、2千億円規模のスタートアップIPO、一般的なマザーズ市場へのIPOなど多くの案件を経験させていただく中で、アドバイザーではない立場で、スタートアップエコシステムをより良いものにしていくために、この情報の非対称性を解消していきたいと考えはじめるようになりました。
スタートアップエコシステムの課題感と、自身の知見を活かせる手段が明確になり、自然とセカンドキャリアについて考え始めた。スタートアップか、VCか。悩んだ末に選んだのは、「産業」を生み出すことに注力できるVCの道だった。
松尾当時のVCには、投資銀行出身者があまりおらず、周囲にエクイティキャピタルマーケットや*IPOプロダクトを専門的に行ってきたメンバーがいませんでした。
一方で、外部から取り入れなければVCにIPOやその後のキャピタルマーケットに関する知見を蓄積するのは難しいのが実情で、これにはいくつかの理由があると考えていました。
VCは投資先のスタートアップに深く入り込み、日々議論を重ねますが、上場直前になると発行体としてのスタートアップとの間にコンフリクトが生じ、ポジションを取らざるを得ないこと。
加えて、証券会社にとっても、VCは意思決定の主体ではないため、あくまでマイノリティ投資家の1人として対応がなされ、細部にわたる実務説明や交渉の主体にはならないことなどが挙げられます。
だからこそVCに参画し、自分自身の経験をレバレッジさせ、エコシステムに還元できることに大きな価値があると考えました。
※IPOプロダクト:公開引受部及び公開引受部が提供する株式公開(IPO)準備に関連する一連のサービス
こうして松尾氏は、国内の著名VCであるグローバル・ブレインへ転職する。そこでは、投資検討から株式売却までを一気通貫で担当するという稀有な経験を積むことになった。
松尾一般的なVCのフロントメンバーは、投資活動に専念し、スタートアップのソーシング、投資検討、投資後の関与といったことに注力すると思いますが、私はグローバル・ブレインの環境や代表の百合本さんのチャンスを与える方針にも恵まれ、ポートフォリオの売却やファンドレイズといった出口と入口にも関与することができました。
VCは、すべての株式を上場時の売出しのタイミングで売却するわけではありません。どの程度の株式を上場時に売却し、どの程度を残すか。そしてそれらをいつ売却するのか。株式売却は投資よりもさらにアートに近い領域な一方で、ファンドパフォーマンスに直結する重要な役割です。売出人として発行体のCFOとは綿密な議論を行い、上場後は株主として定期的に対話を重ね、企業価値の最大化に向けた戦略を共に練っていく。VC時代のこうした経験は、これまでより更に上場後の成長に必要なピースの検討を深める契機となりました。
証券会社と比べ、VCではシード期やアーリー期の若いスタートアップの成長プロセスを間近で体感することができる。「急成長する企業」の共通点を実例として経験できるのが大きな魅力だ。
松尾実現したいビジョンへの渇望や経営陣の実行力を見極め、どういう条件であれば勝てるかを仮説立てて投資判断を行います。俯瞰した立場から幅広いビジネスのプレイブックを集め、スタートアップと共有し、議論する。そうした濃密な機会に恵まれ、本当に感謝しかありません。
スタートアップと接する日々の中で、当初思い描いていたスタートアップへの参画の気持ちもどこかには存在していた。
松尾日本のキャピタルマーケットにおいて、スタートアップに求められていることは成長です。グロース市場での十分な成長資金の獲得とそれを利用した成長投資、その後、プライム市場に移行し、TOPIXを牽引していくことが期待されています。しかし実際には、そこまで順調に到達できるスタートアップは多くありません。
その主な理由は、グロース市場を利用してさらなる成長を遂げる過程での課題にあります。本邦における上場準備が2年前からと長いこともありますが、組織の急拡大と平行して、経営管理体制の整備、1年前には厳格な予実管理が求められる中で、欧米と比べて早期から投資を抑制する方向に経営陣の思考が引きずられてしまいます。
コストの観点だけではなく、例えば足元のトップライン維持のために配置転換の抜擢ができなかったりと十分な成長投資や意思決定を行えないまま、上場を迎え、より短期に厳格な要求への対応がはじまることになります。
こうした課題に直面するスタートアップと議論していく中で、当初思い描いていたCEOのビジョンを実現するために取り組んでいたCFO像が重なり、IPOというプロダクト、上場後の株式を保有する株主としての双方の立場を経験した上で、当事者だったらどうするかを考える機会が増えてきました。
そんな思索を巡らせていたところに訪れたのが、X Mileとの出会いだった。
学生時代からの大きな進化とインサイダーとしてのアドバンテージ──同級生が語るCEO野呂氏の変化量
松尾氏とX Mileの創業者であるCEO野呂氏は、実は大学の同級生である。在学中は時折言葉を交わす程度の関係だったが、X Mile創業から1年が経過し、シードラウンドの調達を検討し始めた頃、野呂氏から松尾氏に連絡が舞い込む。
松尾当時、野呂さんから「スタートアップにおけるファイナンスはどう考えるべきか」「足元の市場環境やVCの動向はどうか」といった相談を受けました。その後も、時折カフェでフランクに話しながら、X Mileの最新の状況を聞くような関係が続きました。
とはいえ、あくまで友人としてファイナンス周りの話題で盛り上がっていただけで、将来X Mileに加わることになるなど、夢にも思っていませんでしたね(笑)。
ところが数年後、野呂氏から松尾氏に「X Mileに来ないか」と打診が届く。X Mileは以前からCFO候補を探していたが、なかなか適任者に出会えずにいた。そんな中、野呂氏が白羽の矢を立てたのが、松尾氏だったのだ。
入社を検討するにあたり、松尾氏はVCとして投資判断を行うときと同様に入念な検討を行った。NDAを締結した上でX Mileのビジネスモデルや財務状況を精査。加えて、同社のミッションやビジョン、経営陣の思想と自身の価値観の合致度合いを、何度も対話を重ね確認していったのだ。
松尾VCとしてはお金でしたが、今回は自分の時間を投資するという観点で気合をいれたデューデリジェンスを行い、野呂さん、渡邉さんに長時間付き合っていただきました。
VCとしての投資検討との特徴的な違いは、自分自身が取り組みたい課題や環境かという視点が加わった点です。純粋な投資としてリターンを検討する時よりも、内省の時間が多くなりました。
その過程で、大きかったのは「物が届いてほしい」というニーズが10年後も変わらないだろうという、市場の不変性への確信でした。同時に私自身が5年後も10年後も、「注文した物が届かなくていいや」とは決して思わないだろうなと思いました。
そういった思考の中で、X Mileのビジョンにも強く共感しました。運輸、建設を含めたインフラ産業は私たちの生活に不可欠な領域でありながら、そこで働く従業員の方々の労働環境は必ずしも恵まれているとは言えません。この問題の解消は、日本の未来を切り拓く上で避けては通れない課題であり、取り組むべき大義があると感じました。
松尾氏のジョインを後押ししたもう1つの要因が、インサイダーとしてのアドバンテージだという。大学時代からの付き合いがあるからこそ、野呂さんの変化率を誰よりも実感しているのだ。
松尾VCとして上場株を売却する際、将来予想の見立てで、明確に上場株の投資家に勝っている部分はこれまでの経営陣と組織の変化率を知っていることだと思っています。逆に言えば他は全て負けている。
それを思ってからはVCとして、変化率を知っていて、想像できる到達点の精度を上げられるかということを大事にしてきました。
野呂さんとは大学の同級生で、同じキャンパスで4年間を過ごしました。今のX Mileの株主やメンバーの方々よりも前から野呂さんを知っているんですね。だからこそ、創業前からここまでの変化の度合いを誰よりも理解しているつもりです。ここまで目覚ましい成長を遂げているのだから、この先も想像を絶するスピードで進化を続けるはず。そう確信できたのです。

振り返れば、大学入学当初の野呂氏とは、はじめからスタートアップに対する議論を行ってきたわけではない。どちらかといえばテストがどうだとか、部活がどうだとかそういった話題が中心だった。それが、大学4年生になる頃には、野呂氏は単身で海外での事業立ち上げを経験し、卒業後もスタートアップの起業へ参画、その後自身で起業するなど圧倒的なスピードで成長してきた。
松尾大学で出会った頃、私と野呂さんの会話は当然のように大学の授業や部活のことばかり。野呂さんが入っている寮のサッカー大会の話を聞いたり、一緒になった授業のテストの話をしていましたね。それが卒業前後で大きく変わり、スタートアップや仕事の話題でも盛り上がるようになったんです。
中でも、X Mileを創業して以降の変化は、目を見張るものがありました。事業の構築やその後の推進力、メンバーや数字に対する責任感の強さ。CEOとしての立場が、野呂さん自身の成長を加速度的に後押ししているのを感じました。
松尾氏にとって、X Mileのミッションとビジョンへの共感、そして野呂氏の経営者としての目覚ましい変貌ぶりが、入社を決断する大きな後押しとなった。
HRプラットフォーム事業を基点に巨大産業の変革を狙う。X Mileの壮大な“マルチバーティカル戦略”の全貌
ここからは、X Mileの事業・組織の強みを改めて、松尾氏の視点から詳らかにしていく。松尾氏はVC時代の投資検討の際のポイントをあげる。3つに大別すると「市場機会」「実行力」「競争力」である。
まず「市場機会」について。ここで重要となるのは、以下の点を明確に説明できるかという観点だという。
- なぜ今、このマーケットで勝負する必要があるのか
- 市場を独占できる可能性がある部分はどこか
- 展開すれば、スケーラビリティを担保できるほど十分に魅力的な市場か
これらの問いに対して、クリアに説明できるかどうかが重要だと話す。
松尾これまでのとおり、深刻になり続けているノンデスク産業の人手不足ですが、2024年の法改正を契機に加速度的に進行すると考えています。また、ノンデスクワーカーよりも先にHRサービスが浸透してきたホワイトワーカー市場ではHR Techが既に十分に立ち上がっており、日本の就業人口の半数以上をノンデスクワーカーが占めることを考慮すると、これまで市場として立ち上がっていなかったノンデスクワーカー向けのHR Techもホワイトワーカー向け以上に成長するポテンシャルを有していると見ています。
次に「実行力」だが、一口に実行力といっても測り方は様々だ。松尾氏は「リーダーシップチームを含めた会社のカルチャーとしての数値へのコミットメントや速度」を「実行力」と表現し、それが高いレベルで備わっているのがX Mileだと評する。
松尾目標数字にコミットして何が何でも達成するという泥臭い部分を丁寧に行えるかが最も重要だと考えています。この企業文化は不可逆なため、Day1から創り上げていく必要があります。
例えば、売上の99%達成をよしとするのか、否か。そもそも高い目標値を置くのがスタートアップの常なので、99%達成であれば緩んでしまうところもあるかと思いますが、そこを突き詰められるかということ。
また、立ち上げに1年くらいかかりそうな事業を、四半期や半期でスピーディーに立ち上げて仮説検証を始められると、実際に1年間かけることとを複数事業で比較したときに進捗もノウハウも数年間で大きな差になり、他社との差別化に直結します。この「速さ」も実行力において重要な点です。
マネジメント層の業界への深い理解と洞察力は、高い実行力を支える重要な要素の一つだ。ビジネスの核心を的確に把握し、それを実現するための適材を迅速に配置する能力は、業界とビジネスモデルへの精通なくしては成し得ない。
X Mileへの入社を決める上で重要な要素となったのは、X Mileの強みを支えるCOO・渡邉氏の存在だった。
松尾氏は、X MileのCOO渡邉氏のHR領域におけるこれまでの経験と業界の解像度の高さ(詳しくは過去の記事を参照)が、同社の大きな優位性になっていると話す。
松尾HR業界には圧倒的な巨人のプレイヤーもいれば、ダイレクトリクルーティングやVertical HR事業それぞれの先駆者のようなスタートアッププレイヤーも存在します。
このビジネスモデルにおいて成長を続けるために最も重要なことは再現性です。組織の人数が短期間で2倍、3倍になっていく過程で、いかにデリバリーの質を落とさず、生産性を維持し続けられるかが重要な要素となります。そのためには新しく入ってきていただいたメンバーが早期に既存メンバーと同じクオリティで物事を実行できるような徹底的なオペレーションの作りこみと磨き上げが必要になります。
もちろん、ビジネスモデルに合わせた緩やかで安定的な成長をし続けることも重要です。しかし、ノンデスク産業向けの市場をドミナントし、「勝ちに行く」という観点では、経営陣がHRにおけるビジネスモデルを深く理解し、レバレッジの効くポイントに的確な投資を行う。そして、急速にグロースさせるための仕組みと覚悟を持つことが市場を制するための重要な要素だと考えています。
最後に「競争力」の観点だが、これはプロダクトやサービスを指しているのではない。
松尾この観点は全てがPLとプロセスKPIに現れるものだと考えているので、定量的に判断しています。例えば、本当にオペレーションが確立されているのであれば1人あたりの売上高の均質性やコスト構造に出てきますし、プロダクトのPMFはプロセスKPIとその成長性に現れます。X Mileはそういった指標のどれをとっても素晴らしい企業でした。
「市場環境」「実行力」「競争優位性」と三拍子揃ったX Mileの事業成長はノンデスク産業やHR領域自体への解像度の高さに加え、スタートアップとしての攻め方、業界に切り込むビジネスモデルのつくり方への拘りがもたらしたものである。
不可逆な流れの中で正しい戦略をはじめから打てている
野呂氏が『CrunchBase』(世界最大級のベンチャーデータベース)の上から下まで約3,000社のビジネスモデルを調べ尽くしたうえでX Mileの事業領域とその進め方を決めたことは以前の記事でも紹介したところ。この徹底的な調査と分析に基づく戦略立案が、X Mileの成長の確実性と持続可能性を高めている。
ここで、冒頭で紹介した松尾氏の発言を再掲する。
松尾物流や建設業界は、市場規模が大きく、DX化の遅れも大きいことからスタートアップにとって魅力的な市場であり、余地も十分にあるため、実際に参入を狙うスタートアップは数多い。
多くのスタートアップが参入する中で、この市場を勝ち切っていくためにはどの順番で業界、企業の課題を解決していくかが重要である、と松尾氏は推察する。
松尾ノンデスク産業の企業にとっての一丁目一番地の課題は人手不足です。日本の構造的な課題として人口減少があり、だからこそノンデスク産業以外にも多くのスタートアップがこの課題の解決に向けて生産性の向上を図るデジタルサービスを提供しています。
鶏と卵の議論に見えますが、私個人としてはノンデスク産業においては明確に順番があり、人手不足に対する直接的な課題解決を進めるべきだと考えています。実際にシステムやツールの導入検討をする人たちは目の前の業務に忙殺されていて、そこまで手が回らないのが現状です。それに、今のままでもまだ紙やExcelを使えば対応できてしまっているので、便利なデジタルサービスであっても今すぐの導入となりづらい構造になってます。
X Mileは楔であるHRプラットフォーム事業によって“人手不足の解決”というノンデスク産業にとっての喫緊の課題で面をとり、それをフックに本格的なDX化を推し進めるという戦略をとっており、ここがユニークな点だと感じています。

X MileはまずはHRプラットフォーム事業で顧客網の獲得と信頼関係の醸成を行う。その後、積み上げた顧客網を起点に業務効率化ツールや経営管理ソリューションなどのデジタルサービスを提供していく。DX化によって生産性の向上が実現でき、顧客側のPLを改善させることができれば、従業員の給与水準も向上し、またHRプラットフォーム事業が強くなっていく。最終的にノンデスク産業向けの経営プラットフォームでメインであるトランザクション、例えば受発注プラットフォームのような事業にも染み出していく構想だ。
このようにマルチバーティカルな経営プラットフォームになっていくことで、巨大なノンデスク産業のデジタルサービスにおけるポジションを確保する。
「解決したい課題に対する山の登り方とそれを実行に移す力が、X Mileの特に秀でている部分である」と松尾氏は強調する。市場構造を的確に捉え、その流れに沿った戦略を最初から展開できているところに、X Mileの真の強みがあるのだ。
DXの必要性が叫ばれて久しいが、実際の導入となると二の足を踏む企業が少なくない。特にノンデスク産業では、ITリテラシーの問題や、現場の業務プロセスのアナログ性の高さから、新しいシステムやツールへの抵抗感が根強い。この心理的ハードルをいかにクリアするかが、ノンデスク領域のDXを進める上での課題だ。
この事業者のハードルに刺さっているのが、松尾氏が指摘するX Mileの「喫緊の課題から攻める」という順番である。人材不足という深刻な課題を入り口に、まずは顧客との信頼関係を築く。その上で、蓄積した顧客基盤をテコにデジタルサービスの導入を促進していく。「X Mileがいうならやってみるか」という自然な流れで受け入れを促すアプローチだ。「担い手の不足」、「生産性の向上」のどちらも行わなければいけない業界において、シンプルだが泥臭いくとを求められる「担い手の不足」側から入り、「生産性の向上」を推し進めていく事業の進め方はノンデスク事業者の本音を理解した上での戦略と言えるだろう。
ヘルスケアを筆頭に同じく業界課題の解決手段として「人手不足」を入口としている企業は存在し、蓋然性を備えた戦略に見える中で、なぜ他社はX Mileと同じ戦略を取らないのか。その理由について、松尾氏はスタートアップにおけるビジネスモデルそのものの特性を挙げて説明する。
松尾スタートアップにおける大きなテーマの1つはソフトウェアにおける自動化です。人の介在余地が少なく、スケールがしやすいため、損益分岐を超えた段階以降圧倒的な利益創出が可能である一方、先行投資が必要なため、そのJカーブをリスクマネーでカバーするというモデルはVCとも相性が良く、多くのスタートアップが取り組んでいます。
一方で、HR事業は成長に合わせて一定のオペレーションが介在するため、Jカーブを描くビジネスモデルではなく、また日々のオペレーションの磨きこみによって優位性が発現できるものであり、急成長を求められるスタートアップには取り組みづらいビジネスモデルだと思います。
ただ、上場企業、未上場企業問わず、ソフトウェア企業において、売上の増加に伴ってリニアにS&M(セールス&マーケティング)の比率が増加している企業も多く、当初期待していた利益率を達成できていない向きもある中で、私自身は日本において、利益規模の急速な拡大に必要なビジネスモデルがソフトウェアに限られるとは思っていません。

スタートアップとして一見敬遠されがちなビジネスモデルを入口とすることは、ノンデスク産業と時間をかけて向き合っていくことの証左であり、この業界のDX化が一足飛びにできるものではないことを理解しているからに他ならない。X MileのHRプラットフォーム事業は、ノンデスク産業にとって避けては通れない課題と真っ向から向き合うものだ。2024年以降本格化してくるであろう労働力不足は、同社の強い追い風となるはずだ。
X Mileのもう1つの特徴が、オペレーションやデータへの積極投資である。松尾氏の指摘通り、この点は過去の記事で登場人物のほぼ全員が言及しているところだ。
ヘルスケア領域を例に挙げて松尾氏は語る。
松尾様々なプレーヤーの参入があった中で、エス・エム・エスが高いシェアを維持し、業界のリーディングカンパニーとして創業以来20期連続で増収増益を達成しているのは、オペレーショナルエクセレンスを磨き続けているからだと思います。過去の取引データを資産として溜め、PDCAを回して仕組み化していくことで後続との圧倒的な差が生じています。
シードやアーリーフェーズではデータマネジメントやデータベースへの投資に手が回らないケースが多いのですが、X Mileではしっかりと将来使える形で残し続けています。これはDay1からそれらが競争優位性に繋がることを経営陣で同期しており、また全社員がデータ及びそれによって改善されるオペレーションの重要性を理解し、日々の業務やナレッジを共有しているところからなるX Mileの特異なポイントです。
「市場機会」「実行力」「競争力」の3点を満たし、先を見据えた経営を実現している点にX Mileの圧倒的な強みを見出した松尾氏。これからCFOとしてどのような未来図を描いているのか、次から見ていこう。
CFOとして、IPOの在り方に“新しい風”を吹き込む
X MileのCFOとして、松尾氏が注力する領域は大きく3つだ。
1つ目は今後のスケーラビリティを担保するためのガバナンス強化である。内部管理体制の構築を通じて、会社の基盤を盤石なものとする。 2つ目はファイナンス戦略の立案と実行だ。既存事業とM&Aによる成長機会を探るべく、最適な資金配分の在り方を検討していく。 3つ目がIRだ。既存のステークホルダーとの双方向コミュニケーションを企業価値の向上に還元していくこと、新規のステークホルダー候補の方にX Mileの魅力を理解してもらうことである、という。
これらはいずれも、松尾氏のこれまでのキャリアで培ってきた知見とスキルを存分に活かせる領域だ。
松尾X Mileの急速な成長に置いて行かれないよう両輪としてのコーポレート機能強化に注力したいと思っています。これまで見てきた事例はありつつも全く同じ状況の会社というものは存在しないため、日々外部のCFOの諸先輩に教えていただきながらキャッチアップしている部分も多く存在しています。これまでの経験と足元の環境を踏まえてX Mileにとって最適なコーポレート機能を全員で作っていければと考えています。
内部管理体制の整備、“非”オーガニック成長、ステークホルダーとの信頼関係構築。どれも一朝一夕にはなし得ない困難な課題だが、松尾氏はその実現に挑んでいく。また、新卒から一貫してスタートアップに関わってきた同氏がこだわっているのがIPOというプロダクトとそのスタンダードについてだ。
スタンダードの“書き換え”に挑む。
「令和のメガベンチャー」へ
CFOとしての注力分野を語った松尾氏に、「令和を代表するメガベンチャーを創る」というX Mileのミッションを実現するために、今何が必要かを尋ねた。
松尾平成を代表するメガベンチャーはどこか?と聞けば多くの人はメルカリと答えるのではないかなとと思います。公開価格ベースでの時価総額は約4,100億円、上場日には一気に8,000億円を超える水準まで株価が高騰しました。
結果として、VCを含むその後のスタートアップ環境も大きく変わり、ヒト・カネが大きく流れ込むきっかけになったと思います。あのインパクトを、令和の時代に多くのスタートアップが再現することを目指す中で、どこが代表かと聞かれればX Mileだと名前を上げてもらえる。それが私たちが目指している絵姿です。
この10年から20年の間に上場を果たした日本企業の中で、時価総額が3,000億円から5,000億円の壁を突破した例は稀だ。まずはこの厚い壁を打ち破ることが、X Mileにとっての当面の目標となる。
松尾全上場企業と、直近20年で上場したスタートアップ(子会社や民営化を除く)を比較すると、1,000億円以上、3,000億円以上、5,000億円以上の時価総額を持つ企業の比率に大きな違いが見られます。
2020-2022年のmultipleの高騰による影響を除外すると、20年以内に上場した企業のうち、一定の時価総額規模に達している企業の比率は、全体の比率と比較して一桁異なる水準となっています。
時価総額とは事業規模を基準として評価されるものであり、まずは事業の規模、すなわち社会への付加価値を積み上げていき、エムスリーやリクルートといった巨人の仲間入りを果たしてこそ、「令和のメガベンチャー」として名前が挙がってくる存在になれるのだと思います。
時価総額という定量的な物差しだけでなく、松尾氏は「令和のメガベンチャー」の条件を定性的な側面からも定義する。
松尾多くのスタートアップがより成長しやすい環境を整えていくために既存のスタンダードを変革していく存在であることも重要だと感じています。
特に日本のIPO市場に目を向けると、スタートアップの成長における制約がまだまだ存在しています。例えば、資金使途やロックアップの設計は本当にスタートアップにとって最適なものになっているのか?また、上場後の成長の発射台として適切なN期の体制を構築するための上場審査論点が十分に練られたものになっているのか?など、まだまだ細かな部分での情報の非対称性が多く存在していると感じています。
IPOを目指すスタートアップは、上場準備期間中のM&Aに一定の制限を受ける。調達した資金の使途についても、厳しい制約の下に置かれるのが一般的だ。
松尾証券会社の立場にいて感じることは「No」という回答には理由があるということです。
例えばM&Aの場合、M&A対象先の予実管理やガバナンス体制を、自社と同等の水準まで引き上げるのにどれほどの時間が必要なのか。そこから逆算して、いつが締切となるのか。これらの判断は、発行体と対象先の事業規模や管理体制の実態、さらには発行体自身の体制によっても大きく変わってきます。
こうした複雑な要因が絡み合い、一律の判断を下すことが難しい中で、重要となるのは、どのような準備をし、どのようなコミュニケーションを取れば自分たちの理想の状態を達成できるかという点であり、粘り強く対話を重ねてベストプラクティスを設計していくことが肝要です。
IPO時の審査論点のすり合わせ、*シンジケートストラクチャーの設計、オファリング戦略、プライシングの交渉に至るまで、スタートアップにとっての“高い壁”は多岐にわたる。それらを1つずつ乗り越え、これまでやりたかったが前例がないからできないと言われた事象に対して前例を産み出していく。それこそが、松尾氏の言う「スタンダードを変革すること」なのだ。
※シンジケートストラクチャー:新たに発行される有価証券を引き受けるための関係業者の団体をどのような構成にするかの戦略のことを指す。
陸上競技の100メートル走で、日本人選手は長らく「10秒の壁」を突破できずにいた。だが、1人の選手が壁を打ち破ると、途端に後に続く者が続出した。1人の先駆者が新たな道を切り拓くことで、不可能と思われていた記録がスタンダードになっていく。
松尾氏にとって、IPOとファイナンスの在り方を変えていくことは、日本のスタートアップ業界全体への恩返しでもある。

松尾率先して変革にチャレンジすることで、後に続くスタートアップが新しいスタンダードの下で、より良質な産業を作り上げていき、また新しいチャレンジを行う。そういったサイクルに参加し、貢献していくこと、より大きく、早くしていくことが日本のスタートアップが競争力を維持していく上で重要なことだと思っています。
令和の時代を象徴するメガベンチャーとして、X Mileがスタートアップの新たなロールモデルを確立する日。その到来は、決して遠くはないのかもしれない。
松尾氏CFO就任のプレスリリースも改めてご覧ください(写真をクリック)
こちらの記事は2024年07月11日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
落合 真彩
写真
藤田 慎一郎
おすすめの関連記事
マイベスト、実は前代未聞の“データプラットフォーム企業”だった──「あの企業の“実は”ここがすごい」Vol.2
VCも起業家も、“常識外れ”な挑戦がまだ足りない!大企業コンサルやデータ基盤提供に加え、ビルや街まで構想する「欲張り」なVC・HAKOBUNE木村・栗島の構想とは
- HAKOBUNE株式会社 Founding Partner
FinTech×EC支援で事業を連続創出できる理由とは?BASEのツーサイドプラットフォームに魅せられた山村・髙橋の躍動を追う
- BASE株式会社 上級執行役員COO
個人やスモールチームの可能性を最大限に広げるプラットフォームへ─GMV1,500億円超もまだまだ成長途上。BASEでさまざまなBizDevに挑戦できる理由とは
- BASE株式会社 BASE事業 Business Management Division Manager
2倍成長を続けるTOKIUMに学ぶ「最強のオペレーション戦略」とは──「壮大・緻密・柔軟」の3要素で、BPaaSとしての成長を実現した秘訣
勝ち筋は「国産の生成AIミドルウェア」にあり──Vol.1 miibo CEO功刀雅士氏【寄稿:DNX Ventures新田修平】
- 株式会社miibo 代表取締役
日本発グローバルスタンダードは、“介護”から──「複雑×長期×規制」極まる社会課題。ユナイテッド × KAERU / CareFranはどう挑む?
- ユナイテッド株式会社 投資事業本部 キャピタリスト マネージャー