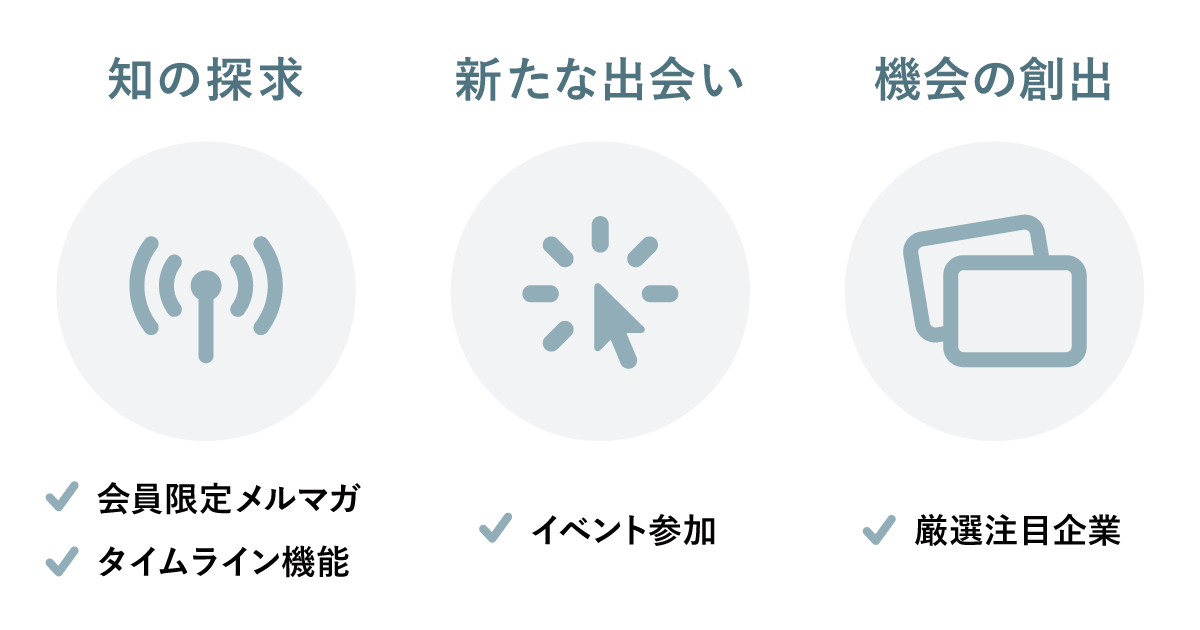特許技術「id」とAIによる行動予測を駆使し、日本初のDXPを現実にする──FLUXの開発力・開発組織の特異性を、Archetype Ventures福井氏らと探る
Sponsored2018年の創業以来、プロダクトリリースから3年半で顧客数は750社に達し、組織も急拡大を遂げているSaaSスタートアップのFLUX。国内最速レベルでARR10億円到達が見込まれるその成長スピードに、多くの人が驚きを隠さない。
その背景には、DXP(Digital Experience Platform)の開発という壮大な未来図がある。個々のプロダクトが各々の役割を果たすだけでなく、顧客が体験するデジタル上のタッチポイントを全て統合させ、一気通貫でサービスを提供する、という構想。つまり、単なるマルチプロダクト戦略ではなく、長い時間軸を見越しての展開なのだ。
しかし、海外ではDXPを実現している会社も存在する一方で、日本では第一想起を取れている企業は存在しないといって良いだろう。もちろん、国内においてその第一人者を目指しているFLUX創業代表の永井元治氏も、マーケティングやエンジニアリングに対する深い知見があったわけではない。さらには、CTOを務めるEdwin Li氏も、SaaSスタートアップでの開発経験はなかったという。
その開発の裏側にはどのような思想が存在しているのだろうか?そして、「FLUX Digital Experience Platform」をどのように実現させようとしているのだろうか?
本記事ではこの両氏に加え、株主でもあるArchetype Venturesの福井俊平氏(FLUX社外取締役も兼務)、同社をはじめとした様々なスタートアップの人事組織支援を行うReBoost代表の河合聡一郎氏も招いた座談会を記録。Li氏が持つ特異なバックグラウンドに迫りつつ、投資家らが「FLUXだけがDXPを具現化できる」と語る理由を深掘りする。
- TEXT BY SAE OTA
- PHOTO BY SHINICHIRO FUJITA
爆速開発の秘訣は、プロダクトですらない“最小限のMVP”
創業4年にして、『FLUX Autostream』、『FLUX CMS』と大きく2つのプロダクトをローンチし、さらには2022年にリリース予定のプロダクトを2つ控えている。猛スピードで事業開発を進めているが、その速さの秘訣には、MVP開発に対するこだわりがあるという。
永井我々がMVP(Minimum Viable Product)をつくる時には、本当にMinimumなMVPしかつくりません。
「顧客のどのような課題を解決するか」を徹底的に突き詰め、「その中で一番価値のある機能は何か」ということを考え抜きます。そして細かなUIなどには拘泥せず、一番大事な機能だけに全力を注いで開発をする。その結果として、仮に多少UIに不備があっても、お客様の本当に解決したい課題が解消されれば、必ずそのプロダクトは使っていただけると思っています。
ですから、後の開発サイクルを速めるためにも、まずはロジックづくりをとにかく早いうちから突き詰めていくことにこだわっているんです。
さらには、スピードだけでなく、MVPの段階でのプロダクトの精度にも並々ならぬこだわりがある。
Liいま言った一つのMVPをつくるのにも、永井と2人で最低20個程度は仮想のMVPをつくり、ディスカッションを繰り返した上でお客様にご提案します。その頃には3〜5ラウンドは試行錯誤した状態ですので、MVPと言っても、課題解決をイメージできるほど精度は高いんです。
永井も言った通り、私たちはクライアントがコアに解決したい課題は何か、何を改善したらクライアントは喜ぶのか、を徹底的に考え抽出したものをロジックとしてつくります。逆に、あえて余分な機能は加えません。そうすると、一旦ロジックのみで勝負できることがわかるわけですから、その後の新規機能や追加画面の提供などは全て付加価値になる。まずは、クライアントのペインに刺さる最小限の要件定義を行うようにしています。

このMVPのスピード・精度の高さには、Li氏がアカデミック、かつ多言語なバックグラウンドを保有していることが大きく影響している。
Li氏は、永井氏が発想したアイデアや海外等の他社プロダクトの情報に対して、徹底的に調査を実施。インターネット上に存在する情報や資料、事例等を読み解く中で、細かいニュアンスを的確に捉え、どのような技術を用い、どのように実現させているのか、を瞬時に理解することができるというから驚きだ。このLi氏の驚くべき能力については、後ほど詳しく触れることにしよう。
いずれにせよ、MVPのスピードと精度の高さ、この2つのこだわりこそが、FLUXが他のSaaS企業を凌駕する大きな要因だと、福井氏も語る。
福井BtoB SaaSのプロダクトは、BtoCと比較すると顧客の反応量が多くないため、開発サイクルを速く回転させにくい。そこで永井さんたちは、プロダクト開発よりも小さなサイクルで、仮説検証だけを細かく何度も行っているというわけです。
そうすることで、本格的な開発の前段階で精度の高い仮説を構築できる。積み重ねた試行錯誤の量が違うんですね。だから、より“当たる”事業をつくりやすいという強さがあるのだと感じています。

特許技術「id」とAIを駆使した機能開発
その開発スピードをもってして、一見すると「複数のプロダクト・サービス」を作っているように見えるFLUXであるが、その中身はidを基軸とした「連続的な複数の機能群」であり、それを統合したものこそが、FLUX Digital Experience Platformというわけだ。
そしてFLUX Digital Experience Platformが目指すものは、idを中心としてジャーニーを統合し、一気通貫で顧客に価値を提供できるようにすること。これこそが、FLUXが描く未来図だ。


FLUX Digital Experience Platform 図解
一方で、こうした構想の実現はそう簡単なものではない。一人のユーザーの情報をいかに統合・集約するか、という技術及びプライバシーの観点での問題が生じるからだ。
では、なぜその課題をFLUXならばクリアにすることができるのか。その理由が、FLUXが持つ最大の武器である「id」という特許技術の存在だ。

永井「id」とは、個人情報に配慮した形でCookieに依存しないユーザーの行動をトラッキングできる独自の技術のこと。『FLUX Autostream』では「id」の技術を活用し、ユーザーの細かな行動履歴からセグメンテーションを行うことで、広告やプッシュ通知最適化などのビジネス効率向上に繋げてきました。
この「id」を取り入れたプロダクトでの成果は目を見張るもので、導入した企業のチャーンレート(解約率)は約0.2%と、日本のSaaS企業でトップレベル。技術が顧客利益に大きく貢献している証拠だ。
福井我々Archetype VenturesがFLUXへの投資を決めたのも、この「id」の技術に大きな期待を寄せたからです。
EUのGDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)の動きに見て、まもなくクッキーレスの時代が来るであろうと見込んでいました。しかし、クッキーレスの中でマーケティングテック関連のサービスを実現するには、これまでにない技術を用いてデータ収集をする必要があります。それができるのが、「id」という特許技術を持つFLUXだと思ったんです。
Li氏は、こうしたビジネス環境の移り変わりを見越して特許を取得していたことに、FLUXの強さがある、と語る。
Li現在ほどプライバシーに関する規制が大きく騒がれる前である2019年の段階で、すでに特許を出願しており、そのおかげで昨年(2021年)4月に無事特許を取得することができました。マーケットも、我々の技術も、FLUXが保有しているデータも成熟してきた今のタイミングで「id」という特許技術を使うことができるのは、FLUXにとって最大の武器になります。
第一回の連載記事でも触れた通り、大手メディア関連企業を多数顧客にもつFLUXは、日本でもトップクラスのデータ量を日々取り扱っており、その中でユーザーの行動からユーザーの購買予兆やLTVなどを予測する機械学習の精度を高めてきた実績を持つ。
Li弊社の技術があれば、プライバシーを保護した環境の中で、1st party dataのみを活用し、機械学習による効果的なセグメント作成を実現することができます。DXPの根幹となる「データ」を最も多く保有する会社として、DXPは必ず実現できるはずです。
今後は、この「id」で作ったセグメントを、外部のツールにも連携できるようにするという。これには、単なるツール連携を超えた非常に大きな可能性があると永井氏は語る。
永井従来、この「id」で作ったセグメントは、弊社内のツールでのレイアウト最適化や広告表示最適化などに用いられてきました。しかし、今後はこれを外部のツールに接続することにより、様々な場面で活用できるようにしていきます。例えば、FacebookやGoogleを活用して広告出稿する際、弊社のセグメントを自動で連携させ広告出稿を最適化したり、MAツールに自動連携してWeb接客の最適化が出来ようになったり、というイメージです。
重要なポイントは、AIが自動でセグメントを作成してくれるため、担当者はMAツール上でのシナリオ設計などの工数が不要な点ですね。
こうしたFLUXが提供するプロダクトならではの「利用の簡単さ」という特徴を活かし、今ミドル〜エンタープライズ向けにメインで展開しているサービスを、中長期的にはSMB(中小企業)向けにも展開できるようにと考えております。
どのような規模の企業であろうと、経済価値を最大化できるプロダクトを提供する。FLUXのそうしたミッションには、福井氏も強く共感する。
福井導入したプロダクトを活用するスキルがない、そのような人材がいない、というような企業であっても成果を得ることができれば、プロダクトを通じたビジネスのエンパワメントに確実に寄与します。完全自動化、すなわちデジタルエクスペリエンスオートメーションのような領域が、まさにFLUXが描くDXP構想に内包されていると考えています。
行動データを蓄積していくことで、次に採るべきアクションを高精度にレコメンドできるようになっていくでしょう。どのような規模の企業でも活かせる技術になりますから、つまりはスモールビジネス事業者でも大きく成長できる可能性がある。これはまさに、「id」技術を持つFLUXでしかなし得ないことです。
「id」という特許技術を活用し、あらゆる規模の企業に対して、最適な顧客体験を提供する。それによる経済価値の最大化をFLUXは今後も目指し続けるのだ。
CEOとCTOの“視座の同期性”が、超高速な開発カルチャーを支えている
では、なぜFLUXではDXP構想のようなビッグビジネスが実現可能であると言えるのだろうか。
その強さの理由の一つは、「事業組み立てスピードの速さ」だ。
プロダクトを開発する際には、主に永井氏とLi氏が2人でディスカッションを行い、「このプロダクトには、こういうアルゴリズムが使われているはず」「こういうものをつくるためには、この技術を使えばよいはず」などと当たりをつけて、いわば開発の「上流」の部分を決めていくという。この精度の高さが効率的な事業創造を生んでいる。
だが、それだけではない。先にも触れた、プロダクトの大枠を決めた後のMVPをつくる際のスピードの速さ、そして顧客の経済価値を最大化する、という方針に忠実にアプローチを行うところが、FLUXの持つ真の強さである。
永井氏、Li氏のMVP開発に対するこだわりは相当なものだ。顧客が最も強く課題感を持つであろうポイント、真のペインポイントに、直接効くようなロジックを徹底的につくり上げる。余計な機能は限りなく削ぎ落として、顧客との具体的かつ本質的な対話サイクルを速める。そうして仮説検証の質を最大限の高めることで、顧客に刺さる事業を確実につくっていく。
永井氏・Li氏の開発のスピードの速さには、河合氏も共感する。
河合まず、お客様がそのサービスを使いたいと思ってくれる理由は何か、というペインを探りに行くスピードとリアリティを突き詰めるまでが、ものすごく速い。加えて、そのペインポイントに刺さる最小限のMVPをつくろう、という方針が2人の間ですぐにアラインできることが凄い。
CEOとCTOが顧客課題を、同じ感度・目線でディスカッションしてリーンにプロダクトを構想できるスタートアップは、本当に強いですよね。

「李さんの顧客課題をビジネスモデルへ転換する、言語化力の高さがそれを実現させているのだろう」と河合氏は表現する。そのスピードの速さは、投資家から見ても魅力的に映るポイントだ。福井氏は、他のスタートアップと比較したFLUXの開発スピードの速さを、こう語る。
福井こういう世界になったらいいよね、と未来を描くような話をしても、それに取り掛かれるのが4~5年後というのはよくある話。でも、FLUXの場合、話していたものが実現するまでのスピードがとにかく速い。たった数カ月でプロダクトを提供し始めている、なんてこともあります。
他社がリサーチをしたりロジックを組んだりしている間に、もう開発に着手している、ということですから、この速さは他の投資先と比較しても突出していると言って良い。
この速さを見ていると、FLUXのプロダクト開発の速度を他のスタートアップが真似しようとしても、まあ無理だろうと思います。スピードと、開発をはじめとした組織・メンバーの強さと、全てがここまでうまくかけ合わさっているスタートアップは見たことがありません。このアセットを持つFLUXだからこそ、FLUX Digital Experience Platformを実現できるだろうと信じることができるんです。
世界中のキーパーソンともコネクションを持つ、CTO Li氏の情報収集力
社員規模100名に達しながらも開発速度を保ち、DXP実現に向けてプロダクト開発をつくり続ける。そのスピードの要因のひとつに、まだあまり知られていない、Li氏の特異なバックグラウンドがある。
Li氏は、英ケンブリッジ大学のコンピューターサイエンス学部や東京工業大学工学部でアルゴリズムや機械学習などを学んだ経験を持ち、母語の中国語に加え、日本語・英語・フランス語の計4カ国語をネイティブレベルで操る秀才。さらには、中国でかつて高級官僚を登用するために行われていた試験制度「科挙」で数百年もの間トップをとり続けた家系の末裔であるというから、その頭脳明晰っぷりは遺伝子レベルだ。
父は情報科学の研究者であったため、幼い頃からPCに慣れ親しんでいたものの、そのバックグラウンドは学術的なものが中心。なんとFLUXを立ち上げるまでスタートアップにおけるSaaS分野の開発は初めての経験であったというから驚きだ。
Li氏を採用した永井氏は、この実務経験の少なさについて、そう心配していなかったという。なぜならば、その学習能力の高さを知っていたからだ。
永井Liは当初あったときは、マーケティングや広告の分野に関してほぼ知見がありませんでした。一方で、すぐに関連分野のビジネス/技術的知見を吸収し、1カ月以内にはスムーズに開発できるレベルまでもっていっており、非常に驚きました。
その学習能力の高さには本当に驚愕しまして、これならば何の心配もないだろう、と思えましたね(笑)。
ソフトウエアエンジニアリングの経験がなく、アカデミックな知識をベースに持つLi氏。しかし、そのアカデミックなバックグラウンドこそが、今のFLUXの強みに繋がっているわけなのだ。
LiFLUXのビジネスの根幹は「ビッグデータ」ですが、その取扱いはまさに私が昔から研究してきたテーマ。産業界にまだ十分に降りてきていない、アカデミックな最先端の技術を応用できている自信があります。
というのも、データを使ってどうやって最短距離で結果を出すか、という発想は、まさにアカデミックな考え方。常に最短距離を意識して、日々アップデートされる世界中の技術情報を漁っていますから、一個のツールや一個の言語にこだわることなく、データそのものからインサイトを得てサービスに活用することができます。論文や特許からヒントを得ている分、他社よりずっと早い段階で新しい技術を仕入れることができますし、かつ概念だけでなく実用化の部分まで深く理解することができるのです。
例えば、FLUXの事業を始めた当初は、マーケティングテックのナレッジが非常にニッチなものであることに苦労しました。中国語や英語で調べても、どこにも求めている情報が載っていない。ただ、だからこそマーケティングテック関連の論文や世界中の大学の研究室が開発する技術や特許などから逆算して、アルゴリズムのヒントを得ました。
こうした方法で情報を取得すると、ビジネスに実装された業界ナレッジから紐解くよりも、より深い部分で技術そのものを理解することができます。学術界に転がっている様々な見解、仮説、技術などを集めることで、自分自身の中でプロダクトに必要な技術を探し当てることができるようになっていったのです。

そのアカデミックなバックグラウンドと豊富な言語能力ゆえに、Li氏がアクセスできる情報量は凄まじい。例え大手企業が力を持ちやすい世界であっても、その速さから「先手」を打つことができるのが、FLUXの強みだ。
Li氏は「個人情報保護の領域など、大手企業が規格を決めることになるであろう領域は多々あります。そのディスカッションを左右する力は我々のようなスタートアップにはありません」と言いつつも、「彼らがどう出るか、を非常に早い段階で見極めて、先手を打つことはできます」と余裕を見せる。
その自信の背景として、Li氏がW3Cをはじめとした国際団体で希少な情報に触れることができる立場にあることも大きい。
W3C(World Wide Web Consortium)とは、Web技術の標準化を行う非営利団体のこと。世界で461の団体が所属する。日本からは電通や楽天、ソニーなど大企業をはじめとした38社が加盟しているが、そのうちの1社がFLUXなのだ。
永井FLUXは、いわば技術革新の中心地であるW3Cのメンバーとして、最先端のデータや情報を取得することができています。加えてLiは、その言語能力の高さゆえ、英語・中国語・フランス語の全ての論文にアクセスし、学術レベルでの最先端技術を日々取り入れています。
日本では希釈化されてわかりやすいニュースになるような情報を、その1年前にはより深く知っているような状態である、というわけです。規格を決める主導権を握ることができなくとも、「こうなるだろう」と先を読むことはできます。
加えて、技術革新の最先端の情報を、ただの「情報」としてではなく、それをどうやって実装するのか、という深さまで理解できるのが、アカデミックなバックグラウンドを持つLi氏の強いところだ。
Li公式発表やニュースでわかるのは、どういった技術なのか、という部分までです。一方私は、技術開発につながった論文に直接アクセスすることで、それをどうやって実装するのか、実装したらどのような影響が発生し得るのか、という点まで理解しようとしています。ビジネスに活用した後の対策、リスクヘッジまで同時に考えることができるのです。
論文や特許など、最新かつ生の情報を仕入れることができるアカデミックな背景と、その言語面での情報アクセスにおける強みは、FLUXが持つユニークな特徴だと言えよう。
「自分をエンジニアとは捉えていない」CTO Li氏が最重視するのは、技術でなく“組織”
数週間で数々のプログラミング言語をマスターし、「プログラミング言語なんて、それぞれ役割と特徴があるだけ。その違いは些細なこと」と飄々と言い放つLi氏は、まさに“THE 天才肌”なキャラクターに思える。
この能力をもってすれば、Li氏一強、いわゆる「ワンマンアーミー」のような開発組織になるのでは、と思いきや、Li氏の志向性がそうではないのが、また面白いところ。
というのも、Li氏がFLUXにジョインすることを決めたのは「ゼロイチで組織をつくりたかったから」だ。
Li学生時代から、中国で英語を教える塾の先生をしていたのですが、その頃から「誰しもに能力や才能があるはずで、それが発揮できないのは勉強法や考え方を間違えているだけだ」という思想を持っていました。
私にとっての会社組織は、プロダクトのようなもの。組織づくりにおいて、エンジニアそれぞれが持つポテンシャルを最大限発揮できるようにしたい、という想いがあるのです。
Li氏の組織づくりに対するコミットメントの強さは、福井氏から見ても「ポジティブサプライズ」だったという。

福井以前、うちのメンバーがArchetype Venturesの投資先のCTOを集めて“CTO会”なるものを開催したことがあります。そこでも、Liさんは組織についてものすごく熱く語っていたんです。評価制度や設計、育成方針なども含めて、深い考えを持っていると感じました。
CTOは技術に強いけれど組織づくりに弱い、というケースはよくありますが、Liさんは技術にめっぽう強いにも関わらず、技術の枝葉ではなく「何をすべきか?」「何を成したいのか?」という大局観を持ってエンジニアリングを捉えている。それを踏まえて組織をつくり、プロダクト実装を実現できるというのは特異ですし、FLUXの開発組織の強みだと言えるでしょう。
「自分のことをエンジニアだとは思っていない」と語るLi氏。開発組織にとって今必要なものは何か、を俯瞰の視点から見抜き、理想を現実化するLi氏にとって、組織づくりはプロダクトつくりと同じように面白みを感じられるものなのだ。
求めるものは「自発性」だけ。
開発者よ、FLUXなら“世界基準”で成長できる
FLUX Digital Experience Platformの実現に向けて、今後もさらなるプロダクト増強が見込まれるFLUX。開発組織の強化も課題となるが、その点、Li氏は柔軟な考え方を見せる。
Liエンジニアには様々な特性を持った人がいますが、それぞれのポテンシャルを発揮できるような組織でありたい、と考えています。具体的には、技術に対してとことんこだわるスペシャリスト系のエンジニアもいれば、エンジニアリングはあくまでもツールや手段であり、ビジネスに対して貢献したい、と考えるタイプもいますよね。その両方を内包する組織をつくりたい。
実際に、スペシャリスト寄りとビジネス寄りのエンジニアで、それぞれのカラーに合わせて評価方法も変えています。無理にどちらかに合わせようとするのではなく、それぞれが真剣に自身のキャリアやスキルを磨ける場にしたいのです。
「スペシャリストとビジネス寄りの志向をもつエンジニア。スタートアップがその両方を抱えることは事業成長において非常に大切であり、そうした組織のバランスは、今後ますますスタンダードになっていくだろう」と、河合氏は語る。FLUXがこうした方針を掲げられるのは、CTO・Li氏とSVPoE (SVP, Engineering)・中川晃氏のバランスが、まさにその2軸を体現している、という背景があるからだ。
永井Liはどちらかというとテクノロジースペシャリストな性質が強い一方、中川はPdM的で事業開発に強く、コミュニケーション能力も高い。それぞれのバランスがとても良いし、極端にどちらか、ではなく、その両方の特徴を内包できる組織になっていると感じます。

先述の通り国際的なバックグラウンドを持つLi氏は、FLUXの開発組織として目指す未来もまた、国を超えた大きなものを描いている。
LiW3Cのような国際組織に加盟している以上、そのコミュニティを利用するだけではなく、しっかりと組織やメンバーに対しても貢献できるような体験をつくっていきたいと考えています。スタートアップであっても、世界の最新技術を日本に流通させるようなポジションになりたいし、なれると自負しています。そうした志向性をもつ人とは、スペシャリスト的な位置付けで一緒に働いていきたい。
一方で、FLUXはとにかく新規事業の回転が速く、新しい情報をキャッチアップして実装させる、というサイクルを超高速で回していますから、ビジネス志向の強いエンジニアや、将来はPdM、CTOになるキャリアを描いているエンジニアにとっては、かなり刺激的な環境のはず。
FLUXの開発組織は、自身が培ってきた技術やエンジニアリングスキルをどうビジネスグロースに活かすか、をとことん試せる場であると言えるでしょう。
そんな組織づくりにおいてLi氏が最も大切にしているのは、「自発性」というカルチャーの浸透だ。
Li中途採用では、どうしてもこれまでの経歴などを気にしがちですが、我々が最も大切にしたいのは、移り変わりの速いこの業界において新しい知識を自ら学んでいく意欲があるということ。業務時間外にはあまり勉強したくない、という人もいるかと思いますが、そうした人たちとは考え方や姿勢が180度異なります。
最初のレベルが期待役割に若干満たないとしても、その後自らたくさん勉強 してたくさん質問してキャッチアップしようとするような人が、最も魅力的です。我々のチームは勉強会も頻繁に開催しますし、質問大歓迎のカルチャーです。
加えて、「何のために勉強するのか」というイメージがついた状態で学ぶ、つまり我々のMVP開発に対する考え方と同じようにビジネスにおける「最短」にこだわる組織にしていきたいんです。
世界の最先端の情報と、その実用化に至るまで、全てを手に入れることのできる環境は、自身の市場価値を高めたいエンジニアにとって最適な成長機会となるであろう。
FLUXが描くDXP構想は、日本のSaaSビジネスの大きな転換点となりうるビッグビジネスだ。今回のインタビューで見えてきたFLUXの強さ、すなわちプロダクト開発のスピードと精度の高さ、そして特異なバックグラウンドを持つCTO・Li氏の存在をもってすれば、FLUXの今後のプロダクトロードマップにも非常に期待できるのではないか、という凄みすら感じた。
こちらの記事は2022年04月18日に公開しており、
記載されている情報が現在と異なる場合がございます。
執筆
太田 冴
写真
藤田 慎一郎
おすすめの関連記事
「600万人の難病患者」を救う"四方よし"のビジネスモデル構築術──Medii山田・GCP高宮対談にみた、投資家も唸る“秀逸”な着眼点と組織作りとは
- 株式会社Medii 代表取締役医師
- 東京医科歯科大学客員准教授
「ハイパフォーマーが最も報われる環境に」大型調達を経た未上場スタートアップが挑戦するカルチャー醸成と報酬設計をFLUX永井・布施が語る
- 株式会社FLUX 代表取締役CEO
「創業者の熱意」を、スケールさせていく事業・組織戦略とは?ヘルスケアDXの雄、Rehab for JAPAN・ファストドクター・カケハシの実践論に学ぶ
- 株式会社Rehab for JAPAN 取締役副社長 COO
創造するのは“X年先のMust Have”。SaaS界をリードし続けるコミューン、FLUX、ゼロボードの勝ち筋を、DNX倉林が問う
- 株式会社FLUX 代表取締役CEO
急成長SaaSスタートアップの、5つの共通項とは?──カケハシ・コミューン・FLUXの思想と戦略から、成長実現カルチャーを学べ
- 株式会社FLUX 代表取締役CEO
急成長する3社に学ぶ、「産業課題の解決手法」──“次世代のインフラ”を目指すユーザーライク・レンティオ・タイミーの事業・組織の創り方
- ユーザーライク株式会社 代表取締役CEO
調達額では測れない!FastGrowだから知っている、大型調達スタートアップ経営者4人の知られざる魅力
- 株式会社FLUX 代表取締役CEO
なぜFLUXは、プロダクトを順調にグロース出来たのか──DNX倉林氏が太鼓判押すマチュアな経営者・永井氏が持つ素養“Tenacity”に迫る
- 株式会社FLUX 代表取締役CEO
DXP構想で「経済価値を最大化」させる──国内最速レベルでのARR10億円到達にひた走るFLUX、代表・永井氏の事業・組織戦略
- 株式会社FLUX 代表取締役CEO
カルチャーは事業成長の源泉。「ユーザー起点×データ」にこだわる組織文化をどのように創り、浸透しているのかをCEO武井・CMO戸口とReBoost河合に聞く
- ユーザーライク株式会社 代表取締役CEO
仕組みを変えればものづくりの商慣習すら変えられる!2大BtoBプラットフォーマー、ラクスル・キャディのSCM戦略
- ラクスル株式会社 ラクスル事業本部 SCM部 部長